前の続きー。
弐 夕陽、その光
夢の中で、あいつが笑った。四00CCのバイクに乗って、こちらを振り返った。亮介は叫んだ。ばかやろう。
そこで目が覚めた。頭、いや、ここは、…首が痛い。
辺りを見回すと白灰色のコンクリート床が大きく広がっていた。その先の周囲は金網に囲まれている。天上は青い空。亮介は立ちあがる。学生服を脱ぎ、両手で掲げて服の背部分を見ると、薄く白墨のような砂に汚されているのに気づいた。それを叩き、ついでに尻も叩いてから再度学生服を着て腰を落とし、コンクリート床の上に胡坐をかいた。ここは?と思いしばし考えてみたら、学校の屋上であることを思い出した。俺はいつのまにか眠ってしまっていたのか、このコンクリートが広がるど真ん中に。こんなところでよく眠れたものだと思いながら、「あいつ」の夢を見てしまったことに胸が絞られるような思いがした。あれからもう十か月にもなるのか。
今はもう、四時限目の授業のはずだ。今日こそは真面目に授業に出ようと思っていた。が、それは果たせず、亮介が起床したのは朝の十時半で、一生懸命無駄な作業を省略し、自転車で三十分駆けて来て甲斐西高等学校の正門を通過したのは、十一時十五分頃だった。駐輪場に自転車を置いて、ゆっくり歩いても四時限目からではあるが、取りあえず授業に間に合ったはずだった。が、亮介は急にやる気が失せ、そのまま三階建ての校舎の屋上にまで来てしまったのだった。その後、いつのまにかこんな所で眠りこけた。傍らの黒い合成革鞄を凝視して、これを枕代わりにしてだよな、と思うとより首の重い痛みが酷くなったような気がして憂鬱感が満載になる。どこまでも青い空、柔らかな太陽の光が降り注ぐ十月なのに。
親友の文則との付き合いが縁遠くなってきたのは、高校に入ってからだった。亮介はこの進学高校に、文則は私立の大学付属高校へと昨年の四月にそれぞれ別れた。本当は同じ高校に通いたかった。そのために中三の初めから一緒に受験勉強を始めた。教師は文則にお前には無理だと言っていたという。でも、教師が断言するほど、文則の学力は悪いものではなかった。むしろ努力を続ければ、必ずや県内の進学校に合格するレベルにまで至ると亮介は確信していた。本人も亮介と同じ高校に通いたい気持ちから、いっちょやったるか、と気合を入れていた。それなのに生来の飽き性も手伝ってか、三か月も経つと気力もなくなり、やがて二人の共通の勉強場所である街の図書館に、文則はまったく来なくなった。亮介は何度か文則を説得しようと試みたが、彼はまったくその気はなくなったと応ずることはなかった。亮介は落胆したが、それで二人の仲がどうかなる、ということはなかった。学校ではいつもと変わりがなかったし、相変わらず休みの日には互いの家を行き来していたし、何よりも亮介らは高校が別々になっても親友であり続けることに決して疑いはしなかった。ただ、後々思い返してみて、もしかしたら文則はこのときの亮介に対して、複雑な思いがあったのかもしれないと考えるようになった。一緒に受験勉強をやろうと最初に持ち掛けたのは亮介だし、それについて主導権を握っていたのは亮介の方だったから。
中学二年生になった頃から亮介の身長は急激に伸び出し、三学期が終わる頃には学年一の身長を誇る文則とほぼ変わらない高さになった。それとともに筋肉も発達してゆき、男の身体を形作ったことによって、大きな自信が芽生え、文則が付いていなくても、あの横山達に対しての怯えも全くといっていいほどなくなり、逆に彼らの方が亮介を避けるようになった。だから亮介の中での文則は、もう盾になってもらう存在ではなく、互いに肩を並べる真の盟友のような関係になっていた。それは文則にとっても喜ばしいことであったに違いないが、一方でもう亮介に頼られなくなったことに、自分の存在への疑問と一抹の寂しさを感じていたのかもしれない。その後、二人の関係性の変化があったことで、例え文則が不得手な事柄で仕方がないことだとしても、どうしても「文則が亮介に頼る」というそれまでとは逆の構図が出来上がってしまう場合が多々あった。プライドの高い文則が複雑な感情を持ってしまうのは当然のことなのだと思う。
文則との関係で特にぎこちなさを感じ始めたのは、彼の両親の離婚が成立した後からだった。中学校の卒業式の後、文則は校門の前で左の口端を上げながら、亮介に向かって告げた。「俺は母親に付いていくことに決めたよ。N市に引っ越す」。猫のミーコはどうするんだ、と頭に浮かんだが、それについて文則は「猫たちは近所で飼いたい家があったんで、頼んだよ。ばあさんが一人で住んでいる家で、ミーコもその他の猫も纏めて面倒見てくれるってさ」と寂しげに語った。
それから亮介らは別々の高校へ進学していったが、それでも亮介は諦めず、最初のうちは休みの度に会うようにしていた。それが徐々に変わっていったのは亮介が彼のあの行動を許せなかったからだった。
四時限目の授業の終わりを告げるチャイム音が響いた。ここからは昼飯の時間だ。どうする?素知らぬ顔で教室にでも入っていくか。そう思ってみても亮介は動く気がしなかった。鞄を引き寄せ、中から弁当箱を出した。古新聞に包まれたそいつを、鞄を下敷きにして目前に置いた。あまり食う気がしない。
「亮介」
声がしたので後ろを振り返ると屋上への出入り口から、光がやってきた。左の腕に座布団を挟み、手にはピンクで可愛らしいランチボックスってやつを持ちながら。
「何故ここにいると分かった」
「だって亮介言ってたじゃん。俺がいないときには屋上にいるって」
「そんなこと言ったか」
「言った、絶対言った」
口を尖らせながら光は持っていた座布団を敷いて、亮介の前に膝を立てて体育座りをした。
バカ、パンツが見えるじゃねえかと思ったが、光の穿いているスカートは地面に触れそうなほど長かった。膝を立てても踝が露になる程度だ。さっそくランチボックスの蓋を開けようとしている光を見ながら、亮介は深い溜息を吐いた。彼女の髪の毛は黄色い、それに癖毛だ。大きな二重で瞳の色は普通の日本人よりずっと薄い。「限りなく透明に近いブラウンだ」と普段亮介は彼女をからかっていた。彼女の祖父がロシア人だということを何かの折に聞いた。
「昨日、一昨日と来ないもんだから熱出して寝てるって二宮に言っておいたよ」
「ああ、それで家にも連絡がなかったのか」
「感謝してよ。あたしは一週間前からどうもあんたの様子がおかしいと思ってたんだ。目が血走っていたしな」
「持つべきものは不良の友人、ってことか。サンキュウな」
「シバくぞ」
二宮は進学校には珍しく生徒の目線に立ってくれる女教師だ。〝眠れない〟、亮介は九月初めの面談で二宮に相談した。文則のことも、教師になりたいと考えていることも。恐らく彼女には何もかもお見通しなのだと思う。だから、光の嘘に気づいていても、敢えて無断欠席の亮介を見逃してくれた。大いに悩め。今はそれが一番いい解決策だと。
「食べないの?」
光は不思議そうに亮介の顔色を窺った。「食う食う」と頷き、亮介は掛けられているゴムを外して新聞紙を開いた。
光との出会いは、まるで少女漫画のようなシチュエーションだった。高校初めての授業が終了したあと、帰宅しようと向かった校舎裏の駐輪場で彼女は三人の男子生徒たちに絡まれていた。亮介は、面倒はごめんだなと思ったが、生憎彼らは亮介の自転車を引き出すのに必要な空間を占領していた。光は迫られ追い詰められたのか、その自転車の後ろ、金属で形作られた荷台に尻が触れていた。仕方がないので亮介は歩を進め、彼らの間に割って入るようにして男たちに顔を向け、なるべく自分の感情を読み取られないようにして彼らを睨んだ。
「自転車が出られない」
たったそれだけのことだったのだが、彼らより十センチは高い亮介に見下ろされて驚愕したのか、彼らは一瞬のうちに揃って逃げ出してしまった。それから後に残った光が亮介の前に来て頭を垂れようとしたので、そういうのに慣れていない亮介は、自転車も出さずにまるで逃げるように、その場をあとにしてしまったのだった。
そのときから、亮介、亮介と彼女はことあるごとに亮介に話しかけ、デートしない?と亮介を街中に誘うようになった。そんな光の馴れ馴れしさに亮介はどぎまぎし、不良少女のように派手な様相から、最初の内は無視を決め込んでいたのだが、真っ直ぐ亮介を見つめる光の積極さに、いつしか巻き込まれていき、やがて亮介は流れのままに彼女と付き合うようになった。付き合うといっても亮介のその想いは、恋ではなく親愛の情といったものだった。彼女の中性的な性格は、亮介には親しみを感じさせたが、恋になるにはもう一つ何かが必要だった。多分、光もそれを感じているはずで、一年以上、亮介らは恋だとか愛だとかは一切語らず、まるで男同士の友情のような絆で結ばれていた。
「午後からは授業に出るのか?」
太陽のひかりに晒されて、光の微妙に輝く瞳に見つめられて、亮介は心の中を見透かされるような気がした。
「出ないことにした」
「ここまで来ているのに?何するんだい」
「考えて考え抜く」
「変な奴」
光はそう笑い、また座布団を腕に挟み、空になったランチボックスを手に持って、屋上の場を去って行った。屋上はなにもないし、普通の生徒にはまずここへの用というものもない。つまり、もうここには誰も来ない。あとに残ったのは、近くの国道を走る車のエンジン音と、何気に聴こえる教室の騒めきだけだった。
文則―。
彼は優しい奴だった。優しいが故に、進んだ高校でも一緒になった横山なんかに引きずられた。
四月生まれだった文則は早速普通二輪の免許を取った。その内すぐにⅭB四00というバイクを乗り回すようになった文則を見るたびに、亮介はいいようのない胸騒ぎを覚えた。お前、まさか…、と尋ねると横山と一緒にレーシングチームに加入したと文則は俯いた。レーシングチームなんて嘘っぱちだ、暴走族だろうと亮介が迫ると彼は開き直って、ああそうだ、何が悪い、と亮介を睨んだ。たまたま、文則の家の近所だったという光を紹介しようと、彼女を連れだって行った土曜の夕方だったのだが、亮介は憤慨し、それからは段々と足が遠のいていった。
あれは昨年の十二月九日の夕方だったか。ジョン・レノンが殺害されたニュースが駆け巡っていた。前日、亮介は文則が所属しているというチームの所業が余りにも酷いとの噂を聞きつけて、居ても経ってもいられず文則の家に行った。亮介の文則への警告もこれが最後だと思ってのことだ。しかし、やはり頑固な彼は亮介の話も聞かず、その夜バイクに乗って出て行ってしまった。一瞬こちらを振り返り、亮介に向けて邪心のない笑顔を見せて。
光からの電話があって、亮介はきっとジョン・レノンのことだと思った。光はジョン・レノンのファンだったから。しかし、違った。受話器を通して聴こえた光の声は、近所の人から聞いたと前置きをしてから、亮介にとっては体を引きちぎられる様な悲しい事実を伝えたのだった。
悔やんでも悔やみきれない。十か月経った今はさすがに落ち着いたが、それでもまだその影響は時として表面化する。
カラス?
いつの間にか陽が傾き、一日の最終ラウンドを迎えつつあることに亮介は気が付いた。革鞄を手に立ち上がって、落下防止のための金網に向かい、片手を置いて地上の様子を眺めた。弱小野球部が練習をしている。ピッチャーが投げる。バッターは大きく空振り。外野は何を考えているのかグラウンドに胡坐をかいている。声もない。だから駄目なんだと思っていたら、轟音が響き、一台のバイクが入ってきたのが見えた。一旦、急ブレーキをかけて止まったと思ったら、エンジンを何度も噴かし、また動き出す。大きく旋回する。八の字を描く。息継ぐまもなくバリ音を轟かしていた。野球部が活動している場所からは離れているものの、その轟音と荒々しい運転に野球部の連中は慌てふためき、練習を中止して皆レフト側のベンチに引き上げてしまった。それに気をよくしたのかバイクはよりグラウンドを広く使い、なおも荒っぽい運転を続けた。亮介はバイクの車体に注視した。マフラーは曲線を描くような特別仕様。座席をタンクよりも沈むように設計されたあれは、如何にも暴走族を思わせた。馬鹿もんがと、怒りが沸々と湧き上がって来るのを感じながら、亮介はふとあのバイクに見覚えがあることに気が付いた。確か、文則の家の前で、だ。
あれは…横山なのか。
しばらくして、バイクが停止した。ノーヘルの頭がこちらを見上げるように傾いたときに亮介は確信した。紛れもなく横山。遠目でも分かった。
ふっと、また記憶が蘇った。
横山はあの時、文則を残して真っ先に逃げ出したと聞いた。卑怯者。
ああ、卑怯者、卑怯者、卑怯者、卑怯者、ひ・きょう・も・の。
亮介の怒りが熱く鉄を溶かすような激しいものに変わったとき、無性に体が震えた。抑えきれない。でも駄目だ、行っては。亮介の中の理性が必死に訴えかけている。しかし亮介は結局我慢が出来なかった。屋上から出、階段を駆け巡り、怒りそのままにグラウンドにまで駆けていってしまった。
よこやま―。
亮介の声が響き、バイクに乗りながらこちらを向いた横山は、そのまま急停車した。「ああ、亮介じゃねえか。久しぶりだねえ。丁度いい、待ってろ」
そう笑った横山はニ、三度エンジンを噴かし、今度は亮介に向かって一直線にバイクを走らせてきた。轟音が近づく。亮介はぎりぎりまで耐えてタイヤが触れる寸前で横に飛んだ。転がり制服が砂だらけになるなと思った。それからすぐに立ち上がり、奴はどうしたと確認した。バイクは離れたところに派手に倒れ、まるで何かに引きずられたように車体が白く砂まみれになっていた。前輪には亮介の黒い合成革鞄が見事に嵌り、スポークがぐにゃりと妙な形に変わっていた。後輪は未だ少し惰性で回っている。その近くで、跳ね上げられ落下した横山は、腰を打って起き上がれないようで、その部分を押さえ丸くなっていた。
それでも亮介の怒りは収まらなかった。亮介は今まさに横山に向かって突進せんと構えた。するとそのほんの一瞬のうちに、するりとか細い両の腕が、背中から亮介の腰に巻きつき、制服を強く掴んで亮介を抑えたのだ。誰だ。亮介は怒りの表情そのままで振り返った。果たして、亮介の目には薄いブラウンの目をした、不良娘の悲しそうな顔の表情が映った。…光……。光は必死に亮介に話しかけた。「駄目だよ。あたしが居たからよかったものの。あんた将来何になりたいんだい。思い出せよ。これ以上やったら多分あんた駄目になっちゃう。それでもやるっていうならあんたはどうしょうもないバカだ」
しかし、と思って亮介はまた前を向いた。光は亮介の脇の隙間から制服を掴んでいた右手を離し、前に出して、西方の一方向を指さした。
「見なよ。綺麗な夕焼けだ。こんな夕焼けを見てもまだ敵討ちをしたいのかい」
遠くに見える山々が薄い赤黄色に染まっている。太陽は今まさに奥の山に隠れる寸前だ。西の空には夕焼け。いつか見た夕焼け…。絵画のようなその風景を亮介は何処かで見たことがあった。あれはいつのことだっけ。
騒ぎを聞きつけ、二宮を始め何人かの教員が校舎から出て来た。
ああ、思い出した。いつも学校への行き帰りに歩いていた、あの土手。その道から見えるあの風景。思い出したよ。
それから亮介は光の腕を外し、教師たちが来る短い時間(とき)の中で、その美しい風景に魅入っていたのだった。
参 夕陽と彼と響子ちゃんと
駅前も変わったな。
亮介は、K町駅前に立ち、辺りを見回しながら、昔を懐かしんでいた。
あれから二十年が経ち、時代は昭和から平成へと移っていた。
亮介と文則は中学時代の横山との一件から、よりいっそう親交を深めていった。二人は傍から見ても、鬱陶しいほどいつも一緒に行動し、互いに信頼するまでになったのである。
それが変化したのは中学を卒業してからだった。亮介の両親が正式に離婚し、亮介は母方に引き取られ、K町から比較的近いN市に引っ越していった。彼らは、別々の高校に進み、最初の内はそれなりに行き来をしていたものの、徐々に縁遠くなっていった。
親友と思っていた文則と何故、離れていったのかは、文則の置かれた環境が変わったこともあるが、本当のところはもう一つの理由があったのだった。それは今にして思うと、「後悔」という二文字がついてくるのだが、あの時の亮介にはどうすることもできなかった。ただ、いえることは、彼らは別れるべくして別れ、亮介は文則とその後永遠に会えなくなったということだけだ。
高校を卒業して、彼は県外の大学の教育学部に進学した。四年間勉学とバイトに励み、教職の免許を取った。教師になることに両親は反対したが、亮介の姉だけは、あんたの経験したことが何処かで生きるに違いないと賛成してくれた。彼は地元の教員採用試験を受験し、晴れて念願の中学校の教師になることが出来た。
教師になってからは、無我夢中だった。登校拒否や虐め、家庭内暴力と様々な問題に直面し、その都度最良の選択を迫られ、なんとか解決らしき方向へと導き、それでも、これで良かったのか?と苦悩し続けた。教師になって十年というもの、亮介は常に神経をすり減らし、こんなはずではなかったと、精神が悲鳴を上げない日はなかった。
そんな時に、偶然中学生の時、団地から引っ越していった響子ちゃんに出会った。
響子ちゃんは教科書販売の会社に勤めていて、たまたま彼が勤めている中学校を営業で訪れていたところだった。
「…亮介くん?」
そう職員室で声を掛けられた時、亮介は一瞬誰なのだろうと疑った。だがすぐに変わらない清廉さに昔の面影を見、懐かしさで一杯になった。
「響子ちゃん?」
「うん、久しぶりだね」
「久しぶりなんてもんじゃない、二十年ぶりなのかな」
「引越しの時からだから、…そうね、もうその位になるのかもね」
響子ちゃんは、相変わらず優しさが香るような空気を纏っていた。目尻に笑い皴が目立つことと髪をショートにしていることを除けば、他はあの頃と変わりがない。彼が話を続けようとすると、ごめんなさい、今日商談があるの、と急いで自宅の電話番号を書き記したメモを亮介に渡し、電話頂戴ね、とその場から奥にある校長室へと消えていった。
それから数日の間、忙しさにかまけて、メモの存在を忘れていた彼は、たまたま寄ったコンビニでの支払いで財布を出した時、財布のカード入れの間にあるメモを見つけた。
あの時のメモか、と思い至りどうしょうか逡巡したが、明日が日曜日だということに気づき、ともかく電話を架けてみることにした。家の電話の受話器を取り、ナンバーをプッシュすると、数秒の呼出音の後響子ちゃんが直接出た。響子ちゃんは、待っていたのよと言い、明日K町駅前の喫茶店で会って話をしましょうと言った。午前中は用があるからというので、亮介は、それじゃあ、午後三時にと約束を交わし電話を切った。彼は、これはデートになるのだろうかと考えたが、すぐに彼女はもう人妻なんだろうなと思い直し、自分の考えの浅はかさを反省した。
次の日の日曜日、彼はK町駅前の喫茶店に向かった。
途中、一旦止まって時計を見た。午後三時にはなっていなかったが、多分響子ちゃんはもう待っているだろうなと思い、その先の道路を挟んで向かいにある喫茶店を目指した。
ドアを開けると日曜日だというのに、喫茶店の中は閑散としていた。隅に座っていた彼女は、彼をすばやく見つけると、ここよ、ここと大きく手を振った。
亮介が響子ちゃんの前に座ると、ウェイトレスが、注文を受けに来たので、響子ちゃんの前に飲みかけのアイスコーヒーが置いてあるのを見て、同じものを注文した。
「…ほんとに二十年ぶりね」
響子ちゃんは懐かしそうに彼の顔を眺めた。
「君は二十年経っても変わらない」
「すぐには分からなかった癖に」
「いきなりだったからね」
「ほんと、偶然。まさか亮介君が学校の先生になっていたなんてね」
「似合わない?」
「いいえ、ただ、私の中の亮介君は、大人しくてほんとに優しい男の子だったから。まさか人前に立つ職業に就くなんて思いもしなかったの」
「二十年経てば、人は変わるんだよ」
「そうね。年月は人を変えるものなのよね。…私だって色々あったもの」
彼女は遠い目をしていた。彼はそんな彼女を見て、以前こんなシチュエーションに出くわしたことがあるような気がしていた。それは何時のことだったのだろう。彼はしばし考えたが皆目検討がつかなかった。
「今何処に住んでるの」
彼女がそう訊いてきたので、彼は、A市だよ、あれから丁度俺が県外の大学に入学した年に引っ越したんだと答えた。彼女はそれを聞くと、私は一度県外に住んでいたのだけれど、またY市に戻ってきたのと話しながら、アイスコーヒーのグラスを手に取って、ストローで溶けかけた中の大きな氷を軽く突いた。Y市、ということを聞いて彼は自分が一番気になっていることを訊いてみようと思った。
「…・結婚は?」
「一度ね、結婚したわ。二十五の時…。それも三年で破局したけどね」
「それは、悪いことを聞いちゃったかな」
「いいえ、そんなことはないわ。私の中ではもうすでに終わったことなんだもの」
「強いんだな」
「そうよ、私は昔から、気の強いお転婆な女の子なのよ」
お転婆な女の子、と彼女が言ったところで、彼は思わず噴出してしまった。余りにもイメージとかけ離れているし、こんなに大きな女の子がいるわけがない。彼女は怒った風にして、そうよ、そうよね、私はもうおばさんよね、と口を尖らせた。
「ごめん、笑ったりして」
「いいのよ、もう私も三十四になるんだもの」
「さっきも言ったけど、君は変わらないよ。年齢よりも、ずっと若くみえる」
「そういってもらえると、少しは救われるかな」
それから彼女は、少しの間、沈黙した。ウェイトレスが亮介のアイスコーヒーを持って来たので、彼はストローを使わず、一口、口をつけた。窓から外を眺めると、駅から降りてきたらしい母親とまだ小さな男の子が一緒に歩いていた。男の子は何かを強請っているのか、母親のスカートの端を掴み、必死に訴えていた。響子ちゃんもそれを眺めていて、顔を向き合わせると、微かに笑った。
「彼は元気なのかしら?」
響子ちゃんは突然思い出したとでもいうように、話の方向を変えてきた。
「彼?」
「ミーコを貰ってくれた、亮介。…確か文則君っていったかしら」
彼は当然出るであろうその話題にまったく無防備であったことに気が付いた。知らないとでも言っておくかと思ったが、一寸考え、本当のことを言うことに決めた。
「文則は死んだんだ」
「えっ」
「文則は亡くなったんだ、高一の冬に…」
「そんな」
響子ちゃんは絶句した。
高校に入って、亮介と文則は段々と、付き合いをやめるようになっていった。いろいろとあったが、最大の理由は文則が一緒の学校になった横山と付き合い始め、暴走族のメンバーの一員になったからだった。文則は土曜日の夜になるたびに、召集をかけられ、暴走を繰り返した。両親の離婚が文則の不良化の根源にあったのかもしれない。それともすでに文則を同格に思っていた彼の存在に文則のプライドが許さなかったのかもしれない。亮介はそんな文則を見かねて、何度もメンバーから抜けることを進言したが、文則は何処吹く風で、彼のいうことを決して聞こうとしなかった。亮介は、自分の言うことに耳を貸さない文則の態度に腹が立ち、やがて二人は決裂し、彼は文則と二度と会うもんか、と思った。
文則が亡くなったのは、ジョン・レノンが亡くなったまさにその日だった。前日の夜半、抗争相手と派手な喧嘩を繰り広げ、旗持ちだった文則は、何人もの人間に、ターゲットにされ、鉄パイプで何度も殴りつけられたらしい。夜中の午前三時ごろに病院に運び込まれたときには、もう意識がなかった。文則は生命の糸が今にも途切れそうな中で、意識もない癖に何度も死にたくないと繰り返し、最後には静かな、本当に安らかな死を迎えたのだった。
亮介は高校の同級生、光から、文則がどのようにして亡くなったのかを知ったが、葬式に行くことも、線香をあげにいくこともしなかった。ただ、ひたすら悲しく、文則のいなくなった現実を呪った。実は最後だと思い、文則が抗争に向かうまさにその直前に、彼は文則に会った。しかし、文則は亮介の最後の忠告も聞かず、バイクを走らせ行ってしまった。そのとき一瞬振り向き、彼に対して向けた笑顔。それを思い浮かべると、俺に出来ることはなかったのだろうか?と何度も繰り返し、後悔した。文則を見捨てるべきではなかった。
それから、亮介は教師になることに決めた。教師になって、彼のような境遇の人間を一人でも無くしたい、そう思った。今、考えるとそれはまったく的外れなことなのだと思うのだが、そのときの亮介は真剣にそう思っていたのだ。
「いなくなっちゃったんだ、文則君…」
響子ちゃんは顔を伏せた。
「うん、いなくなっちゃったんだ」
「悲しいね」
「悲しいことだけど…もう、昔のことだよ」
「文則君がミーコを抱き上げたとき、ああ、この人優しい人なんだなって思ったわ」
「奴は、心優しい猫好きの寂しがりやだったな」
彼も響子ちゃんもしばらくの間、しんみりと文則のことを思った。あんまり、しんみりとしてしまったので、亮介はわざと話題をかえ、当たり障りのないことをこれでもかという位に彼女に披露した。亮介が教師になった頃のこと、今の生徒や親がいかに扱いづらいかとか、教師同士の軋轢だとか、終いには聞かれてもいないのに、自分が独身で、そろそろ結婚を考えなきゃなとか、ともかく思いつくこと全てを喋り続けた。
やがて、話題も尽き、それじゃ帰ろうかと腰を浮かせかけた時、彼女は、ねえ、あの場所行ってみない?と顔を上げた。
「あの場所って」
「亮介君と二人でよく歩いた場所」
「それって…土手の道」
「そう、久しぶりに歩いてみたいな、亮介君と」
二人は喫茶店を出て、土手のある方向へ歩いて行った。近隣の町にいながら、この十年間というもの、一度も土手の道を訪れることがなかった。土手の道はきっと様変わりしているだろうなと思った。
二人は、駅前から人通りの少ない道に外れ、昔の記憶を辿りながら、土手へと向う。途中、昔ミーコのいた空き地は何処だったかなと寄り道してみたが、家が立ち並び、それが何処だったのか分からなくなっていた。
そこから、また五分ほど歩いて、二人は土手の入り口に辿りついた。
土手の道はそれが当然だという風に、昔とそれ程変わりなく存在した。変わったことといったら、道が土ではなく、舗装されていたことくらいだ。
「舗装されたんだ」
響子ちゃんは少し驚いた風にして歩き始めた。
「中学までは毎日この道を歩いたもんだな」亮介も並んで歩く。
「うん、小学校の時は、登校班で、毎日亮介君と歩いたわ」
「テレビの話題ばかりだったな、俺達」
「あの頃はそれが楽しかったのよ」
「そうかな」
「そうよ」
「ねえ」
「何」
「この川ってこんなだったかな」
二人は、土手の階段を降りて、川原から川の流れを観察した。川の水量は昔より、かなり少なく感じ、このままでは干上がってしまうのではないかと思われた。それに空き缶やら、萎んだビニール袋やらごみがちらほら浮いている。
「これじゃ、困ったことになるね」
響子ちゃんは川を見て心配し、二人は、また土手の上に戻り、道を歩き始めた。
「昔は川も、もっときれいだったな」
「そうね」
「俺、川で泳いだ憶えがあるよ」
「そうなの?それは初耳」
「それ位きれいで豊富な水だったんだ。この川は…」
彼は川の流れを眺めながら歩き、あの頃のことを思い出していた。横山達がいて、文則もいて、俺たちは皆十三歳だったんだ。いろいろな個性を持つ彼らとの出来事が走馬灯のように彼の頭の中を巡った。高校時代の文則の死もあり、今は何処にいるのか、光という頼もしい女性徒の親友もいた。彼らとのことは、今では、懐かしい出来事として過去の産物となりつつある。しかし、それでも、あの頃の彼にとって、それらのこと一つ一つが大変なことで、悩み、苦しみ、日々をもがいて生きていたのだ。三十三歳になった亮介は様々な試練に揉まれ、経験していくうちに昔の辛い出来事を「懐かしい」といえるまでになった。それは彼が大人になったということなのだろうか。
歩き続け、ふと前の方に目を向けると橋が見えた。橋は相変わらず忙しそうに車が行き交っていた。陽は山に傾き、二人の影を大きく引き伸ばしていた。もう陽が沈む時間か、二人は歩みを止め、その方向を見た。
「…綺麗」
橋の向こうには南アルプスの山々が聳え立ち、夕陽が、茜色に照らし、その山の木々を一本一本までくっきりと浮かび上がらせていた。
「まるで、一枚の絵画のようだ」
亮介は思わず口に出し、響子ちゃんも、そうね、と賛同してくれた。
夕陽は沈みつつあり、残った光は夕焼け空をつくった。
「明日は晴れかな」
彼の問いに、
「きっと、晴れるわよ」
響子ちゃんはそう答えた。
亮介が響子ちゃんの方を見て、一瞬目が合うと、響子ちゃんはいたずら小僧のような目をして、私達恋人同士にみえるかしら、と、笑った。
彼は響子ちゃんのその問いには答えず、本当にそうなれるように、また前を向いて生きて行きたい、と心の中で呟いた。
それからまた夕焼け空と、山の向こうに隠れそうな夕陽を眺めている内に、記憶は夕陽色に染まっていくのだなと、思った。
弐 夕陽、その光
夢の中で、あいつが笑った。四00CCのバイクに乗って、こちらを振り返った。亮介は叫んだ。ばかやろう。
そこで目が覚めた。頭、いや、ここは、…首が痛い。
辺りを見回すと白灰色のコンクリート床が大きく広がっていた。その先の周囲は金網に囲まれている。天上は青い空。亮介は立ちあがる。学生服を脱ぎ、両手で掲げて服の背部分を見ると、薄く白墨のような砂に汚されているのに気づいた。それを叩き、ついでに尻も叩いてから再度学生服を着て腰を落とし、コンクリート床の上に胡坐をかいた。ここは?と思いしばし考えてみたら、学校の屋上であることを思い出した。俺はいつのまにか眠ってしまっていたのか、このコンクリートが広がるど真ん中に。こんなところでよく眠れたものだと思いながら、「あいつ」の夢を見てしまったことに胸が絞られるような思いがした。あれからもう十か月にもなるのか。
今はもう、四時限目の授業のはずだ。今日こそは真面目に授業に出ようと思っていた。が、それは果たせず、亮介が起床したのは朝の十時半で、一生懸命無駄な作業を省略し、自転車で三十分駆けて来て甲斐西高等学校の正門を通過したのは、十一時十五分頃だった。駐輪場に自転車を置いて、ゆっくり歩いても四時限目からではあるが、取りあえず授業に間に合ったはずだった。が、亮介は急にやる気が失せ、そのまま三階建ての校舎の屋上にまで来てしまったのだった。その後、いつのまにかこんな所で眠りこけた。傍らの黒い合成革鞄を凝視して、これを枕代わりにしてだよな、と思うとより首の重い痛みが酷くなったような気がして憂鬱感が満載になる。どこまでも青い空、柔らかな太陽の光が降り注ぐ十月なのに。
親友の文則との付き合いが縁遠くなってきたのは、高校に入ってからだった。亮介はこの進学高校に、文則は私立の大学付属高校へと昨年の四月にそれぞれ別れた。本当は同じ高校に通いたかった。そのために中三の初めから一緒に受験勉強を始めた。教師は文則にお前には無理だと言っていたという。でも、教師が断言するほど、文則の学力は悪いものではなかった。むしろ努力を続ければ、必ずや県内の進学校に合格するレベルにまで至ると亮介は確信していた。本人も亮介と同じ高校に通いたい気持ちから、いっちょやったるか、と気合を入れていた。それなのに生来の飽き性も手伝ってか、三か月も経つと気力もなくなり、やがて二人の共通の勉強場所である街の図書館に、文則はまったく来なくなった。亮介は何度か文則を説得しようと試みたが、彼はまったくその気はなくなったと応ずることはなかった。亮介は落胆したが、それで二人の仲がどうかなる、ということはなかった。学校ではいつもと変わりがなかったし、相変わらず休みの日には互いの家を行き来していたし、何よりも亮介らは高校が別々になっても親友であり続けることに決して疑いはしなかった。ただ、後々思い返してみて、もしかしたら文則はこのときの亮介に対して、複雑な思いがあったのかもしれないと考えるようになった。一緒に受験勉強をやろうと最初に持ち掛けたのは亮介だし、それについて主導権を握っていたのは亮介の方だったから。
中学二年生になった頃から亮介の身長は急激に伸び出し、三学期が終わる頃には学年一の身長を誇る文則とほぼ変わらない高さになった。それとともに筋肉も発達してゆき、男の身体を形作ったことによって、大きな自信が芽生え、文則が付いていなくても、あの横山達に対しての怯えも全くといっていいほどなくなり、逆に彼らの方が亮介を避けるようになった。だから亮介の中での文則は、もう盾になってもらう存在ではなく、互いに肩を並べる真の盟友のような関係になっていた。それは文則にとっても喜ばしいことであったに違いないが、一方でもう亮介に頼られなくなったことに、自分の存在への疑問と一抹の寂しさを感じていたのかもしれない。その後、二人の関係性の変化があったことで、例え文則が不得手な事柄で仕方がないことだとしても、どうしても「文則が亮介に頼る」というそれまでとは逆の構図が出来上がってしまう場合が多々あった。プライドの高い文則が複雑な感情を持ってしまうのは当然のことなのだと思う。
文則との関係で特にぎこちなさを感じ始めたのは、彼の両親の離婚が成立した後からだった。中学校の卒業式の後、文則は校門の前で左の口端を上げながら、亮介に向かって告げた。「俺は母親に付いていくことに決めたよ。N市に引っ越す」。猫のミーコはどうするんだ、と頭に浮かんだが、それについて文則は「猫たちは近所で飼いたい家があったんで、頼んだよ。ばあさんが一人で住んでいる家で、ミーコもその他の猫も纏めて面倒見てくれるってさ」と寂しげに語った。
それから亮介らは別々の高校へ進学していったが、それでも亮介は諦めず、最初のうちは休みの度に会うようにしていた。それが徐々に変わっていったのは亮介が彼のあの行動を許せなかったからだった。
四時限目の授業の終わりを告げるチャイム音が響いた。ここからは昼飯の時間だ。どうする?素知らぬ顔で教室にでも入っていくか。そう思ってみても亮介は動く気がしなかった。鞄を引き寄せ、中から弁当箱を出した。古新聞に包まれたそいつを、鞄を下敷きにして目前に置いた。あまり食う気がしない。
「亮介」
声がしたので後ろを振り返ると屋上への出入り口から、光がやってきた。左の腕に座布団を挟み、手にはピンクで可愛らしいランチボックスってやつを持ちながら。
「何故ここにいると分かった」
「だって亮介言ってたじゃん。俺がいないときには屋上にいるって」
「そんなこと言ったか」
「言った、絶対言った」
口を尖らせながら光は持っていた座布団を敷いて、亮介の前に膝を立てて体育座りをした。
バカ、パンツが見えるじゃねえかと思ったが、光の穿いているスカートは地面に触れそうなほど長かった。膝を立てても踝が露になる程度だ。さっそくランチボックスの蓋を開けようとしている光を見ながら、亮介は深い溜息を吐いた。彼女の髪の毛は黄色い、それに癖毛だ。大きな二重で瞳の色は普通の日本人よりずっと薄い。「限りなく透明に近いブラウンだ」と普段亮介は彼女をからかっていた。彼女の祖父がロシア人だということを何かの折に聞いた。
「昨日、一昨日と来ないもんだから熱出して寝てるって二宮に言っておいたよ」
「ああ、それで家にも連絡がなかったのか」
「感謝してよ。あたしは一週間前からどうもあんたの様子がおかしいと思ってたんだ。目が血走っていたしな」
「持つべきものは不良の友人、ってことか。サンキュウな」
「シバくぞ」
二宮は進学校には珍しく生徒の目線に立ってくれる女教師だ。〝眠れない〟、亮介は九月初めの面談で二宮に相談した。文則のことも、教師になりたいと考えていることも。恐らく彼女には何もかもお見通しなのだと思う。だから、光の嘘に気づいていても、敢えて無断欠席の亮介を見逃してくれた。大いに悩め。今はそれが一番いい解決策だと。
「食べないの?」
光は不思議そうに亮介の顔色を窺った。「食う食う」と頷き、亮介は掛けられているゴムを外して新聞紙を開いた。
光との出会いは、まるで少女漫画のようなシチュエーションだった。高校初めての授業が終了したあと、帰宅しようと向かった校舎裏の駐輪場で彼女は三人の男子生徒たちに絡まれていた。亮介は、面倒はごめんだなと思ったが、生憎彼らは亮介の自転車を引き出すのに必要な空間を占領していた。光は迫られ追い詰められたのか、その自転車の後ろ、金属で形作られた荷台に尻が触れていた。仕方がないので亮介は歩を進め、彼らの間に割って入るようにして男たちに顔を向け、なるべく自分の感情を読み取られないようにして彼らを睨んだ。
「自転車が出られない」
たったそれだけのことだったのだが、彼らより十センチは高い亮介に見下ろされて驚愕したのか、彼らは一瞬のうちに揃って逃げ出してしまった。それから後に残った光が亮介の前に来て頭を垂れようとしたので、そういうのに慣れていない亮介は、自転車も出さずにまるで逃げるように、その場をあとにしてしまったのだった。
そのときから、亮介、亮介と彼女はことあるごとに亮介に話しかけ、デートしない?と亮介を街中に誘うようになった。そんな光の馴れ馴れしさに亮介はどぎまぎし、不良少女のように派手な様相から、最初の内は無視を決め込んでいたのだが、真っ直ぐ亮介を見つめる光の積極さに、いつしか巻き込まれていき、やがて亮介は流れのままに彼女と付き合うようになった。付き合うといっても亮介のその想いは、恋ではなく親愛の情といったものだった。彼女の中性的な性格は、亮介には親しみを感じさせたが、恋になるにはもう一つ何かが必要だった。多分、光もそれを感じているはずで、一年以上、亮介らは恋だとか愛だとかは一切語らず、まるで男同士の友情のような絆で結ばれていた。
「午後からは授業に出るのか?」
太陽のひかりに晒されて、光の微妙に輝く瞳に見つめられて、亮介は心の中を見透かされるような気がした。
「出ないことにした」
「ここまで来ているのに?何するんだい」
「考えて考え抜く」
「変な奴」
光はそう笑い、また座布団を腕に挟み、空になったランチボックスを手に持って、屋上の場を去って行った。屋上はなにもないし、普通の生徒にはまずここへの用というものもない。つまり、もうここには誰も来ない。あとに残ったのは、近くの国道を走る車のエンジン音と、何気に聴こえる教室の騒めきだけだった。
文則―。
彼は優しい奴だった。優しいが故に、進んだ高校でも一緒になった横山なんかに引きずられた。
四月生まれだった文則は早速普通二輪の免許を取った。その内すぐにⅭB四00というバイクを乗り回すようになった文則を見るたびに、亮介はいいようのない胸騒ぎを覚えた。お前、まさか…、と尋ねると横山と一緒にレーシングチームに加入したと文則は俯いた。レーシングチームなんて嘘っぱちだ、暴走族だろうと亮介が迫ると彼は開き直って、ああそうだ、何が悪い、と亮介を睨んだ。たまたま、文則の家の近所だったという光を紹介しようと、彼女を連れだって行った土曜の夕方だったのだが、亮介は憤慨し、それからは段々と足が遠のいていった。
あれは昨年の十二月九日の夕方だったか。ジョン・レノンが殺害されたニュースが駆け巡っていた。前日、亮介は文則が所属しているというチームの所業が余りにも酷いとの噂を聞きつけて、居ても経ってもいられず文則の家に行った。亮介の文則への警告もこれが最後だと思ってのことだ。しかし、やはり頑固な彼は亮介の話も聞かず、その夜バイクに乗って出て行ってしまった。一瞬こちらを振り返り、亮介に向けて邪心のない笑顔を見せて。
光からの電話があって、亮介はきっとジョン・レノンのことだと思った。光はジョン・レノンのファンだったから。しかし、違った。受話器を通して聴こえた光の声は、近所の人から聞いたと前置きをしてから、亮介にとっては体を引きちぎられる様な悲しい事実を伝えたのだった。
悔やんでも悔やみきれない。十か月経った今はさすがに落ち着いたが、それでもまだその影響は時として表面化する。
カラス?
いつの間にか陽が傾き、一日の最終ラウンドを迎えつつあることに亮介は気が付いた。革鞄を手に立ち上がって、落下防止のための金網に向かい、片手を置いて地上の様子を眺めた。弱小野球部が練習をしている。ピッチャーが投げる。バッターは大きく空振り。外野は何を考えているのかグラウンドに胡坐をかいている。声もない。だから駄目なんだと思っていたら、轟音が響き、一台のバイクが入ってきたのが見えた。一旦、急ブレーキをかけて止まったと思ったら、エンジンを何度も噴かし、また動き出す。大きく旋回する。八の字を描く。息継ぐまもなくバリ音を轟かしていた。野球部が活動している場所からは離れているものの、その轟音と荒々しい運転に野球部の連中は慌てふためき、練習を中止して皆レフト側のベンチに引き上げてしまった。それに気をよくしたのかバイクはよりグラウンドを広く使い、なおも荒っぽい運転を続けた。亮介はバイクの車体に注視した。マフラーは曲線を描くような特別仕様。座席をタンクよりも沈むように設計されたあれは、如何にも暴走族を思わせた。馬鹿もんがと、怒りが沸々と湧き上がって来るのを感じながら、亮介はふとあのバイクに見覚えがあることに気が付いた。確か、文則の家の前で、だ。
あれは…横山なのか。
しばらくして、バイクが停止した。ノーヘルの頭がこちらを見上げるように傾いたときに亮介は確信した。紛れもなく横山。遠目でも分かった。
ふっと、また記憶が蘇った。
横山はあの時、文則を残して真っ先に逃げ出したと聞いた。卑怯者。
ああ、卑怯者、卑怯者、卑怯者、卑怯者、ひ・きょう・も・の。
亮介の怒りが熱く鉄を溶かすような激しいものに変わったとき、無性に体が震えた。抑えきれない。でも駄目だ、行っては。亮介の中の理性が必死に訴えかけている。しかし亮介は結局我慢が出来なかった。屋上から出、階段を駆け巡り、怒りそのままにグラウンドにまで駆けていってしまった。
よこやま―。
亮介の声が響き、バイクに乗りながらこちらを向いた横山は、そのまま急停車した。「ああ、亮介じゃねえか。久しぶりだねえ。丁度いい、待ってろ」
そう笑った横山はニ、三度エンジンを噴かし、今度は亮介に向かって一直線にバイクを走らせてきた。轟音が近づく。亮介はぎりぎりまで耐えてタイヤが触れる寸前で横に飛んだ。転がり制服が砂だらけになるなと思った。それからすぐに立ち上がり、奴はどうしたと確認した。バイクは離れたところに派手に倒れ、まるで何かに引きずられたように車体が白く砂まみれになっていた。前輪には亮介の黒い合成革鞄が見事に嵌り、スポークがぐにゃりと妙な形に変わっていた。後輪は未だ少し惰性で回っている。その近くで、跳ね上げられ落下した横山は、腰を打って起き上がれないようで、その部分を押さえ丸くなっていた。
それでも亮介の怒りは収まらなかった。亮介は今まさに横山に向かって突進せんと構えた。するとそのほんの一瞬のうちに、するりとか細い両の腕が、背中から亮介の腰に巻きつき、制服を強く掴んで亮介を抑えたのだ。誰だ。亮介は怒りの表情そのままで振り返った。果たして、亮介の目には薄いブラウンの目をした、不良娘の悲しそうな顔の表情が映った。…光……。光は必死に亮介に話しかけた。「駄目だよ。あたしが居たからよかったものの。あんた将来何になりたいんだい。思い出せよ。これ以上やったら多分あんた駄目になっちゃう。それでもやるっていうならあんたはどうしょうもないバカだ」
しかし、と思って亮介はまた前を向いた。光は亮介の脇の隙間から制服を掴んでいた右手を離し、前に出して、西方の一方向を指さした。
「見なよ。綺麗な夕焼けだ。こんな夕焼けを見てもまだ敵討ちをしたいのかい」
遠くに見える山々が薄い赤黄色に染まっている。太陽は今まさに奥の山に隠れる寸前だ。西の空には夕焼け。いつか見た夕焼け…。絵画のようなその風景を亮介は何処かで見たことがあった。あれはいつのことだっけ。
騒ぎを聞きつけ、二宮を始め何人かの教員が校舎から出て来た。
ああ、思い出した。いつも学校への行き帰りに歩いていた、あの土手。その道から見えるあの風景。思い出したよ。
それから亮介は光の腕を外し、教師たちが来る短い時間(とき)の中で、その美しい風景に魅入っていたのだった。
参 夕陽と彼と響子ちゃんと
駅前も変わったな。
亮介は、K町駅前に立ち、辺りを見回しながら、昔を懐かしんでいた。
あれから二十年が経ち、時代は昭和から平成へと移っていた。
亮介と文則は中学時代の横山との一件から、よりいっそう親交を深めていった。二人は傍から見ても、鬱陶しいほどいつも一緒に行動し、互いに信頼するまでになったのである。
それが変化したのは中学を卒業してからだった。亮介の両親が正式に離婚し、亮介は母方に引き取られ、K町から比較的近いN市に引っ越していった。彼らは、別々の高校に進み、最初の内はそれなりに行き来をしていたものの、徐々に縁遠くなっていった。
親友と思っていた文則と何故、離れていったのかは、文則の置かれた環境が変わったこともあるが、本当のところはもう一つの理由があったのだった。それは今にして思うと、「後悔」という二文字がついてくるのだが、あの時の亮介にはどうすることもできなかった。ただ、いえることは、彼らは別れるべくして別れ、亮介は文則とその後永遠に会えなくなったということだけだ。
高校を卒業して、彼は県外の大学の教育学部に進学した。四年間勉学とバイトに励み、教職の免許を取った。教師になることに両親は反対したが、亮介の姉だけは、あんたの経験したことが何処かで生きるに違いないと賛成してくれた。彼は地元の教員採用試験を受験し、晴れて念願の中学校の教師になることが出来た。
教師になってからは、無我夢中だった。登校拒否や虐め、家庭内暴力と様々な問題に直面し、その都度最良の選択を迫られ、なんとか解決らしき方向へと導き、それでも、これで良かったのか?と苦悩し続けた。教師になって十年というもの、亮介は常に神経をすり減らし、こんなはずではなかったと、精神が悲鳴を上げない日はなかった。
そんな時に、偶然中学生の時、団地から引っ越していった響子ちゃんに出会った。
響子ちゃんは教科書販売の会社に勤めていて、たまたま彼が勤めている中学校を営業で訪れていたところだった。
「…亮介くん?」
そう職員室で声を掛けられた時、亮介は一瞬誰なのだろうと疑った。だがすぐに変わらない清廉さに昔の面影を見、懐かしさで一杯になった。
「響子ちゃん?」
「うん、久しぶりだね」
「久しぶりなんてもんじゃない、二十年ぶりなのかな」
「引越しの時からだから、…そうね、もうその位になるのかもね」
響子ちゃんは、相変わらず優しさが香るような空気を纏っていた。目尻に笑い皴が目立つことと髪をショートにしていることを除けば、他はあの頃と変わりがない。彼が話を続けようとすると、ごめんなさい、今日商談があるの、と急いで自宅の電話番号を書き記したメモを亮介に渡し、電話頂戴ね、とその場から奥にある校長室へと消えていった。
それから数日の間、忙しさにかまけて、メモの存在を忘れていた彼は、たまたま寄ったコンビニでの支払いで財布を出した時、財布のカード入れの間にあるメモを見つけた。
あの時のメモか、と思い至りどうしょうか逡巡したが、明日が日曜日だということに気づき、ともかく電話を架けてみることにした。家の電話の受話器を取り、ナンバーをプッシュすると、数秒の呼出音の後響子ちゃんが直接出た。響子ちゃんは、待っていたのよと言い、明日K町駅前の喫茶店で会って話をしましょうと言った。午前中は用があるからというので、亮介は、それじゃあ、午後三時にと約束を交わし電話を切った。彼は、これはデートになるのだろうかと考えたが、すぐに彼女はもう人妻なんだろうなと思い直し、自分の考えの浅はかさを反省した。
次の日の日曜日、彼はK町駅前の喫茶店に向かった。
途中、一旦止まって時計を見た。午後三時にはなっていなかったが、多分響子ちゃんはもう待っているだろうなと思い、その先の道路を挟んで向かいにある喫茶店を目指した。
ドアを開けると日曜日だというのに、喫茶店の中は閑散としていた。隅に座っていた彼女は、彼をすばやく見つけると、ここよ、ここと大きく手を振った。
亮介が響子ちゃんの前に座ると、ウェイトレスが、注文を受けに来たので、響子ちゃんの前に飲みかけのアイスコーヒーが置いてあるのを見て、同じものを注文した。
「…ほんとに二十年ぶりね」
響子ちゃんは懐かしそうに彼の顔を眺めた。
「君は二十年経っても変わらない」
「すぐには分からなかった癖に」
「いきなりだったからね」
「ほんと、偶然。まさか亮介君が学校の先生になっていたなんてね」
「似合わない?」
「いいえ、ただ、私の中の亮介君は、大人しくてほんとに優しい男の子だったから。まさか人前に立つ職業に就くなんて思いもしなかったの」
「二十年経てば、人は変わるんだよ」
「そうね。年月は人を変えるものなのよね。…私だって色々あったもの」
彼女は遠い目をしていた。彼はそんな彼女を見て、以前こんなシチュエーションに出くわしたことがあるような気がしていた。それは何時のことだったのだろう。彼はしばし考えたが皆目検討がつかなかった。
「今何処に住んでるの」
彼女がそう訊いてきたので、彼は、A市だよ、あれから丁度俺が県外の大学に入学した年に引っ越したんだと答えた。彼女はそれを聞くと、私は一度県外に住んでいたのだけれど、またY市に戻ってきたのと話しながら、アイスコーヒーのグラスを手に取って、ストローで溶けかけた中の大きな氷を軽く突いた。Y市、ということを聞いて彼は自分が一番気になっていることを訊いてみようと思った。
「…・結婚は?」
「一度ね、結婚したわ。二十五の時…。それも三年で破局したけどね」
「それは、悪いことを聞いちゃったかな」
「いいえ、そんなことはないわ。私の中ではもうすでに終わったことなんだもの」
「強いんだな」
「そうよ、私は昔から、気の強いお転婆な女の子なのよ」
お転婆な女の子、と彼女が言ったところで、彼は思わず噴出してしまった。余りにもイメージとかけ離れているし、こんなに大きな女の子がいるわけがない。彼女は怒った風にして、そうよ、そうよね、私はもうおばさんよね、と口を尖らせた。
「ごめん、笑ったりして」
「いいのよ、もう私も三十四になるんだもの」
「さっきも言ったけど、君は変わらないよ。年齢よりも、ずっと若くみえる」
「そういってもらえると、少しは救われるかな」
それから彼女は、少しの間、沈黙した。ウェイトレスが亮介のアイスコーヒーを持って来たので、彼はストローを使わず、一口、口をつけた。窓から外を眺めると、駅から降りてきたらしい母親とまだ小さな男の子が一緒に歩いていた。男の子は何かを強請っているのか、母親のスカートの端を掴み、必死に訴えていた。響子ちゃんもそれを眺めていて、顔を向き合わせると、微かに笑った。
「彼は元気なのかしら?」
響子ちゃんは突然思い出したとでもいうように、話の方向を変えてきた。
「彼?」
「ミーコを貰ってくれた、亮介。…確か文則君っていったかしら」
彼は当然出るであろうその話題にまったく無防備であったことに気が付いた。知らないとでも言っておくかと思ったが、一寸考え、本当のことを言うことに決めた。
「文則は死んだんだ」
「えっ」
「文則は亡くなったんだ、高一の冬に…」
「そんな」
響子ちゃんは絶句した。
高校に入って、亮介と文則は段々と、付き合いをやめるようになっていった。いろいろとあったが、最大の理由は文則が一緒の学校になった横山と付き合い始め、暴走族のメンバーの一員になったからだった。文則は土曜日の夜になるたびに、召集をかけられ、暴走を繰り返した。両親の離婚が文則の不良化の根源にあったのかもしれない。それともすでに文則を同格に思っていた彼の存在に文則のプライドが許さなかったのかもしれない。亮介はそんな文則を見かねて、何度もメンバーから抜けることを進言したが、文則は何処吹く風で、彼のいうことを決して聞こうとしなかった。亮介は、自分の言うことに耳を貸さない文則の態度に腹が立ち、やがて二人は決裂し、彼は文則と二度と会うもんか、と思った。
文則が亡くなったのは、ジョン・レノンが亡くなったまさにその日だった。前日の夜半、抗争相手と派手な喧嘩を繰り広げ、旗持ちだった文則は、何人もの人間に、ターゲットにされ、鉄パイプで何度も殴りつけられたらしい。夜中の午前三時ごろに病院に運び込まれたときには、もう意識がなかった。文則は生命の糸が今にも途切れそうな中で、意識もない癖に何度も死にたくないと繰り返し、最後には静かな、本当に安らかな死を迎えたのだった。
亮介は高校の同級生、光から、文則がどのようにして亡くなったのかを知ったが、葬式に行くことも、線香をあげにいくこともしなかった。ただ、ひたすら悲しく、文則のいなくなった現実を呪った。実は最後だと思い、文則が抗争に向かうまさにその直前に、彼は文則に会った。しかし、文則は亮介の最後の忠告も聞かず、バイクを走らせ行ってしまった。そのとき一瞬振り向き、彼に対して向けた笑顔。それを思い浮かべると、俺に出来ることはなかったのだろうか?と何度も繰り返し、後悔した。文則を見捨てるべきではなかった。
それから、亮介は教師になることに決めた。教師になって、彼のような境遇の人間を一人でも無くしたい、そう思った。今、考えるとそれはまったく的外れなことなのだと思うのだが、そのときの亮介は真剣にそう思っていたのだ。
「いなくなっちゃったんだ、文則君…」
響子ちゃんは顔を伏せた。
「うん、いなくなっちゃったんだ」
「悲しいね」
「悲しいことだけど…もう、昔のことだよ」
「文則君がミーコを抱き上げたとき、ああ、この人優しい人なんだなって思ったわ」
「奴は、心優しい猫好きの寂しがりやだったな」
彼も響子ちゃんもしばらくの間、しんみりと文則のことを思った。あんまり、しんみりとしてしまったので、亮介はわざと話題をかえ、当たり障りのないことをこれでもかという位に彼女に披露した。亮介が教師になった頃のこと、今の生徒や親がいかに扱いづらいかとか、教師同士の軋轢だとか、終いには聞かれてもいないのに、自分が独身で、そろそろ結婚を考えなきゃなとか、ともかく思いつくこと全てを喋り続けた。
やがて、話題も尽き、それじゃ帰ろうかと腰を浮かせかけた時、彼女は、ねえ、あの場所行ってみない?と顔を上げた。
「あの場所って」
「亮介君と二人でよく歩いた場所」
「それって…土手の道」
「そう、久しぶりに歩いてみたいな、亮介君と」
二人は喫茶店を出て、土手のある方向へ歩いて行った。近隣の町にいながら、この十年間というもの、一度も土手の道を訪れることがなかった。土手の道はきっと様変わりしているだろうなと思った。
二人は、駅前から人通りの少ない道に外れ、昔の記憶を辿りながら、土手へと向う。途中、昔ミーコのいた空き地は何処だったかなと寄り道してみたが、家が立ち並び、それが何処だったのか分からなくなっていた。
そこから、また五分ほど歩いて、二人は土手の入り口に辿りついた。
土手の道はそれが当然だという風に、昔とそれ程変わりなく存在した。変わったことといったら、道が土ではなく、舗装されていたことくらいだ。
「舗装されたんだ」
響子ちゃんは少し驚いた風にして歩き始めた。
「中学までは毎日この道を歩いたもんだな」亮介も並んで歩く。
「うん、小学校の時は、登校班で、毎日亮介君と歩いたわ」
「テレビの話題ばかりだったな、俺達」
「あの頃はそれが楽しかったのよ」
「そうかな」
「そうよ」
「ねえ」
「何」
「この川ってこんなだったかな」
二人は、土手の階段を降りて、川原から川の流れを観察した。川の水量は昔より、かなり少なく感じ、このままでは干上がってしまうのではないかと思われた。それに空き缶やら、萎んだビニール袋やらごみがちらほら浮いている。
「これじゃ、困ったことになるね」
響子ちゃんは川を見て心配し、二人は、また土手の上に戻り、道を歩き始めた。
「昔は川も、もっときれいだったな」
「そうね」
「俺、川で泳いだ憶えがあるよ」
「そうなの?それは初耳」
「それ位きれいで豊富な水だったんだ。この川は…」
彼は川の流れを眺めながら歩き、あの頃のことを思い出していた。横山達がいて、文則もいて、俺たちは皆十三歳だったんだ。いろいろな個性を持つ彼らとの出来事が走馬灯のように彼の頭の中を巡った。高校時代の文則の死もあり、今は何処にいるのか、光という頼もしい女性徒の親友もいた。彼らとのことは、今では、懐かしい出来事として過去の産物となりつつある。しかし、それでも、あの頃の彼にとって、それらのこと一つ一つが大変なことで、悩み、苦しみ、日々をもがいて生きていたのだ。三十三歳になった亮介は様々な試練に揉まれ、経験していくうちに昔の辛い出来事を「懐かしい」といえるまでになった。それは彼が大人になったということなのだろうか。
歩き続け、ふと前の方に目を向けると橋が見えた。橋は相変わらず忙しそうに車が行き交っていた。陽は山に傾き、二人の影を大きく引き伸ばしていた。もう陽が沈む時間か、二人は歩みを止め、その方向を見た。
「…綺麗」
橋の向こうには南アルプスの山々が聳え立ち、夕陽が、茜色に照らし、その山の木々を一本一本までくっきりと浮かび上がらせていた。
「まるで、一枚の絵画のようだ」
亮介は思わず口に出し、響子ちゃんも、そうね、と賛同してくれた。
夕陽は沈みつつあり、残った光は夕焼け空をつくった。
「明日は晴れかな」
彼の問いに、
「きっと、晴れるわよ」
響子ちゃんはそう答えた。
亮介が響子ちゃんの方を見て、一瞬目が合うと、響子ちゃんはいたずら小僧のような目をして、私達恋人同士にみえるかしら、と、笑った。
彼は響子ちゃんのその問いには答えず、本当にそうなれるように、また前を向いて生きて行きたい、と心の中で呟いた。
それからまた夕焼け空と、山の向こうに隠れそうな夕陽を眺めている内に、記憶は夕陽色に染まっていくのだなと、思った。
















![アイナ・ジ・エンド - 帆 [Official Music Video]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/77/f5/92393401bdbc0a86905caa6f8f33ec10.jpg)
![アイナ・ジ・エンド - 帆 [Official Music Video]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/35/7c/21f0d773d7635daee13341c7a29e3a9f.jpg)


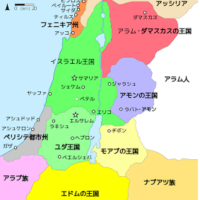







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます