Jo Boxers - Just Got Lucky (Official Video)
HAKU / Every breath you take cover
The Moody Blues - "Tuesday Afternoon" (Official Video)
佐藤千亜妃 - タイムマシーン(Music Video)
踊ろうマチルダ - 化け物が行く @ THE CAMP BOOK
佐藤千亜妃 - タイムマシーン。分かっている人もあろうけど、これは宇多田かおるさんへのリスペクトを込めて作られた曲です。
メロディやアレンジや歌詞などいたるところに宇多田ひかるがちりばめられています。
以下は以前書いたやつですが、題名を変えて加筆修正しました。よかったら読んでください。なお、コピペしたものなので段落とか一マスあけるとかおかしくなっていますが、ご容赦を。
記憶は夕陽色
響子ちゃんは亮介の隣で夕陽を眺めている。恋人同士に見えるかしら、という言葉を投げかけられたが、それに対して亮介は何も答えようとしなかった。ただ、心の中ではある誓いをたてた。―青の炎のような静かな情熱をもって。
亮介はこうやって夕陽を眺めていると、過去の事柄を懐かしむだけではなく、この夕陽は未来に向かって連続しているのではないかと想像する。時間がもしも円の軌跡を描くものであるとしたら、未来は即ち、過去にまた向かっていることになる。夕陽がその軌跡をなぞっているものだとしたら?
また、宇宙には様々な世界があって、同一の次元を持つパラレルワールドがあるという。それらが少しずつ互いに「時間のずれ」を生じさせながら、実はどこかで重なり合っている部分があるとしたら?
亮介は未来に、過去に、また別の世界でこの夕陽を眺めることになるのだろうか。
壱 夕陽の時代
もうこれが最後だと思っていた。しかし、文則はそれまで集金した金の流れを記録したB6サイズのノートを眺めながら、未だだと否定した。亮介がそんなはずはない、三千円にはなるはずだと反論すると、うるせえ未だと言ったら未だなんだよと、文則は語気を荒げて亮介を睨んだ。
「もう、十回以上はお前に渡したはずだ」
「いいや、九回だ。それに三千円には程遠いぜ。今回のやつと合わせて千八百円だ」
文則の言い分は嘘だと分かっていた。彼の言葉を信じれば、亮介は二百円ずつ九回しか払ってないことになる。でも亮介の記憶では一回の殆どが三百円で、もう十数回も彼に渡している。まさか千八百円ぽっちだなんて、そのようなことがあるはずがなかった。
「もう、限界だ。親にばれる」
亮介がそう訴えると文則は暴力的な目を向け、俺に逆らうのかというがごとく、ノートを乱暴に閉じた。
二人は文則の自宅の裏庭に居た。裏庭は雑草が鬱蒼と生い茂っていて、亮介の太腿に掻痒感が走る位無節操に天に向かって伸びていた。亮介が背中を預けている家の壁には窓が二つある。恐らく風呂と便所の窓である。どちらも人の気配がしない。誰か来てくれと、神仏に懇願している自分を想像してみても、誰も来る気配はしなかった。文則は一人っ子であり、両親は共働きで帰ってくるのが遅いといつか嘆いていた。誰もいないのかと亮介は諦めた。
「それなら、後三回だ」
文則は、渋っている亮介に対して業を煮やし、懐柔策に出た。
「百円ずつでいいぜ、あと三回で許してやる」
「本当に?」
「ああ、本当だ。百円ずつなら分らねえだろ。百円位なら、お前のお袋も何かに遣ったんだろう位にしか思わねえだろうからさ、お前も助かるってもんだ」
何がお前も助かるだと言い返したかったが、なにしろ身長百八十は裕にある巨体だ。逆らって勝てる相手ではなかった。
「本当だね。じゃあ、後三百円だ。でも約束は果たしてよ」
「ああ分かったよ、俺は言った事は守る主義だ、安心してくれ」
文則はそう胸を張ると、さっさとその場所から離れ、お前も早く帰れよ、クラスの連中に会うとまたやっかいだぜと言い残して家に入っていった。
帰り道、亮介は走って帰った。文則が言ったようにクラスの連中に遭遇してはいけない。
取り分けあのグループには。
亮介が酷い虐めを受けるようになったのは、小学校の高学年になってからだった。きっかけは「風呂」だ。
当時、昭和四十年代後半、亮介は町の西端に並ぶ公営団地に住んでいた。家族は両親に祖父、姉がいて、亮介を加えての五人家族だった。団地の部屋は六畳二間に四畳半と台所と、それなりの間取りではあったが、如何せん風呂がなく、亮介たち家族は週三、四回近くの銭湯に通っていた。
ある日、友人の一人が風呂に毎日入っていると聞いて驚いた。風呂というものは、そんなに入るものとは思っていなかったからである。えっ、と目を見開きながら、俺の家は一日置きだよ、思わず口にするとそこに居た級友達は皆声を揃えて、汚ね―、と声を揃えて囃し立てた。
当時の田舎はまだまだ農家が多く、しかもそれなりの資産をもっていたので、皆古かろうが継ぎ接ぎだらけであろうが、自分の家を持っていた。それに再開発が進み、新興住宅が建てられ始めていた時期で、そういった家には当然内風呂が存在し、住人は毎日風呂に入れる恩恵に与っていたのだ。
そのような環境の中、「週三」の亮介は疎外されない訳がなかった。
級友達の虐めは辛辣であった。亮介の机やノート等に落書きをするのは当り前で、集団で便所の個室に亮介を閉じ込め、頭上から水を浴びせ掛けたり、衆人の前で亮介のズボンをパンツごと引き摺り下ろしたり、終いには亮介を無視し出し、たまに話しかけてきても、亮介の目前で(南無阿弥陀仏)と手を合わせて焼香をする真似をする。亮介を同じ空気を吸っている、同じ人間としての扱いをしているようには到底思えない行為であった。
小五の時は何とか踏ん張ったが、小六になり事態が収まりそうもないことが分かると、亮介は次第に精神的に病むようになった。具合が悪いと事あるごとに親に告げ学校を休み、数々の病院を回った。医者は何れも原因不明とし、思春期の始まりにはよくあることですよと答えた。本当は、虐めが辛いんだよと亮介は告白したかったが、それでも決して亮介からそれを口にすることはなかった。疲れ果て精神は消耗し切っていたが、頑固なプライドだけは未だ残っていた。小六の一年間、亮介は殆ど学校に登校出来ず、それでもなんとか卒業することが出来た。
中学校に入学してからの亮介は、しばらくの間平穏な日々を過ごしていた。中学校は町内の各小学校からの寄せ集めで、クラスは効率よく分けられていた。亮介は同じクラスの中に虐めっ子達がいないことを確認し、ほっと肩を撫で下ろした。一学期の間は至って平和で、ああこんな日が来るとはとつくづく思った。
事態が暗転したのは夏休み後だった。クラスの男子生徒の一人、横山が、お前小学校殆ど行ってないんだってなと騒ぎ出したのだ。彼はクラスのリーダー格で、周囲に対する影響力を持ち合わせていた。それを聞くとクラスメイト達の亮介を見る目が変わっていった。二、三日もすると、皆亮介を汚いものでもみるような目で見、無視し始め、リーダー格の横山は何人かの生徒を引き連れて亮介を囲み、玩具を手に入れたとばかりに弄んだ。新たな虐めの始まりだった。
中学校での虐めは、それなりに我慢することは出来ると踏んでいた。どれくらい我慢すれば、最小限の被害で済むのか経験値で分かっていた。が、亮介はもうこれ以上我慢するのは真っ平御免だった。これからの中学生活を、まるで甲羅を背負った亀のように過ごさなければならないなんて、そんな辛いことはない。それでこの状況を打開しようと、頭を巡らし結論に至ったのが「文則と友人になること」だったのである。
文則は、孤高の存在だった。中一にして百八十を超える長身で、いつも眼球を不必要にぎらつかせ、横山も迂闊に手を出せなかった。彼は何故か私立のエスカレーター式の小学校から公立の中学に入学して来ており、そのせいで彼についての情報は誰も持ち合わせてはいなかった。そのせいか、彼に纏わる色々な噂、大きな暴力事件を起こして小六の殆どを少年院で過ごしていたとか、半殺しにされた相手はもう少しで死ぬところだったとかは半ば伝説化していて、話の真偽はともかく何人ともいえぬ恐れから、彼に話しかけるものは誰もいなかった。
亮介はそんな彼と友人となることで、「横山達に虐められる」という環境から脱却しようと考えたのである。
「文則君一寸いいかな」
亮介が文則にやっとの思いでそう話しかけることが出来たのは、九月の半ば近く、放課後二人きりになった時だった。亮介は文則が、いつも放課後最後まで教室に残っていることを知っていて、チャンスを窺がっていたのだ。恐怖心から、話しかける前にかなりの緊張を強いられ、胸の中に大きな鉛玉を抱えたように苦しかったが、勇気を振り絞って話しかけてみると、意外にすんなり言葉を発することが出来た。
文則はじろりと亮介を見たが、何だおまえかという顔をして、つまらなそうに亮介から視線を外した。亮介は構わず単刀直入に本題に入った。
「俺は今虐められているんだ」
頬が何だか火照っている。
すると文則は今更何を言い出すのかという顔をして、「だから?」と呟いた。
「俺を助けて欲しいんだ」
「助ける?」
「俺の友人になってくれればそれでいい」
「俺がお前の?はは、笑わせるじゃねえか」
「笑い事じゃなく本気なんだ。君が俺の友人になってくれれば、横山達は一切俺に手を出せなくなる」
「俺には全く関係のないことだ。おまえが何されようとな」
文則のつれない返答に、それでも亮介は諦め切れず、
「何でもする、何でもするから、頼むから友達になってほしい」心底から頭を下げた。
すると意外にもその言葉が効いたのか、文則はしばらく頭を下げた亮介を眺めながら、やがて薄く笑みを浮かべた。
「何でもするのか?」
「ああ、嘘は言わない」
文則は何かを考えているようだった。腕を組み亮介を凝視していたが、視線は亮介の身体を射抜き後ろの壁にまで到達していた。
「……五千円」と文則は呟いた。
「もし、五千円俺にくれるのなら、クラスが一緒の間はいつもお前の傍にいてやる」
そう言われて少し驚いたが、考えてみれば、彼と自分とを結び付けるには、そういった報酬のようなものが必要なのは当り前だと亮介は気がついた。
「五千円で本当にいいのか」
「ああ、無理なら別に構わない。この話はなかったことになる」
「分かった、五千円用意する」
当時の亮介は月に二千円の小遣いを親からもらっていた。事情を話し、残りの三千円はあとでもいいかと文則に訊くと、「分割払いにしてやる。ただし一ヶ月以内だ。金が五千円に達するまでは、俺はお前を守らない」と冷たく返された。
亮介は承諾し、それから毎日のように母親の財布から少しずつ小銭を抜き取る羽目になった。
ブラスチックで出来た、ぺこちゃん貯金箱を手にすると、亮介は底に嵌められた半透明の丸い蓋をそっと外し、貯金箱を軽く振った。すると開けられた小さな穴から、小銭と小さく折り畳められている紙幣が何枚か、じゃらじゃらと机上に滑り落ちてきて、亮介はその中から百円玉三枚だけをを手にし、残りは元に戻した。
四畳半の部屋は、亮介と姉の小夜子との共同の勉強部屋で、窓側に机が二つ縦に、合わさるようにして並べられていた。姉の机上の本立てには大学入試の問題集が何冊も立てかけてあり、ぺこちゃんの貯金箱はいつもその前に置かれていた。
姉が今にも帰ってきそうだったので、亮介は目的を果たすと蓋を嵌め、注意深くぺこちゃんを元通りの場所に置き、ごめんなさいと手を合わせた。その貯金箱は、姉が中学生の時から、大学受験の費用の足しになるようにと、少ない小遣いから少しずつ貯めてきたものなのだ。
それまで亮介は、母親の財布から小銭を抜いて来た。最初は気づいていないようだったが、何度もやる内に、さすがに何かおかしいと感づいたのだろう、母は亮介の行動を監視するようになった。亮介はこれ以上母の財布から金を抜き取ることは出来ないと判断し、姉の貯金箱からしばらくの間借りることにした。
ペコちゃんに謝った後、亮介は自分の机の椅子に座り、机の一番上の引き出しを引いて小銭を仕舞った。明日にでも文則に全て払ってしまおう、そう思い亮介は勉強部屋から出て行った。
その日の夕飯後、食卓のテーブルを挟んで姉と父は対峙していた。
「そんな話は聞いていない」
父は怒りを含んだ声を上げた。
「でも私決めたのよ」
姉は負けずに応酬した。
父と姉がこのように喧嘩するのを見たのは初めてのことだった。小さな頃から姉は、父に特別な存在として扱われて育ってきた。怒るなんてもっての外で、かわいいかわいいとお金が無いにもかかわらず、姉の望むものは何でも買ってやっていた。小さな頃亮介が何か物を強請ると、父は決まってお前は男だからと言い我慢させられた。アルバム一つにしても姉は六冊を数え、亮介は一冊しかなかった。彼女は事あるごとに父に写真を撮ってもらい、自分が育ってきた歴史を残してきたのだ。一度母に、自分は父の子ではないのではないかと訊いてみたことがあったが、母は、ばかねえ、そんなこと言うもんじゃないよと苦笑していた。
さすがに成長してくると、姉は自我が芽生え物を強請ることもなくなり、貯金をするようにもなったが、父にとっての姉は、愛おしい何物にも代えがたいものに変わりがなかった。
そんな父が、本気で姉に怒りの目を向けている。その時亮介は同じ部屋の隅にいて、事の成り行きに少しの不安と少しの期待を抱いていた。
「ともかく、私は東京の大学を受験するわ、それは中学校から決めていたことだし、変わることはないのよ」
「東京ってお前、地元の大学に進むんじゃないのか」
「私はここを出て行きたいのよ」
「出て行きたいだと。ここの何が不満なんだ」
「不満は無いわ。でもここに居たら私駄目になるわ、きっと」
「ふざけんな」
父は顔を真っ赤にして、握った拳をぶるぶると震わせていた。それを見た亮介はまるで、仁王様のようだと思った。
「東京に行くにしてもだ、学費や生活費はどうするんだ。東京に行くというなら、俺はびた一文として、出すつもりはないぞ」
「そう言うと思って、奨学金の手続きをしたわ、それにバイトをすれば何とかなると思うの」
「勝手にしろ」
なんだ、結局父さん折れているじゃないかと亮介はがっかりした。姉は、それじゃ私勉強するからと、さっさと四畳半の勉強部屋へと襖を引き入っていった。
「誰に育ててもらったと思ってるんだ」
父はテーブルをドンと拳で叩き、酒もってこいと台所にいる母に向かって叫んでいた。
それから亮介も勉強部屋へ直行することにした。父が酒を飲みだしたからだ。火の粉がこちらに降り懸らないともいえない。父は酒乱というほどではないが、酒を飲むととたんに人が変わり、傍にいる誰かれなくしつこいように絡む癖があった。姉に対する不満を亮介にぶちまけられても困る。亮介は逃げ出すようにして父を見捨てた。
「なんか用?」
ノックをして襖を開けると、机を前にした姉は不審者を見つけたような顔つきで亮介を見た。
「俺もマジやばいんで、逃げてきたよ」
「そう……またお酒?」
「うん」
亮介が返事をすると、仕方が無いわねという風に姉はふーっと溜息をついた。
「何で東京なの?」
亮介がそう訊くと、本当はね、と姉は喋り始めた。
「……本当は東京じゃなくてもいいのよ。ここ以外のどこか、ならね。親もいない、地元の友達にも会うこともない、人生一度リセットして、一人になって、一人で考えられる場所に住むって理想じゃない。そう思わない?」
姉の言っていることは、もっともだと思った。亮介も一人になりたいと何度も考えていたからだ。誰にも邪魔されない自分だけの世界。横山のことも文則のことも考えないで済む世界。亮介も人生一度リセットしてやり直せたらどんなに幸せかと思っていた。
「…そう出来たらいうことない」
「そうね、だからその為に、私はここから出て行くのよ」
姉の言葉には確固たる意志が込められていた。どんなことがあっても、折れることのない太く硬い意志。それは、どんな過程でつくられたのだろうか。そこまで考えた時姉は、でもね、と呟いた。
「何」
「うん、でも、一つだけ気がかりなことがあるのよ」
「気がかり」
「亮介、あんたのことが心配なの」
気づいていたのか、と思った。姉の「心配」という言葉は、まさに亮介が虐められいることに対して向けられたものだった。
「亮介、あんた虐められているんじゃない。お母さん、最近あんたが元気ないって言っているのよ」
「そんなことはない」
「いいえ、嘘いってもだめよ。私の目から見ても最近のあんたはおかしい。小学校の頃と一緒。目が虚ろで毎日を生きているのが精一杯って感じだよ」
小学生の頃、虐められていたことをいち早く気づいたのが姉だった。卒業文集に書き綴られた、「学校にも来ないのに、迷惑、消えて欲しい」という亮介に対して向けられた級友の一文に彼女は怒り、それを平然と載せた学校の担任に抗議をしにいった。それはまるで自分がそうされたかのような怒り方だった。
「姉ちゃん、俺のことは心配しなくてもいいよ。虐められてはいないし、元気がない訳でもない。…そうそう強いていえば勉強のことかな。ついていくのが大変なんだよ、時間があったら今度教えておくれよ。数学がさ、苦手なんだ」
姉はその亮介の言い訳に、小さく嘘っぱち…、と呟いてやがて亮介を無視するように机に向かった。亮介は机の前に腰掛けて教科書を広げ、勉強するふりをした。机の引き出しの中には三百円があった。姉ちゃんごめん、亮介は心の内で姉に謝り、土下座している自分を想像した。
上空を見上げると青い空が広がっていた。
白い太陽はまだまだ沈む気配はなく、亮介たちの世界の色を明確にしていた。キーンという音の後に、飛行機雲が、暢気に追いかけている。
「何余裕かましてんだよ」
何となく上空を見上げていた亮介を見て苛立ったのか、横山は語気を強めた。横山の他にあと二人いる。佐野と梶原だ。そこは学校の屋上だった。
放課後、横山ら三人に屋上へ来いと呼ばれた。屋上で何をされるのかは大体分かっていたが、逆らえばその場で、ズボンを引き摺り下ろされるか、プロレスごっと称して殴られるか、ともかく「虐め」と呼ばれる行為をされることは明白だった。亮介はなるべく衆人の前で辱めを受けたくなかったので、大人しくついていくことにした。
横山達は、亮介を連れて屋上に上がると、隅にある大きな浄水タンクの裏まで来て、ズボンのポケットから煙草とマッチを出し、火を点け煙草を吸った。
彼らが煙草を吸っている間、亮介は他にすることもないので上空を見ていた。その様子を見て横山は苛つき、怒声を亮介に浴びせたのだった。
「お前、生意気なんだよ」
横山は唾を吐く。
「死んじまえ」とも。
その言葉に、さあいよいよ始まるか、と亮介は覚悟し、全身に力を込めた。
「やれ」
横山の合図とともに、佐野は後方に回って、亮介を羽交い絞めにし、もう一人の梶原が亮介の前方に立った。
梶原は、にやりと醜悪に笑い、舌なめずりをすると、亮介のワイシャツのボタンを一つずつ外していった。ボタンを一通り外し終えると、今度は現れた下着を亮介の首の辺りまで捲り挙げた。
亮介が何とかしてすり抜けようと身体を左右に揺さぶると、
「さあて、楽しいショーの始まりだ」
横山はそう口にし、火の点いた煙草を手にして亮介に接近した。
「一度やってみたかった」
横山が残忍な笑みを浮かべた瞬間、脇腹に熱い痛みを感じて亮介は呻き声を上げた。
ちりちり、と肉が焼けるときのものなのか、煙草自身が発するものなのか分からない音がした。熱く抉るような痛みが脇腹に走る。亮介は痛みで気を失いそうになった。
横山は煙草の先を亮介の脇腹に押し付けていたのだ。
それから何度も横山から同じ行為を受けたが、その都度同じ表情とアクションを繰り返す亮介に飽きたのか、横山は、つまらねえと呟き、最後に煙草に火を点けたはいいが、それを一、二回吸っただけで、まだ十分な長さのあるまま地面に落とし、踵で踏み潰してしまった。
「それじゃあ、俺にやらせろよ」
佐野が羽交い絞めにした手を緩めると、亮介は膝から崩れ、そのまま地面に仰向けになった。もうどうなってもよかった。亮介は脇腹を押さえ、やけくそになっている自分に気づき、微かに笑っていた。
「おいこいつ、笑ってやがる」
「気持ち悪いなあ」
「マゾなんじゃねえか、こいつ」
亮介を見下ろし、横山達は、亮介の身体に軽く蹴りを入れていたが、やがて抵抗もしない亮介の態度に興ざめし、帰るぞとその場から去って行った。
仰向けになったまましばらく空を眺めていると、渡り鳥らしい三角に編隊した大群が北から南の山向こうへと消えていった。
鳥になりたい、亮介はそう独りごち、すると涙がとめどなく頬を伝いどうしょうもなくなった。脇腹の痛みは、そこだけ脈打つような重い痛みに変わっていた。
脇腹にじりじりする痛みを抱えながら土手の道を歩いていた。土手の道は亮介が小学校から慣れ親しんだ道だった。大通りを通って帰る方法もあったのだが、こちらのほうが、学校の行き帰りには近いので、団地に住んでいる殆どの生徒が土手の道を利用していた。
片側には大きな川が流れ、もう片側には雑多で背の高い草がこちらに向かってくるように生茂っていた。前日、大量の雨が降ったせいか川の水量は多い。何とはなしに、筏に乗って川を下っていく自分を想像して、少しだけ楽しい気分になった。
帰りに文則の家に寄って、三百円渡そうか迷っていたが、脇腹の痛みが酷く少し熱を感じた亮介はそのまま家に帰ることに決めた。前方をみると川を渡す橋が見え、その上を車が何台も右へ左へと行き交っていた。橋の向こうには山が聳え立ち茜色の夕陽が沈みかけると、山の稜線をくっきりと浮かび上がらせていた。
そんな景色に少なからず何かを感じ足を止めていたら、後ろから誰かに声を掛けられた。振り向くと、響子ちゃんが立っていて、はあはあ、と息を切らせていた。
「さっきから、声を掛けていたのに、亮介君気づかずに、どんどん行ってしまうんだもの」
「ごめん、気づかなかった」
「何を見ていたの」
響子ちゃんの言葉に、あれだよ、と山の方角を指差した。
「ああ、なんて綺麗な茜色…」
響子ちゃんは、顔を紅潮させながら目を細めた。
響子ちゃんとは、同じ団地に住んでいる間柄だった。棟は違ったが、小学生の頃、登校班が一緒だったこともあり、よく二人で砂埃の立つ土手の道を通いながら、昨日見たテレビの話などをしていたものだ。彼女は優しく亮介の憧れの娘だった。彼女は亮介よりも学年がひとつ上で、亮介が六年生になると一足先に中学生になった。その後彼女とは接点がなくなったが、今思うと亮介が小学校に行かなくなった理由の一つには彼女がいなくなったことによるショックもあったに違いない。
「今、部活の帰りなの」
「そうよ、陸上部は厳しいのよ、帰宅部くんとはちがうのよ」
「帰宅部って、これでも一応新聞部だぜ、…まあ、もっともこれといった活動はしてないけどさ」
亮介たちは並んで歩き始めた。セーラー服の彼女は、地味だけど、時折見せる笑顔がとても魅力的だった。瞳は薄茶色で、髪はみつあみにしていた。清楚という言葉がぴったり当てはまる彼女だった。
「あのね」
「何」
「まだ、来年のことだけどね、うちね、引っ越すことになったの」
「えっ、そうなんだ」
唐突な彼女の告白に、亮介は驚きを禁じえなかった。
「そ、それで何処に引っ越すの」
「Y市に引っ越すのよ。今、家を新築しているの。完成予定が二月の予定かな。だから今の中学とも、来年の三月でバイバイだね」
「…」
亮介は、大きなショックを受けた。いくらなんでも、そんな。…今日、響子ちゃんに出会わなければよかった。会話を交わしたのは小学校以来で、中学校に入ってからは初めてのことである。久しぶりに会って話した結果がこれだなんて…。これが最後の会話になるのかもしれない。引越し迄亮介と響子ちゃんは結局話す機会もなく、彼女は何年か住み慣れ親しんだ団地を去るのである。来年には姉も家を出て行く。そう思うと、なんだかひとり取り残されるようで亮介はいっそう悲しくなった。
「寂しくなるな」
亮介はそう言うのが精一杯だった。
それから響子ちゃんは団地に着くまで他愛無い話を亮介に向けてきたが、亮介の方は、はいとかうん、だとか言って、適当に答えていた。
「じゃあね、さよなら」
団地の前で二人は別れた。三階建ての団地群は古く、夕闇の中で亮介と響子ちゃんをかこんでいる妖怪達の群れのように見えた。亮介は、響子ちゃんが、妖怪の口の中に消えていくのを確認すると、あーあ食われちまった、と微かに呟き、しばらくの間そこに立ち尽くしていた。
家に帰ると、亮介は居間の箪笥の上にある薬箱を下ろした。それから薬箱の蓋を開け軟膏を取り出す。脇腹は相変わらずじんとして熱く、痛みがあった。祖父が六畳の部屋から出てきて、怪訝そうな顔で亮介の方を見ていたので、工作で指切ったんだと言って、箪笥から着替えも持ち出し祖父の前をするりと抜け、姉のいない四畳半の襖を引いた。襖を閉め部屋に入り、外の様子をうかがったが誰も来ないと悟り、亮介は自分の机の椅子に腰掛け、ふうと溜息をついた。それから思い切ってシャツを全部脱ぎ捨て、脇腹の状態を確認した。煙草を押し付けられた跡は四箇所あった。四つとも皮膚を破られた中央に赤い肉片が現われ、周囲は焼け焦げたような盛り上がりを見せている。亮介は、やれやれこれは跡に残るだろうな、と思い落胆した。下着にも点々と血の跡が付着している。亮介はそれを放りなげ、傷口に軟膏を塗りたくった。
軟膏を塗って一息付いたあと立ち上がり、もう一度血の付いた下着を手に取り、どうしようかと思案した。本当はその日の下着は、台所脇にある青色の篭の中に放り込んでおくのが常だったが、母が洗濯するときに気づくに違いないなかった。気づけば母は亮介を問い詰めない訳にはいかない。厄介ごとはごめんだと思い、亮介は机脇の大きい方の引き出しに下着を放り込んだ。誰もいないときに持ち出して、何処かに捨てにいけばいい。一瞬いい考えだと自賛したがすぐに憂鬱になり、自分の現状を呪った。横山とのこと、文則とのこと、今日会った響子ちゃんとのこと、いろいろなことが、亮介の頭の中で旋回し、落ちて行く。ざまあねえわな、亮介は呟き、天上を仰ぎ、必死に涙を堪えようとした。亮介は今日何回泣いただろうと恥じ、涙の跡が残らないように注意深く手の甲で拭い、それから着替えを済まして勉強部屋から出ていった。
夕飯時に父の姿はなかった。どうしたのかと母に尋ねると、父さんは管理職だから大変なのよと仕方なさそうな顔をした。姉は無言で食事を済ませ、母が何かを言いたそうにしているのを尻目に、さっさと勉強部屋へと消えていった。それから亮介は姉以外の自分を含め、四人の寝室となる六畳の部屋へと入り、祖父が個人的に購入したサンヨーのパーソナルテレビのスイッチを点け、水戸黄門を見ていると祖父が後から入って来た。
「水戸光圀か・・」
亮介の隣に座ると祖父は何とはなしに呟いた。
テレビでは、助さんと格さんが悪代官の手下を相手に立ち回りを繰り広げている最中だった。
「光圀が各地を漫遊したのは、物語の中だけの話なんだ」
祖父は亮介の方を向く。
「へえ」
亮介が、そう返事を返すと、祖父は得意げな顔をして話し始めた。
「光圀が名君だったのは本当のことだが、実際は江戸と鎌倉にしか行ったことがないんだよ。物語の元になったのは、当時の人気戯作者の十返舎一九の(東海道中膝栗毛)らしいな。それを参考にして講談師が(水戸黄門漫遊記)なるものを創作したということだ」
祖父がそう話しているのに、胡坐をかき、うんうんと生返事をしてテレビの画面を眺めていた。各さんが葵の御紋の入った印籠を出し、お決まりの、この紋所が目にはいらぬかと悪者達を平伏させていた。その瞬間亮介の中にも、妙な優越感が生まれた。亮介が印籠を出し、横山達が、亮介に平伏す姿を想像して痛快な気分になった。それから畳の上に後ろ手をつき、体勢を少し斜めに捻った。すると脇腹に引きつるような痛みが走った。いててと思わず口に出すと、祖父がこちらを見ているのが分かった。
「どこか、怪我してるのか、お前」
「いいや、ちょっと体勢を崩して腰を捻っただけさ」
「それにしては辛そうな顔をしているぞ」
「何でもない、何でもないよ」
亮介がそう言うと祖父は、何でもないねえと訝りながらも、それ以上何も言ってはこなかった。
テレビに目をやると黄門様が、カッカッカーと笑っている。
明日だ。明日で亮介は「文則」という印籠を手にすることになり、横山達は現実に、亮介に対して平伏することになる。亮介は、彼らが自分に向かって土下座している姿を想像して、微かに笑った。
ねえ、亮介、亮介ったら…。
亮介が朝歯磨きをしていると、姉の小夜子がそう言って、便所脇の小さな洗面所に飛び込んできた。何騒いでるんだ、と驚いた顔をして姉の方を見遣ると、何やら事件が勃発したらしい。亮介が、なんだい、と勤めて冷静に訊くと、いつからあんたらそんな仲になったのよ、と亮介を問い詰めた。
「そんな仲って?」
「だから響子ちゃんよ、響子ちゃん、あんたを迎えに来てるのよ」
「えっ?」
「だ・か・ら、今、玄関口に居るのよ」
姉は目を丸くしながら息急き切った。
亮介は、一瞬、その意味が分からず、しばらく姉の言った言葉を反芻していたが、やがて事の重大さに気づき、慌てた。響子ちゃんが来てるって?何故?ともかく亮介は、待たせてはいけないと歯磨きもそこそこに、急いで制服に着替え、ショルダーの鞄を肩に掛け、玄関口に出た。
響子ちゃんは少し俯き加減にお早う、と亮介に言い、それから紅潮した顔を上げると一緒に学校に行かない?と亮介を誘った。どうやら姉と亮介の会話は筒抜けだったようだ。
「じゃあ、俺もう出かけるから」
亮介が奥にいるはずの母に向かって叫ぶと、姉がしゃしゃり出て来て、いってらっしゃい、お元気で、と訳の分からない言葉を投げかけ亮介たちを見送った。
亮介たちは、小学校の時そうであったように、並んで歩いていった。朝の空気は冷たく、時折頬を削り取るような激しい突風が吹いた。土手に差し掛かるまで、亮介たちは互いに沈黙を守っていた。
亮介と響子ちゃんがこうやって一緒に歩くのは、あの日以来凡そ二か月ぶりのことだった。
「迷惑だったかな?」
土手の道を歩きながら響子ちゃんは小首を傾ける。
「いいや、そんなことはない」
「よかった…」
響子ちゃんは呟いた。
「朝、こうやって登校するのも小学校以来だね」
「そういえば、そうかあ」
それよりも今日は、突然またどうしてと思い、亮介は疑問をそのまま口にした。
「それで、今日はどうして」
「ほんとは前に話しておくべきだったのだけれど…お願いがあるのよ」
「お願い」
「そう、お願い…」
「お願いってなに」
「うん、もう少し、もう少し歩けば分かるわ」
亮介たちは砂埃の舞う土手道を渡りきり、学校へ向かうのとは違う道の角を曲がった。亮介が学校はこっちだよ、と学校の方向を指差していると、彼女は少し寄り道するの、と空き地が点在する方角に亮介を誘い、ここよと行き止まりになった先の空き地に入っていった。空き地は草木も枯れ、中央に大きな土管が何本か積まれていた。響子ちゃんはそこまで来ると、中腰になり、その中の一本の土管の穴を覗き込み、両手を穴の中に差し伸べ、やがて小さな猫を抱き上げた。
亮介が近づいても、猫はぴくりとも動かず、気持ち良さそうに響子ちゃんの胸に抱かれていた。典型的な茶色の縞々のある猫で、近くで見ると、肋骨が心なしか、浮いているような気がした。抱いてみる?と、響子ちゃんに訊かれ、彼女から手渡しされ、抱いてみると、猫はミャーンと一鳴きして、亮介をその大きな瞳で一瞥し、腕の中で丸くなった。
「この猫、名前は?」
「メスだから、ミーコ」
「ここにいたの」
「そう、ここで半年前に見つけたの。夕方ね、部活の帰りにね、どこからか、猫の声がすると思って、偶然ここまできてみたら、彼女が顔をだしていたの…この穴から」
亮介は再度ミーコと呼ばれるその猫を観察してみた。所々毛が禿げている、栄養不良のためか子猫と見間違うほど、小さい、それから彼女の後ろ足、右足だが、妙に不自然に内側に湾曲していた。
亮介がそれをしげしげと眺めていることに気づき、響子ちゃんは、
「車に撥ねられたみたいね、骨が折れてそのままにしていたから、不自然に曲がっちゃったのかしら。彼女はその為、行動範囲が狭まってしまっているの」
ああ、それでね、と亮介が理解すると、ミーコはまた亮介を見つめて、ミャーと鳴いた。
「それで、ミーコを俺に任せたいってことかい」
亮介は先回りした。
「そうしてもらえたら、嬉しいんだけど。私は、年が変われば直に引っ越さなければならない。連れて行ければいいのだけれど、母にそれとなく相談したら反対されたわ。このコは足のせいで、自分の食料さえも確保できないの。私がいなくなった後、餌だけでも与えてもらえればそれでいいのよ。ねえ、お願い出来るかな」
彼女は顔の前で手を合わせ、まるで後がないといったように懇願した。
響子ちゃんの申し出に亮介は戸惑った。亮介に猫を世話する甲斐性があるとは、到底思えなかった。かといって響子ちゃんの必死の願いを、無闇に断る勇気はなかった。亮介は、何かいい解決策はないかと逡巡した。
「駄目よね、当り前だわ、亮介君、優しいから、もしかして、って思ったの。ごめんね、悩ませたりして」
響子ちゃんは亮介が逡巡している様子をみて、前言を撤回した。
「待って、結局はミーコを世話する人が現われればいいんだよね」
「それは、私も友達に当たってみたの…でも、ミーコの足のこともあって、誰も見向きもしなかったの」
「ともかく、俺が何とかしてみるよ」
亮介は笑いながら、あいつなら、と思っていた。あいつならきっと、ミーコを喜んで引き受けてくれるに違いない。心配しないで、何とかなるから、響子ちゃん。
突風が幾つかの小さなつむじ風をつくり、枯葉を舞い上がらせていた。
亮介はもう冬なんだなと、片手でミーコを抱き、もう一方の手を制服のポケットに突っ込んだ。
「俺に猫を引き取れだと」
文則は、大きな声を教室内に響き渡らせた。
横山達は、その声に驚き、忌々しげにこちらを見ている。
亮介は文則を、凡そ二か月前に「友達」として雇い、それから何時も行動を共にするようになった。金で「友達」を雇うなんて不純な行為ではあったが、彼と行動を共にすると、横山達は面白いように亮介から手を引き、その後、亮介は「虐め」とは無縁の日々を送っていた。やはり彼らにとって、文則は恐怖の対象なのだ。
偽りの友達から始めた付き合いだったが、付き合う内に、亮介は文則の意外な一面を見ることになった。カレーライスとラーメンに目がないこと、お人好しなところがあり、一人が決して好きな訳ではなく、本当は人一倍の寂しがりやであること、そして動物が大好きで、無類の猫好きであること。亮介は初めて彼の家に招き入れてもらったときの事を思い出していた。
「さあ、入れよ」
文則は恥ずかしそうに俯いて、自分の家に入るように亮介を促した。
「いいのか」
「いいっていってるじゃねえか、それに誰もいねえよ」
「分かった、じゃあ、お邪魔します」
上がり框に足を掛けると、猫が一匹寄って来て亮介の足に纏わりついてきた。
亮介が吃驚して見ていると、文則は、猫が好きなんだ、とその猫を抱きかかえ、亮介を二階へと案内した。
猫は、二階の文則の部屋にも何匹かたむろし、亮介たちの周りを行ったり来たりしていた。その内、文則が餌だぞとキャットフードを何皿かに分けて出すと、猫たちは一斉に飛びつきがつがつと旨そうに食べ始めた。それからその猫たちの様子を眺めている亮介に対して文則は、お前の五千円、こいつらの餌代で消えちまった、と嬉しそうに笑った。
その笑顔を見た時から亮介は、文則を少し見直すようになった。彼は悪ぶってはいたが、本当は、心根の優しい人間なんだなと思った。五千円を奪われた相手を何故、そう思えたのかは分からない。ただ、屈託のない彼の笑顔は何の混じりけのないものに思えたのだった。
「で、その猫は何処にいるんだ」
文則は、話にのってきた。
「三丁目の空き地だ、そこの土管の中にいる」
「土管の中?それはまた酔狂なところにいるんだな」
「後ろ足が不自由なんだよ、その足のせいでそいつは動ける範囲が知れているんだ」
「一度、俺をそこへ連れてけよ。引き取るのは可能だが、その前に見ておきたい」
「分かった。今まで世話してた人がいるんで、その人立会いでいいかい」
「そいつは何処の誰なんだ」
「女性だ。俺と同じ団地に住んでる一年上の先輩だ」
女か…、そいつはおまえのこれなのか、と文則は小指を立てるまねをした。亮介が、違う違う、同じ団地に住んでいるだけだと言うと、文則はそうだよな、根暗のお前に彼女なんてできるはずがねえ、と大きく笑った。
亮介はこいつってこんな楽しそうに笑うような奴だっけ?と思ったが、まあいいや、ともかく彼女に急いで知らせなきゃと、昼休みに文則を連れて二年生の教室に響子ちゃんを訪ねていった。
響子ちゃんは、文則を前にして、余りの威圧感に一瞬たじろいだが、オッス、自分文則って言いますよろしくッス、と何時にもなく硬く挨拶する文則に好感を持ったのか、相好を崩し、じゃあ放課後校門前で待っててね、と約束をしてくれた。教室へ戻る道すがら、文則は彼女は天使だ、運命の出会いだと逆上せ上がり、亮介はまあまあと宥めるのに苦労した。
放課後になり、さっそく亮介たち三人は空き地へと向かって行った。
土管の前まで来て、文則が猫は何処に居るんだと訊いてきたので、そこだと中央の土管を指差すと、彼は大きな身体をこれでもかという位に屈めて、土管の中に手を伸ばし猫のミーコを抱き上げた。それからしばらくの間、彼はミーコの様子を観察し、何やら反応を確かめ終えると、これはまずいな、と呟いた。
「何がまずいのかしら」
響子ちゃんが訊ねると、
「こいつ、目が見えてないんだ」
と文則は返答した。
まさか目まで見えないと思っていなかった亮介たちは、驚きを隠しきれなかった。
「事故のせいかしら」
「分からねえ、ほら、こうやって人差指を左右に振っても何の反応もないんだ。こいつの目が不自由な証拠さ」
「じゃあ、引き取ってもらえない」
「いいや、逆にこいつは、足も悪いし、然る場所で誰かに世話してもらわないと生きられねえ。あんたが餌をやっていたにしろ、よくまあ、こんな土管の中で生き続けていられたもんだ」
「それじゃあ…」
「うん、俺が面倒みるよ」
文則がそう答えると、響子ちゃんは安堵し、良かったと笑顔を見せ、その瞳は少し潤んでいるように見えた。
亮介が文則に、男だねえというと、当たりめえだろうと文則は返してきた。
ミーコはというと、文則の大きな身体に抱かれてとても気持ちよさそうにしていた。
ミーコはこうして文則の飼い猫の一員として迎えられたのだった。
ミャーン。
猫のミーコが不自由そうに、ひょこひょこと近づき、胡坐をかいた中央の空間に滑り込もうとしていたので、亮介は彼女をそっと両手で抱えて、その空間に置いた。居場所を確保した彼女の大きな目はこちらの方を向いている。彼女の目は、こちらをじっと見つめているようにも思え、人差指を彼女の目の前で左右に振って見せたが、反応をみせないのでやはり見えないのかと亮介は溜息をついた。
文則の部屋は、散らかっていた。脱ぎっぱなしの服や靴下、読んだまま放り出してある漫画雑誌、炬燵の上に転がっているカップヌードルの殻、ジュースの空き缶、そして、我が物顔であちこち行き来している猫たちはジュース缶を倒したりしている。どうしたらこんな状態になるのか不思議だった。
亮介が、文則に親は何にも言わないのかと訊ねると、文則は読んでいた漫画雑誌から顔をあげ、親、今いないからと答えた。
「親がいないって、どういうことだ」
亮介がそう不思議そうに訊ねると、
「親父もお袋も、この家には一週間に一回しか戻ってこねえよ。俺はいつも一人だ」
と文則はやけくそ気味に笑った。
「一週間に一回?」
亮介が理解できないといった顔をしていると、文則は仕方がないといったように話し始めた。
「ああ、別居中っていうのかな、ともかく二人は一瞬たりとも同じ家で同じ空気を吸ってられないらしくてな、それで出て行っちまって、二人とも自分の(いいひと)の所にいるよ。今じゃ、一週間に一回俺の様子を見に来るだけさ」
「それじゃ、お前一人でこの家に住んでるようなものじゃないか。食事なんかどうしている?お前一人じゃどうにもならんだろう」
「たまに二人から、これでいろんな支払いを済ませなさいって、金をもらっているよ。支払いを済ました残りでパンや弁当を買って、食っている。金はこいつらの餌も買ったりしているから、何時もピーピーだな」
「どちらかについて行くって考えはないのか」
「俺はどちらの味方もしねえよ、俺は自分の意志でここにいるんだ。もっとも親父もお袋も二人とも、俺を引き取りたくないんで、本当のところは俺が見捨てられたっていうのが事実だがな」
「そんな…」
亮介は絶句した。これまで、何度か文則の家を訪ねてきたが、そんなことになっていたなんて思いもしなかった。文則はいたって普通のことのように話していたが、それがどんなに辛いことか。家に帰っても誰もいない、食事も何もかも自分ひとりで済ます日々、亮介は一時期一人になりたいと思っていたが、今では一人でいることは辛い、そう思うようになっていた。文則は一人でいることが苦痛ではないのか。
「だからって、俺を哀れむんじゃねえぞ、猫たちもいるし、俺は今の状況が結構気に入ってるんだ」
文則はそう言うと、漫画雑誌に再び目を戻し、もうこれ以上話さないとばかりに無口になった。
文則が買出しに行くというので、亮介も帰ることにした。
駅前のスーパーの前で文則と別れて、一人になった。一人になると急になんともいえない不安が亮介を襲った。不安は亮介の胸の中で暗雲となって広がり、亮介の胸を一杯にした。
文則はこれからもひとりで生活していくのだろうか。でも、いずれはその生活は崩壊する。あんな生活が何時までも許されるはずがない。きっと彼は父親ではなく、母親の方に引き取られるに違いない。彼のまだ十三歳という年齢を考慮すると、その可能性が高いのだ。母親に引き取られることになった彼は、転校を余儀なくされ、支えを失った亮介や猫達は行き場を失うことになる。最悪だ。けれど…。
そのようなことを考えながら、橋の袂に差し掛かった。ふと土手の下の川原に目をむけると、何人かの人間がたむろしている。彼らは川原から亮介を目ざとく見つけ、急勾配の土手坂を急いで登りきると亮介の前に立ち、道を塞いだ。
横山達だった。
「よお、亮介くんじゃないの、今日は一人かい。ボディガードくんはいないんだ」
横山達はいやらしい笑みを浮かべていた。
「ボディガード?」
「惚けんじゃねえ。文則のことだよ」
「あいつは別に俺の用心棒じゃないよ。唯の友達だ」
亮介が構わず彼らの間をすり抜けようとすると、横山は亮介の肩に手を掛け、待てよ、と揺すった。
「なあ、お前さあ、文則と仲良くなったからって、いい気になってんじゃないぞ。文則だって、万能じゃないんだ。いいか、文則に言っておけ、俺らはお前の本当の過去を知っているってな。奴を知っている私立中の連中から聞いたんだ。それを聞いて俺は笑ったね。噂なんて、当てにならないってさ」
横山は、薄笑いを浮かべ、亮介の肩から手を外す。彼は、いいよ、今日は行っちまえよ、と亮介の背中を軽くポンと押した。
亮介は彼らから解放され、いくつかの視線を背中に感じながら、逃げるようにして前進した。それから百メートルほど進んだあと立ち止まり、後ろを振り返ると彼らはもうそこにはいなかった。亮介は安堵した。それと同時に亮介は横山が言った言葉が気になり始めた。文則の過去を知ってると横山は言っていた。噂が当てにならないとも言った。彼らは文則の何を知ったというのだろうか。亮介は一抹の不安を感じながら、再度前を向き帰路についた。
次の日の朝は大変なことになっていた。亮介が教室の中に入ると、がやがやと級友達が騒いでおり、何人かが前を指差していた。彼らの視線の先を追ってみると、何やら黒板に大きな文字が書かれている。
(衝撃的事実!文則は、小六の時、自殺未遂を起こしていた!)
汚く殴り書きしたような文字の羅列だった。
文則が自殺?一瞬にして、馬鹿なと思い、亮介はすぐに黒板消しを手にして黒板に押し付け、車のウィンカーのごとく右手を大きく左右に動かし、その卑劣な文字を消していった。
文字を消し終わり後ろを睨むと、級友達は、あーあ、消しちまった、という顔をしていたが、彼らはすぐに別の事に関心を移していったようだ。
教室の隅にいる横山達が、にやついた視線をこちらに向けている。犯人は奴らか、前日のことを思い浮かべ亮介は直感した。
当事者である文則の方に視線を向けると、彼は何時ものように腕を組み、首を解すような仕草をしていた。どうやらダメージはなさそうだ。亮介は、ほっと胸を撫で下ろし、自分の席に着いた。
その日の授業内容はまるで頭の中に入ってこなかった。黒板に書かれていたことが脳裏から離れなかったのだ。文則に自殺の過去がある?振って沸いたような、その事実かどうか判定できない事柄に、亮介はこの二ヶ月間の文則との付き合いを照らし合わせて考えてみた。亮介には到底信じられなかった。
恐れられている彼が、実は心優しき人物であることは亮介には分かっていた。でも、それは彼の心の弱さを示すものではない。彼は一人で居ることも厭わない、強く我慢強い人間なのだ。横山達が、私立中の連中から聞いてきた噂なのだろうが、何かの間違いだと思った。きっと彼に纏わる数々の伝説のように、私立中の連中が事実を捻じ曲げ、面白おかしく横山達に伝えたに違いない、亮介はそう思うことにした。
放課後、亮介たちは横山達に屋上へと呼ばれた。
使い走りの佐野と梶原が、教室に残っていた亮介たちに近づき、「横山君が屋上で待っている」と、にやつきながら、囁いてきた。彼らの目には、もう文則に対する怯えの一欠けらも残ってはいなかった。
二人に導かれるままに、屋上に出た。青い空だな、両手をズボンのポケットに突っ込みながら、文則は呟き、暢気に上空を見上げた。横山は右手を不自然に身体で隠し、浄水タンクの前に立っていた。
「お前には騙されたよ」
横山の前まで来ると、彼は顎をやや斜め気味に上げた。
「騙された?」
「少年院に行っていたなんて嘘八百じゃねえか」
「俺は、自分でそんなことを言った覚えはねえ。噂が勝手に一人歩きしただけさ」
「まあ、いい。でも、お前が自殺未遂した事実だけは消えないぜ」
横山は含み笑いをしながら、カランと右手を前に出した。横山は金属バットを手にしていた。
「汚ねえ奴だな、お前…」
「念には念を入れてな。噂が嘘だとしても、その巨体だ。暴れられると始末に負えねえ」
横山を中心にして、梶原と佐野が亮介たちを囲んだ。何時の間にか彼らの手にも金属バットが握られていた。亮介がどうしたものかと逡巡して、文則の方に目を遣ると、彼は、お前は邪魔だ、逃げろ、と耳打ちしてきた。でも、一人じゃ、と亮介が言い掛けると、突然彼は、亮介の後方に居た梶原に飛び掛り押さえつけた。
「逃げろ」
文則は叫び、亮介は反射的に彼の言うままその場から逃げ出した。屋上の出入り口から階段を必死に駆け下りた。階段から廊下を走り、教室の前まで来てから後ろを窺がったが、誰も追いかけてくる様子がなかった。
それからしばらくの間、亮介は教室の机の椅子に座り、事態の結果を待った。横山達が、文則を叩きのめし、意気揚々と教室に入って来ることも考えられたが、亮介はそこから動くことが出来なかった。亮介は完全に逃げ切ることを拒否した。
「お前、未だいたのか」
文則が教室にのっそりと姿を現したので亮介は安堵し、涙が溢れそうになった。文則の制服は所々砂埃で汚れ、頭からは流血していた。亮介が、お前大丈夫か、と駆け寄ると、あいつら結構しぶとかったな、と笑い、いたたと額に手をやった。あいつらは?と亮介が訊くと、文則は、半殺しにしてやった、と言いながら考える仕草をして、続けてまあ、大丈夫だろう、と答えた。亮介は、何が大丈夫なんだと思ったが、それ以上追求するのはやめた。文則に帰えろうと声を掛けた。彼は、おう、と返し、それから亮介たち二人は帰路についたのである。
まったくあんた達は…。
姉は脱脂綿を消毒液に湿らせ、文則の額の傷口を覗き込むように探ると、乱暴に押し付けた。
いたた、痛いですよ、お姉さん。文則は大げさに痛がっていたが、裏腹に目尻は明らかに下がり気味で、その状況を楽しんでいるようだった。
ほら、じゃあ、上着も全部脱いで、ほらほら…。
さすがに年上の女性に裸を見られるのは恥ずかしいのか文則は抵抗したが、やがて諦めた。
文則の上半身には何箇所かの打撲痕が青く残っていた。横山達に金属バットで殴打された痕は、いかに彼が奮闘したかを物語っていた。姉は、まあ、すごい、と大げさに驚き、シップ薬を薬箱から取り出すと、その痕一つ一つに丁寧に貼り付けた。
さっ、これでよし、服着ていいよ。
姉は、文則の背中をピシャリと掌で打つと、薬箱を手にさっさと四畳半の部屋から出て行った。
「いい姉ちゃんだな」
いたたと背中に手をやりながら、文則は言った。
「今日は猫被っている」
「そんなことねえだろう」
「怒るとすごいんだ。それで喧嘩の毎日さ」
「でも、仲良く喧嘩できる相手がいるってのはいいもんだ、俺は一人っ子だからな」
文則は、遠くを見る目をしていた。亮介は彼のその目を見て、いつか見た茜色の夕陽を思い出していた。寂しげで、それでいて、どこか力強いあの夕陽、亮介はあの夕陽に感動したのだった。
「なあ」
「うん」
「聞かねえのか」
「何のことだ」
「…自殺の事とか」
彼の突然の問いかけに亮介は驚いた。自尊心の強い彼から、そんな言葉が出てくるとは思ってもみなかったからだ。
「お前が、話したかったら、話せばいい。そうじゃなかったら、話す必要がないよ。俺に気兼ねするなんて、お前らしくない」
亮介はそう言い、文則は、そうかと、呟き、沈黙した。沈黙の時間は長く、時間が亮介の背中に圧し掛かってくるように感じた。それからどのくらい経ったのだろうか、長い沈黙の後、彼は静かに言葉を選ぶように話し始めた。
「…あの頃、俺は精神的に参っていたんだ。両親は毎日喧嘩ばかりしていたし、俺はというと、毎日クラスの連中に、無視されていた。きっかけは、俺の身長が馬鹿でかくなっていったことにあるのかな。巨人症っていわれたよ、それまで仲良くしていた友人からな。それから、俺はそいつばかりか、それまで仲良くしていた友人全員に無視されるようになったんだが、意外とそれには耐えることができた。もともと、俺は一人でいることが苦痛ではなかったからだ。むしろ、家にいる方が苦痛だった。一番参ったのは、両親の喧嘩だな。最初は、親父の不倫からはじまったんだ。親父は不倫がお袋にばれ、お袋は、一度は親父を許した。けれど、親父の顔を見ると、彼女はどうしても許せなくなって、ほんの些細なことでも、親父を責めたてて、終いには、大喧嘩さ。それが毎日続き、その内家には俺の居場所がなくなったように感じるようになった。…・そして居場所をなくした俺は、学校でムカつき、荒れるようになったんだ。俺を無視した連中全てに、喧嘩を吹っかけ殴るようになっていたな。殴って殴って殴りまくったよ。…・或る時血に染まった相手の顔を見て、ふと俺は自分が必要のない人間に思えてきたんだ。一体何だったんだろうな、あの感情は。振り払おうと何度も相手の顔を殴ったが殴れば殴るほどそう思えてしょうがなかった。結局、そいつを殴り倒したあと、駆けつけた教師の手を振り切って、俺は教室の窓に足を掛け、一気に飛び降りたよ。三階からだったから、死んでもおかしくなかった。校舎の近くに植えられた木がクッションになって、助かったんだ。腕も足も至る所が骨折したけれど、とりあえずは生きていたんだ。病室には両親とも現われたけど、お互いに、俺がそうなったのは、お前のせいだと俺の前で、罵り合っていた。俺は、それをみて醜いと思ったよ。そして、俺はなんで生きているんだと思った。出来たらもう一度何処かから飛び降りて死んでしまいたいって思ったよ。…小学校の五年の時の話さ、もう二年近く前。なあ、亮介よお、俺は生きていてよかったのか?俺は今でも死にたくなるんだ。横山達を殴り倒したあと、何故か空しくなって屋上から飛び降りたらどうなるんだろうって思ったよ。なあ、亮介、俺はお前の何なんだろうな」
文則の告白は衝撃的なものだった。凡その想像はしていたが、それを遥かに大きく上回る経験を文則はしていた。亮介は、激しい鼓動を感じながら、ゆっくりと、確かに言葉を選んだ。
「文則は俺の親友さ、それ以上でもそれ以下でもないよ」
「本当か」
「勿論」
亮介が笑うと、文則は突然目を伏せ、嗚咽した。それこそ今までの不安の一切を吐き出すように。自分が一人ではないということを確認するために。
「じゃ、明日またな」
文則は母の、一緒に夕御飯でもという申し出を、猫たちが待っているからと丁重に断り、帰っていった。
姉は、文則が帰ったあと、亮介に向けて、あんたたちいいコンビだね、と言った。そうなのかも知れない。亮介は姉のその言葉を否定せずに、あいつは俺の初めての親友だから、と笑った。
次へと続く。
HAKU / Every breath you take cover
The Moody Blues - "Tuesday Afternoon" (Official Video)
佐藤千亜妃 - タイムマシーン(Music Video)
踊ろうマチルダ - 化け物が行く @ THE CAMP BOOK
佐藤千亜妃 - タイムマシーン。分かっている人もあろうけど、これは宇多田かおるさんへのリスペクトを込めて作られた曲です。
メロディやアレンジや歌詞などいたるところに宇多田ひかるがちりばめられています。
以下は以前書いたやつですが、題名を変えて加筆修正しました。よかったら読んでください。なお、コピペしたものなので段落とか一マスあけるとかおかしくなっていますが、ご容赦を。
記憶は夕陽色
響子ちゃんは亮介の隣で夕陽を眺めている。恋人同士に見えるかしら、という言葉を投げかけられたが、それに対して亮介は何も答えようとしなかった。ただ、心の中ではある誓いをたてた。―青の炎のような静かな情熱をもって。
亮介はこうやって夕陽を眺めていると、過去の事柄を懐かしむだけではなく、この夕陽は未来に向かって連続しているのではないかと想像する。時間がもしも円の軌跡を描くものであるとしたら、未来は即ち、過去にまた向かっていることになる。夕陽がその軌跡をなぞっているものだとしたら?
また、宇宙には様々な世界があって、同一の次元を持つパラレルワールドがあるという。それらが少しずつ互いに「時間のずれ」を生じさせながら、実はどこかで重なり合っている部分があるとしたら?
亮介は未来に、過去に、また別の世界でこの夕陽を眺めることになるのだろうか。
壱 夕陽の時代
もうこれが最後だと思っていた。しかし、文則はそれまで集金した金の流れを記録したB6サイズのノートを眺めながら、未だだと否定した。亮介がそんなはずはない、三千円にはなるはずだと反論すると、うるせえ未だと言ったら未だなんだよと、文則は語気を荒げて亮介を睨んだ。
「もう、十回以上はお前に渡したはずだ」
「いいや、九回だ。それに三千円には程遠いぜ。今回のやつと合わせて千八百円だ」
文則の言い分は嘘だと分かっていた。彼の言葉を信じれば、亮介は二百円ずつ九回しか払ってないことになる。でも亮介の記憶では一回の殆どが三百円で、もう十数回も彼に渡している。まさか千八百円ぽっちだなんて、そのようなことがあるはずがなかった。
「もう、限界だ。親にばれる」
亮介がそう訴えると文則は暴力的な目を向け、俺に逆らうのかというがごとく、ノートを乱暴に閉じた。
二人は文則の自宅の裏庭に居た。裏庭は雑草が鬱蒼と生い茂っていて、亮介の太腿に掻痒感が走る位無節操に天に向かって伸びていた。亮介が背中を預けている家の壁には窓が二つある。恐らく風呂と便所の窓である。どちらも人の気配がしない。誰か来てくれと、神仏に懇願している自分を想像してみても、誰も来る気配はしなかった。文則は一人っ子であり、両親は共働きで帰ってくるのが遅いといつか嘆いていた。誰もいないのかと亮介は諦めた。
「それなら、後三回だ」
文則は、渋っている亮介に対して業を煮やし、懐柔策に出た。
「百円ずつでいいぜ、あと三回で許してやる」
「本当に?」
「ああ、本当だ。百円ずつなら分らねえだろ。百円位なら、お前のお袋も何かに遣ったんだろう位にしか思わねえだろうからさ、お前も助かるってもんだ」
何がお前も助かるだと言い返したかったが、なにしろ身長百八十は裕にある巨体だ。逆らって勝てる相手ではなかった。
「本当だね。じゃあ、後三百円だ。でも約束は果たしてよ」
「ああ分かったよ、俺は言った事は守る主義だ、安心してくれ」
文則はそう胸を張ると、さっさとその場所から離れ、お前も早く帰れよ、クラスの連中に会うとまたやっかいだぜと言い残して家に入っていった。
帰り道、亮介は走って帰った。文則が言ったようにクラスの連中に遭遇してはいけない。
取り分けあのグループには。
亮介が酷い虐めを受けるようになったのは、小学校の高学年になってからだった。きっかけは「風呂」だ。
当時、昭和四十年代後半、亮介は町の西端に並ぶ公営団地に住んでいた。家族は両親に祖父、姉がいて、亮介を加えての五人家族だった。団地の部屋は六畳二間に四畳半と台所と、それなりの間取りではあったが、如何せん風呂がなく、亮介たち家族は週三、四回近くの銭湯に通っていた。
ある日、友人の一人が風呂に毎日入っていると聞いて驚いた。風呂というものは、そんなに入るものとは思っていなかったからである。えっ、と目を見開きながら、俺の家は一日置きだよ、思わず口にするとそこに居た級友達は皆声を揃えて、汚ね―、と声を揃えて囃し立てた。
当時の田舎はまだまだ農家が多く、しかもそれなりの資産をもっていたので、皆古かろうが継ぎ接ぎだらけであろうが、自分の家を持っていた。それに再開発が進み、新興住宅が建てられ始めていた時期で、そういった家には当然内風呂が存在し、住人は毎日風呂に入れる恩恵に与っていたのだ。
そのような環境の中、「週三」の亮介は疎外されない訳がなかった。
級友達の虐めは辛辣であった。亮介の机やノート等に落書きをするのは当り前で、集団で便所の個室に亮介を閉じ込め、頭上から水を浴びせ掛けたり、衆人の前で亮介のズボンをパンツごと引き摺り下ろしたり、終いには亮介を無視し出し、たまに話しかけてきても、亮介の目前で(南無阿弥陀仏)と手を合わせて焼香をする真似をする。亮介を同じ空気を吸っている、同じ人間としての扱いをしているようには到底思えない行為であった。
小五の時は何とか踏ん張ったが、小六になり事態が収まりそうもないことが分かると、亮介は次第に精神的に病むようになった。具合が悪いと事あるごとに親に告げ学校を休み、数々の病院を回った。医者は何れも原因不明とし、思春期の始まりにはよくあることですよと答えた。本当は、虐めが辛いんだよと亮介は告白したかったが、それでも決して亮介からそれを口にすることはなかった。疲れ果て精神は消耗し切っていたが、頑固なプライドだけは未だ残っていた。小六の一年間、亮介は殆ど学校に登校出来ず、それでもなんとか卒業することが出来た。
中学校に入学してからの亮介は、しばらくの間平穏な日々を過ごしていた。中学校は町内の各小学校からの寄せ集めで、クラスは効率よく分けられていた。亮介は同じクラスの中に虐めっ子達がいないことを確認し、ほっと肩を撫で下ろした。一学期の間は至って平和で、ああこんな日が来るとはとつくづく思った。
事態が暗転したのは夏休み後だった。クラスの男子生徒の一人、横山が、お前小学校殆ど行ってないんだってなと騒ぎ出したのだ。彼はクラスのリーダー格で、周囲に対する影響力を持ち合わせていた。それを聞くとクラスメイト達の亮介を見る目が変わっていった。二、三日もすると、皆亮介を汚いものでもみるような目で見、無視し始め、リーダー格の横山は何人かの生徒を引き連れて亮介を囲み、玩具を手に入れたとばかりに弄んだ。新たな虐めの始まりだった。
中学校での虐めは、それなりに我慢することは出来ると踏んでいた。どれくらい我慢すれば、最小限の被害で済むのか経験値で分かっていた。が、亮介はもうこれ以上我慢するのは真っ平御免だった。これからの中学生活を、まるで甲羅を背負った亀のように過ごさなければならないなんて、そんな辛いことはない。それでこの状況を打開しようと、頭を巡らし結論に至ったのが「文則と友人になること」だったのである。
文則は、孤高の存在だった。中一にして百八十を超える長身で、いつも眼球を不必要にぎらつかせ、横山も迂闊に手を出せなかった。彼は何故か私立のエスカレーター式の小学校から公立の中学に入学して来ており、そのせいで彼についての情報は誰も持ち合わせてはいなかった。そのせいか、彼に纏わる色々な噂、大きな暴力事件を起こして小六の殆どを少年院で過ごしていたとか、半殺しにされた相手はもう少しで死ぬところだったとかは半ば伝説化していて、話の真偽はともかく何人ともいえぬ恐れから、彼に話しかけるものは誰もいなかった。
亮介はそんな彼と友人となることで、「横山達に虐められる」という環境から脱却しようと考えたのである。
「文則君一寸いいかな」
亮介が文則にやっとの思いでそう話しかけることが出来たのは、九月の半ば近く、放課後二人きりになった時だった。亮介は文則が、いつも放課後最後まで教室に残っていることを知っていて、チャンスを窺がっていたのだ。恐怖心から、話しかける前にかなりの緊張を強いられ、胸の中に大きな鉛玉を抱えたように苦しかったが、勇気を振り絞って話しかけてみると、意外にすんなり言葉を発することが出来た。
文則はじろりと亮介を見たが、何だおまえかという顔をして、つまらなそうに亮介から視線を外した。亮介は構わず単刀直入に本題に入った。
「俺は今虐められているんだ」
頬が何だか火照っている。
すると文則は今更何を言い出すのかという顔をして、「だから?」と呟いた。
「俺を助けて欲しいんだ」
「助ける?」
「俺の友人になってくれればそれでいい」
「俺がお前の?はは、笑わせるじゃねえか」
「笑い事じゃなく本気なんだ。君が俺の友人になってくれれば、横山達は一切俺に手を出せなくなる」
「俺には全く関係のないことだ。おまえが何されようとな」
文則のつれない返答に、それでも亮介は諦め切れず、
「何でもする、何でもするから、頼むから友達になってほしい」心底から頭を下げた。
すると意外にもその言葉が効いたのか、文則はしばらく頭を下げた亮介を眺めながら、やがて薄く笑みを浮かべた。
「何でもするのか?」
「ああ、嘘は言わない」
文則は何かを考えているようだった。腕を組み亮介を凝視していたが、視線は亮介の身体を射抜き後ろの壁にまで到達していた。
「……五千円」と文則は呟いた。
「もし、五千円俺にくれるのなら、クラスが一緒の間はいつもお前の傍にいてやる」
そう言われて少し驚いたが、考えてみれば、彼と自分とを結び付けるには、そういった報酬のようなものが必要なのは当り前だと亮介は気がついた。
「五千円で本当にいいのか」
「ああ、無理なら別に構わない。この話はなかったことになる」
「分かった、五千円用意する」
当時の亮介は月に二千円の小遣いを親からもらっていた。事情を話し、残りの三千円はあとでもいいかと文則に訊くと、「分割払いにしてやる。ただし一ヶ月以内だ。金が五千円に達するまでは、俺はお前を守らない」と冷たく返された。
亮介は承諾し、それから毎日のように母親の財布から少しずつ小銭を抜き取る羽目になった。
ブラスチックで出来た、ぺこちゃん貯金箱を手にすると、亮介は底に嵌められた半透明の丸い蓋をそっと外し、貯金箱を軽く振った。すると開けられた小さな穴から、小銭と小さく折り畳められている紙幣が何枚か、じゃらじゃらと机上に滑り落ちてきて、亮介はその中から百円玉三枚だけをを手にし、残りは元に戻した。
四畳半の部屋は、亮介と姉の小夜子との共同の勉強部屋で、窓側に机が二つ縦に、合わさるようにして並べられていた。姉の机上の本立てには大学入試の問題集が何冊も立てかけてあり、ぺこちゃんの貯金箱はいつもその前に置かれていた。
姉が今にも帰ってきそうだったので、亮介は目的を果たすと蓋を嵌め、注意深くぺこちゃんを元通りの場所に置き、ごめんなさいと手を合わせた。その貯金箱は、姉が中学生の時から、大学受験の費用の足しになるようにと、少ない小遣いから少しずつ貯めてきたものなのだ。
それまで亮介は、母親の財布から小銭を抜いて来た。最初は気づいていないようだったが、何度もやる内に、さすがに何かおかしいと感づいたのだろう、母は亮介の行動を監視するようになった。亮介はこれ以上母の財布から金を抜き取ることは出来ないと判断し、姉の貯金箱からしばらくの間借りることにした。
ペコちゃんに謝った後、亮介は自分の机の椅子に座り、机の一番上の引き出しを引いて小銭を仕舞った。明日にでも文則に全て払ってしまおう、そう思い亮介は勉強部屋から出て行った。
その日の夕飯後、食卓のテーブルを挟んで姉と父は対峙していた。
「そんな話は聞いていない」
父は怒りを含んだ声を上げた。
「でも私決めたのよ」
姉は負けずに応酬した。
父と姉がこのように喧嘩するのを見たのは初めてのことだった。小さな頃から姉は、父に特別な存在として扱われて育ってきた。怒るなんてもっての外で、かわいいかわいいとお金が無いにもかかわらず、姉の望むものは何でも買ってやっていた。小さな頃亮介が何か物を強請ると、父は決まってお前は男だからと言い我慢させられた。アルバム一つにしても姉は六冊を数え、亮介は一冊しかなかった。彼女は事あるごとに父に写真を撮ってもらい、自分が育ってきた歴史を残してきたのだ。一度母に、自分は父の子ではないのではないかと訊いてみたことがあったが、母は、ばかねえ、そんなこと言うもんじゃないよと苦笑していた。
さすがに成長してくると、姉は自我が芽生え物を強請ることもなくなり、貯金をするようにもなったが、父にとっての姉は、愛おしい何物にも代えがたいものに変わりがなかった。
そんな父が、本気で姉に怒りの目を向けている。その時亮介は同じ部屋の隅にいて、事の成り行きに少しの不安と少しの期待を抱いていた。
「ともかく、私は東京の大学を受験するわ、それは中学校から決めていたことだし、変わることはないのよ」
「東京ってお前、地元の大学に進むんじゃないのか」
「私はここを出て行きたいのよ」
「出て行きたいだと。ここの何が不満なんだ」
「不満は無いわ。でもここに居たら私駄目になるわ、きっと」
「ふざけんな」
父は顔を真っ赤にして、握った拳をぶるぶると震わせていた。それを見た亮介はまるで、仁王様のようだと思った。
「東京に行くにしてもだ、学費や生活費はどうするんだ。東京に行くというなら、俺はびた一文として、出すつもりはないぞ」
「そう言うと思って、奨学金の手続きをしたわ、それにバイトをすれば何とかなると思うの」
「勝手にしろ」
なんだ、結局父さん折れているじゃないかと亮介はがっかりした。姉は、それじゃ私勉強するからと、さっさと四畳半の勉強部屋へと襖を引き入っていった。
「誰に育ててもらったと思ってるんだ」
父はテーブルをドンと拳で叩き、酒もってこいと台所にいる母に向かって叫んでいた。
それから亮介も勉強部屋へ直行することにした。父が酒を飲みだしたからだ。火の粉がこちらに降り懸らないともいえない。父は酒乱というほどではないが、酒を飲むととたんに人が変わり、傍にいる誰かれなくしつこいように絡む癖があった。姉に対する不満を亮介にぶちまけられても困る。亮介は逃げ出すようにして父を見捨てた。
「なんか用?」
ノックをして襖を開けると、机を前にした姉は不審者を見つけたような顔つきで亮介を見た。
「俺もマジやばいんで、逃げてきたよ」
「そう……またお酒?」
「うん」
亮介が返事をすると、仕方が無いわねという風に姉はふーっと溜息をついた。
「何で東京なの?」
亮介がそう訊くと、本当はね、と姉は喋り始めた。
「……本当は東京じゃなくてもいいのよ。ここ以外のどこか、ならね。親もいない、地元の友達にも会うこともない、人生一度リセットして、一人になって、一人で考えられる場所に住むって理想じゃない。そう思わない?」
姉の言っていることは、もっともだと思った。亮介も一人になりたいと何度も考えていたからだ。誰にも邪魔されない自分だけの世界。横山のことも文則のことも考えないで済む世界。亮介も人生一度リセットしてやり直せたらどんなに幸せかと思っていた。
「…そう出来たらいうことない」
「そうね、だからその為に、私はここから出て行くのよ」
姉の言葉には確固たる意志が込められていた。どんなことがあっても、折れることのない太く硬い意志。それは、どんな過程でつくられたのだろうか。そこまで考えた時姉は、でもね、と呟いた。
「何」
「うん、でも、一つだけ気がかりなことがあるのよ」
「気がかり」
「亮介、あんたのことが心配なの」
気づいていたのか、と思った。姉の「心配」という言葉は、まさに亮介が虐められいることに対して向けられたものだった。
「亮介、あんた虐められているんじゃない。お母さん、最近あんたが元気ないって言っているのよ」
「そんなことはない」
「いいえ、嘘いってもだめよ。私の目から見ても最近のあんたはおかしい。小学校の頃と一緒。目が虚ろで毎日を生きているのが精一杯って感じだよ」
小学生の頃、虐められていたことをいち早く気づいたのが姉だった。卒業文集に書き綴られた、「学校にも来ないのに、迷惑、消えて欲しい」という亮介に対して向けられた級友の一文に彼女は怒り、それを平然と載せた学校の担任に抗議をしにいった。それはまるで自分がそうされたかのような怒り方だった。
「姉ちゃん、俺のことは心配しなくてもいいよ。虐められてはいないし、元気がない訳でもない。…そうそう強いていえば勉強のことかな。ついていくのが大変なんだよ、時間があったら今度教えておくれよ。数学がさ、苦手なんだ」
姉はその亮介の言い訳に、小さく嘘っぱち…、と呟いてやがて亮介を無視するように机に向かった。亮介は机の前に腰掛けて教科書を広げ、勉強するふりをした。机の引き出しの中には三百円があった。姉ちゃんごめん、亮介は心の内で姉に謝り、土下座している自分を想像した。
上空を見上げると青い空が広がっていた。
白い太陽はまだまだ沈む気配はなく、亮介たちの世界の色を明確にしていた。キーンという音の後に、飛行機雲が、暢気に追いかけている。
「何余裕かましてんだよ」
何となく上空を見上げていた亮介を見て苛立ったのか、横山は語気を強めた。横山の他にあと二人いる。佐野と梶原だ。そこは学校の屋上だった。
放課後、横山ら三人に屋上へ来いと呼ばれた。屋上で何をされるのかは大体分かっていたが、逆らえばその場で、ズボンを引き摺り下ろされるか、プロレスごっと称して殴られるか、ともかく「虐め」と呼ばれる行為をされることは明白だった。亮介はなるべく衆人の前で辱めを受けたくなかったので、大人しくついていくことにした。
横山達は、亮介を連れて屋上に上がると、隅にある大きな浄水タンクの裏まで来て、ズボンのポケットから煙草とマッチを出し、火を点け煙草を吸った。
彼らが煙草を吸っている間、亮介は他にすることもないので上空を見ていた。その様子を見て横山は苛つき、怒声を亮介に浴びせたのだった。
「お前、生意気なんだよ」
横山は唾を吐く。
「死んじまえ」とも。
その言葉に、さあいよいよ始まるか、と亮介は覚悟し、全身に力を込めた。
「やれ」
横山の合図とともに、佐野は後方に回って、亮介を羽交い絞めにし、もう一人の梶原が亮介の前方に立った。
梶原は、にやりと醜悪に笑い、舌なめずりをすると、亮介のワイシャツのボタンを一つずつ外していった。ボタンを一通り外し終えると、今度は現れた下着を亮介の首の辺りまで捲り挙げた。
亮介が何とかしてすり抜けようと身体を左右に揺さぶると、
「さあて、楽しいショーの始まりだ」
横山はそう口にし、火の点いた煙草を手にして亮介に接近した。
「一度やってみたかった」
横山が残忍な笑みを浮かべた瞬間、脇腹に熱い痛みを感じて亮介は呻き声を上げた。
ちりちり、と肉が焼けるときのものなのか、煙草自身が発するものなのか分からない音がした。熱く抉るような痛みが脇腹に走る。亮介は痛みで気を失いそうになった。
横山は煙草の先を亮介の脇腹に押し付けていたのだ。
それから何度も横山から同じ行為を受けたが、その都度同じ表情とアクションを繰り返す亮介に飽きたのか、横山は、つまらねえと呟き、最後に煙草に火を点けたはいいが、それを一、二回吸っただけで、まだ十分な長さのあるまま地面に落とし、踵で踏み潰してしまった。
「それじゃあ、俺にやらせろよ」
佐野が羽交い絞めにした手を緩めると、亮介は膝から崩れ、そのまま地面に仰向けになった。もうどうなってもよかった。亮介は脇腹を押さえ、やけくそになっている自分に気づき、微かに笑っていた。
「おいこいつ、笑ってやがる」
「気持ち悪いなあ」
「マゾなんじゃねえか、こいつ」
亮介を見下ろし、横山達は、亮介の身体に軽く蹴りを入れていたが、やがて抵抗もしない亮介の態度に興ざめし、帰るぞとその場から去って行った。
仰向けになったまましばらく空を眺めていると、渡り鳥らしい三角に編隊した大群が北から南の山向こうへと消えていった。
鳥になりたい、亮介はそう独りごち、すると涙がとめどなく頬を伝いどうしょうもなくなった。脇腹の痛みは、そこだけ脈打つような重い痛みに変わっていた。
脇腹にじりじりする痛みを抱えながら土手の道を歩いていた。土手の道は亮介が小学校から慣れ親しんだ道だった。大通りを通って帰る方法もあったのだが、こちらのほうが、学校の行き帰りには近いので、団地に住んでいる殆どの生徒が土手の道を利用していた。
片側には大きな川が流れ、もう片側には雑多で背の高い草がこちらに向かってくるように生茂っていた。前日、大量の雨が降ったせいか川の水量は多い。何とはなしに、筏に乗って川を下っていく自分を想像して、少しだけ楽しい気分になった。
帰りに文則の家に寄って、三百円渡そうか迷っていたが、脇腹の痛みが酷く少し熱を感じた亮介はそのまま家に帰ることに決めた。前方をみると川を渡す橋が見え、その上を車が何台も右へ左へと行き交っていた。橋の向こうには山が聳え立ち茜色の夕陽が沈みかけると、山の稜線をくっきりと浮かび上がらせていた。
そんな景色に少なからず何かを感じ足を止めていたら、後ろから誰かに声を掛けられた。振り向くと、響子ちゃんが立っていて、はあはあ、と息を切らせていた。
「さっきから、声を掛けていたのに、亮介君気づかずに、どんどん行ってしまうんだもの」
「ごめん、気づかなかった」
「何を見ていたの」
響子ちゃんの言葉に、あれだよ、と山の方角を指差した。
「ああ、なんて綺麗な茜色…」
響子ちゃんは、顔を紅潮させながら目を細めた。
響子ちゃんとは、同じ団地に住んでいる間柄だった。棟は違ったが、小学生の頃、登校班が一緒だったこともあり、よく二人で砂埃の立つ土手の道を通いながら、昨日見たテレビの話などをしていたものだ。彼女は優しく亮介の憧れの娘だった。彼女は亮介よりも学年がひとつ上で、亮介が六年生になると一足先に中学生になった。その後彼女とは接点がなくなったが、今思うと亮介が小学校に行かなくなった理由の一つには彼女がいなくなったことによるショックもあったに違いない。
「今、部活の帰りなの」
「そうよ、陸上部は厳しいのよ、帰宅部くんとはちがうのよ」
「帰宅部って、これでも一応新聞部だぜ、…まあ、もっともこれといった活動はしてないけどさ」
亮介たちは並んで歩き始めた。セーラー服の彼女は、地味だけど、時折見せる笑顔がとても魅力的だった。瞳は薄茶色で、髪はみつあみにしていた。清楚という言葉がぴったり当てはまる彼女だった。
「あのね」
「何」
「まだ、来年のことだけどね、うちね、引っ越すことになったの」
「えっ、そうなんだ」
唐突な彼女の告白に、亮介は驚きを禁じえなかった。
「そ、それで何処に引っ越すの」
「Y市に引っ越すのよ。今、家を新築しているの。完成予定が二月の予定かな。だから今の中学とも、来年の三月でバイバイだね」
「…」
亮介は、大きなショックを受けた。いくらなんでも、そんな。…今日、響子ちゃんに出会わなければよかった。会話を交わしたのは小学校以来で、中学校に入ってからは初めてのことである。久しぶりに会って話した結果がこれだなんて…。これが最後の会話になるのかもしれない。引越し迄亮介と響子ちゃんは結局話す機会もなく、彼女は何年か住み慣れ親しんだ団地を去るのである。来年には姉も家を出て行く。そう思うと、なんだかひとり取り残されるようで亮介はいっそう悲しくなった。
「寂しくなるな」
亮介はそう言うのが精一杯だった。
それから響子ちゃんは団地に着くまで他愛無い話を亮介に向けてきたが、亮介の方は、はいとかうん、だとか言って、適当に答えていた。
「じゃあね、さよなら」
団地の前で二人は別れた。三階建ての団地群は古く、夕闇の中で亮介と響子ちゃんをかこんでいる妖怪達の群れのように見えた。亮介は、響子ちゃんが、妖怪の口の中に消えていくのを確認すると、あーあ食われちまった、と微かに呟き、しばらくの間そこに立ち尽くしていた。
家に帰ると、亮介は居間の箪笥の上にある薬箱を下ろした。それから薬箱の蓋を開け軟膏を取り出す。脇腹は相変わらずじんとして熱く、痛みがあった。祖父が六畳の部屋から出てきて、怪訝そうな顔で亮介の方を見ていたので、工作で指切ったんだと言って、箪笥から着替えも持ち出し祖父の前をするりと抜け、姉のいない四畳半の襖を引いた。襖を閉め部屋に入り、外の様子をうかがったが誰も来ないと悟り、亮介は自分の机の椅子に腰掛け、ふうと溜息をついた。それから思い切ってシャツを全部脱ぎ捨て、脇腹の状態を確認した。煙草を押し付けられた跡は四箇所あった。四つとも皮膚を破られた中央に赤い肉片が現われ、周囲は焼け焦げたような盛り上がりを見せている。亮介は、やれやれこれは跡に残るだろうな、と思い落胆した。下着にも点々と血の跡が付着している。亮介はそれを放りなげ、傷口に軟膏を塗りたくった。
軟膏を塗って一息付いたあと立ち上がり、もう一度血の付いた下着を手に取り、どうしようかと思案した。本当はその日の下着は、台所脇にある青色の篭の中に放り込んでおくのが常だったが、母が洗濯するときに気づくに違いないなかった。気づけば母は亮介を問い詰めない訳にはいかない。厄介ごとはごめんだと思い、亮介は机脇の大きい方の引き出しに下着を放り込んだ。誰もいないときに持ち出して、何処かに捨てにいけばいい。一瞬いい考えだと自賛したがすぐに憂鬱になり、自分の現状を呪った。横山とのこと、文則とのこと、今日会った響子ちゃんとのこと、いろいろなことが、亮介の頭の中で旋回し、落ちて行く。ざまあねえわな、亮介は呟き、天上を仰ぎ、必死に涙を堪えようとした。亮介は今日何回泣いただろうと恥じ、涙の跡が残らないように注意深く手の甲で拭い、それから着替えを済まして勉強部屋から出ていった。
夕飯時に父の姿はなかった。どうしたのかと母に尋ねると、父さんは管理職だから大変なのよと仕方なさそうな顔をした。姉は無言で食事を済ませ、母が何かを言いたそうにしているのを尻目に、さっさと勉強部屋へと消えていった。それから亮介は姉以外の自分を含め、四人の寝室となる六畳の部屋へと入り、祖父が個人的に購入したサンヨーのパーソナルテレビのスイッチを点け、水戸黄門を見ていると祖父が後から入って来た。
「水戸光圀か・・」
亮介の隣に座ると祖父は何とはなしに呟いた。
テレビでは、助さんと格さんが悪代官の手下を相手に立ち回りを繰り広げている最中だった。
「光圀が各地を漫遊したのは、物語の中だけの話なんだ」
祖父は亮介の方を向く。
「へえ」
亮介が、そう返事を返すと、祖父は得意げな顔をして話し始めた。
「光圀が名君だったのは本当のことだが、実際は江戸と鎌倉にしか行ったことがないんだよ。物語の元になったのは、当時の人気戯作者の十返舎一九の(東海道中膝栗毛)らしいな。それを参考にして講談師が(水戸黄門漫遊記)なるものを創作したということだ」
祖父がそう話しているのに、胡坐をかき、うんうんと生返事をしてテレビの画面を眺めていた。各さんが葵の御紋の入った印籠を出し、お決まりの、この紋所が目にはいらぬかと悪者達を平伏させていた。その瞬間亮介の中にも、妙な優越感が生まれた。亮介が印籠を出し、横山達が、亮介に平伏す姿を想像して痛快な気分になった。それから畳の上に後ろ手をつき、体勢を少し斜めに捻った。すると脇腹に引きつるような痛みが走った。いててと思わず口に出すと、祖父がこちらを見ているのが分かった。
「どこか、怪我してるのか、お前」
「いいや、ちょっと体勢を崩して腰を捻っただけさ」
「それにしては辛そうな顔をしているぞ」
「何でもない、何でもないよ」
亮介がそう言うと祖父は、何でもないねえと訝りながらも、それ以上何も言ってはこなかった。
テレビに目をやると黄門様が、カッカッカーと笑っている。
明日だ。明日で亮介は「文則」という印籠を手にすることになり、横山達は現実に、亮介に対して平伏することになる。亮介は、彼らが自分に向かって土下座している姿を想像して、微かに笑った。
ねえ、亮介、亮介ったら…。
亮介が朝歯磨きをしていると、姉の小夜子がそう言って、便所脇の小さな洗面所に飛び込んできた。何騒いでるんだ、と驚いた顔をして姉の方を見遣ると、何やら事件が勃発したらしい。亮介が、なんだい、と勤めて冷静に訊くと、いつからあんたらそんな仲になったのよ、と亮介を問い詰めた。
「そんな仲って?」
「だから響子ちゃんよ、響子ちゃん、あんたを迎えに来てるのよ」
「えっ?」
「だ・か・ら、今、玄関口に居るのよ」
姉は目を丸くしながら息急き切った。
亮介は、一瞬、その意味が分からず、しばらく姉の言った言葉を反芻していたが、やがて事の重大さに気づき、慌てた。響子ちゃんが来てるって?何故?ともかく亮介は、待たせてはいけないと歯磨きもそこそこに、急いで制服に着替え、ショルダーの鞄を肩に掛け、玄関口に出た。
響子ちゃんは少し俯き加減にお早う、と亮介に言い、それから紅潮した顔を上げると一緒に学校に行かない?と亮介を誘った。どうやら姉と亮介の会話は筒抜けだったようだ。
「じゃあ、俺もう出かけるから」
亮介が奥にいるはずの母に向かって叫ぶと、姉がしゃしゃり出て来て、いってらっしゃい、お元気で、と訳の分からない言葉を投げかけ亮介たちを見送った。
亮介たちは、小学校の時そうであったように、並んで歩いていった。朝の空気は冷たく、時折頬を削り取るような激しい突風が吹いた。土手に差し掛かるまで、亮介たちは互いに沈黙を守っていた。
亮介と響子ちゃんがこうやって一緒に歩くのは、あの日以来凡そ二か月ぶりのことだった。
「迷惑だったかな?」
土手の道を歩きながら響子ちゃんは小首を傾ける。
「いいや、そんなことはない」
「よかった…」
響子ちゃんは呟いた。
「朝、こうやって登校するのも小学校以来だね」
「そういえば、そうかあ」
それよりも今日は、突然またどうしてと思い、亮介は疑問をそのまま口にした。
「それで、今日はどうして」
「ほんとは前に話しておくべきだったのだけれど…お願いがあるのよ」
「お願い」
「そう、お願い…」
「お願いってなに」
「うん、もう少し、もう少し歩けば分かるわ」
亮介たちは砂埃の舞う土手道を渡りきり、学校へ向かうのとは違う道の角を曲がった。亮介が学校はこっちだよ、と学校の方向を指差していると、彼女は少し寄り道するの、と空き地が点在する方角に亮介を誘い、ここよと行き止まりになった先の空き地に入っていった。空き地は草木も枯れ、中央に大きな土管が何本か積まれていた。響子ちゃんはそこまで来ると、中腰になり、その中の一本の土管の穴を覗き込み、両手を穴の中に差し伸べ、やがて小さな猫を抱き上げた。
亮介が近づいても、猫はぴくりとも動かず、気持ち良さそうに響子ちゃんの胸に抱かれていた。典型的な茶色の縞々のある猫で、近くで見ると、肋骨が心なしか、浮いているような気がした。抱いてみる?と、響子ちゃんに訊かれ、彼女から手渡しされ、抱いてみると、猫はミャーンと一鳴きして、亮介をその大きな瞳で一瞥し、腕の中で丸くなった。
「この猫、名前は?」
「メスだから、ミーコ」
「ここにいたの」
「そう、ここで半年前に見つけたの。夕方ね、部活の帰りにね、どこからか、猫の声がすると思って、偶然ここまできてみたら、彼女が顔をだしていたの…この穴から」
亮介は再度ミーコと呼ばれるその猫を観察してみた。所々毛が禿げている、栄養不良のためか子猫と見間違うほど、小さい、それから彼女の後ろ足、右足だが、妙に不自然に内側に湾曲していた。
亮介がそれをしげしげと眺めていることに気づき、響子ちゃんは、
「車に撥ねられたみたいね、骨が折れてそのままにしていたから、不自然に曲がっちゃったのかしら。彼女はその為、行動範囲が狭まってしまっているの」
ああ、それでね、と亮介が理解すると、ミーコはまた亮介を見つめて、ミャーと鳴いた。
「それで、ミーコを俺に任せたいってことかい」
亮介は先回りした。
「そうしてもらえたら、嬉しいんだけど。私は、年が変われば直に引っ越さなければならない。連れて行ければいいのだけれど、母にそれとなく相談したら反対されたわ。このコは足のせいで、自分の食料さえも確保できないの。私がいなくなった後、餌だけでも与えてもらえればそれでいいのよ。ねえ、お願い出来るかな」
彼女は顔の前で手を合わせ、まるで後がないといったように懇願した。
響子ちゃんの申し出に亮介は戸惑った。亮介に猫を世話する甲斐性があるとは、到底思えなかった。かといって響子ちゃんの必死の願いを、無闇に断る勇気はなかった。亮介は、何かいい解決策はないかと逡巡した。
「駄目よね、当り前だわ、亮介君、優しいから、もしかして、って思ったの。ごめんね、悩ませたりして」
響子ちゃんは亮介が逡巡している様子をみて、前言を撤回した。
「待って、結局はミーコを世話する人が現われればいいんだよね」
「それは、私も友達に当たってみたの…でも、ミーコの足のこともあって、誰も見向きもしなかったの」
「ともかく、俺が何とかしてみるよ」
亮介は笑いながら、あいつなら、と思っていた。あいつならきっと、ミーコを喜んで引き受けてくれるに違いない。心配しないで、何とかなるから、響子ちゃん。
突風が幾つかの小さなつむじ風をつくり、枯葉を舞い上がらせていた。
亮介はもう冬なんだなと、片手でミーコを抱き、もう一方の手を制服のポケットに突っ込んだ。
「俺に猫を引き取れだと」
文則は、大きな声を教室内に響き渡らせた。
横山達は、その声に驚き、忌々しげにこちらを見ている。
亮介は文則を、凡そ二か月前に「友達」として雇い、それから何時も行動を共にするようになった。金で「友達」を雇うなんて不純な行為ではあったが、彼と行動を共にすると、横山達は面白いように亮介から手を引き、その後、亮介は「虐め」とは無縁の日々を送っていた。やはり彼らにとって、文則は恐怖の対象なのだ。
偽りの友達から始めた付き合いだったが、付き合う内に、亮介は文則の意外な一面を見ることになった。カレーライスとラーメンに目がないこと、お人好しなところがあり、一人が決して好きな訳ではなく、本当は人一倍の寂しがりやであること、そして動物が大好きで、無類の猫好きであること。亮介は初めて彼の家に招き入れてもらったときの事を思い出していた。
「さあ、入れよ」
文則は恥ずかしそうに俯いて、自分の家に入るように亮介を促した。
「いいのか」
「いいっていってるじゃねえか、それに誰もいねえよ」
「分かった、じゃあ、お邪魔します」
上がり框に足を掛けると、猫が一匹寄って来て亮介の足に纏わりついてきた。
亮介が吃驚して見ていると、文則は、猫が好きなんだ、とその猫を抱きかかえ、亮介を二階へと案内した。
猫は、二階の文則の部屋にも何匹かたむろし、亮介たちの周りを行ったり来たりしていた。その内、文則が餌だぞとキャットフードを何皿かに分けて出すと、猫たちは一斉に飛びつきがつがつと旨そうに食べ始めた。それからその猫たちの様子を眺めている亮介に対して文則は、お前の五千円、こいつらの餌代で消えちまった、と嬉しそうに笑った。
その笑顔を見た時から亮介は、文則を少し見直すようになった。彼は悪ぶってはいたが、本当は、心根の優しい人間なんだなと思った。五千円を奪われた相手を何故、そう思えたのかは分からない。ただ、屈託のない彼の笑顔は何の混じりけのないものに思えたのだった。
「で、その猫は何処にいるんだ」
文則は、話にのってきた。
「三丁目の空き地だ、そこの土管の中にいる」
「土管の中?それはまた酔狂なところにいるんだな」
「後ろ足が不自由なんだよ、その足のせいでそいつは動ける範囲が知れているんだ」
「一度、俺をそこへ連れてけよ。引き取るのは可能だが、その前に見ておきたい」
「分かった。今まで世話してた人がいるんで、その人立会いでいいかい」
「そいつは何処の誰なんだ」
「女性だ。俺と同じ団地に住んでる一年上の先輩だ」
女か…、そいつはおまえのこれなのか、と文則は小指を立てるまねをした。亮介が、違う違う、同じ団地に住んでいるだけだと言うと、文則はそうだよな、根暗のお前に彼女なんてできるはずがねえ、と大きく笑った。
亮介はこいつってこんな楽しそうに笑うような奴だっけ?と思ったが、まあいいや、ともかく彼女に急いで知らせなきゃと、昼休みに文則を連れて二年生の教室に響子ちゃんを訪ねていった。
響子ちゃんは、文則を前にして、余りの威圧感に一瞬たじろいだが、オッス、自分文則って言いますよろしくッス、と何時にもなく硬く挨拶する文則に好感を持ったのか、相好を崩し、じゃあ放課後校門前で待っててね、と約束をしてくれた。教室へ戻る道すがら、文則は彼女は天使だ、運命の出会いだと逆上せ上がり、亮介はまあまあと宥めるのに苦労した。
放課後になり、さっそく亮介たち三人は空き地へと向かって行った。
土管の前まで来て、文則が猫は何処に居るんだと訊いてきたので、そこだと中央の土管を指差すと、彼は大きな身体をこれでもかという位に屈めて、土管の中に手を伸ばし猫のミーコを抱き上げた。それからしばらくの間、彼はミーコの様子を観察し、何やら反応を確かめ終えると、これはまずいな、と呟いた。
「何がまずいのかしら」
響子ちゃんが訊ねると、
「こいつ、目が見えてないんだ」
と文則は返答した。
まさか目まで見えないと思っていなかった亮介たちは、驚きを隠しきれなかった。
「事故のせいかしら」
「分からねえ、ほら、こうやって人差指を左右に振っても何の反応もないんだ。こいつの目が不自由な証拠さ」
「じゃあ、引き取ってもらえない」
「いいや、逆にこいつは、足も悪いし、然る場所で誰かに世話してもらわないと生きられねえ。あんたが餌をやっていたにしろ、よくまあ、こんな土管の中で生き続けていられたもんだ」
「それじゃあ…」
「うん、俺が面倒みるよ」
文則がそう答えると、響子ちゃんは安堵し、良かったと笑顔を見せ、その瞳は少し潤んでいるように見えた。
亮介が文則に、男だねえというと、当たりめえだろうと文則は返してきた。
ミーコはというと、文則の大きな身体に抱かれてとても気持ちよさそうにしていた。
ミーコはこうして文則の飼い猫の一員として迎えられたのだった。
ミャーン。
猫のミーコが不自由そうに、ひょこひょこと近づき、胡坐をかいた中央の空間に滑り込もうとしていたので、亮介は彼女をそっと両手で抱えて、その空間に置いた。居場所を確保した彼女の大きな目はこちらの方を向いている。彼女の目は、こちらをじっと見つめているようにも思え、人差指を彼女の目の前で左右に振って見せたが、反応をみせないのでやはり見えないのかと亮介は溜息をついた。
文則の部屋は、散らかっていた。脱ぎっぱなしの服や靴下、読んだまま放り出してある漫画雑誌、炬燵の上に転がっているカップヌードルの殻、ジュースの空き缶、そして、我が物顔であちこち行き来している猫たちはジュース缶を倒したりしている。どうしたらこんな状態になるのか不思議だった。
亮介が、文則に親は何にも言わないのかと訊ねると、文則は読んでいた漫画雑誌から顔をあげ、親、今いないからと答えた。
「親がいないって、どういうことだ」
亮介がそう不思議そうに訊ねると、
「親父もお袋も、この家には一週間に一回しか戻ってこねえよ。俺はいつも一人だ」
と文則はやけくそ気味に笑った。
「一週間に一回?」
亮介が理解できないといった顔をしていると、文則は仕方がないといったように話し始めた。
「ああ、別居中っていうのかな、ともかく二人は一瞬たりとも同じ家で同じ空気を吸ってられないらしくてな、それで出て行っちまって、二人とも自分の(いいひと)の所にいるよ。今じゃ、一週間に一回俺の様子を見に来るだけさ」
「それじゃ、お前一人でこの家に住んでるようなものじゃないか。食事なんかどうしている?お前一人じゃどうにもならんだろう」
「たまに二人から、これでいろんな支払いを済ませなさいって、金をもらっているよ。支払いを済ました残りでパンや弁当を買って、食っている。金はこいつらの餌も買ったりしているから、何時もピーピーだな」
「どちらかについて行くって考えはないのか」
「俺はどちらの味方もしねえよ、俺は自分の意志でここにいるんだ。もっとも親父もお袋も二人とも、俺を引き取りたくないんで、本当のところは俺が見捨てられたっていうのが事実だがな」
「そんな…」
亮介は絶句した。これまで、何度か文則の家を訪ねてきたが、そんなことになっていたなんて思いもしなかった。文則はいたって普通のことのように話していたが、それがどんなに辛いことか。家に帰っても誰もいない、食事も何もかも自分ひとりで済ます日々、亮介は一時期一人になりたいと思っていたが、今では一人でいることは辛い、そう思うようになっていた。文則は一人でいることが苦痛ではないのか。
「だからって、俺を哀れむんじゃねえぞ、猫たちもいるし、俺は今の状況が結構気に入ってるんだ」
文則はそう言うと、漫画雑誌に再び目を戻し、もうこれ以上話さないとばかりに無口になった。
文則が買出しに行くというので、亮介も帰ることにした。
駅前のスーパーの前で文則と別れて、一人になった。一人になると急になんともいえない不安が亮介を襲った。不安は亮介の胸の中で暗雲となって広がり、亮介の胸を一杯にした。
文則はこれからもひとりで生活していくのだろうか。でも、いずれはその生活は崩壊する。あんな生活が何時までも許されるはずがない。きっと彼は父親ではなく、母親の方に引き取られるに違いない。彼のまだ十三歳という年齢を考慮すると、その可能性が高いのだ。母親に引き取られることになった彼は、転校を余儀なくされ、支えを失った亮介や猫達は行き場を失うことになる。最悪だ。けれど…。
そのようなことを考えながら、橋の袂に差し掛かった。ふと土手の下の川原に目をむけると、何人かの人間がたむろしている。彼らは川原から亮介を目ざとく見つけ、急勾配の土手坂を急いで登りきると亮介の前に立ち、道を塞いだ。
横山達だった。
「よお、亮介くんじゃないの、今日は一人かい。ボディガードくんはいないんだ」
横山達はいやらしい笑みを浮かべていた。
「ボディガード?」
「惚けんじゃねえ。文則のことだよ」
「あいつは別に俺の用心棒じゃないよ。唯の友達だ」
亮介が構わず彼らの間をすり抜けようとすると、横山は亮介の肩に手を掛け、待てよ、と揺すった。
「なあ、お前さあ、文則と仲良くなったからって、いい気になってんじゃないぞ。文則だって、万能じゃないんだ。いいか、文則に言っておけ、俺らはお前の本当の過去を知っているってな。奴を知っている私立中の連中から聞いたんだ。それを聞いて俺は笑ったね。噂なんて、当てにならないってさ」
横山は、薄笑いを浮かべ、亮介の肩から手を外す。彼は、いいよ、今日は行っちまえよ、と亮介の背中を軽くポンと押した。
亮介は彼らから解放され、いくつかの視線を背中に感じながら、逃げるようにして前進した。それから百メートルほど進んだあと立ち止まり、後ろを振り返ると彼らはもうそこにはいなかった。亮介は安堵した。それと同時に亮介は横山が言った言葉が気になり始めた。文則の過去を知ってると横山は言っていた。噂が当てにならないとも言った。彼らは文則の何を知ったというのだろうか。亮介は一抹の不安を感じながら、再度前を向き帰路についた。
次の日の朝は大変なことになっていた。亮介が教室の中に入ると、がやがやと級友達が騒いでおり、何人かが前を指差していた。彼らの視線の先を追ってみると、何やら黒板に大きな文字が書かれている。
(衝撃的事実!文則は、小六の時、自殺未遂を起こしていた!)
汚く殴り書きしたような文字の羅列だった。
文則が自殺?一瞬にして、馬鹿なと思い、亮介はすぐに黒板消しを手にして黒板に押し付け、車のウィンカーのごとく右手を大きく左右に動かし、その卑劣な文字を消していった。
文字を消し終わり後ろを睨むと、級友達は、あーあ、消しちまった、という顔をしていたが、彼らはすぐに別の事に関心を移していったようだ。
教室の隅にいる横山達が、にやついた視線をこちらに向けている。犯人は奴らか、前日のことを思い浮かべ亮介は直感した。
当事者である文則の方に視線を向けると、彼は何時ものように腕を組み、首を解すような仕草をしていた。どうやらダメージはなさそうだ。亮介は、ほっと胸を撫で下ろし、自分の席に着いた。
その日の授業内容はまるで頭の中に入ってこなかった。黒板に書かれていたことが脳裏から離れなかったのだ。文則に自殺の過去がある?振って沸いたような、その事実かどうか判定できない事柄に、亮介はこの二ヶ月間の文則との付き合いを照らし合わせて考えてみた。亮介には到底信じられなかった。
恐れられている彼が、実は心優しき人物であることは亮介には分かっていた。でも、それは彼の心の弱さを示すものではない。彼は一人で居ることも厭わない、強く我慢強い人間なのだ。横山達が、私立中の連中から聞いてきた噂なのだろうが、何かの間違いだと思った。きっと彼に纏わる数々の伝説のように、私立中の連中が事実を捻じ曲げ、面白おかしく横山達に伝えたに違いない、亮介はそう思うことにした。
放課後、亮介たちは横山達に屋上へと呼ばれた。
使い走りの佐野と梶原が、教室に残っていた亮介たちに近づき、「横山君が屋上で待っている」と、にやつきながら、囁いてきた。彼らの目には、もう文則に対する怯えの一欠けらも残ってはいなかった。
二人に導かれるままに、屋上に出た。青い空だな、両手をズボンのポケットに突っ込みながら、文則は呟き、暢気に上空を見上げた。横山は右手を不自然に身体で隠し、浄水タンクの前に立っていた。
「お前には騙されたよ」
横山の前まで来ると、彼は顎をやや斜め気味に上げた。
「騙された?」
「少年院に行っていたなんて嘘八百じゃねえか」
「俺は、自分でそんなことを言った覚えはねえ。噂が勝手に一人歩きしただけさ」
「まあ、いい。でも、お前が自殺未遂した事実だけは消えないぜ」
横山は含み笑いをしながら、カランと右手を前に出した。横山は金属バットを手にしていた。
「汚ねえ奴だな、お前…」
「念には念を入れてな。噂が嘘だとしても、その巨体だ。暴れられると始末に負えねえ」
横山を中心にして、梶原と佐野が亮介たちを囲んだ。何時の間にか彼らの手にも金属バットが握られていた。亮介がどうしたものかと逡巡して、文則の方に目を遣ると、彼は、お前は邪魔だ、逃げろ、と耳打ちしてきた。でも、一人じゃ、と亮介が言い掛けると、突然彼は、亮介の後方に居た梶原に飛び掛り押さえつけた。
「逃げろ」
文則は叫び、亮介は反射的に彼の言うままその場から逃げ出した。屋上の出入り口から階段を必死に駆け下りた。階段から廊下を走り、教室の前まで来てから後ろを窺がったが、誰も追いかけてくる様子がなかった。
それからしばらくの間、亮介は教室の机の椅子に座り、事態の結果を待った。横山達が、文則を叩きのめし、意気揚々と教室に入って来ることも考えられたが、亮介はそこから動くことが出来なかった。亮介は完全に逃げ切ることを拒否した。
「お前、未だいたのか」
文則が教室にのっそりと姿を現したので亮介は安堵し、涙が溢れそうになった。文則の制服は所々砂埃で汚れ、頭からは流血していた。亮介が、お前大丈夫か、と駆け寄ると、あいつら結構しぶとかったな、と笑い、いたたと額に手をやった。あいつらは?と亮介が訊くと、文則は、半殺しにしてやった、と言いながら考える仕草をして、続けてまあ、大丈夫だろう、と答えた。亮介は、何が大丈夫なんだと思ったが、それ以上追求するのはやめた。文則に帰えろうと声を掛けた。彼は、おう、と返し、それから亮介たち二人は帰路についたのである。
まったくあんた達は…。
姉は脱脂綿を消毒液に湿らせ、文則の額の傷口を覗き込むように探ると、乱暴に押し付けた。
いたた、痛いですよ、お姉さん。文則は大げさに痛がっていたが、裏腹に目尻は明らかに下がり気味で、その状況を楽しんでいるようだった。
ほら、じゃあ、上着も全部脱いで、ほらほら…。
さすがに年上の女性に裸を見られるのは恥ずかしいのか文則は抵抗したが、やがて諦めた。
文則の上半身には何箇所かの打撲痕が青く残っていた。横山達に金属バットで殴打された痕は、いかに彼が奮闘したかを物語っていた。姉は、まあ、すごい、と大げさに驚き、シップ薬を薬箱から取り出すと、その痕一つ一つに丁寧に貼り付けた。
さっ、これでよし、服着ていいよ。
姉は、文則の背中をピシャリと掌で打つと、薬箱を手にさっさと四畳半の部屋から出て行った。
「いい姉ちゃんだな」
いたたと背中に手をやりながら、文則は言った。
「今日は猫被っている」
「そんなことねえだろう」
「怒るとすごいんだ。それで喧嘩の毎日さ」
「でも、仲良く喧嘩できる相手がいるってのはいいもんだ、俺は一人っ子だからな」
文則は、遠くを見る目をしていた。亮介は彼のその目を見て、いつか見た茜色の夕陽を思い出していた。寂しげで、それでいて、どこか力強いあの夕陽、亮介はあの夕陽に感動したのだった。
「なあ」
「うん」
「聞かねえのか」
「何のことだ」
「…自殺の事とか」
彼の突然の問いかけに亮介は驚いた。自尊心の強い彼から、そんな言葉が出てくるとは思ってもみなかったからだ。
「お前が、話したかったら、話せばいい。そうじゃなかったら、話す必要がないよ。俺に気兼ねするなんて、お前らしくない」
亮介はそう言い、文則は、そうかと、呟き、沈黙した。沈黙の時間は長く、時間が亮介の背中に圧し掛かってくるように感じた。それからどのくらい経ったのだろうか、長い沈黙の後、彼は静かに言葉を選ぶように話し始めた。
「…あの頃、俺は精神的に参っていたんだ。両親は毎日喧嘩ばかりしていたし、俺はというと、毎日クラスの連中に、無視されていた。きっかけは、俺の身長が馬鹿でかくなっていったことにあるのかな。巨人症っていわれたよ、それまで仲良くしていた友人からな。それから、俺はそいつばかりか、それまで仲良くしていた友人全員に無視されるようになったんだが、意外とそれには耐えることができた。もともと、俺は一人でいることが苦痛ではなかったからだ。むしろ、家にいる方が苦痛だった。一番参ったのは、両親の喧嘩だな。最初は、親父の不倫からはじまったんだ。親父は不倫がお袋にばれ、お袋は、一度は親父を許した。けれど、親父の顔を見ると、彼女はどうしても許せなくなって、ほんの些細なことでも、親父を責めたてて、終いには、大喧嘩さ。それが毎日続き、その内家には俺の居場所がなくなったように感じるようになった。…・そして居場所をなくした俺は、学校でムカつき、荒れるようになったんだ。俺を無視した連中全てに、喧嘩を吹っかけ殴るようになっていたな。殴って殴って殴りまくったよ。…・或る時血に染まった相手の顔を見て、ふと俺は自分が必要のない人間に思えてきたんだ。一体何だったんだろうな、あの感情は。振り払おうと何度も相手の顔を殴ったが殴れば殴るほどそう思えてしょうがなかった。結局、そいつを殴り倒したあと、駆けつけた教師の手を振り切って、俺は教室の窓に足を掛け、一気に飛び降りたよ。三階からだったから、死んでもおかしくなかった。校舎の近くに植えられた木がクッションになって、助かったんだ。腕も足も至る所が骨折したけれど、とりあえずは生きていたんだ。病室には両親とも現われたけど、お互いに、俺がそうなったのは、お前のせいだと俺の前で、罵り合っていた。俺は、それをみて醜いと思ったよ。そして、俺はなんで生きているんだと思った。出来たらもう一度何処かから飛び降りて死んでしまいたいって思ったよ。…小学校の五年の時の話さ、もう二年近く前。なあ、亮介よお、俺は生きていてよかったのか?俺は今でも死にたくなるんだ。横山達を殴り倒したあと、何故か空しくなって屋上から飛び降りたらどうなるんだろうって思ったよ。なあ、亮介、俺はお前の何なんだろうな」
文則の告白は衝撃的なものだった。凡その想像はしていたが、それを遥かに大きく上回る経験を文則はしていた。亮介は、激しい鼓動を感じながら、ゆっくりと、確かに言葉を選んだ。
「文則は俺の親友さ、それ以上でもそれ以下でもないよ」
「本当か」
「勿論」
亮介が笑うと、文則は突然目を伏せ、嗚咽した。それこそ今までの不安の一切を吐き出すように。自分が一人ではないということを確認するために。
「じゃ、明日またな」
文則は母の、一緒に夕御飯でもという申し出を、猫たちが待っているからと丁重に断り、帰っていった。
姉は、文則が帰ったあと、亮介に向けて、あんたたちいいコンビだね、と言った。そうなのかも知れない。亮介は姉のその言葉を否定せずに、あいつは俺の初めての親友だから、と笑った。
次へと続く。

















![アイナ・ジ・エンド - 帆 [Official Music Video]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/77/f5/92393401bdbc0a86905caa6f8f33ec10.jpg)
![アイナ・ジ・エンド - 帆 [Official Music Video]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/35/7c/21f0d773d7635daee13341c7a29e3a9f.jpg)


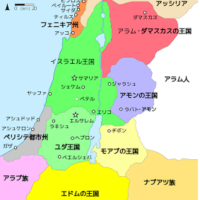






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます