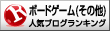8月13日、腰堡から長城線へむかう途中のA

四挺の重機が「折とぞよけれ」と、猛然敵の側面に、背面に、火蓋を切ったのである。予期しない変化は、今や攻守の立場を異にした。さしもに競い立ったA高地の敵も、段々谷底に向って退る気配が見える。
高地での遭遇戦。中国軍の人数は辻少佐がひきいていた中隊の「数十倍」ということなので3000〜5000ぐらいか。この場合、日本軍はすぐに撤退するべきだと思うのだが、そこに踏みとどまって防御射撃を行った。
距離50メートルはスコードリーダーでいえば1ヘックス、近接射撃にあたる。とうぜん防御側が瞬時に壊滅するかという時、思いがけない変化が起こった。
以下、辻少佐の回想録より抜粋。
「今日は駄目だ、参った」と観念し、最後の斬込みを、今か今かとばかり考えている時、全く思いがけない変化が起った。
Bの斜面から、コロコロと敵がころがり落ちて来る。その数が次第にふえて、雪崩のようにAの側面に近づいた。
けたたましい重機の音が、間もなくすべてを明かにしてくれた。
坂田支隊長は、この事あるを想して、朝早く、機関銃隊長内堀中尉に、B高地の占領を命じて置いたのだ。

四挺の重機が「折とぞよけれ」と、猛然敵の側面に、背面に、火蓋を切ったのである。予期しない変化は、今や攻守の立場を異にした。さしもに競い立ったA高地の敵も、段々谷底に向って退る気配が見える。
「突込め!」
高所から低所へ、猛然襲いかかるわが反撃は、B高地からの支援射撃で、戦術原則を絵に書いたような結果になった。
広い斜面に、無数の死傷者が横たわり、底を流れる小流は、文字通り赤くなった。 間もなく豪雨が、数刻の激闘を洗うかのように戦場を包んだ。
この雨の中に、もう既に勝負を終った戦場の草叢で、此処にも、彼処にも、手榴弾の炸裂する音が聞える。
何事であろうと、用心深く近寄って見ると、こは如何に、傷ついた敵の将兵が、自らの手で、命を絶ちつつあるのだ。
無傷の捕虜は一名もなく、重傷のものも…
屍体の標識によると、「中央軍、第二師」の「二個連隊」であった。
我に十倍する敵ではあるが、若い中小隊長が、先頭に立って突撃する姿は、五年前の上海事変には、想像さえ出来なかった事であり、負傷者が、自らの手で命を絶つことは、日本軍にさえ珍しい覚悟である。
「五年見ぬ間にこうも変ったものか? また呉下の阿蒙ではない…後方から、部下に拳銃をつきつけた五年前の督戦は、どこに姿を隠したのだろう。天晴れだ! 天晴れだ! 敵ながら天晴れだ! 共に東洋人だ! 」