
下手に要約すると、実は重要なことが抜けて伝わらなかったり、間違ったことが伝わってしまったりするのではないかという懸念と、この内容を要約するような力が私にはないということとで、大変な長文になってしまった。私自身にとっては役に立ったけれど、18,000字くらいなので、読んでみようと思われる方はそのつもりでお願いします。太字部分が本からそのままの引用部分です。
前の章では、「むかしむかし、人々は物々交換という方法で物の交換をしていました」というお話が単なる作り話に過ぎないことが明らかにされた。この章でも、まず、いまなお、「なぜ経済学の教科書が架空の村からはじまるか」というと、「物々交換の神話は経済学の言説全体の中核をなしているため、なきものにするわけにはいかない、といったところが答えであろう」というところから始まる。
とりわけ興味深いのは、『国富論』で「スミスが示したかったのは、この経済なるものが同時代にアイザック・ニュートンが発見していた物質世界を支配する法則と同種の法則にしたがって動いている、ということだった」という点である。「足枷のない自由市場さえ与えられれば、わたしたちの自己利益の追求は、[利己的である]にもかかわらず[神の見えざる手]によってみちびかれて一般的福利を促進する」ということである。
わたしたちは、ニュートンが発見した「物質世界を支配する法則」に逆らうことはできない。それは受け入れざるを得ないものである。もし、「この経済なるもの」がそれと同種の法則にしたがって動いているなら、わたしたちは「足枷のない自由市場」で「自己利益の追求」をするほかないことになってしまう。
この点は重要だと思われる。なぜなら、「足枷のない自由市場」で「自己利益の追求」をするにあたって、つまり「この経済なるもの」が支配する世界の中で有利な条件を持つ人たちに対して、彼らがそうすることによって最大の利益を得ることについての根拠や、そうすることの正当性を与えることになるからだ。反対に、不利な条件を持つ人たちにとっては、たとえどんなに悲惨で、絶望的な状態に陥っても、「この経済なるもの」の支配する世界は受け入れざるを得ないものとなる。それは変えることができない世界の法則なのだから。
続いて、貨幣についてのお話になるが、経済学者たちは貨幣の存在ないし不在にまつわる問いそのものをとくに重要でないとみなすようになり、「貨幣自体に意義はなし。経済――[実体経済]――とは膨大な物々交換なり」という結論に至る。
しかし、つぎのようの理由で、「貨幣自体に意義はなし」とするわけにはゆかない。
・貨幣が存在しないなら、そのような大規模な物々交換のシステムも発生することはない。
・「自分たちは、[主要な生業(なりわい)が事物の交換であるような個人および国家の集合」である」と想像することを可能にしたのは貨幣である。
後者については、「貨幣の存在それだけではこのような世界観を植えつけることはできなかったこともはっきりして」いるとし、そのために必要なことは、「アダム・スミスが価値を切り下げようと試みた政府の政策」であったと述べる。市場の育成や以下のような通貨政策である。
・通貨価値を銀に連結し安定させる。
・貨幣供給、とりわけ流通する小銭量の大幅な増加。
・当時唯一の紙幣供給源であった銀行の慎重な統制。
・紙幣を貴金属にしっかり連結させておく。
「この見解(経済とは膨大な物々交換なりという見解)が主流派経済学のものとなったわけだが、そのため貨幣を信用とみなすもうひとつの諸理論――ミッチェル・イネスの主張したような――は、たちまち周縁的な地位に追いやられてしまった」「というわけで、これらの代替的理論が実際にどのようなものだったか、考察してみるのは有益だろう」となり、「貨幣の国家理論と貨幣の信用理論」の話に移る。
<貨幣の国家理論と貨幣の信用理論>
「信用論者たちは、貨幣は商品ではなく計算手段である、いいかえると、貨幣は[モノ]でないと主張した」「1時間や1立方センチメートルにふれることができないように、1ドルや1ドイツマルクにふれることはできない。通貨単位とは抽象的な尺度単位にすぎない」というわけだ。
では、「貨幣が尺度にすぎないなら、それはなにを測定するのか?」という問題になるが、グレーバーは言う。「答えは単純だ。負債である。一枚の硬貨とは実質的に借用証書なのである」「このようなことが真実であるのはまちがいない。というのも、金や銀の硬貨が使用されているときであってもそれらが金銀地金の価値で流通することは、ほとんど絶対にないからである」と。
そして、「信用貨幣はどのように発生しえたのか?」という話になる。
ある人が発行した借用証書が信用に足るものとして、同じ目的でつぎつぎに第三者に対して使われてゆけば、その借用証書は貨幣と同じ役割を果たすことになる。AはXに対し、あるものを譲った。代わりにXはAに借用証書を渡した。BはAが欲しいと思っているものを持っている。AはBからそれを譲り受け、代わりにXから受け取った借用証書をBに渡す。これが繰り返し行なわれるとき、その借用証書は貨幣と同じ役割を果たすということだ。ただし、ここでは、その借用証書について、誰もが信頼している必要がある。Bはその借用証書が、B自身が欲しいと思っているものを持っているCに対しても使えるということを確信している必要がある。それに続く、D、Eがいて、その誰もが最初にXが発行した借用証書を信頼している必要がある
ここで問題は、「人びとが紙切れを信用しつづける理由を」どのように立証するかということになる。いま各国で使われている銀行券=紙切れはどうして信用され、流通しているのかという問題でもある。「貨幣国家理論」ではつぎのように説明する。
先の借用証書について、もし、借用証書の発行元、上記の例ではXが、かのイングランド王ノルマンディー公アイルランド、アンジュー伯であるヘンリーⅡ世だったら、ほとんど問題は消えてなくなる。つまり、その借用証書はだれもが信頼し、受け取るだろうということだ。ヘンリーⅡ世、皇帝、国王、国家が借用証書の発行元であれば、国民のだれもが信頼し、受け取るだろうということである。
貨幣国家論者であるクナップは「それが純銀であろうと、悪鋳された銀であろうと、革製の代用貨幣であろうと、鱈の干物であろうと、どうでもいいのだ。つまり、国家が、それによる税金の支払いを受け入れさえすればよい。というのも、なんであろうと国家に受け入られているものは、当の受け入れられているというそのことによって通貨となる」と述べる。
さらに、その借用証書が貨幣としての役割をはたすのは、あくまで元の発行者がみずからの負債を返済しないということという点も重要である。返済が完了した借用証書は記念にはなっても、何の意味も効力もなくなるので、当然のことである。
「1694年にイギリスの銀行家たちからなる協会が、国王に120万ポンドの融資をおこなった。そのかわりに彼らが受け取ったのは、……新たに生まれた国王の負債を流通させる、ないし[貨幣化する]権利である」「それがうまくいくのはあくまでも元の融資が未払いであるかぎりにおいてである。今日にいたるまでこの貸付けは返済されていない。返済日が来ることもありえない。もし返済されてしまったら、英国の金融システム全体が消滅してしまうだろう」というわけである。
「そもそもなぜ王国は臣民たちに納税を強いたのか?」これがつぎの問いになる。「金を徴収し、じぶんの肖像をそこに刻印し、臣民のあいだで流通させたあとで、そのおなじ臣民たちに、それを[税として]返すよう要求する目的はなんなのか?」ということである。
「もしアダム・スミスが正しければ、そして金と銀が政府から完全に独立した市場の自然なはたらきを通じて貨幣になったのなら、金山と銀山を支配することだけですむではないか?」「実際に古代の国王たちは通常それをおこなっていた」「領地内に金山や銀山があれば王たちはそれらを独占したのである」
グレーバーの答えはつぎのようになる。
「貨幣と市場が同時に出現したのでないとするのなら、完全に理にかなっている。これが市場を生みだす最もかんたんで効果的な方法だからだ」としてつぎのような仮説的な例をあげる。
「ある国王は五万人からなる常備軍を維持したい。古代および中世の諸条件のもとでは、それだけの兵力を養うのは大問題であった。このような軍勢は、駐屯しているあいだに、野営地の10マイル以内で食べられるものならなんでも食い尽くしてしまう。行軍中でなければ、必要な食糧を貯蔵し入手し運搬するためだけに、ほとんど[軍勢と]おなじ数の人間と動物を雇う必要が出てくる。それに対して、兵士たちに硬貨を配布し、ついで、王国内のすべての世帯にその硬貨の一部を王に返すべしと要求するなら、一夜にして国民経済は兵士への物資供給のための巨大機械に転換することになる。いまやすべての世帯が、硬貨を手に入れるためにあれこれと方法をさがしだし、兵士の欲しがるものを供給するという全般的なもくろみに参加することになる。市場はその副次的効果として発生するのである」
「市場の発生したのが古代の軍隊の周囲においてであることはまったくあきらかである」「古代の支配者たちはそのほとんどが、実に多くの時間を費やして鉱山と兵士と税と食糧のあいだの関係について考えをめぐらせている」(カウティリヤの『実理論』、ササン朝の『統治の環』、中国の『塩鉄論』など)「国家と市場はいずれにせよ対立するというスミスの遺産に由来する根強い自由主義的想定にもかかわらず、歴史の記録によれば事実はその正反対であるということだ。国家なき社会は市場ももたない傾向がある」と言う。
「しばしば主流経済学者たちは、実際には政府のために活躍する」とも言う。彼らが対立しているはずの「表券主義者(貨幣そのものが実質的にその名目どおりの価値を持っているわけではないという考え方をする人=信用貨幣論者)たちが描写したような政策――つまりそれまでなかったところに市場を創出するための税制を追求するよう助言している」とのことである。
この市場創出は「ことさら植民地世界にあてはまる」として、マダガスカルでフランスが行なった政策(人頭税の導入)によって、島民のそれまでの生活が破壊され、フランスの植民地となり、市場が形成されたことが紹介される。「このような事例はあげだしたらきりがない。そこに市場がそれまで存在していなかった世界ならどこでも、ヨーロッパの軍隊に征服されたあとでは、おなじようなことが起きたのである。物々交換を発見はしなかったが、ヨーロッパ人たちは市場のようなものをそこにつくるため、主流派経済学が拒絶したまさにその技術を存分に活用したのである」とのこと。
<神話をもとめて>
経済学者たちが、「かくもおびただしい反証にもかかわらずあいもかわらぬ物語(物々交換の神話)を語りつづける」のは、「人類学者たちが、単純で説得力ある貨幣の起源の物語を提唱できない」かららしい。
人類学者であるグレーバーは言う。(貨幣の起源の物語を提唱できないのは)「そういったものが存在すると信じる根拠がないからである。貨幣は音楽や数学や装身具とおなじように[発明された」ものではない。……それは、1つのXは6つのYに相当するというように、物事を割合として数学的に比較するひとつの手段なのである。だからそれはおそらく人間の思考とおなじぐらい古いものとなる。起源であるものをより具体的に求めようとするやいなや、わたしたちは今日[貨幣」と呼ぶものに収斂している数多くの多種多様な習慣や実践を発見してしまうのだ。経済学者や歴史家などが単一の定義にいたることに非常な困難をおぼえる理由がまさにこれなのである」と。
つまり、今日わたしたちが、まったく疑うこともなく、当然のこととして考えている貨幣なるものの使い方や意味は、人類史としてみれば、「多種多様な習慣や実践」のうちの一つに過ぎないということだ。だから、経済学者や歴史家が、単一の定義にいたるお話を作り出そうとしてもできないということになる。
ここで、「大規模な経済崩壊のたびに、旧来の自由放任主義的経済学者たちは一撃をくらってきた」([神の見えざる手]は機能せず、崩壊が起きた)「1930年代の大恐慌までには、政府が貨幣と貴金属との安定した連結を保証しているかぎり市場は自己調整しうるという発想そのものが徹底的に失墜することになる」ということで、ケインズ主義のお話になる。「およそ1933年から1979年のあいだに、すべての主要な資本主義国は方向転換し、いずれのヴァージョンかはともかくケインズ主義を採用」することになったという。
「正統派ケインズ主義の出発点にある想定は、政府が効果的に乳母の役割を演じないかぎり資本主義的市場がうまくいくことはないというものである」スミスの神の見えざる手を否定している。
また、ケインズは「その最初期の起源がなんだったにしても、過去4000年のあいだ、貨幣は実質的に国家の創造物だった」「今日ではすべての文明社会の貨幣が表券主義的であることは議論の余地がない。……貨幣とは信用であり私人間の契約上での合意(たとえば融資)によって存在することができるのであって、国家は合意を執行し法律条項を指令するにすぎない」と言っている。「銀行は貨幣を創る、そしてその権能に内在的限界は存在しない。銀行がどれほど貸付けようと借手は特定の銀行にカネを返すよりほかない。だから銀行システム全体の観点からすると借方と貸方の総計は常に相殺されるであろう」とも言っている。
ここで、「貨幣についての国家=信用理論の真の弱い環は、常に税という要素だった」として、国家が「いかなる権利において」税を要求するのか、「それはどう正当化されるのか」という問題が提起される。先の問題は、なぜ国は国民から税を徴収するのか、その目的は何かというものであったが、ここでの問題は、「国民はなぜ国に税金を払わなければならないのか?」「国が国民から税を徴収する権利、正当性はどこにあるのか?」という問題である。
「いまでは、その答えなら知っているとだれもがおもい込んでいる」「税金を払うのは、それでもって政府が保障を与えてくれるからさ、というわけだ」「初期国家が実際に提供できた唯一の保障が軍事的保護だった。もちろん、いまでは政府はあらゆるものを提供している」「こういったことはどれも、万人がなんらかのかたちで合意したある種の原初的[社会契約]に遡行するといわれている」
「ところが、いつ、だれによってその契約がなされたのかを知るものはいない」「遠い祖先の決定によって拘束されなくてはならないのはなにゆえかを知るものもいない」
そこで、「国家=信用理論をふまえつつ考案された代案的な解釈がある。それは[原初的負債論]と呼ばれ」るとして、この章の表題である[原初的負債論]ということばが出てくる。[原初的負債論]は、なぜ国に税金を払わなければならないかを説明する理論のようである。
「この立場が浮上してきたのはごく近年のことであり、ユーロの性質をめぐる論争がきっかけだった」とのこと。つい最近現れた主張だと言ってもいいようだ。しかし、その主張を裏付けるために参照される文献は古い。「初期のサンスクリット語による宗教文学の文献に注目する。ヴェーダおよびブラーフマナに編纂された聖歌、祈祷、詩、それにつづいて数世紀にわたって書かれた聖職者の解説、現在ではヒンドゥー教の思想の基盤と考えられている文書類である。……これらのテキストは負債の本質についての知られているかぎり最古の歴史的考察」だとのこと。
「通貨政策と社会政策を分離しようとするどんな試みも究極的には誤りであるというのが、原初的負債論者たちの核となる主張である」とされる。また、「彼らによれば、……政府は貨幣創造のために税を使うが、それが可能であるのは、市民全員がお互いに負っている負債の守り手となるからである。負債こそ社会の本質そのものなのだ。負債は貨幣や市場にはるかに先立って存在しており、貨幣と市場自体はそれをバラバラに切り刻む手段にすぎない」とのことである。
原初的負債から貨幣の発明、それを国に税として納めるにいたる話はかなり煩雑で長いので、要点だけ述べることにする。
原初的負債論者によれば、人間の存在自体がひとつの負債だということになる。誕生というものを、すべての人間が負う[原負債]とする。なぜならば、この世に生まれてきたことそのことが、この宇宙(神々)が持つ能力のおかげなのだから、すべての人間は生まれながらにして、この宇宙(神々)に対して借りができる、つまり負債を負うことになると言う。しかし、この負債の支払いは完済が不可能(生まれて、生きていることそのものが負債だとすれば、その完済は死をもってするしかなくなる)なので、供犠(神霊に対して供物や生贄を捧げること)というかたちをとることになる。このような信仰=主張は、主権的[至高の]諸権力の発生に結び付いている。この主権的権力は、原宇宙全体を代表する能力を持つということによって正当化される。そして、このような主権的権力こそが、負債を清算する手段としての貨幣を発明したのであるとされる。この貨幣という手段は、「死を課すことが生を守る永遠の手段になる」という供犠の逆説を、抽象化によって解消することを可能にする。このような制度を通して、信仰は通貨に転移される。そして貨幣が流通することになるが、その返済は「生という負債への課税、清算」という別の制度によって組織される。かくして貨幣は支払い手段としての機能もまた担うようになるということになる。
上記の[主権的権力]とは実際には[国家]を意味している。「最初の王たちは聖なる王であり、じぶん自身が神か、あるいは、宇宙を支配する究極のエネルギーと人間とのあいだの特権的な媒介者かのいずれかであった」とのこと。
「もしも、じぶんを創造してくれたということで、社会に対して万人が負っている原初的負債の庇護を王が引き継いだだけであるとするならば、それは、なぜ、政府がわたしたちに税金を支払わせる権利があると感じるのかについて、すっきりとした説明になる。税とは端的に、じぶんを形成した社会に対してわたしたちの負う負債の尺度にすぎないというわけである」
しかし、「このような議論でも、この種の絶対的生の負債がどのようにして貨幣へと換算可能になるのか、はっきり説明されていない」「神に対して負う絶対的負債が、どのようにして、従兄弟やバーテンダーに対して負うようなきわめて具体的な負債にいたりつくのか?」という問題が残る。
原初的負債論者の回答は「もし税がじぶんたちを創造した社会に対して負う絶対的負債を表象するなら、社会に対して負う、もっと具体的な負債を計算しはじめるときが実質貨幣の創造にむかう第一歩である」と言う。「つまり、罰金や手数料や違約金を計算しはじめるときであり、あるいは、なんらかの損害を与えてしまった個人、したがって[罪業」や[罪責性」の関係にある個人に対して負う負債を計算しはじめるときである」となる。
ここで、人類学者としてのグレーバーは、経済学者が、自分たちに都合の悪いものには目を向けないという点を指摘する。
「わたしたちがこれまで検討してきた貨幣の起源についての理論すべてについて奇妙なことのひとつは、それらが人類学的証拠をほとんど完全に無視していることである。人類学者たちは、国家なき社会で経済が実際にどのように動いてきたか、国家と市場によって伝統的な人間の営みが解体されつくしていない場所でいまだ経済がどのように作動しているかについて膨大な知見を有している。たとえば東アフリカや南アフリカにおける貨幣としての牛の使用について、南北アメリカやパプアニューギニアにおける貝殻貨幣について、ビーズ貨幣、羽根貨幣、鉄輪、子安貝、スポンディルス貝殻、真鍮の棒、キツツキの頭皮の貨幣としての使用について、枚挙にいとまのないほどの研究が存在している」
「こういった文献が経済学者に無視されている理由は単純である。この種の[原始通貨]が物の売買に使用されることはめったになく、使用されたとしても、それが鶏や卵や靴やジャガイモといった日常的な資材の売買であることは決してないからである。それらは事物の入手にではなく、主として人びとのあいだの関係の調整のため、とりわけ結婚の取り決めや、殺人や傷害から生じるいさかいの調停のために使用されるのである。わたしたち自身の貨幣もおなじようにはじまったと信じるに足る根拠はいくらでもある」ということだ。
負債論者も「わたしたち自身の貨幣もおなじようにはじまったと」いう可能性に関心を持っており、その理由は「人類学の文献を無視しながら古い法典に眼をむける傾向」にあると言う。
「二〇世紀の最も偉大な貨幣研究家の一人であるフィリップ・グリアーソン」なる人がおり、負債論者はそのグリアーソンの研究からインスピレーションを得たとする。グリアーソンは1970年代に「貨幣は最古の司法上の慣行から出現した可能性がある」と示唆した人である。負債論者はそこに注目したようである。先に引用した部分であるが、原初的負債論者が「実質貨幣の創造にむかう第一歩」として「罰金や手数料や違約金を計算しはじめるときであり、あるいは、なんらかの損害を与えてしまった個人、したがって[罪業」や[罪責性」の関係にある個人に対して負う負債を計算しはじめるときである」と言うのはこのことだろう。
「グリアーソンはヨーロッパ暗黒時代の専門家で、600年代から700年代にかけてローマ帝国が崩壊したあと、多くのゲルマン諸族―ゴート、フリジア、フランクなどによって確立され、ロシアからアイルランドまでいたるところでたちまち法典のモデルとなった、いわゆる[蛮民法典]に魅了されるようになった」とのこと。
それらの文書群には、詳細は省くが、賠償を必要とするさまざまな具体例があげられ、また、賠償にあたって有用になる「一般家庭にありそうなあらゆる物品(こういった品物のほとんどが当時市場で購入可能だったようにはみえないにもかかわらず)の貨幣価値まで詳細な分類」が明記されていた。グリアーソンの言う「司法上の慣行」を表していることになる。グレーバーは「賠償金の取立てこそが常に等価計算を要請してきたに違いない」と言う。
ところで、「わたしたちは自己存在すべてを他者に負っている。これはいわずもがなの真実である」だから「以上のような議論のうちには、きわめて説得力のあるなにかがひそんでいる」「直感に訴えるところが大きい」とグレーバーは言う。
しかし、「これを負債として考えることに意味はあるのか?」という大きな疑問を投げかける。
「結局のところ負債とは定義からして少なくとも返済することを想像できるものである。ところが、じぶんの両親への借りを清算したいと望むことはとても奇異なことなのである。そこにはもはや彼らを親とは考えたくないというふくみがひそんでいるのだから。そうだとしたら、人類全体に対して借りを清算したいなどとわたしたちは本当に望んでいるのだろうか?そもそもそこにはたして意味があるのだろうか?それにそういった欲望は本当に全人類の思考にとって本質的な特性なのだろうか?」という疑問だ。
「原初的負債論者は……神話を発明しているのだ」と言う。「ヴェーダという資料を選択することのもつ意味は大きい。わたしたちはこれらの文書を創作した人びとについてほとんどなにも知らず、それらの人びとを形成した社会についての知識もきわめて乏しい。……その[えられる知識の乏しさの]結果、資料はまっさらなキャンバスのようなもの、または未知の言語の象形文字で覆われたキャンバスとして機能することが可能になる。その表面にほとんどなんでも望むものを投影できるのである」つまり、新たに神話を作り出し、それを投影できるということだ。
「古代世界において、自由市民が税を支払うことは、ふつうはなかったということである。一般的にいって貢納を徴収されたのは被征服民のみだったのである。これは古代メソポタミアにおいてすでにそうだった。独立都市の住民たちに直接税を支払う必要は通常なかったのだ」「それどころか市は、ときに市民に金銭をばらまくことさえあったのだ」という指摘も興味深い。
「ヴェーダの創作におそらく2000年先立って、有利子の貨幣貸付という実践が最初に発明されたにもかかわらず――それに世界ではじめて国家が生まれた場所もまたメソポタミアであったにもかかわらず――[原初的負債論者」がシュメールやバビロニアについてあまり語ることがない」のはつぎのような理由による。「ここでもまたみいだされるのは、さまざまな点でこうした理論家たちの予想とは正反対の事態」だったからである。
そこでは、「宇宙の支配者の権能において臣下の生に干渉するとき、公共の負債を課すよりも、民間の負債を帳消しにするという手段を彼らはとった」有利子貸し付けが商業貸付だけでなく、消費貸付にも及び、返済できなくなったものは、すべての財産を取り上げられ、「負債懲役人」にまでおとしめられた。「負債懲役人とは奴隷ではないが奴隷にきわめて接近した存在であり、債権者の家庭、ときには神殿や宮殿で永久に奉仕を強制された」という。「しばしば社会を引き裂く脅威となった」「全面的な社会崩壊の可能性に直面し、シュメールのちにはバビロンの王たちはくり返し、……債務帳消しと呼ぶところの全面的特赦を布告している」とのこと。
*******
この後、まとめに入ってゆく。
「おそらくこういった研究全体の最大の問題は、最初の仮定、すなわち[社会]なるものに対する無限の負債からはじめるという仮定である。そこでは、神々にむけてひとが投影しているのは社会に対するこの負債であるということになる。そして、つづいて王たちや国民政府によって徴収されるのは、このおなじ負債であるというわけだ」
「世界は[社会]という一連のコンパクトなモジュール単位に組織されていて、だれもがじぶんはそのなかのどこにいるのか知っていると想定されている」が、「歴史的にみれば、これはきわめてまれな事例である」
「歴史上の大部分の人間にとって、じぶんがどの政府に属しているのか明白だったことはなかったのだ。ごく最近にいたるまで世界の多くの住民は、じぶんがどの国の市民なのか、あるいはそれがなぜ重大な問題なのか、確信をもったことなどなかったのである」とのことだ。
「[社会]と呼ばれる自然な単位は存在しない。とはいえ、もしそうだとすれば、わたしたちは本当のところだれに対してなにを負っているのか?万人?万物?それとも、人や物によって程度に強弱があるのか?それに、かくも拡散しているなにものかに、どうやって負債を支払うのだろう?あるいは、より端的にいって、いったいだれが、どんな根拠をもって、返済方法を指示する権威を発動できるのか?」という問題になるが、「ブラーフマナの作者たちは空前絶後の洗練をきわめたモラルについての省察を与えてくれている」ようである。
「彼らによる答えに(古代インドにも王や政府が確実に存在していたにもかかわらず)社会にも国家にも言及がみられないのは意義深い。そのかわり負債は、神に、賢者に、父に、[人間たち(men)」に個別的に定められている」としてグレーバーはつぎのようにまとめている。
・宇宙、宇宙の力、現代的にいいかえると〈自然〉に対しての負債は、儀式によって返済される。
・わたしたちにとって最も価値ある知識と文化的成果をなしえた人びとに対しての負債は、わたしたち自身が学習し人間の知識と文化に貢献することで支払われる。
・わたしたちの両親、およびその両親、つまり祖先に対しての負債は、じぶん自身が祖先となることで返済される。
・人類全体に対しての負債は、異邦人に対する寛容によって、人間的諸関係つまり生を可能なものにする、社会性にかかわる基本的なコミュニズム的土台を維持することによって返済する。
「これらは商業的負債とはなんの関係もない」「ブラーフマナの作者たちが本当に示そうとしていたのは、究極的には、宇宙に対する人間の関係は根本からして商取引とはほど遠く、そうなる可能性もないということであろう」「このリストは以下のようなふくみを巧みなやりかたで表現していると解釈することさえできる」とグレーバーは言う。
「負債から[自己を解放する」ただひとつの方法は、文字通りに負債を返済することではなく、負債など存在しないことを示すことである」
そして、「わたしたちの罪責性は、宇宙に対する負債を返済できないことによるものではない。わたしたちの罪責性とは、[存在するすべて、またはこれまで存在してきたすべて]と、いかなる意味であれ同等のものと考えるほどおもいあがっているため、そもそもそのような負債を構想できてしまうことにある」
「ひとはみんな人類、社会、自然または宇宙(いかようにもお好みでよい)に対して無限の負債を負っている」と考えたとしても「[じぶん以外の]別のだれかが支払い方法を指示できるわけではない」「もしそうだとすれば、確立された権威のシステムのほとんどすべて宗教、道徳、政治、経済、刑事司法体制を、それぞれ異なる欺瞞の方法とみなすことができる。それらは計算不可能なものを計算できるとうそぶき、制約なき負債のうちのあれこれの部分をかくかくしかじかのように返済せよと指令する権限を詐称するにすぎないのだ」と言う。
もしその負債を返済したい、その必要があると思うのなら「返済方法をどうしたいかをじぶん自身で決定するわたしたちの能力」こそ「人間の自由」ということになると言う。
ところが、「実存的[存在的」負債についての理論は、そのかわり権威の構造を正当化するあるいは権威の座を主張する手段に堕してきた」と言う。
「[原初的負債論者]には、それ以外にも重要な課題があった。彼らが本当に興味をもっていたのは宇宙ではなく[社会]だったのである」[社会]という言葉が「かくも単純かつ自明な概念にみえるのは、たいていの場合、「国(nation)」の同義語として使用されているからである」とする。
しかし、「単一の境界に囲まれた統一体として「社会」を想像することが可能になった」のは「入念な国境管理と社会政策をともなった近代国家においてはじめて」であると言う。
そして、「この[社会]という概念をヴェーダの時代や中世に遡及的に投影することは、常に一片の欺瞞なしにはありえない」「原初的負債論者がおこなっているのは、まさにこれ、すなわち概念の過去への投影である」と問題点を指摘する。
「実際に、原初的負債論者の語る複雑な思考のすべて――社会なるものが存在しており、それに対してひとは負債を負っており、政府はそれを代弁しており、世俗的神のようなものとして想像されうるといった――は、おおよそフランス革命の頃かその直後に一斉に出現したものである。いいかえると、それは近代的国民国家の理念に並行して生まれたのである」つまり、ヴェーダの時代や中世に、そのような考え方などまったくなかったということである。
これらの思考のすべては、19世紀の哲学者で政治パンフレット作家でもあったオーギュスト・コントの著作にはっきりとみてとれるとのこと。
「社会への無限の義務という彼(コント)の思想は、最終的に[社会的負債]という観念に結晶化し、社会改良家や、のちにはヨーロッパおよびそれ以外の多くの地域で社会主義的政治家によって取り入れられたのだ」「われわれはみな社会への債務者として生まれる」「国家とはわたしたちを形成するところの社会にだれもが負っている実存的負債の管理者にすぎない」となる。
コントの影響を受けた「デュルケームによれば、あらゆる宗教のあらゆる神々は常にすでに社会の投影である。だから、社会の宗教などあらためて必要でさえない」「宗教とはすべて、わたしたちの相互依存、決してその総体について自覚されることのない無数のやり方でわたしたちに影響している依存を、認識する方法にすぎないのである。[神]と[社会]は、究極的に同一のものなのだ」となる。
グレーバーは言う。「これまで数百年にわたって、相互依存によってだれもが負う負債の守護者、個人を個人たらしめている無形の社会的総体の正当な代理人は、必然的に国家でなくてはならないと想定されてきた。これが問題なのである」と。
そして、「[原初的負債]という思想のうちに、究極のナショナリズム神話をみてとることさえできる。わたしたちは、かつてわたしたちを創造した神々にわたしたちの生を負っていた。動物を生贄にするというかたちでその利子を支払い、究極的にはみずからの生によって返済を完了した。今日わたしたちはじぶんたちを形成した〈国〉(Nation)に対してみずからの生を負っているのであり、税というかたちでその利子を支払い、敵から国を防衛するさいにはみずからの生命をもって支払っている」と言う。
そして、最後のまとめはつぎのようになる。
「これは二〇世紀の大いなる罠である。一方には市場の論理がある。たがいになにも負うことのない個人の出会う場であると好んで想定されているのが市場である。他方には国家の論理がある。だれもが決して返済しえない負債を背負って出発する場所である。そして市場と国家は正反対のものであり、それらのあいだ「中間」にこそ人間の唯一の真の可能性があると、わたしたちはたえまなく教えられてきた。しかしこれはあやまった二分法である。国家は市場を創造する。市場は国家を必要とする。どちらもたがいなくしては存続しえないし、少なくとも今日知られているようなかたちでは存続しえないのである」
* ビットコイン(デジタル通貨)について
貨幣についてのここまでの理解で、ビットコインなどのデジタル通貨について考えてみたい。こんにちの貨幣も、それが物の交換にあたっての価値(交換価値)を計る尺度であることは間違いがない。尺度であるためには、その目盛は安定している必要がある。目盛の間隔がいつも変わってしまうようなものは尺度としては使えない。デジタル通貨はその取引価格が常に乱高下しており、さらに変動幅も大きい。他の商品の購入にあたって、デジタル通貨での支払いも行なわれているとしても、デジタル通貨そのものが、投機の対象となって取引きされているのが実態であると思われる。また、デジタル通貨は、その価値を誰もが認め、受け取るという保障もなければ、税金の支払いにも使えない。つまり、国がそれを保障しているわけでもない。したがって、少なくとも、いまの時点でデジタル通貨は貨幣とは言えない。デジタル通貨は投機商品の1つに過ぎない。
将来、デジタル通貨の安全性や取り扱いの簡便性などが国によって認められ、国がその管理をし、安定性を保障するようになれば、それが貨幣となる可能性はある。













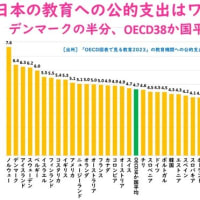



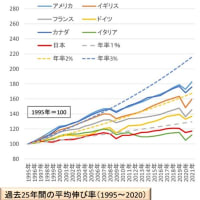


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます