
* 以下、太字部分は『負債論』からの引用部分
「ただの義務、すなわち、あるやり方でふるまわねばならないという感覚、あるいはだれかに何かを負っている [借りがある] という感覚、それと負債との違いとは、正確にいえば、なんであろうか?」「負債と義務との違いは、負債が厳密に数量化できることである。このことが貨幣を要求する」。だから「貨幣と負債はまったく同時に登場している。……負債の歴史とは必然的に貨幣の歴史なのである」したがって、「負債が人間社会において果たしてきた役割を理解する最も簡単な方法は、幾世紀にもわたり貨幣がまとってきた形態とその使われ方――そして後追いで現れたそうした事象の意味についての議論――をたどることである」ということで、この章は始まる。
「経済学者たちが貨幣の起源について語るとき、負債は常に二次的なものである。最初に物々交換があらわれて、ついで貨幣がやってくる。信用はそのあとではじめて発展する。……ほぼ一世紀のあいだ、筆者のような人類学者たちは、このような見方にはなにか大きなまちがいがあると指摘してきた」「現実の共同体や市場などのほとんどすべての場所でほとんどだれもが、実にさまざまなかたちで、だれかに負債を負っていて、それらのほとんどの取引が通貨を使用することなくおこなわれていることが発見される」
この章では、ほとんどの人の常識となっているつぎのようなお話が「神話」に過ぎないとして否定される。
「むかしむかし物々交換がありました。でも物々交換が成り立つにはとても骨が折れたのです。そこでひとは、お金を発明しました。そこから銀行や信用が発展したのです」
物々交換においては、交換当事者の一方であるAは、自分が必要とする物を持っているBを探さなければならないだけではなく、さらにそのBは、Aが持っている物と交換したいと考えている必要がある(欲求の二重の一致)。このような一致が頻繁に起きるとは考えにくい。したがって、そのような一致を条件とする交換が一般的に行なわれる社会(=物々交換の社会)というものが可能になるのだろうかという疑問が出てくる。欲求の「二重の一致」以外にも、それぞれが持っている物の交換価値をどのように測り、両者が納得できるようにするかという問題も大きい。また、むかしむかし、人々が貨幣を発明しなければならないほどの量の「交換を目的とする物」を生産していたのかという疑問もある。
グレーバーによれば、「コロンブス以降の時代、スペインとポルトガルの冒険家たちが金と銀を求めて世界中を探査するにつれて、こんなあやふやな物語は消え去っていった。物々交換の土地を発見したという報告はどこからもなかったからである」「インド諸島やアフリカに向かった16世紀と17世紀の旅行家たちのほとんどが、すべての社会が政府を持ちすべての政府が通貨を発行しているのだから、あらゆる社会が独自の形態の貨幣を持っていると考えていた」「数世紀にもわたって研究者たちは、この物々交換のおとぎの国を発見しようと努力してきたが、だれひとりとして成功しなかった」「その代わり(に)発見されたのは、ほとんど無際限に多様である経済システムだった」とのことである。
ケンブリッジ大学の人類学者キャロライン・ハンフリーも、「物々交換経済について純粋で単純な事例が記述されたことなどない。物々交換からの貨幣の発生についてはなおさらである。入手可能なあらゆる民族誌が、そんなものは存在しなかったことをはっきり示している」とその著作で述べているとのこと。
そもそも物々交換というものがこの世界には存在しなかったのかというと、そうではないとする。貨幣が生まれる前の社会でも、物と物との交換があったことは間違いないようである。しかし、つぎのように、それはわれわれが想像するようなものとはまったく異なる形態で行なわれていた。
「普通、物々交換が起きるとすれば、それはよそ者どうしの間においてであった。敵どうしの間ですら例外ではない。ただし、その社会は単純社会であり、分業的要素があまりなく、伝統的にせいぜい100人程度の小規模なバンド(狩猟採集社会に見られる居住集団。動植物資源を追って季節的に移動する。50人前後からなっている場合が多い)に組織されている」「こうした物々交換による交易の事例すべてに共通しているのは、ふたたび会うことのほとんどない、どのような継続的な関係ももつことがないようなよそ者どうしの交換であることだ」
その交換の形態の例も挙げられている。詳細は述べないが、それは、特別な宴会を伴う儀式めいたかたちの中で行なわれ、けっして日常的なものではなかったと見られる。
また、「物々交換がことさら古い現象ではない」とも言う。「真に普及したのは近代においてはじめてである」「物々交換のシステムの出現するのは、しばしば国民経済が崩壊するときである」「最近の例では、1990年代のロシア、そして2002年のアルゼンチンである。そのとき、ロシアではルーブルが、アルゼンチンではドルが、実質的に消失した」「物々交換は、現金取引に慣れた人びとがなんらかの理由で通貨不足に直面したときに実践したもの」ということである。日本でも、先の敗戦直後には貨幣に対する信用がなくなり、物々交換が行なわれた。つまり、物々交換が成立するためには、すでに貨幣が存在し、貨幣による取引が行なわれていた社会であるという条件が必要だということになる。
物々交換から貨幣が生まれたと説く経済学者の話に共通しているのは、すでに貨幣を使って日常的に物を交換している人たちに対し、「もし貨幣がなかったら大変でしょう」と同意を求め、「だから貨幣が発明されたのです」という説明方法を採っていることである。しかし、生活に必要なものを交換によって手に入れることなどしていなかった人たち、交換などめったにしなかった人たちが、その話に同意するとは思えないし、そもそも、その人たちが貨幣の必要性を感じることなどありえないのである。
信用についてもつぎのように、経済学の言うような最後に現れたものではない。
「いまに伝わる人類最初期の書き物による文書のなかにメソポタミアの銘板がある。それらに記録されているのは、信用による貸借、神殿による支給の配分、神殿領地の地代、穀物と銀それぞれの価格などである」(エジプトの象形文字やメソポタミアの楔形文字の翻訳されることによって)「書かれた歴史についての学者たちの知識をスミスの時代にさかんに参照されたホメロスの時代(前800年頃)から約前3500年へと、ほぼ3000年も押し戻した。まさにこの種の信用システムが、事実上、硬貨の発明に数千年間も先行していたということが、これらの文書によってあきらかにされた」「楔形文字による記録のほとんどは金融についてのものであって、わたしたちがメソポタミアについて多くの知識を有しているとしたら、そのめぐりあわせゆえにである」
グレーバーは「現実の共同体や市場などのほとんどすべての場所でほとんどだれもが、実にさまざまなかたちで、だれかに負債を負っていて、それらのほとんどの取引が通貨を使用することなくおこなわれている」「信用と負債の存在は経済学者たちにとって常に躓きの石であった。金銭の貸し借りをする人びとが、純粋に「経済的」な動機によって行動していると(たとえば他人に貸すのもいとこに貸すのもなにも変わらないというように)言い張るのはほとんど不可能だからである」と言う。
でも、どうして物々交換についての「神話」というものが、いまだに人々の間で信じられているのだろう。グレーバーは、アダム・スミスによって創設された経済学というものに理由があるとする。「インド諸島やアフリカに向かった16世紀と17世紀の旅行家たちのほとんどが、すべての社会が政府を持ちすべての政府が通貨を発行しているのだから、あらゆる社会が独自の形態の貨幣を持っていると考えていた」「こうしたなかアダム・スミスは、同時代には慣習的であったそうした知識を決然と転覆せんとはかったのである」と述べ、アダム・スミスによって、彼の経済学と共に、この「神話」が創設されたとしている。そして、その経済学の教科書は未だに書き換えられず、その考え方が人々の間に浸透している。
アダム・スミスの人間観はつぎのようなものである。
「スミスは……財産と貨幣と市場は政治的諸制度以前に存在していただけでなく、まさに人間社会の基礎そのものであると主張した。さらに政府は……通貨の安定性を保障する役割に自己限定すべきである(とも主張した)」「スミスが、経済的なものを固有の原理と法則を有する――つまり倫理学や政治学と区別された――人間的探究の場であると主張することができたのも、こうした議論を展開することによってのみだったのである」
「政府は……通貨の安定性を保障する役割に自己限定すべきである」という部分は、新自由主義者の「小さな政府」という主張と一致している。
「人間は、みずからの意志にゆだねるならば、不可避に事物を取り換えたり、比較したりしはじめるだろう。これこそ人間固有のいとなみなのだ。論理や会話さえも、実際には交易の形態でしかなく、万事において人間は常に各人にとって最高の有利さを求め、交換から最大の利益を引き出そうとするものなのだ」
「万事において人間は常に各人にとって最高の有利さを求め、交換から最大の利益を引き出そうとするものなのだ」という言明は、彼の経済学の前提となっている。最近の行動経済学では、心理学を導入し、その経済モデルの中での人間について、行動に関する変数を増やし、より現実の人間に近づけようとしている。しかし、その人間が行動する場としての経済モデルの基本(商品経済社会)は変わらない。もし経済学が本当に現実の人間の間で行なわれている取引、交換、信用を取り扱おうとすれば、すなわち、家族など近しい者たちの間、知らない者どうしの間、一方が他方に依存している両者の間、敵対的な人たちの間、支配者と被支配者との間など、さまざまな人間関係を組み入れてモデル化する必要があるが、それは不可能だろう。
さらにアダム・スミスは言う。「分業というものは、こうした広い範囲にわたる有用性には無頓着な、人間の本性上のある性向、すなわち、ある物をほかの物と取引し、交易し、交換しようとする性向の、緩慢で斬新的ではあるが、必然的な帰結なのである」
たしかに経済的効率性という観点から見れば、分業は必然的だとは思うが、「ある物をほかの物と取引し、交易し、交換しようとする性向」が「人間の本性上のある性向」という部分には疑問がある。必要なものを自分で採集する、狩る、作り出すということ(あるいは、盗む、奪うこと)が「本性上の性向」であり、「取引」「交易」「交換」は、それができない場合に行なわれる代替行為ではないだろうか。奪い合いは多くの犠牲を強いるわけで、それを避けるために取引や交換が生まれたのではないだろうか。先の2つの世界大戦は市場の再分割戦、奪い合いであった。その結果、数千万人の犠牲者が出た。その後、再び世界は「取引」「交易」「交換」の世界に戻った。しかし、いま、日本を含む多くの国ではそれが行き詰まりつつある。再び力による奪い合いの世界がやってくるのだろうか。
この章では、「物々交換 ⇒ 貨幣 ⇒ 信用」というこれまでの図式がひっくり返されるが、大切なことは、本当は逆であったという事実そのものではなく、その事実から、この社会の在り方についてもう一度見直してみることだろう。
経済学は、それが成立するために必要なお話を作り、そのお話を基に人間の物の交換活動をモデル化したものである。それにもかかわらず、その経済学によって定式化された商品経済社会を、人間の本性に基づく不可避のもの、「これしかないもの」として人々に受け入れさせるという効果をもたらしていると思われる。実際には、地球規模で商品経済社会が一般化したのはここ数百年くらいのことであり、それ以前の数千年間は、世界のそれぞれの場所で、それぞれのコミュニティーが、その環境にふさわしい社会を形成していたはずである。つぎのような例も示されている。
19世紀中盤のルイス・ヘンリー・モーガンによるイロコイ6部族連邦についての研究によれば「イロコイ諸部族連邦の主要な経済制度がロングハウスであって、そこに物財のほとんどが貯蔵されては女性たちの評議会がそれらを分配している」
「ロングハウス」については訳者の註がある。
「文字通りの複数の居室が連なる長屋式の家屋である。一つの居室を共にする家族的小集団がいくつも連合した家屋共同体であり、血縁のみに規定されない複合的な社会関係をなす。東南アジアの諸民族に見られるが、北アメリカのイロコイ族にも見られる」
その多様な社会が、商品経済社会にとって都合のよい仕組みの社会へと強引に(歴史的に見ればほとんど暴力的に)変形させられてしまった。wezzyというサイトの「コロンブスの銅像を撤去せよ!~新大陸 “発見”と大虐殺」という記事(http://wezz-y.com/archives/50038)によれば、コロンブスの時代、西インド諸島はスパイスと金が採れることから、次々と欧州の植民地とされた。どの島にも先住民が暮らしており、「平和的かつ友好的」で「ものを所有する概念が薄く」、かつ「体躯ががっしり」していた。それを見たコロンブスは、サンサルバドル島に到着した初日の日誌に「優れた奴隷になるだろう」と記しているとのこと。そして実際に奴隷にした。反抗する先住民は虐殺した。「今、全米各地のコロンブスの銅像にペンキがかけられる、頭部がはねられる、台座が壊されるといった事件が続いている」という。先住民の末裔や、その人たちに共感する人たちによる仕業だろう。インカ帝国やアステカ文明がどのように崩壊したのかを見ても、いま世界のあちこちで「先住民」と呼ばれている人たちがどんな目に遭ったのかがわかる。
人間社会の在り方の一つとしての商品経済社会は、その内部においても、その社会に適した能力を持って生まれ、その能力を生かせる環境に恵まれた人は莫大な富を蓄積し、一方、そのような種類の能力に欠け(金儲けの能力はないが、ほかの能力はあるはず)、環境にも恵まれない人は貧困に陥ることになる。日本では、福祉国家としてその問題の解決を目指していたが、いまは「自己責任」として、福祉に頼らざるを得ない人たちを非難する風潮さえ出てきている。小田原市の生活保護担当の職員が「保護なめんな」「不正受給はクズだ」などの言葉が入ったジャンパーを勤務中に着用していたという問題があった。公的機関でこのようなことが起きるということは、千兆円を超える借金をかかえる政府そのものに同様の考え方があり、末端の組織がそれを忖度した結果として起きたことではないだろうか。おそらく、現在の富裕者の富を貧困に苦しむ人に分配すれば、貧困問題はなくなるほどに、人間の生産力は増大しているはずである。しかし、莫大な富を持つ人は、富の蓄積そのものが自己目的化しており、分配、社会的還元には興味がないようである。
過去から現在までを、ある視点から見てみると、強いものが弱いものを隷属させ、富を自身に集中させ、自身の欲望を満たしてきたことが、人間の本性に基づく歴史ではないのかとも思えてくる。いまもそれは続いている。妄想かもしれないが、現在の経済システムは、より狡猾に、より効率よく、より多くのものを、弱者から収奪するシステムではないかとも思われてくる。しかし、一方、人は問題を認識することによって、その解決を図ろうとするという本性を持っている。そこに可能性があり、希望もある。













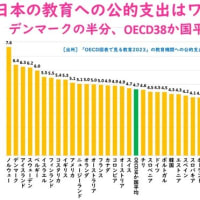



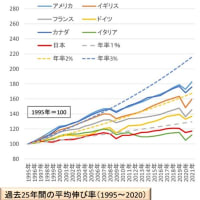


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます