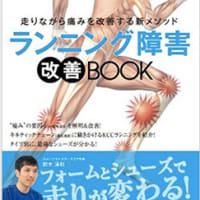ランニング障害とは、ランニングをして受傷してしまった痛みや違和感を指します。しかし、受傷機転や解消方法は複雑で、まだまだ理解や解明の余地がある分野とも言えます。こちらでは、ランニング障害を解消するために、少しでも知識を深めて頂けたらという思いで掲載いたします。
-そもそもランニング障害って何?
スポーツの怪我は、大きく「3つ」に分類されています。「外傷」「傷害」「障害」になります。それぞれ様態や処置方法、対応方法が異なりますので、簡単にも理解しておくと便利です。
・外傷:外から物がぶつかって受傷した怪我のこと。打撲など。
・傷害:受傷機転が明確なもの。捻挫、肉離れなど。
・障害:いつから受傷したのか不明瞭なもの。シンスプリント、アキレス腱、かっくんなど。
-傷害とは違うの?アイシングじゃ治らないの?
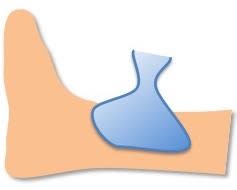
傷害と障害は別物です。しかし、痛みが出ている部分が損傷(傷害)を受けている場合には、外傷や傷害と同じく「RICE処置」を併用することがあります。
-RICE処置って何?
いわゆる怪我をした時の対処方法の頭文字をとって「RICE(ライス)処置」と呼ばれています。RICEのそれぞれの処置方法は以下をご参考ください。
Rest:安静、休養
Icing:アイシング、冷やす
Compression:圧迫
Elevation:挙上
痛めたり、血が出た時は「動かさず」「圧迫」して「持ち上げ」ることが知られています。炎症を抑えるために「冷やす」ことも知られています。
-RICEじゃ治らないの?
障害はRICEだけでは解決しません。
確かに、痛みの出ている部分は損傷し、炎症を起こしているかもしれません。しかし、「どうして損傷してしまったのか」を解明し、解決しないことには「障害を解決した」とはいえないのです。
炎症を抑えたり鎮痛を図ること自体はもっとも大事なことなのですが、痛みを忘れたからと言って「再び同じ悪さをするストレス」をかけてしまうと、重症化していってしまいます。さらに、痛みをかばうことでかばう動き(代償運動)を行い、さらに複雑化していってしまうケースが多く見られます。
-プールや自転車など、クロストレーニングはどうなの?


確かに、原因となっているストレスを一時的にも回避することができれば、損傷部位の治癒は行われます。しかし、再び走り始めた時に同じストレスをかけることとなると、やはり再受傷となってしまいます。
-タイツやテーピング、インソールはどうなの?
確かに、一定の効果があるというデータを見つけることもできますので、ご自身で納得できるようでしたら使用されるのも悪くないかもしれません。
ただ当サポートでは、自身の身体の治癒と安全で安心できる競技復帰をサポートするために、この手の商品を利用することも勧めることも、販売することもありません。
-走るのをやめればいいんでしょ?
ものによります。
確かに走って痛めたのですから、走るのをやめることで悪いストレスをかけなくなれば、治癒によって組織が修復されます。しかし、ランニングは日常動作よりも運動負荷は大きいのです。いいかえると、大きな負荷を身体にかけ、損傷を受けたということになります。よって、日常生活よりも大きな力で身体を壊したということもできます。日常生活を送ることで、もとの怪我をしないバランスが取れるかというと難しいケースも多くあり、ランニングをやめたほうがより悪化したというケースもあります。
-体幹を鍛えれば治るでしょ!


体幹と障害の因果関係がわからないので、回答が難しいです。
当サポートでは、体幹を鍛えることは一度も行ったことはありません。
-柔軟をすればいいんでしょ?



そうとも言い切れません。
確かにストレッチが必要なケースは多くありますが、不必要なストレッチはさらに骨格を崩したり、バランスを崩してしまいます。これにより症状が悪化してしまうケースもありますので、やみくもな、また不必要なストレッチもおすすめできません。
-それで結局、何をしたら良いの?


当トレーナーがオススメするのは「骨格のリセット」と「それに伴う正しい動き」を獲得することです。
それには正しい骨格の理解から「骨格リセットストレッチ」を行い、同時進行で「自分らしい動き」を覚えていきます。競技特性や体型、筋肉の質によって大きく変わります。
何かに頼る、思い切り動けない、思うように動かないという方は、自分の身体を最大限に生かし切るプログラムを試してみると良いかもしれません。