
「lab~亀井戸~」の劇作ノートです。
今作はわたしの世界観を抽象的に表現するファンタジー芝居であります。実際の事件や実際の地名や実際の建物等出てきますが、それはそちら側に寄っただけのことで、基本的にはファンタジーでありSFであり物語なのです。
合理性について考えます。
基本的に物語の進行には意味を持たせています。誰かが書いていましたが、「亀が井戸の中にいる」というのは男女の生殖行為を意味させ、神を吐き出すというのは「超越的神秘的存在→人」を作り出すという暗喩です。また「井戸→id」であり、主人公はスタート地点から「南→S極→es」に向かいます。つまりワタシはフロイトの言う氷山の一角から下に潜り無意識の中に旅立ちます。その世界は我々の世界と同様でありつつも微妙に異なります。そんなパラレルワールドではワタシと関係のある人物がそれぞれ別の人間としてその役割を当てられています。「父→教祖→支配的存在」「母→亀→受容的存在」といったように。なお、男性の竹田氏演じる佐賀は「器」であり陰茎の象徴、女性の中川さん演じる亀は陽物の象徴であり、先述した内容とは異なり二人の「性」が逆転しています。我々の「性」は生殖器の違いで決定づけられ、未完の存在であり不安定な存在である我々は失った片割れの「性」を求めるために異性を求めます。つまり二つ「性」を持つ「佐賀」「亀」は究極的、超越的存在なのです。
わたしの作品は抽象的表現なものですから分からないという言葉も多く耳にします。感覚的に「分かる」作品を創れなかった私の責任でもあるのですが、ただ、全て辻褄が合って、1から10まできっちり説明された作品が全て面白いかというと決してそうは思いません。「分からない」からこそ自身と照らし合わせる、「分からない」からこそ想像の余地があるといったポイントにわたしは「面白い」を見出します。たとえ合理的でなくても「想像すること」が面白いのです。
今作品のプロットは
ワタシが影を探す→ワタシがエレベーターに乗る→井戸の底に着く→予言を聞く→パラレルワールドに辿りつく→事件を目の当たりにする→亀を見つける→亀と闘う→井戸に戻る→影を見つける
といった内容でした。ファンタジーですが、インド世界観、新約旧約聖書、ユングの元型、ドストエフスキーの神論をちりばめています。例えそれらを知らなくても「良く分からなかったけどなんか元気でた」とか「街を見る眼がちょっと変わった」と思ってもらえたのならば、この戯曲に意味があったと思います。説教臭くなったり押し付けがましくなるのが嫌なのでラストシーンも抽象にしてあります。それでも人間賛歌、生きることの素晴らしさが伝われば幸いです。
そしてもう一つ、主観を失うことの恐怖がこの作品で言いたかったことです。オウムや西鉄、秋葉原といった事件は「主観」「想像力」の欠如、またはそれらが捻じ曲がってしまったことによって起こった事件であると思います。それは本当に恐ろしいことです。
ワタシも主観を放棄した人間です。彼女は事件を目の当たりにしても動こうとはしません。また耳を貸そうともしません。しかし、影を見つけ、認め、取り込むことで彼女は主観を取り戻し、ステップを踏み出すのです。
「神の御子」も、佐賀は「器」であり、幹部達の崇拝によりその存在を確立し、一方の幹部達は佐賀という存在の畏怖の念により「幹部」という己の存在を確立している。つまりはお互いがお互いを存在させている空虚な団体なのです。主観がない、幻想の集団。故に恐ろしい。主観のない行動は暴走し、他者を傷つけます。それはあってはならないことなのです。行動には責任が付き添います。主観を失くすことで責任を放棄したのです。それがオウムのサリン事件であると思います。
最後の手話は「私は神」。主観は自身の中にあるのです。
わたしも30歳になり、今までやってきた、試してきた作品の要素全てを少しずつ染み込ませた作品です。集成の作品です。これまで関わってきてくれた全ての皆様に感謝の意を込めて披露した作品です。この時期、このメンバー、この舞台でやれたことを本当に感謝します。ありがとうございました。

そしてこれからも宜しくお願いします。やりきった感があるのにまた新しい欲求が生まれてくる。だから芝居は面白い。














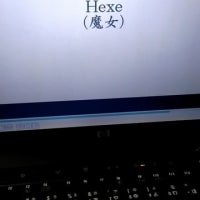





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます