
「lab~亀井戸~」
演出としては大人数を使った壮大さ、舞台上からの「力」を観客席に届けることを念頭に思案。組体操、手話、一曲流しつつ突如歌唱は昔からやりたかったこと。48人使えるこの舞台にこそと、全て挿入。役者の負担は極端に増えたが、同じ「文脈」で話せる人間が増えたことで「いける」という確信はあった。
以下話に沿って演出の観点から考察。
眼鏡は仮面であり、ネクタイは正装…礼儀である。役者の肉体は楽器でありコンディションをみる必要があり、また観客の「男時・女時」を見るために調弦のシーンを挿入。
OP、冒頭のタクシーシーンは竹田氏への感謝とオマージュである。線路という「橋」を進み日常からほんの少し外れた世界へ向かうワタシ。影は彼女を見守りつつその対局に位置する。車のペンライトシーンでは照明の進路に進んだ子にお褒めの言葉を頂く。「赤いペンライトが一つだけあったのですがいいんですか?」と質問が飛んだが、車のライトとして進んだ光は「星」の意味も持つダブルミーニング。赤い星はアンタレスでもある。故に車進行が終わった後に空中に浮かぶ光は幻想的で美しい。四角シャボンの「she」も相成り納得の出来。
ペンギンダンス。ドン・キホーテの「ドンキー=猿=ウータン=ウータンダンス」という思考により、ウータンダンスに挑戦。足は一歩であるが手は二手という振りだったため稽古初日では非常に戸惑いを見せたが、本番はきっちり出来た。
歩道橋のシーン全般は座付きの照明様の力があってこそ。打ち合わせの時に大分無理を言わせて頂く。当日見た光はまさにイメージ通り。ありがたい。ここも「橋」であり、「ハシ」から覗く世界はワタシにとって無関係であり、同時に己もそこに包括されている。
「最後の晩餐」であるかのように集う「神の御子」、そして目の前には金を拾う民達。その姿は愚者であり、まるで蜘蛛の糸をつかむカンダタのようでもある。一縷の望みを掛けて我々は天に向かって手を伸ばす。それを上から覗く教祖佐賀。
終盤、一同が集まり影がどこからか話し出すシーン。一同の衣装は黒。一人一人の影が集まるとそれは闇となる。これはわたしが昔から感じている集団の恐怖を具現化したものである。複雑に絡む一同。闇でもあり、井戸の内側でもあり、彼女の耳を塞ぐイヤホン、そこから出ているコードでもある。
生きていくこと決めたワタシ。影は曼荼羅のように広がり、その中でしっかりと己の立ち居地を見つけるワタシ。曼荼羅の意味は「本質を得る」。最後の手話は「私は神」。つまり主体は己であり、ワタシがそこにいるから世界が生まれるという、わたしなりの人間賛美の意。
ラストダンス。「生きることは進むことである」という発想から足技のハウス。パドブレ、シャッフルを多様する。役者の体に多大なる負担を掛けたが本番の躍動感は凄まじかった。音響が止まるというアクシデントがあったが皆の勢いは止まらず。
ラストの音響ストップは演出ですかという質問が出たが、あれが演出となると、再び音を閉ざす世界に戻るという意味が出てきてしまい、劇作の意図とずれてしまう。音を取り戻した彼女が最後に「神」と体で話すことに、この物語の意義がある。これだけは本当に悔やまれる。
次は演出として見た今回の出演者。メインパート31人全員にコメントしたいのでなかなかの量と時間になる。














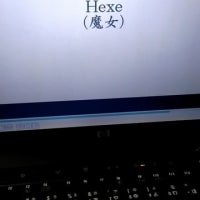





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます