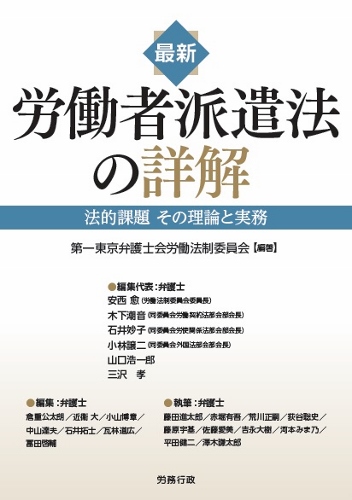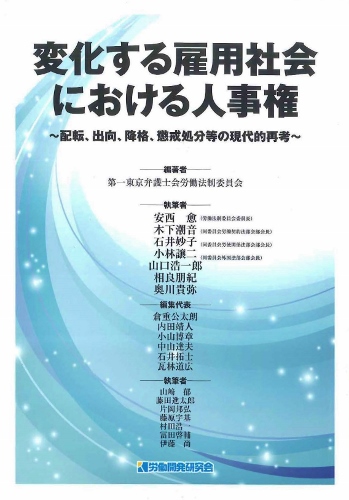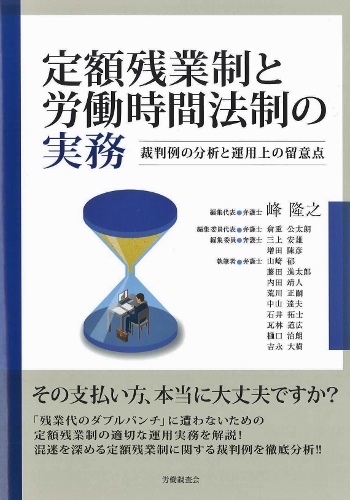Q12 精神疾患を発症して欠勤や休職を繰り返す。
精神疾患を発症して欠勤や休職を繰り返す社員については,まず,業務により精神障害が悪化することがないよう配慮する必要があります。
精神疾患を発症していることを知りながらそのまま勤務を継続させ,その結果,業務に起因して症状を悪化させた場合は,労災となり,会社が安全配慮義務違反を問われて損害賠償義務を負うことになりかねません。
社員が精神疾患の罹患していることが分かったら,それに応じた対応が必要であり,本人が就労を希望していたとしても,漫然と放置してはいけません。
所定労働時間内の通常業務であれば問題なく行える程度の症状である場合は,時間外労働や出張等,負担の重い業務を免除する等して対処すれば足りるでしょう。
しかし,長期間にわたって所定労働時間の勤務さえできない場合は,原則として,私傷病に関する休職制度がある場合は休職を検討し,私傷病に関する休職制度がない場合は普通解雇を検討せざるを得ません。
精神疾患を発症した労働者が出社してきた場合であっても,労働契約の債務の本旨に従った労務提供ができない場合は,就労を拒絶して帰宅させ,欠勤扱いにすれば足ります。
労働契約の債務の本旨に従った労務提供ができるかどうかは,職種や業務内容を特定して労働契約が締結された場合は当該職種等についてのみ検討すれば足りるケースが多いですが,職種や業務内容を特定せずに労働契約が締結されている場合は,現に就業を命じた業務について労務の提供が十分にできないとしても,当該社員が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供ができ,かつ,本人がその労務の提供を申し出ているのであれば,債務の本旨に従った履行の提供があると評価されるため(片山組事件最高裁第一小法廷平成10年4月9日判決),他の業務についても検討する必要があります。
労働契約の債務の本旨に従った労務提供があるかどうかを判断するにあたっては,専門医の助言を参考にする必要があります。
本人が提出した主治医の診断書の内容に疑問があるような場合であっても,専門医の診断を軽視することはできません。
主治医への面談を求めて診断内容の信用性をチェックしたり,精神疾患に関し専門的知識経験を有する産業医等への診断を求めたりして,病状を確認する必要があります。
主治医の診断に疑問がある場合に,会社が医師を指定して受診を命じたところ,本人が指定医への受診を拒絶した場合は,労働契約の債務の本旨に従った労務提供がないものとして労務の提供を拒絶し,欠勤扱いとすることができる可能性がありますが,慎重な検討が必要となります。
私傷病に関する休職制度は,普通解雇を猶予する趣旨の制度であり,必ずしも休職制度を設けて就業規則に規定しなければならないわけではありません。
休職制度を設けずに,私傷病に罹患して働けなくなった社員にはいったん退職してもらい,私傷病が治癒したら再就職を認めるといった運用も考えられます。
明らかに精神疾患を発症しているにもかかわらず,本人が精神疾患の発症や休職事由の存在を否定し,専門医による診断を拒絶することがありますが,精神疾患等の私傷病を発症しておらず健康であるにもかかわらず,労働契約の債務の本旨に従った労務を提供することができていないとすれば,通常は普通解雇事由に該当することになります。
本人の言っていることが事実だとすれば,普通解雇を検討せざるを得ない旨伝えた上で,専門医による診断を促すのが適切なケースもあるかもしれません。
精神障害を発症した社員が出社と欠勤を繰り返したような場合であっても,休職させることができるようにしておくべきでしょう。
例えば,一定期間の欠勤を休職の要件としつつ,「欠勤の中断期間が30日未満の場合は,前後の欠勤期間を通算し,連続しているものとみなす。」等の通算規定を置くか,「精神の疾患により,労務の提供が困難なとき。」等を休職事由として,一定期間の欠勤を休職の要件から外すこと等が考えられます。
再度,長期間の欠勤がなければ,休職命令を出せないような規定を置くべきではありません。
私傷病に関する休職制度があるにもかかわらず,精神疾患を発症したため労働契約の債務の本旨に従った労務提供ができないことを理由としていきなり解雇するのは,解雇権を濫用(労契法16条)したものとして解雇が無効と判断されるリスクが高いので,お勧めできません。
解雇が有効と認められるのは,休職させても回復の見込みが客観的に乏しい場合に限られます。
医学的根拠もなく,主観的に休職させても回復しないだろうと思い込み,精神疾患に罹患した社員を休職させずに解雇した場合,解雇が無効と判断されるリスクが高くなります。
本人が休職を希望している場合は,休職申請書を提出させてから,休職命令を出すことになります。
休職申請書を提出させることにより,休職命令の有効性が争われるリスクが低くなります。
「合意」により休職させる場合は,休職期間(どれだけの期間が経過すれば退職扱いになるのか。)についても合意しておく必要があります。
通常,就業規則に規定されている休職期間は,休職「命令」による休職に関する規定であり,合意休職に関する規定ではありません。
原則どおり,本人から休職申請書を提出させた上で,休職「命令」を出すのが,簡明なのではないでしょうか。
精神疾患が治癒しないまま休職期間が満了すると退職という重大な法的効果が発生することになりますので,休職命令発令時に,何年の何月何日までに精神疾患が治癒せず,労務提供ができなければ退職扱いとなるのか通知するとともに,休職期間満了前の時期にも,再度,休職期間満了日や精神疾患が治癒しないまま休職期間が満了すれば退職扱いとなる旨通知すべきでしょう。
休職を繰り返されても,真面目に働いている社員が不公平感を抱いたり,会社の負担が重くなったりしないようにするために最も重要なことは,休職期間は無給とすることです。
休職期間中も有給とした場合,会社の活力が失われてしまいかねません。
傷病手当金の支給申請には協力するようにして下さい。
復職後間もない時期(復職後6か月以内等)に休職した場合には,休職期間を通算する(休職期間を残存期間とする)等の規定を置くべきでしょう。
そのような規定がない場合は,普通解雇を検討せざるを得ませんが,有効性が争われるリスクが高くなります。
復職の可否は,休職期間満了時までに治癒したか(休職事由が消滅したか)否かにより判断されるのが原則です。
ただし,職種や業務内容を特定せずに労働契約が締結されている場合は,現に就業を命じた業務について労務の提供が十分にできないとしても,当該社員が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供ができ,かつ,本人がその労務の提供を申し出ているのであれば,債務の本旨に従った履行の提供があると評価されるため(片山組事件最高裁第一小法廷平成10年4月9日判決),他の業務についても労働契約の債務の本旨に従った労務提供ができるかどうかについても検討する必要があります。
また,休職期間満了時までに精神疾患が治癒せず,休職期間満了時には不完全な労務提供しかできなかったとしても,直ちに退職扱いにすることができないとする裁判例も存在します。
例えば,エール・フランス事件東京地裁昭和59年1月27日判決は,「傷病が治癒していないことをもって復職を容認しえない旨を主張する場合にあっては,単に傷病が完治していないこと,あるいは従前の職務を従前どおりに行えないことを主張立証すれば足りるのではなく,治癒の程度が不完全なために労務の提供が不完全であり,かつ,その程度が,今後の完治の見込みや,復職が予定される職場の諸般の事情等を考慮して,解雇を正当視しうるほどのものであることまでをも主張立証することを要するものと思料する。」と判示しています。
休職期間満了時までに精神疾患が治癒せず,休職期間満了時には不完全な労務提供しかできなかったとしても,直ちに退職扱いにすることができないとしたのでは,休職期間を明確に定めた意味がなくなってしまい,使用者の予測可能性・法的安定性が害され妥当ではないと考えられますが,反対の立場を取るにせよ,このような裁判例が存在することを理解した上で対応を検討していく必要があります。
復職の可否を判断するにあたっては,専門医の助言を参考にする必要があります。
本人が提出した主治医の診断書の内容に疑問があるような場合であっても,専門医の診断を軽視することはできません。
主治医への面談を求めて診断内容の信用性をチェックしたり,精神疾患に関し専門的知識経験を有する産業医等への診断を求めたりして,病状を確認する必要があります。
主治医の診断に疑問がある場合に,会社が医師を指定して受診を命じたところ,本人が指定医への受診を拒絶した場合は,休職期間満了時までに治癒していない(休職事由が消滅していない)ものとして取り扱って復職を認めず,退職扱いとすることができる可能性がありますが,慎重な検討が必要となります。
休職制度の運用は,公平・平等に行うことが重要です。
勤続年数等により異なる扱いをする場合は,予め就業規則に規定しておく必要があります。
休職命令の発令,休職期間の延長等に関し,同じような立場にある社員の扱いを異にした場合,紛争になりやすく,敗訴リスクも高まる傾向にあります。
精神疾患の発症の原因が,長時間労働,セクハラ,パワハラによるものだから労災だとの主張がなされることがある。精神疾患の発症が労災か私傷病かは,『心理的負荷による精神障害の認定基準』(基発1226第1号平成23年12月26日)を参考にして判断することになりますが,その判断は必ずしも容易ではありません。
実務的には,労災申請を促して労基署の判断を仰ぎ,審査の結果,労災として認められれば労災として扱い,労災として認められなければ私傷病として扱うこととすれば足りることが多いものと思われます。
精神疾患の発症が労災の場合,療養するため休業する期間及びその後30日間は原則として解雇することができません(労基法19条1項)。
欠勤が続いている社員を解雇しようとしたり,休職期間満了で退職扱いにしたりしようとした際,精神疾患の発症は労災なのだから解雇等は無効だと主張されることがあります。
また,精神疾患の発症が労災として認められた場合,業務と精神疾患の発症との間に相当因果関係が認められたことになるため,労災保険給付でカバーできない損害(慰謝料等)について損害賠償請求を受けるリスクも高くなります。
精神疾患を発症して欠勤や休職を繰り返す社員については,まず,業務により精神障害が悪化することがないよう配慮する必要があります。
精神疾患を発症していることを知りながらそのまま勤務を継続させ,その結果,業務に起因して症状を悪化させた場合は,労災となり,会社が安全配慮義務違反を問われて損害賠償義務を負うことになりかねません。
社員が精神疾患の罹患していることが分かったら,それに応じた対応が必要であり,本人が就労を希望していたとしても,漫然と放置してはいけません。
所定労働時間内の通常業務であれば問題なく行える程度の症状である場合は,時間外労働や出張等,負担の重い業務を免除する等して対処すれば足りるでしょう。
しかし,長期間にわたって所定労働時間の勤務さえできない場合は,原則として,私傷病に関する休職制度がある場合は休職を検討し,私傷病に関する休職制度がない場合は普通解雇を検討せざるを得ません。
精神疾患を発症した労働者が出社してきた場合であっても,労働契約の債務の本旨に従った労務提供ができない場合は,就労を拒絶して帰宅させ,欠勤扱いにすれば足ります。
労働契約の債務の本旨に従った労務提供ができるかどうかは,職種や業務内容を特定して労働契約が締結された場合は当該職種等についてのみ検討すれば足りるケースが多いですが,職種や業務内容を特定せずに労働契約が締結されている場合は,現に就業を命じた業務について労務の提供が十分にできないとしても,当該社員が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供ができ,かつ,本人がその労務の提供を申し出ているのであれば,債務の本旨に従った履行の提供があると評価されるため(片山組事件最高裁第一小法廷平成10年4月9日判決),他の業務についても検討する必要があります。
労働契約の債務の本旨に従った労務提供があるかどうかを判断するにあたっては,専門医の助言を参考にする必要があります。
本人が提出した主治医の診断書の内容に疑問があるような場合であっても,専門医の診断を軽視することはできません。
主治医への面談を求めて診断内容の信用性をチェックしたり,精神疾患に関し専門的知識経験を有する産業医等への診断を求めたりして,病状を確認する必要があります。
主治医の診断に疑問がある場合に,会社が医師を指定して受診を命じたところ,本人が指定医への受診を拒絶した場合は,労働契約の債務の本旨に従った労務提供がないものとして労務の提供を拒絶し,欠勤扱いとすることができる可能性がありますが,慎重な検討が必要となります。
私傷病に関する休職制度は,普通解雇を猶予する趣旨の制度であり,必ずしも休職制度を設けて就業規則に規定しなければならないわけではありません。
休職制度を設けずに,私傷病に罹患して働けなくなった社員にはいったん退職してもらい,私傷病が治癒したら再就職を認めるといった運用も考えられます。
明らかに精神疾患を発症しているにもかかわらず,本人が精神疾患の発症や休職事由の存在を否定し,専門医による診断を拒絶することがありますが,精神疾患等の私傷病を発症しておらず健康であるにもかかわらず,労働契約の債務の本旨に従った労務を提供することができていないとすれば,通常は普通解雇事由に該当することになります。
本人の言っていることが事実だとすれば,普通解雇を検討せざるを得ない旨伝えた上で,専門医による診断を促すのが適切なケースもあるかもしれません。
精神障害を発症した社員が出社と欠勤を繰り返したような場合であっても,休職させることができるようにしておくべきでしょう。
例えば,一定期間の欠勤を休職の要件としつつ,「欠勤の中断期間が30日未満の場合は,前後の欠勤期間を通算し,連続しているものとみなす。」等の通算規定を置くか,「精神の疾患により,労務の提供が困難なとき。」等を休職事由として,一定期間の欠勤を休職の要件から外すこと等が考えられます。
再度,長期間の欠勤がなければ,休職命令を出せないような規定を置くべきではありません。
私傷病に関する休職制度があるにもかかわらず,精神疾患を発症したため労働契約の債務の本旨に従った労務提供ができないことを理由としていきなり解雇するのは,解雇権を濫用(労契法16条)したものとして解雇が無効と判断されるリスクが高いので,お勧めできません。
解雇が有効と認められるのは,休職させても回復の見込みが客観的に乏しい場合に限られます。
医学的根拠もなく,主観的に休職させても回復しないだろうと思い込み,精神疾患に罹患した社員を休職させずに解雇した場合,解雇が無効と判断されるリスクが高くなります。
本人が休職を希望している場合は,休職申請書を提出させてから,休職命令を出すことになります。
休職申請書を提出させることにより,休職命令の有効性が争われるリスクが低くなります。
「合意」により休職させる場合は,休職期間(どれだけの期間が経過すれば退職扱いになるのか。)についても合意しておく必要があります。
通常,就業規則に規定されている休職期間は,休職「命令」による休職に関する規定であり,合意休職に関する規定ではありません。
原則どおり,本人から休職申請書を提出させた上で,休職「命令」を出すのが,簡明なのではないでしょうか。
精神疾患が治癒しないまま休職期間が満了すると退職という重大な法的効果が発生することになりますので,休職命令発令時に,何年の何月何日までに精神疾患が治癒せず,労務提供ができなければ退職扱いとなるのか通知するとともに,休職期間満了前の時期にも,再度,休職期間満了日や精神疾患が治癒しないまま休職期間が満了すれば退職扱いとなる旨通知すべきでしょう。
休職を繰り返されても,真面目に働いている社員が不公平感を抱いたり,会社の負担が重くなったりしないようにするために最も重要なことは,休職期間は無給とすることです。
休職期間中も有給とした場合,会社の活力が失われてしまいかねません。
傷病手当金の支給申請には協力するようにして下さい。
復職後間もない時期(復職後6か月以内等)に休職した場合には,休職期間を通算する(休職期間を残存期間とする)等の規定を置くべきでしょう。
そのような規定がない場合は,普通解雇を検討せざるを得ませんが,有効性が争われるリスクが高くなります。
復職の可否は,休職期間満了時までに治癒したか(休職事由が消滅したか)否かにより判断されるのが原則です。
ただし,職種や業務内容を特定せずに労働契約が締結されている場合は,現に就業を命じた業務について労務の提供が十分にできないとしても,当該社員が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供ができ,かつ,本人がその労務の提供を申し出ているのであれば,債務の本旨に従った履行の提供があると評価されるため(片山組事件最高裁第一小法廷平成10年4月9日判決),他の業務についても労働契約の債務の本旨に従った労務提供ができるかどうかについても検討する必要があります。
また,休職期間満了時までに精神疾患が治癒せず,休職期間満了時には不完全な労務提供しかできなかったとしても,直ちに退職扱いにすることができないとする裁判例も存在します。
例えば,エール・フランス事件東京地裁昭和59年1月27日判決は,「傷病が治癒していないことをもって復職を容認しえない旨を主張する場合にあっては,単に傷病が完治していないこと,あるいは従前の職務を従前どおりに行えないことを主張立証すれば足りるのではなく,治癒の程度が不完全なために労務の提供が不完全であり,かつ,その程度が,今後の完治の見込みや,復職が予定される職場の諸般の事情等を考慮して,解雇を正当視しうるほどのものであることまでをも主張立証することを要するものと思料する。」と判示しています。
休職期間満了時までに精神疾患が治癒せず,休職期間満了時には不完全な労務提供しかできなかったとしても,直ちに退職扱いにすることができないとしたのでは,休職期間を明確に定めた意味がなくなってしまい,使用者の予測可能性・法的安定性が害され妥当ではないと考えられますが,反対の立場を取るにせよ,このような裁判例が存在することを理解した上で対応を検討していく必要があります。
復職の可否を判断するにあたっては,専門医の助言を参考にする必要があります。
本人が提出した主治医の診断書の内容に疑問があるような場合であっても,専門医の診断を軽視することはできません。
主治医への面談を求めて診断内容の信用性をチェックしたり,精神疾患に関し専門的知識経験を有する産業医等への診断を求めたりして,病状を確認する必要があります。
主治医の診断に疑問がある場合に,会社が医師を指定して受診を命じたところ,本人が指定医への受診を拒絶した場合は,休職期間満了時までに治癒していない(休職事由が消滅していない)ものとして取り扱って復職を認めず,退職扱いとすることができる可能性がありますが,慎重な検討が必要となります。
休職制度の運用は,公平・平等に行うことが重要です。
勤続年数等により異なる扱いをする場合は,予め就業規則に規定しておく必要があります。
休職命令の発令,休職期間の延長等に関し,同じような立場にある社員の扱いを異にした場合,紛争になりやすく,敗訴リスクも高まる傾向にあります。
精神疾患の発症の原因が,長時間労働,セクハラ,パワハラによるものだから労災だとの主張がなされることがある。精神疾患の発症が労災か私傷病かは,『心理的負荷による精神障害の認定基準』(基発1226第1号平成23年12月26日)を参考にして判断することになりますが,その判断は必ずしも容易ではありません。
実務的には,労災申請を促して労基署の判断を仰ぎ,審査の結果,労災として認められれば労災として扱い,労災として認められなければ私傷病として扱うこととすれば足りることが多いものと思われます。
精神疾患の発症が労災の場合,療養するため休業する期間及びその後30日間は原則として解雇することができません(労基法19条1項)。
欠勤が続いている社員を解雇しようとしたり,休職期間満了で退職扱いにしたりしようとした際,精神疾患の発症は労災なのだから解雇等は無効だと主張されることがあります。
また,精神疾患の発症が労災として認められた場合,業務と精神疾患の発症との間に相当因果関係が認められたことになるため,労災保険給付でカバーできない損害(慰謝料等)について損害賠償請求を受けるリスクも高くなります。