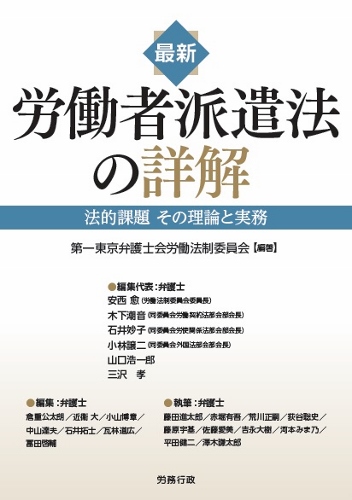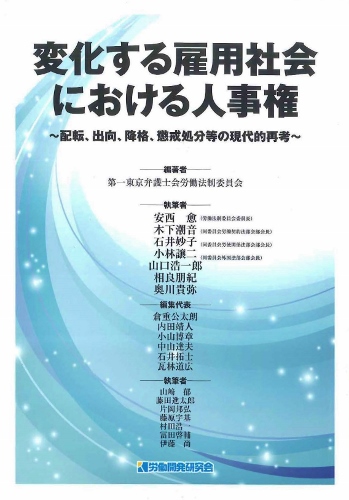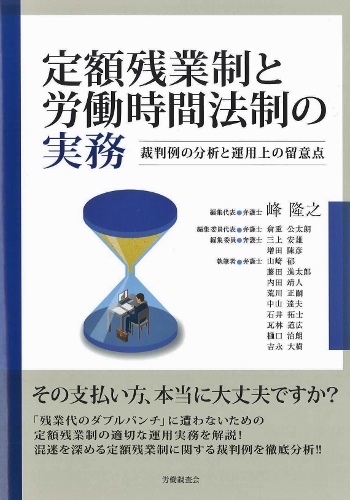使用者は,強制執行により賃金の回収を受ける場合であっても,源泉所得税の源泉徴収義務を負うとするのが最高裁判所第三小法廷平成23年3月22日判決なのですから,使用者が判決に従い任意に賃金を支払う場合は,当然,源泉徴収義務を負い,源泉所得税を納付しなければならないことになります。
したがって,使用者としては,債務名義の有無にかかわらず,源泉徴収した上で,賃金を支払うべきこととなります。
ただし,当該労働者が,源泉徴収しない金額での支払を強硬に主張し,源泉徴収額についても強制執行してきた場合は,「強制執行手続においては,執行債務者が徴収すべき源泉所得税を徴収する手続は予定されていないから,本件のように給与等の債権者がその債務名義に基づいて民事執行法122条2項により弁済を受ける場合には,源泉徴収されるべき所得税相当額をも含めて強制執行をし,他方,源泉徴収義務者は,強制執行により支払った給与等につき源泉徴収すべき所得税を納付した上で,法222条に基づき求償することになる。」(裁判官田原睦夫の補足意見)という手順を採らざるを得ません。
そのようなことにならないよう,上記最高裁判例を労働者側に示して,源泉徴収額についてまで強制執行しないよう話し合っておく必要があります。
所得税法28条1項に規定する給与等の支払をする者が,その支払を命ずる判決に基づく強制執行により賃金の回収を受ける場合であっても,源泉所得税の源泉徴収義務を負うとするのが最高裁判所第三小法廷平成23年3月22日判決ですので,源泉所得税を納付しなければなりません。
源泉徴収できないのに源泉所得税を納付しなければならないのは不当だと言いたくなるかもしれませんが,上記最高裁判決が「上記の場合に,給与等の支払をする者がこれを支払う際に源泉所得税を徴収することができないことは,所論の指摘するとおりであるが,上記の者は,源泉所得税を納付したときには,法222条に基づき,徴収をしていなかった源泉所得税に相当する金額を,その徴収をされるべき者に対して請求等することができるのであるから,所論の指摘するところは,上記解釈を左右するものではない。」と判示している以上,やむを得ません。
使用者としては,源泉所得税納付後,徴収をしていなかった源泉所得税に相当する金額を当該労働者に請求するほかないことになります。
解雇が無効と判断された場合に支払う賃金(バックペイ)から,解雇された労働者が解雇期間中に他社で働いて得た収入(中間収入)や失業手当を控除することはできませんか?
解雇期間中の中間収入(他社で働いて得た収入)がある場合,その収入が副業収入のようなものであって解雇 がなくても取得できた(自社の収入と両立する)といった特段の事情がない限り,
① 月例賃金のうち平均賃金の60%(労基法26条)を超える部分(平均賃金額の40%)
② 平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(賞与等)の全額
が控除の対象となります(米軍山田部隊事件最高裁第二小法廷昭和37年7月20日判決,あけぼのタクシー事件最高裁第一小法廷昭和62年4月2日判決,いずみ福祉会事件最高裁第三小法廷平成18年3月28日判決)。
控除しうる中間収入はその発生期間が賃金の支給対象期間と時期的に対応していることが必要であり,時期が異なる期間内に得た収入を控除することは許されません(あけぼのタクシー事件最高裁第一小法廷昭和62年4月2日判決)。
解雇期間中に失業手当を受給していたとしても,失業手当額は控除してもらえません。
単純化して,解雇期間中の賃金が月額30万円,平均賃金も月額30万円と仮定して説明すると,以下のとおりとなります。
中間収入の額が平均賃金額の40%(12万円)を超えない場合,例えば他社で毎月10万円を稼いでいた場合には,30万円-10万円=20万円の賃金を毎月支払えば足りることになります。
中間収入の額が平均賃金額の40%(12万円)を超える場合,例えば他社で毎月25万円を稼いでいた場合には,30万円-25万円=5万円の賃金を毎月支払えば足りることにはならず,平均賃金の60%(18万円)を毎月支払わなければならないことになりますが,平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(賞与等)がある場合には,その全額を対象として控除することができます。
解雇が無効と判断された場合に解雇期間中の賃金として使用者が負担しなければならない金額を教えて下さい。
解雇 が無効と判断された場合に,解雇期間中の賃金として使用者が負担しなければならない金額は,当該社員が解雇されなかったならば労働契約上確実に支給されたであろう賃金の合計額です。
解雇当時の基本給等を基礎に算定されますが,各種手当,賞与を含めるか,解雇期間中の中間収入を控除するか,所得税等を控除するか等が問題となります。
通勤手当が実費保障的な性質を有する場合は,通勤手当について負担する必要はありません。
残業代 は,時間外・休日・深夜に勤務して初めて発生するものですから,通常は負担する必要がありませんが,一定額の残業代が確実に支給されたと考えられる場合には,残業代についても支払を命じられる可能性があります。
賞与の支給金額が確定できない場合は,解雇が無効と判断されても支払を命じられませんが,支給金額が確定できる場合は,賞与についても支払が命じられることがあります。
解雇された社員に解雇期間中の中間収入(他の事業上で働いて得た収入)がある場合は,その収入があったのと同時期の解雇期間中の賃金のうち,同時期の平均賃金の6割(労基法26条)を超える部分についてのみ控除の対象となります(米軍山田部隊事件最高裁第二小法廷昭和37年7月20日判決,あけぼのタクシー事件最高裁第一小法廷昭和62年4月2日判決)。
中間収入の額が平均賃金額の4割を超える場合には,更に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(賞与等)の全額を対象として利益額を控除することが許されることになります(あけぼのタクシー事件最高裁第一小法廷昭和62年4月2日判決,いずみ福祉会事件最高裁第三小法廷平成18年3月28日判決)。
賃金から源泉徴収すべき所得税,控除すべき社会保険料については,これらを控除する前の賃金額の支払が命じられ,実際の賃金支払の際,所得税等を控除することになります。
仮処分で賃金相当額の仮払いが命じられ,仮払いをしていたとしても,判決では仮払金を差し引いてもらえません。
賃金の支払を命じる判決が確定した場合は,労働者代理人と連絡を取って,既払の仮払金の充当について調整する必要があります。
他方,賃金請求が認められなかった場合は,仮払金の返還を求めることになりますが,労働者が無資力となっていて,回収が困難なケースもあります。
解雇が無効と判断された場合,使用者はいつまでの賃金を支払い続けなければならないのですか?
解雇 が無効と判断された場合,労働者が転職せずに職場復帰を求め続けた場合は,実際には全く働いていない期間についても賃金の支払を命じられることになります。
もっとも,解雇された労働者が他社に正社員として就職したり,使用者が解雇を撤回して労働者に出社するよう命じたにもかかわらず労働者が出社しなかったような場合は,解雇された労働者が労務提供の意思を喪失していると評価できるのが通常であり,解雇された労働者が就労できないのは使用者の責任ではなくなりますから,使用者は以後の賃金支払義務を免れることになります。
解雇が無効だったとしても,ノーワーク・ノーペイなのですから,働いていない期間の賃金は支払う必要はありませんよね?
解雇 が無効の場合において,労働者が就労の意思と能力があるにもかかわらず,使用者が就労を拒絶しているような場合には,就労不能の帰責事由が使用者にあると評価されるのが通常です。
したがって,解雇された労働者が現実には働いていなかったとしても,使用者は賃金支払義務を免れず(民法536条2項),実際には働いていない期間についての賃金についても,支払わなければならなくなります。
例えば,月給30万円の労働者を解雇した1年後に解雇が無効と判断された場合,既に発生している過去の賃金だけで,30万円×12か月=360万円の支払義務を使用者が負担するリスクを負っており,その後も毎月30万円ずつ支払額が増額されていくリスクがあることになります。
上記具体例を見れば,解雇が無効と判断された場合,働いてもいない労働者に対し,高額の賃金を支払わなければならないことが分かると思います。
無効な解雇をさせることができれば,働かずに働いたのと同じ賃金を取得できることから,勤労意欲の低い問題社員 の中には,使用者に対し積極的に自分を解雇するよう働きかけて自分を解雇させ,解雇無効を主張して働かずに毎月の賃金(高額の解決金)を取得しようとする者もいます。
最近,無断録音機をポケットに忍ばせて,経営者に対して解雇だと言わせようと頑張る問題社員が増えていますので,見え透いた罠にはまらないようくれぐれもご注意下さい。
民法628条は,「やむを得ない事由」があるときに契約期間中の解除を認めていますが,労契法17条1項は,使用者は,有期労働契約について,やむを得ない事由がある場合でなければ,使用者は契約期間満了までの間に労働者を解雇 できない旨規定されています。
労契法17条1項は強行法規ですから,有期労働契約の当事者が民法628条の「やむを得ない事由」がない場合であっても契約期間満了までの間に労働者を解雇できる旨合意したり,就業規則に規定して周知させたとしても,同条項に違反するため無効となり,使用者は民法628条の「やむを得ない事由」がなければ契約期間中に解雇することができません。
このため,例えば,契約期間1年の有期労働契約者について3か月の試用期間 を設けた場合,試用期間中であっても「やむを得ない事由」がなければ本採用拒否(解雇)できないものと考えられます。
3か月の試用期間を設けることにより,「やむを得ない事由」の解釈がやや緩やかになる可能性はないわけではありませんが,大幅に緩やかに解釈してもらうことは期待できないものと思われます。
したがって,有期契約労働者についても試用期間を設けることはできるものの,その法的効果は極めて限定されると考えるべきことになります。
では,どうすればいいのかという話になりますが,有期契約労働者には試用期間を設けず,例えば,最初の契約期間を3か月に設定するなどして対処すれば足ります。
このようなシンプルな対応ができるにもかかわらず,有期契約労働者にまで試用期間を設けるのは,あまりセンスのいいやり方とは言えないのではないでしょうか。
正社員とは明確に区別された雇用管理を行うという観点からも,有期契約労働者にまで試用期間を設けることはお勧めしません。
試用期間の趣旨で有期労働契約を締結し,正社員に相応しければ正社員として登用し,正社員に相応しくなれば期間満了で辞めてもらうやり方はどう思いますか?
正社員について,試用期間 を設けたとしても,本採用拒否(留保解約権の行使)が,解雇権濫用法理(労働契約法16条)により無効とされるリスクがあることから,最初から正社員として雇用するのではなく,まずは有期労働契約を締結して正社員と同様の職務に従事させ,労働者に問題があれば雇止めし,問題がない場合には正社員として登用することがあります。
このようなやり方の法的効力は,どのようなものなのでしょうか?
判例上,労働者の適性を評価・判断するための有期契約期間は,契約期間の満了により労働契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き,試用期間として取り扱われることになり,有期労働契約期間中の労働者が正社員と同じ職場で同じ職務に従事し,使用者の取扱いにも格段変わったところはなく,また,正社員登用時に労働契約書作成の手続が採られていないような場合には,原則として解約権留保付労働契約と評価され,本採用拒否(留保解約権の行使)が許される場合でない限り,労働契約を契約期間満了で終了させることができないことになります(神戸弘陵学園事件最高裁第三小法廷平成2年6月5日判決)。
したがって,労働者の適性を評価・判断することを目的とした有期労働契約を締結した場合に,契約期間満了時に問題社員 との労働契約を終了させることができるようにするためには,契約期間の満了により労働契約が当然に終了する旨の明確な合意を書面でしておくとともに,正社員に登用する労働者については正社員登用時に労働契約書作成の手続を確実に採っておくべきことになります。
当初の労働契約が有期労働契約の形式を採っていた場合の方が,長期雇用に対する期待が低いことが多いせいか,正社員の本採用拒否の形式を取るよりも辞めてもらいやすく,紛争になりにくい傾向にあるようですが,他方で,こちらが働き続けて欲しいと思っていてもすぐに辞めてしまいやすいという傾向もあります。
また,正社員として長期間勤務し続ける希望が強い応募者は,最初から正社員として採用してもらえる会社に就職する傾向が強いですから,最初の契約を有期労働契約とした場合,長期雇用を希望する正社員タイプの人材を確保する競争では不利になる面があることは否めません。
よほど魅力の高い職場,業務内容だとか,有期労働契約とすることに特別な意味があるのであれば別ですが,通常の中小企業においては,正社員として長期間働き続けて欲しい人材を募集する場合には,最初から正社員を募集し,よく応募者を見て慎重に選考して採用した方が,いい結果が出るように思えます。
パート,アルバイト等の非正規労働者であれば,いつでも解雇することができますよね?
パート,アルバイト等であればいつでも解雇 できるものと誤解されていることがありますが,全くの誤りです。
3か月とか1年とかいった契約期間が定められている場合は,「やむを得ない事由」がある場合でないと契約期間中に解雇することはできません(労契法17条1項,民法628条)。
「やむを得ない事由」とは「当該契約期間は雇用するという約束があるにもかかわらず,期間満了を待つことなく直ちに雇用を終了させざるを得ないような特別の重大な事由」(『労働法(第十版)』234頁)をいい,期間の定めのない労働契約における解雇の有効性を判断する際の客観的合理性,社会通念上の相当性(労契法16条)よりも厳格な要件と考えられていますので,よほどのことがない限り契約期間中に解雇することはできません。
通常は契約期間満了を待って退職という扱いをさせざるを得ませんので,将来の売上げの見通しが立たない場合は,漫然と長期の労働契約を締結するのではなく,採用を控えるか,ごく短期の労働契約を締結するにとどめておく必要があります。
なお,パート,アルバイト等の非正規社員の中には,期間の定めなく採用されている労働者もいますが,その場合は労契法16条が適用され,解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要となりますので,やはりいつでも解雇することができるわけではありません。
使用者は,有期労働契約について,やむを得ない事由がある場合でなければ,その契約期間が満了するまでの間において,労働者を解雇することができません(労契法17条1項)。
民法628条は,「やむを得ない事由」があるときに契約期間中の解除を認める規定であり,「やむを得ない事由」がない場合に雇用契約の解除をすることができるのかについては必ずしも明らかではなく,見解の対立がありましたが,労契法17条1項の施行により,「やむを得ない事由」がない場合には,使用者は契約期間満了までの間に労働者を解雇 できないことが明らかとなりました。
同条項は強行法規ですから,有期労働契約の当事者が民法628条の「やむを得ない事由」がない場合であっても契約期間満了までの間に労働者を解雇できる旨合意したとしても,同条項に違反するため無効となり,使用者は民法628条の「やむを得ない事由」がなければ契約期間中に解雇することができません。
使用者が契約期間中に有期労働契約を終了させたいと考えたとしても,契約期間中の解雇は「やむを得ない事由」がない限り行えないのですから,通常は上乗せの退職条件を提示するなどして話し合いで退職の同意を取り付けるか,契約期間満了時の雇止めにより契約を終了させるべきことになるでしょう。
民法628条は有期契約労働者の辞職についても適用があり,原則として「やむを得ない事由」がなければ,有期契約労働者は契約期間中に辞職することはできません。
もっとも,契約期間中の労働者の辞職の制限について労契法17条1項があえて規定していないことからすれば,労働者の辞職については,「やむを得ない事由」がなくても行うことができる旨労使間で合意することができるものと考えられます。
したがって,例えば,有期契約労働者の就業規則や労働契約書に「退職の申し出をしてから14日を経過した場合」が退職事由として規定されているような場合は,「やむを得ない事由」がなくても,有期契約労働者は退職日の14日前に退職を申し出ることにより,契約期間満了前に退職することができることになります。
「やむを得ない事由」があれば,解雇予告や解雇予告手当の支払なしに,「直ちに」有期契約労働者を普通解雇することができますか?
民法628条は,「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても,やむを得ない事由があるときは,各当事者は,直ちに契約の解除をすることができる。」と規定しており,一見,「やむを得ない事由」があれば「直ちに」有期契約労働者を普通解雇 することができるようにも読めますが,これは契約期間の定めや民法627条等に拘束されないことを言っているに過ぎず,原則として労基法上の解雇予告義務(労基法20条)の適用があります。
したがって,使用者が有期契約労働者を期間途中で即時解雇 するためには民法628条の「やむを得ない事由」が「天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」(労基法20条1項ただし書)にも該当する場合とか,労働者が労基法21条各号の者に該当する場合でない限り,解雇予告手当の支払が必要となります。
有期契約労働者を期間途中で普通解雇する場合に要求される「やむを得ない事由」とは,どの程度のもののことをいうのですか?
「やむを得ない事由」は,「当該契約期間は雇用するという約束があるにもかかわらず,期間満了を待つことなく直ちに雇用を終了させざるを得ないような特別の重大な事由」(菅野第10版234頁)をいい,期間の定めのない労働契約における解雇 の有効性を判断する際の客観的合理性,社会通念上の相当性(労契法16条)よりも厳格な要件と考えられています。
有期契約労働者を契約期間満了前に普通解雇することはできますか?
民法628条は,「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても,やむを得ない事由があるときは,各当事者は,直ちに契約の解除をすることができる。この場合において,その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは,相手方に対して損害賠償の責任を負う。」と規定しています。
したがって,「やむを得ない事由」があれば,有期契約労働者を契約期間満了前に普通解雇 することができます。
試用期間 満了前であっても,社員として不適格であることが判明し,解約権留保の趣旨,目的に照らして,客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合であれば,本採用拒否(解雇 )することができます。
試用期間中に社員として不適格と判断された社員が,試用期間満了時までに社員としての適格性を有するようになることは稀ですから,使用者としては早々に見切りをつけたいところかもしれません。
しかし,試用期間満了前に本採用拒否(解雇)することを正当化するだけの客観的に合理的な理由を立証することができるかどうかについての判断が甘いケースが目立ちますので,客観的合理性の有無については,証拠に照らして慎重に判断する必要がありますし,本採用拒否(解雇)を試用期間満了前に行うことが社会通念上相当として是認されるかどうかについてもよく検討する必要があります。
また,試用期間中の社員の中には,少なくとも試用期間中は雇用を継続してもらえると期待している者も多く,試用期間満了前の本採用拒否(解雇)には紛争を誘発しやすいという事実上の問題もあります。
したがって,試用期間満了前の本採用拒否(解雇)は慎重に行うべきであり,十分に話し合って退職届を提出してもらえるよう努力するか,試用期間満了日での本採用拒否(解雇)とすることをお勧めします。
「能力が低いのは分かっていたけど,就職できなくて困っているようだし,もしかしたら会社に貢献できる点も見つかるかもしれないから,チャンスを与えるために採用してあげた。」という発想は,雇用主の責任の重さを考えると,極めて危険な考え方です。
緩やかな基準で認められる試用期間中の本採用拒否(解雇 )は,「当初知ることができず,また知ることが期待できないような事実」を理由とする本採用拒否(解雇)に限られますから,新たに本採用拒否に値する事実が判明しない限り,本採用拒否はおそらく無効と判断されることでしょう。
採用されて試用期間中に本採用拒否(解雇)された労働者からは,全く感謝されず,それどころか「中途半端に採用されなければ,他社で正社員として就職することができたのに,人を物のように扱うブラック企業によって人生を狂わされた。」と非難されることも珍しくありません。
使用者は,その応募者に魅力があって雇いたいと考える場合に初めて雇うべきであり,魅力がないと判断したら不採用とする必要があります。
「雇ってあげる。」といった発想で社員を雇った場合,会社経営者は「いいことをしたのだから,感謝されないまでも,悪くは思われることはないだろう。」と思い込んだり,自分が面倒見のいい親分になったような気分に浸ったりして脇が甘くなりやすく,トラブルになるリスクが極めて高くなりますので,そうはならないよう,気持ちを引き締めて採用活動に当たって下さい。