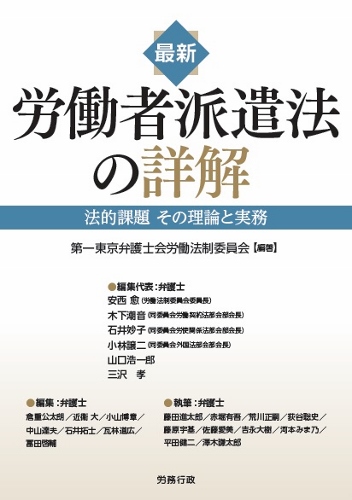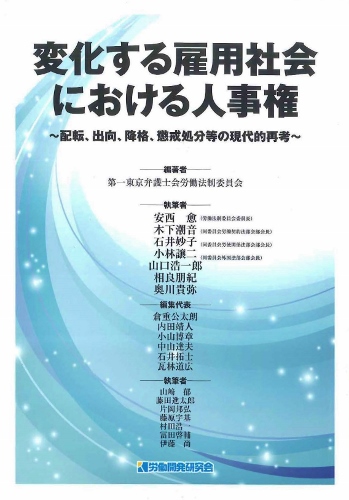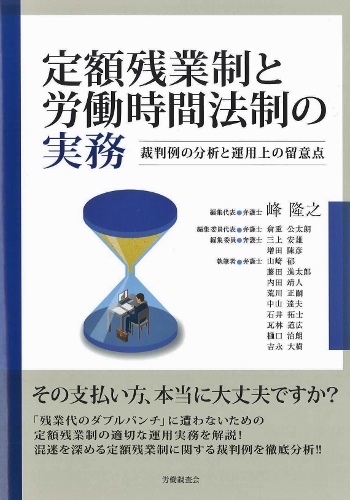解雇 に踏み切るのは,原則として解雇が有効であることを証拠により立証できるようにしてからです。
まずは,何月何日にどこでどのようなことがあったといったような解雇に客観的に合理的な理由があることを基礎付ける事実を紙に書き出してみて下さい。
紙に書かれた事実だけで,解雇に客観的に合理的な理由があるといえるでしょうか?
解雇に客観的に合理的な理由があるといえるような事実を紙に書き出せないようでは,解雇は時期尚早と考えた方がいいでしょう。
次に,紙に書き出した事実を立証するための証拠があるかどうかをチェックして下さい。
客観的証拠がありますか?
それとも,一般に証明力が低いと考えられる陳述書や法廷での証言で立証するほかない状態でしょうか?
証拠の存否や証明力を考慮して事実認定した場合,解雇に客観的に合理的な理由があると評価できるだけの事実を証明することができないようであれば,やはり解雇は時期尚早と考えられます。
解雇に客観的に合理的な理由があることを証明することができるだけの証拠がそろっている場合には,解雇の可否について最終的な検討に入ります。
その解雇が社会通念上相当といえるかどうか,それを証明するための客観的証拠があるかどうかについても,紙に書き出してみるとよいでしょう。
解雇が社会通念上相当であることを証明できると判断した場合には,解雇の準備が整ったことになります。
以上が正攻法ですが,解雇の有効性を証明することができるだけの証拠がそろっていない時点で解雇するケースもなくはありません。
しかし,解雇の有効性を証明することができるだけの証拠がそろっていないわけですから,和解金の金額が高額になりがちですし,労働者側が金銭解決を望まない場合には,どれだけ高額のお金を積んでも辞めてもらえないこともあります。
特別な事情があれば別ですが,できる限り正攻法を選択することを会社の方針とするよう強くお勧めします。
誰の目から見ても勤務態度が悪く,改善するとは到底思えない社員であっても,解雇に先立ち注意指導する必要がありますか?
解雇 権の濫用に当たるかどうか(労契法16条)を判断するにあたっては,注意指導や懲戒処分歴の有無等が考慮されます。
勤務態度の悪さが客観的に改善の見込みが乏しいことを立証できるのであれば別ですが,注意指導や懲戒処分をしていないのでは,よほど悪質な事案でない限り,勤務態度の悪さが客観的に改善の見込みが乏しいことを立証することに困難を伴うのが通常です。
勤務態度の悪さが改善の余地がないと会社が勝手に思い込んでいるだけではないかと思われないようにするためにも,十分な注意指導をし,懲戒処分を積み重ねてから,解雇すべきと考えます。
勤務成績,勤務態度が悪いことは本人が一番よく知っているはずだし,このことは社員みんなが知っているような場合であっても,証拠固めが必要だというのはどうしてですか?
十分な証拠固めをしないまま,「彼の勤務成績,勤務態度が悪いことは,本人が一番良く知っているはずだ。このことは社員みんなが知っていて証言してくれるはずだから,裁判にも勝てる。」といった安易な考えに基づいて「問題社員 」を解雇 する事例が見られますが,訴訟になるような事案では,労働者側はほぼ間違いなく自分の勤務成績,勤務態度には問題がなかったと主張してきますし,経営者,社員等の利害関係人の証言は経営者が思っているほど重視されません。
したがって,解雇に踏み切る前の時点で,解雇されてもやむを得ないと考えられるような具体的事実を説明することができるのかどうか,その事実を立証できるだけの客観的証拠が準備できているかどうかを確認する必要があります。
そして,相手の言い分を聞かないことには,解雇されてもやむを得ないと考えられるような具体的事実があるのかないのかを確認することが難しいのが通常ですから,解雇に踏み切る前に,「問題社員」の言い分を十分に聴取し,使用者側が認識している事実関係と照らし合わせて,客観的にどのような事実が認定できるかを検討すべきと考えます。
問題社員を解雇する際の注意点のうち,最初に理解すべきものを教えて下さい。
漠然と会社が解雇 を有効と判断すべき事情が多いように思えた場合であっても,解雇しても大丈夫だとは直ちにはいえないということには,十分な注意が必要です。
有効に解雇するためには,解雇に「客観的に」合理的な理由が必要であり(労契法16条),会社経営者が主観的に解雇には合理的な理由があると考えただけでは足りません。
勤務成績,勤務態度等が不良であるというためには,その評価を基礎づける「具体的事実」を立証できなければなりませんが,「仕事ができない。」「勤務態度に問題がある。」「協調性がない。」といった抽象的な説明しかできない事例が散見されます。
解雇されてもやむを得ないと考えられるような具体的事実を説明できないようでは,大した理由もないのに,何となく気に入らないから解雇しただけなのではないかとの疑いを払拭することができなくなってしまいます。
紛争が表面化する前の時点で,いつ,どこで,誰が,何を,どのようにしたのかを証明するための客観的証拠を準備し,それのどこがどのように問題なのかを具体的に説明できるようにしておく必要があります。
近年,解雇 を契機として労使紛争が表面化し,使用者が多額の解決金の支払を余儀なくされることが多くなっています。
社員を解雇し,紛争が表面化してから弁護士に相談したのでは,過去の事実は動かせない以上,どれだけ優秀な弁護士に依頼したとしても,それなりの出費は避けられないといった事態になりがちです。
解雇を検討する場合は,解雇に踏み切る前の段階から弁護士に相談し,弁護士の指導の下,解雇を行うことをお勧めします。
近年,解雇 を契機として労使紛争が表面化し,使用者が多額の解決金の支払を余儀なくされることが多くなっています。
社員を解雇し,紛争が表面化してから弁護士に相談したのでは,過去の事実は動かせない以上,どれだけ優秀な弁護士に依頼したとしても,それなりの出費は避けられないといった事態になりがちです。
解雇を検討する場合は,解雇に踏み切る前の段階から弁護士に相談し,弁護士の指導の下,解雇を行うことをお勧めします。
使用者は,強制執行により賃金の回収を受ける場合であっても,源泉所得税の源泉徴収義務を負うとするのが最高裁判所第三小法廷平成23年3月22日判決なのですから,使用者が判決に従い任意に賃金を支払う場合は,当然,源泉徴収義務を負い,源泉所得税を納付しなければならないことになります。
したがって,使用者としては,債務名義の有無にかかわらず,源泉徴収した上で,賃金を支払うべきこととなります。
ただし,当該労働者が,源泉徴収しない金額での支払を強硬に主張し,源泉徴収額についても強制執行してきた場合は,「強制執行手続においては,執行債務者が徴収すべき源泉所得税を徴収する手続は予定されていないから,本件のように給与等の債権者がその債務名義に基づいて民事執行法122条2項により弁済を受ける場合には,源泉徴収されるべき所得税相当額をも含めて強制執行をし,他方,源泉徴収義務者は,強制執行により支払った給与等につき源泉徴収すべき所得税を納付した上で,法222条に基づき求償することになる。」(裁判官田原睦夫の補足意見)という手順を採らざるを得ません。
そのようなことにならないよう,上記最高裁判例を労働者側に示して,源泉徴収額についてまで強制執行しないよう話し合っておく必要があります。
所得税法28条1項に規定する給与等の支払をする者が,その支払を命ずる判決に基づく強制執行により賃金の回収を受ける場合であっても,源泉所得税の源泉徴収義務を負うとするのが最高裁判所第三小法廷平成23年3月22日判決ですので,源泉所得税を納付しなければなりません。
源泉徴収できないのに源泉所得税を納付しなければならないのは不当だと言いたくなるかもしれませんが,上記最高裁判決が「上記の場合に,給与等の支払をする者がこれを支払う際に源泉所得税を徴収することができないことは,所論の指摘するとおりであるが,上記の者は,源泉所得税を納付したときには,法222条に基づき,徴収をしていなかった源泉所得税に相当する金額を,その徴収をされるべき者に対して請求等することができるのであるから,所論の指摘するところは,上記解釈を左右するものではない。」と判示している以上,やむを得ません。
使用者としては,源泉所得税納付後,徴収をしていなかった源泉所得税に相当する金額を当該労働者に請求するほかないことになります。
解雇が無効と判断された場合に支払う賃金(バックペイ)から,解雇された労働者が解雇期間中に他社で働いて得た収入(中間収入)や失業手当を控除することはできませんか?
解雇期間中の中間収入(他社で働いて得た収入)がある場合,その収入が副業収入のようなものであって解雇 がなくても取得できた(自社の収入と両立する)といった特段の事情がない限り,
① 月例賃金のうち平均賃金の60%(労基法26条)を超える部分(平均賃金額の40%)
② 平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(賞与等)の全額
が控除の対象となります(米軍山田部隊事件最高裁第二小法廷昭和37年7月20日判決,あけぼのタクシー事件最高裁第一小法廷昭和62年4月2日判決,いずみ福祉会事件最高裁第三小法廷平成18年3月28日判決)。
控除しうる中間収入はその発生期間が賃金の支給対象期間と時期的に対応していることが必要であり,時期が異なる期間内に得た収入を控除することは許されません(あけぼのタクシー事件最高裁第一小法廷昭和62年4月2日判決)。
解雇期間中に失業手当を受給していたとしても,失業手当額は控除してもらえません。
単純化して,解雇期間中の賃金が月額30万円,平均賃金も月額30万円と仮定して説明すると,以下のとおりとなります。
中間収入の額が平均賃金額の40%(12万円)を超えない場合,例えば他社で毎月10万円を稼いでいた場合には,30万円-10万円=20万円の賃金を毎月支払えば足りることになります。
中間収入の額が平均賃金額の40%(12万円)を超える場合,例えば他社で毎月25万円を稼いでいた場合には,30万円-25万円=5万円の賃金を毎月支払えば足りることにはならず,平均賃金の60%(18万円)を毎月支払わなければならないことになりますが,平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(賞与等)がある場合には,その全額を対象として控除することができます。
解雇が無効と判断された場合に解雇期間中の賃金として使用者が負担しなければならない金額を教えて下さい。
解雇 が無効と判断された場合に,解雇期間中の賃金として使用者が負担しなければならない金額は,当該社員が解雇されなかったならば労働契約上確実に支給されたであろう賃金の合計額です。
解雇当時の基本給等を基礎に算定されますが,各種手当,賞与を含めるか,解雇期間中の中間収入を控除するか,所得税等を控除するか等が問題となります。
通勤手当が実費保障的な性質を有する場合は,通勤手当について負担する必要はありません。
残業代 は,時間外・休日・深夜に勤務して初めて発生するものですから,通常は負担する必要がありませんが,一定額の残業代が確実に支給されたと考えられる場合には,残業代についても支払を命じられる可能性があります。
賞与の支給金額が確定できない場合は,解雇が無効と判断されても支払を命じられませんが,支給金額が確定できる場合は,賞与についても支払が命じられることがあります。
解雇された社員に解雇期間中の中間収入(他の事業上で働いて得た収入)がある場合は,その収入があったのと同時期の解雇期間中の賃金のうち,同時期の平均賃金の6割(労基法26条)を超える部分についてのみ控除の対象となります(米軍山田部隊事件最高裁第二小法廷昭和37年7月20日判決,あけぼのタクシー事件最高裁第一小法廷昭和62年4月2日判決)。
中間収入の額が平均賃金額の4割を超える場合には,更に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(賞与等)の全額を対象として利益額を控除することが許されることになります(あけぼのタクシー事件最高裁第一小法廷昭和62年4月2日判決,いずみ福祉会事件最高裁第三小法廷平成18年3月28日判決)。
賃金から源泉徴収すべき所得税,控除すべき社会保険料については,これらを控除する前の賃金額の支払が命じられ,実際の賃金支払の際,所得税等を控除することになります。
仮処分で賃金相当額の仮払いが命じられ,仮払いをしていたとしても,判決では仮払金を差し引いてもらえません。
賃金の支払を命じる判決が確定した場合は,労働者代理人と連絡を取って,既払の仮払金の充当について調整する必要があります。
他方,賃金請求が認められなかった場合は,仮払金の返還を求めることになりますが,労働者が無資力となっていて,回収が困難なケースもあります。
解雇が無効と判断された場合,使用者はいつまでの賃金を支払い続けなければならないのですか?
解雇 が無効と判断された場合,労働者が転職せずに職場復帰を求め続けた場合は,実際には全く働いていない期間についても賃金の支払を命じられることになります。
もっとも,解雇された労働者が他社に正社員として就職したり,使用者が解雇を撤回して労働者に出社するよう命じたにもかかわらず労働者が出社しなかったような場合は,解雇された労働者が労務提供の意思を喪失していると評価できるのが通常であり,解雇された労働者が就労できないのは使用者の責任ではなくなりますから,使用者は以後の賃金支払義務を免れることになります。