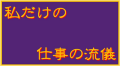● 基礎情報
氏名(ニックネーム) 高野 泰寛 (投稿者です) 福岡市在住 48歳 男性
現在のお仕事 学生・若者の就職支援 6年目 某ハローワーク
● これまで経験したお仕事・またはその一部
畜産農場の作業員・空調機の修理補助・農作業等請負業の経営・養鶏場職員・鶏卵等の営業
鶏卵パック工場責任者・空調機の営業・宅配便倉庫仕分け作業・トラックドライバー・スーパー店員
宅配便配送員・牛丼屋店員・うどん屋店員
● もっとも印象深い仕事とその内容(成功例や失敗例など)
トラックドライバー(4tトラックで食材やお菓子などを運んでいた)
前職の営業マン時代に、配送手配もしていたので運送業者との付き合いもあり、自分も大型免許を取得していたので自信があったが、実際にやってみると、時間に追われて迷惑をかけてばかりだった。
約半年後に、社長に「いつまでやるね?」と肩を叩かれ、ほとんどクビの状態で自主退職しました。
● その仕事を振り返って、今思うこと
自信があると思い込んでいただけに、さすがに心が折れた。思い込みと自分の実力の差を思い知った。
配送業務は基本一人で行うので、最新の注意と確認作業の連続となるが、自分はそもそも集中力が持続しないという短所があることに気付かないまま、単に出来そうだと思い込んでいた。
人には向き不向きがあると云うが、この時に初めて「思いだけでは通用しない」と痛感した。
● 忘れられない仕事での失敗談
失敗など無数にあるが、営業マンとして駆け出しの時、まだ実力がないにも関わらず、大事な得意先の担当になりたいあまり、自分の思いや考え方を手紙に書いて直接先方のトップに送ったこと。
案の定、取引が危うくなるほどの大騒ぎになり、始末書はもちろん書いたが、上司が先方まで謝罪に行き、結局当分出入り禁止処分となった。
● 仕事で影響を受けた人(どんな人と出会ってきたのか)
最初の上司となった N場長から、仕事に対する厳しさと楽しさを学んだ。
養鶏場職員時代の上司 N部長には、論理的に考える術を教えてもらった。
営業マン時代の上司 K社長とM部長には、原理原則論を叩きこまれた。
得意先の N社長には、大人の遊び方を教わった。
霊能者の T先生には、生命・魂の在り方、宗教の成り立ちと意味を学んだ。
そして、観術の創始者に出会い、全ての問題の根本原因と、人間の無限の可能性を知った。
● 仕事で楽しいと思う瞬間
仕事を終わらせる時間が、自分の読み通りになった時。
片づけや、整理整頓が、自分の思うように出来る時。
人から頼み事を引き受ける時。(誰かに必要とされていると実感できる時)
● 今になって思う。仕事のために、やっておけば良かったこと
英会話の練習・読書(特に小説)・海外への一人旅・多くのアルバイトやボランティア活動
● ズバリ、仕事とは何か
仕事は本来、楽しいも苦しいもない。仕事は成果を求めているだけである。
世間に仕え、役立つ事こそが、仕事である。
● 自分にとっての仕事の意味・価値とは・・・
生活の糧を得る手段 ・ 社会の一員であるという実感を得るためのツール
自分の心、技、体を発揮し、鍛え、成長させる場 ・ 人間としての基本的な活動
● 未だ社会に出ていない若者へ、贈る言葉
自分の素晴らしさに気付いて、自信をもって社会に出て来て欲しい。
貴方たちは、何にでもなれるし、何でも出来る。それを信じて欲しい。
★ 私だけの仕事の流儀とは
私は、事務仕事が苦手、というか嫌い。だから、出来るだけ手際よく、短時間で終わらせる手法を編み出そうと懸命になる。嫌な仕事ほど極めたいと思う。なぜなら、嫌な仕事は1秒でも早く終わらせて、好きな仕事はダラダラと時間をかけて何度でも楽しみながらしたいからだ。
これが私だけの仕事の流儀。 しかし、楽しい仕事の時間はいつも短い。
-------------------------------
こんな感じで紹介して行きます。紹介する人物によって、質問項目は変わります。
参加者募集中です。
yws_k@yahoo.co.jp
yws.net.2015@gmail.com
のいずれかにご連絡下さい。