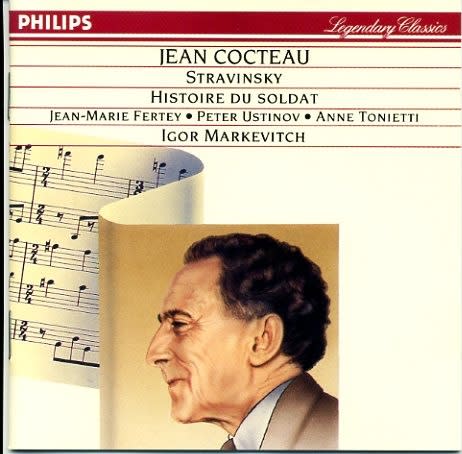
タワレコのwebに「モーリス・アンドレ追悼」と称してマルケヴィチとの「兵士の物語」再入荷との広告が載っていた。国内盤は廃盤だったのだと知った。私の手持ちは1987年のオランダプレスのCDでLegendary ClassicsシリーズでLP初出のジャケットを使用しなかったものだ。しかも輸入版のため原作者Ramuzの版ではなくJean Cocteauの手直しが入った版で、日本語訳がないため、原作との違いが、いまいち明確につかめていなかった。そんな訳で買い直すかどうか悩んだが、結局音質の改善がなされていないことから諦めた。
作曲家マルケヴィチは二人のIgor と言われディアギレフに見出されたストラヴィンスキーとディアギレフの娘と結婚したマルケヴィッチは、デアギレフにとっては正に二人のIgorで、30歳にして作曲の筆を折って以後指揮者に専念したマルケヴィッチはストラヴィンキーのスペシャリストと言われた。このCDは中でも最高の名演奏と言われてきたが、正直この演奏の良さは理解できずにいた。
私にはむしろこの曲の本来の姿である、バレー音楽としてNHKで90年前後に放映された「鬼才ジリ・キリアンの芸術」を見て、曲の凄さを知りストラヴィンスキーの最高傑作はこの曲では思うようになった。
改めて今回NHKを録画したVTRを見直したあとにCDを聞き直すと、狂言回しのウスチノフの語りとマルケヴィッチの音楽が見事に調和して、バレエ音楽とはべつものの、ジャン・コクトー作の音楽物語に変身しているのが理解できた。
そして高らかに小気味良く鳴り響くアンドレのトランペットは惚れ惚れする響きとなってこの音楽物語の場面転換の役割となっている。

My Blogではすでに2007年7月にこのカール・シューリヒトのブランデンブルグ協奏曲には触れているが、演奏はチューリヒ・バロックアンサンブルだけで、独奏者の記載は無いものの、2番のトランペットはモーリス・アンドレであるとの事だった。だいぶ後で知ったのだが、コンサートソサエティのおまけで付いた17cmのLpが彼の演奏を始めて耳にした時だった。ちなみに5番のチェンバロはクリスチーヌジャコッティでオーボエはホリガー、フルートはニコレと大家となった新人陣演奏家の集まりだった。

ハイドンもトランペットもどちらかと言うと今も昔もさほど好きとは言えない分類に入るが、このハイドン協奏曲を集めた1枚のLPは中でもトランペツト協奏曲といえばこれだといえるほどの曲で、やはりこの曲はアンドレと言われるだけあって素晴らしい輝きを放つ演奏だ。
確実に昭和の時代が遠ざかっていく。モーリス・アンドレ 2月25日 享年78歳














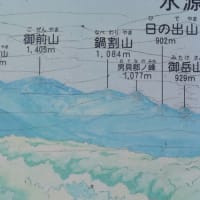






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます