先日昔のソニーが発売していたVideo8のテープを廃棄するため整理していたら、下記のNHKで放映された録画テープが出てきた。このVideoでは、ピアノ版を初演したサバリッシュがインタビューで、管弦楽版では、歌手がとても歌えない部分があるが、ピアノ版ではその点がクリアーされていると語っていた。バーンステインとイスラエルフィルの大地の歌では4楽章でのリハーサル風景が映像で残され、そこではクリスタ・ルードビッヒが、「そんなテンポではとても歌えない」と注文をだすと、バーンステインは、「高音部分を伸ばすことで飛ばしてしまえ」と指示するなど、サバリシュの指摘が示されていた。この練習風景は非常に興味深かったし、ピアノ版の存在価値が分かった気がした。
この映像を捨てるどころか見入ってしまい、改めて深い感動を味わった。ここのところ家庭内の出来事で、鳥撮り散歩も出られずに家にいたことから、だいぶ前に値段が2300円とあまりにも安い価格だったので、ブルーノ・ワルターの7枚組のマーラーの交響曲集を衝動買いした。しかしそれらはすでにLpレコードを所持していたことから、聴かずのままだった。これを機会に併せ手持ちの「大地の歌」の聴き比べをしていた。
我が手持ちのリスト

No.1
 大学に入学して間もないころ、神田神保町の中古レコード店(ミューズ社?)で見つけた、SPレコードからダビングしたと思われる「私家版」のLP。おそらく戦前のものだろうSPをただただダビングしただけの代物で、雑音の中からかすかに音楽が聞き取れるもので「音楽鑑賞」に耐えるものではなかったが、演奏者の名を信じれば、まさに「伝説の演奏人」であることには間違いないが?この件以降中古あさりはやめた。
大学に入学して間もないころ、神田神保町の中古レコード店(ミューズ社?)で見つけた、SPレコードからダビングしたと思われる「私家版」のLP。おそらく戦前のものだろうSPをただただダビングしただけの代物で、雑音の中からかすかに音楽が聞き取れるもので「音楽鑑賞」に耐えるものではなかったが、演奏者の名を信じれば、まさに「伝説の演奏人」であることには間違いないが?この件以降中古あさりはやめた。
No2  No3
No3 No.2はNHK-FM放送を聴いてほしくなり、高校の入学祝い金を親戚からもらいその金をもってレコード店に走って買った。何度も聴き今回面白半分にPCで24bit96kHzでハイレゾ化を試みたが当たり前のことだが、元が悪いことからコピーが良くなることはあり得ない。その後CD化されたNo3を買い求めた。今もって最初にFM-放送で聴いた時の感動がよみがえる。ワルターが初演指揮者と言うこともあって、先に挙げた1936年のSpレコードが伝説化されたが、私にはむしろこの演奏こそが伝説となるべき素晴らしい「大地の歌」だと思う。カスリーン・フェリアーの最後の「永遠に....永遠に......」のリフレインこそ、この演奏の永遠の名盤にふさわしい。モノラル録音ながら、スケールの雄大さと、寂寥感の深淵さを感じるこの演奏を超えるものはない。
No.2はNHK-FM放送を聴いてほしくなり、高校の入学祝い金を親戚からもらいその金をもってレコード店に走って買った。何度も聴き今回面白半分にPCで24bit96kHzでハイレゾ化を試みたが当たり前のことだが、元が悪いことからコピーが良くなることはあり得ない。その後CD化されたNo3を買い求めた。今もって最初にFM-放送で聴いた時の感動がよみがえる。ワルターが初演指揮者と言うこともあって、先に挙げた1936年のSpレコードが伝説化されたが、私にはむしろこの演奏こそが伝説となるべき素晴らしい「大地の歌」だと思う。カスリーン・フェリアーの最後の「永遠に....永遠に......」のリフレインこそ、この演奏の永遠の名盤にふさわしい。モノラル録音ながら、スケールの雄大さと、寂寥感の深淵さを感じるこの演奏を超えるものはない。
No 4 No.5
No.5 大学に入学してそれこそワルターのステレオ盤ということで、輸入盤の廉価盤を購入したが、NO.2を聴いた後では、左右のスピカーから違う音が聞こえる価値にしか思えなかった。
大学に入学してそれこそワルターのステレオ盤ということで、輸入盤の廉価盤を購入したが、NO.2を聴いた後では、左右のスピカーから違う音が聞こえる価値にしか思えなかった。
No.6 アルトのパートをバリトンのフィッシャー・デスカウが務める盤で、1989年に円高で輸入CDが安くなり、国内版より安く入手できた。これ以降はほとんど輸入盤を買うようになった。このCDの魅力はフィッシャー・デスカウに尽きる。特に4楽章の部分も、先に述べたように、ルードビッヒが「テンポが速く歌えない」と訴えた部分を含めゆったりとしたテンポで、大河の流れのように悠久の時を刻むがごとくに全体が流れ進む様が素晴らしい。No.3は別格として、このCDは私の推薦盤だ。
アルトのパートをバリトンのフィッシャー・デスカウが務める盤で、1989年に円高で輸入CDが安くなり、国内版より安く入手できた。これ以降はほとんど輸入盤を買うようになった。このCDの魅力はフィッシャー・デスカウに尽きる。特に4楽章の部分も、先に述べたように、ルードビッヒが「テンポが速く歌えない」と訴えた部分を含めゆったりとしたテンポで、大河の流れのように悠久の時を刻むがごとくに全体が流れ進む様が素晴らしい。No.3は別格として、このCDは私の推薦盤だ。
No.7 円高でバブル期に輸入品が安くなり、指揮がクレンペラーでデルモータの名に魅かれ購入した。バーゲン品としてたしか300円だたので買ったCDだ。録音はモノだが、聴ける音だ。EMIでフィルハーモニア管と録音したNo.8
円高でバブル期に輸入品が安くなり、指揮がクレンペラーでデルモータの名に魅かれ購入した。バーゲン品としてたしか300円だたので買ったCDだ。録音はモノだが、聴ける音だ。EMIでフィルハーモニア管と録音したNo.8 との演奏時間が11分も早く、ワルター同様にマーラーの弟子だったものにはこのテンポが通常だったのかと思わせる。最初のワルターの録音と大差ない。
との演奏時間が11分も早く、ワルター同様にマーラーの弟子だったものにはこのテンポが通常だったのかと思わせる。最初のワルターの録音と大差ない。
ただNo.8との比較では、この演奏が今度は手持ちの中では最長の演奏で、最短・最長の演奏がクレンペラーなのが面白い(バーンステイン盤はバリトン盤として例外)No.8でのクリスタルードビッヒの歌は、1972年のバンステーン盤に比べると私はこちらの方が好ましい。ステレオ録音でアルトの終楽章を望むならば、私はNo.8を推薦する。
No.9 は日本コロンビアのデジタル録音技術が評判となった、マーラーのデジタル録音の全集だ。当時としては画期的なマーラー録音だが今となっては逆に16Bit44kHz録音よりもかつてのアナログ録音を24Bit96Khzに落とし込んだ方が音が良いとされ、やはり音楽は演奏そのものが評価される当たり前に戻ったが、演奏は正直私は好みではない。むしろ買ってから正直あまり聴いていない。
は日本コロンビアのデジタル録音技術が評判となった、マーラーのデジタル録音の全集だ。当時としては画期的なマーラー録音だが今となっては逆に16Bit44kHz録音よりもかつてのアナログ録音を24Bit96Khzに落とし込んだ方が音が良いとされ、やはり音楽は演奏そのものが評価される当たり前に戻ったが、演奏は正直私は好みではない。むしろ買ってから正直あまり聴いていない。
v1 シェーンベルグの編曲になる小オーケストラによるものだが、マーラー音楽の分析の意味はあるものでマーラー好きならば一聴をお勧めする。
シェーンベルグの編曲になる小オーケストラによるものだが、マーラー音楽の分析の意味はあるものでマーラー好きならば一聴をお勧めする。
p1 ピアノ版の大地の歌、サバリシュの世界初演後最初に出たCDだったと思う。サバリシュが初演時のインタビューで語った通りに、歌曲としてはスケールが大きく、オーケストラ版では歌手が歌いにくいところがピアノ版では回避されているとの指摘通りにスケール感の大きな歌曲集に仕上がっている。ピアノ伴奏者?がカツァリス、既にベートーヴェンの交響曲全曲をピアノ版で録音しているだけに、多彩な音色を駆使しての伴奏が面白いが、聴き物はクールに終楽章を歌い上げるブリギッテ・ファスベンダーだ。なぜオーケストラ版を歌わなかったのかが今となっては惜しまれる。
ピアノ版の大地の歌、サバリシュの世界初演後最初に出たCDだったと思う。サバリシュが初演時のインタビューで語った通りに、歌曲としてはスケールが大きく、オーケストラ版では歌手が歌いにくいところがピアノ版では回避されているとの指摘通りにスケール感の大きな歌曲集に仕上がっている。ピアノ伴奏者?がカツァリス、既にベートーヴェンの交響曲全曲をピアノ版で録音しているだけに、多彩な音色を駆使しての伴奏が面白いが、聴き物はクールに終楽章を歌い上げるブリギッテ・ファスベンダーだ。なぜオーケストラ版を歌わなかったのかが今となっては惜しまれる。





















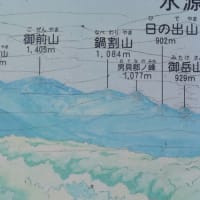






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます