アラン・レネ監督作品のポスターを飾ったので。
「二十四時間の情事」 1959年 フランス/日本
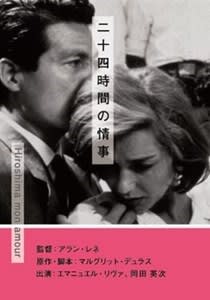
監督 アラン・レネ
出演 エマニュエル・リヴァ 岡田英次
ベルナール・フレッソン
アナトール・ドーマン
ストーリー
原爆をテーマにした映画に出演するため広島にやって来たフランス人女優(エマニュエル・リヴァ)は、偶然知り合った日本人男性(岡田英次)となぜか気が合い、一晩限りの恋に落ちる。
ともに夫も妻もいる身でありながら二人は心のうちを語り合い、少しずつそれぞれの過去が明らかになっていく。かつて第二次世界大戦中、彼女はフランスを支配していたナチス・ドイツの兵士と恋に落ちた経験があった。
しかし、ドイツの降伏を前にその兵士は殺され、彼女の死んだ恋はフランスの敵となり、彼女自身も非国民として頭を丸刈りにされるという辱めを受けた。
その後、しばらく彼女は父親によって家に閉じ込められていたが、ある夜、正気を取り戻した彼女は両親の許しを得て、故郷ヌーブルの街からパリへと旅立った。
その後、女優となった彼女は広島を訪れ、再び忘れかけていた戦争の記憶を蘇らせることになった。
日本人の建築家もまた家族を原爆によって失うという悲しい記憶をもっており、二人は戦争の重い十字架をお互いに思い起こすことで、より深くつながり、わずか一晩の恋が永遠とも思える深い愛情へと発展していく。
しかし、その愛も彼女の帰郷とともに終わりを迎える。
「愛の終わり」は確実に訪れるが、その記憶は「忘却」のために時間を必要としていた。
二人の愛の終わりもまた戦争の記憶とともに長い忘却のための時を必要とするのかもしれない。
彼女は叫んだ。《私はあなたのこと忘れるわ。もう忘れてしまったわ。私が忘れていくのを見て。私を見て》
明け方の駅前広場ではもうネオンが消えた。
寸評
広島を訪れたフランス女性と日本人男性の恋愛を描きながらも、戦争を背景とした異国文化や価値観を共有できるのかと模索している。
同時に異国文化や価値観を通して体験した戦争経験を忘れることなく語り続けていけるのか、いや、戦争が生み出した悲劇を語り継いでいかねばならないのだと訴えている。
薄闇野中で男女が抱きあう印象深いシーンから映画はスタートする。
女は映画の撮影で広島を訪れていて、平和公園に行き、病院を訪問し、原爆資料館も見学している。
ベッドの中で女は「私、広島で何もかも見たわ」とつぶやくのだが、男は「君は何も見ちゃいない」と答える。
訪問した先々で女は原爆投下の悲惨さを知ったのだろうが、しかしそれはあくまでも第三者の目で見たもので、実際の体験者はもっと悲惨だったのだと男の言葉は言っているのかもしれない。
そんな男も両親を広島で亡くしていても、自分は広島の原爆を体験していない。
しかし多くの日本人がそうであるように、彼は原爆を否定し被爆者の苦しみを共有している。
同じように、フランスもナチス・ドイツに侵略された経験を有している。
そこでは女が経験したようなことも起きたであろう。
若者の気持ちは国家の意思とは別に、純粋な愛をも生み出すが、戦争はそれを引き裂く。
侵略されるということの悲惨さを日本人は分かっていないのかもしれない。
知識で得ることと、経験から得たこととは違うものだろう。
彼等はお互いの肉体を通じて、その思いを共有していく。
男は広島そのものの象徴でもあった。
彼等の過去の経験、特に女の体験がラブ・ロマンスとシンクロしてくることで物語の感性に広がりを見せる。
女には母国に夫がいて子供もいるようだし、男には妻がいて幸せな家庭があるようなので、言って見れば二人の関係はダブル不倫で、男は妻の不在をいいことに女を自宅に連れ込んでいる。
恋愛物語としてはとんでもない状況なのだが、それはこの物語の背景にしか過ぎない。
「私は今夜あの異邦人と共にあなたを裏切ったの。私はあなたを忘れて行く。私を見て」と女は死んだドイツ兵を回顧してつぶやく。
その前には「怖いわ、あれだけの愛情を忘れてしまうのは・・・」とも言っている。
忘却することの怖さを語りながらも、忘れ去ってはいけないのだと強く叫んでいるようにも思える。
どんなに愛した人でも、時間が経てば心の傷を埋め、その人のことは忘れ去っていくものなのだろうが、そん艘体験は忘れ去ってはいけないことなのだ。
僕は戦争を体験していない。
それでもそんな世代の人間に大して、戦争がもたらす悲劇、原爆がもたらした悲惨な状況を語り継いでいく必要が有るのだ。
撮影時の広島の町が見事にとらえられているが、あのころの日本はいたる所があのような風景を生み出していて、大阪駅前だって、一歩路地を入るとあのような雰囲気があった。
懐かしい風景を思いさせてくれるのも、僕がこの映画に親しめる一因となっている。
「二十四時間の情事」 1959年 フランス/日本
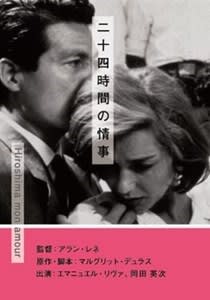
監督 アラン・レネ
出演 エマニュエル・リヴァ 岡田英次
ベルナール・フレッソン
アナトール・ドーマン
ストーリー
原爆をテーマにした映画に出演するため広島にやって来たフランス人女優(エマニュエル・リヴァ)は、偶然知り合った日本人男性(岡田英次)となぜか気が合い、一晩限りの恋に落ちる。
ともに夫も妻もいる身でありながら二人は心のうちを語り合い、少しずつそれぞれの過去が明らかになっていく。かつて第二次世界大戦中、彼女はフランスを支配していたナチス・ドイツの兵士と恋に落ちた経験があった。
しかし、ドイツの降伏を前にその兵士は殺され、彼女の死んだ恋はフランスの敵となり、彼女自身も非国民として頭を丸刈りにされるという辱めを受けた。
その後、しばらく彼女は父親によって家に閉じ込められていたが、ある夜、正気を取り戻した彼女は両親の許しを得て、故郷ヌーブルの街からパリへと旅立った。
その後、女優となった彼女は広島を訪れ、再び忘れかけていた戦争の記憶を蘇らせることになった。
日本人の建築家もまた家族を原爆によって失うという悲しい記憶をもっており、二人は戦争の重い十字架をお互いに思い起こすことで、より深くつながり、わずか一晩の恋が永遠とも思える深い愛情へと発展していく。
しかし、その愛も彼女の帰郷とともに終わりを迎える。
「愛の終わり」は確実に訪れるが、その記憶は「忘却」のために時間を必要としていた。
二人の愛の終わりもまた戦争の記憶とともに長い忘却のための時を必要とするのかもしれない。
彼女は叫んだ。《私はあなたのこと忘れるわ。もう忘れてしまったわ。私が忘れていくのを見て。私を見て》
明け方の駅前広場ではもうネオンが消えた。
寸評
広島を訪れたフランス女性と日本人男性の恋愛を描きながらも、戦争を背景とした異国文化や価値観を共有できるのかと模索している。
同時に異国文化や価値観を通して体験した戦争経験を忘れることなく語り続けていけるのか、いや、戦争が生み出した悲劇を語り継いでいかねばならないのだと訴えている。
薄闇野中で男女が抱きあう印象深いシーンから映画はスタートする。
女は映画の撮影で広島を訪れていて、平和公園に行き、病院を訪問し、原爆資料館も見学している。
ベッドの中で女は「私、広島で何もかも見たわ」とつぶやくのだが、男は「君は何も見ちゃいない」と答える。
訪問した先々で女は原爆投下の悲惨さを知ったのだろうが、しかしそれはあくまでも第三者の目で見たもので、実際の体験者はもっと悲惨だったのだと男の言葉は言っているのかもしれない。
そんな男も両親を広島で亡くしていても、自分は広島の原爆を体験していない。
しかし多くの日本人がそうであるように、彼は原爆を否定し被爆者の苦しみを共有している。
同じように、フランスもナチス・ドイツに侵略された経験を有している。
そこでは女が経験したようなことも起きたであろう。
若者の気持ちは国家の意思とは別に、純粋な愛をも生み出すが、戦争はそれを引き裂く。
侵略されるということの悲惨さを日本人は分かっていないのかもしれない。
知識で得ることと、経験から得たこととは違うものだろう。
彼等はお互いの肉体を通じて、その思いを共有していく。
男は広島そのものの象徴でもあった。
彼等の過去の経験、特に女の体験がラブ・ロマンスとシンクロしてくることで物語の感性に広がりを見せる。
女には母国に夫がいて子供もいるようだし、男には妻がいて幸せな家庭があるようなので、言って見れば二人の関係はダブル不倫で、男は妻の不在をいいことに女を自宅に連れ込んでいる。
恋愛物語としてはとんでもない状況なのだが、それはこの物語の背景にしか過ぎない。
「私は今夜あの異邦人と共にあなたを裏切ったの。私はあなたを忘れて行く。私を見て」と女は死んだドイツ兵を回顧してつぶやく。
その前には「怖いわ、あれだけの愛情を忘れてしまうのは・・・」とも言っている。
忘却することの怖さを語りながらも、忘れ去ってはいけないのだと強く叫んでいるようにも思える。
どんなに愛した人でも、時間が経てば心の傷を埋め、その人のことは忘れ去っていくものなのだろうが、そん艘体験は忘れ去ってはいけないことなのだ。
僕は戦争を体験していない。
それでもそんな世代の人間に大して、戦争がもたらす悲劇、原爆がもたらした悲惨な状況を語り継いでいく必要が有るのだ。
撮影時の広島の町が見事にとらえられているが、あのころの日本はいたる所があのような風景を生み出していて、大阪駅前だって、一歩路地を入るとあのような雰囲気があった。
懐かしい風景を思いさせてくれるのも、僕がこの映画に親しめる一因となっている。
















