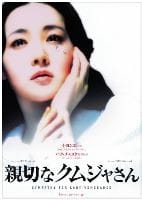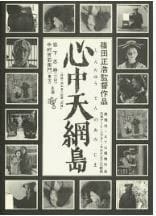1本、思い出したので・・・。
「砂の女」 1964年 日本

監督 勅使河原宏
出演 岡田英次 岸田今日子
三井弘次 伊藤弘子 矢野宣
関口銀三 市原清彦
ストーリー
遥か彼方まで延々と連なる砂丘。
一人の中学校教師、仁木順平は3日間の休暇を利用して、昆虫の採集と生態観察をしにやって来た。
日が暮れかかり、休んでいるところへの男が通りかかった。
この近くで泊まるとこの世話ぐらいしてあげられると、仁木がの男たちに案内されたところは砂丘を掘った中に建てられた一軒の小屋で、その家に住む女が家の中へ招き入れた。
主人に死なれ一人で住んでいるのだという。
女が砂をかき、モッコに載せた砂を上の男たちが滑車で引き上げる。
引き上げた砂はどこかへ捨てるのであろうか、そんな作業は朝まで続くのだった。
翌日、仁木は身支度をし、外へ出てみると自分が降りた筈の梯子がない。
砂をよじ登るが、砂はまったく手ごたえがなく、足元から崩れるばかりだ。
夜、仁木は砂かきを手伝うが、仁木にはこんな生活に明け暮れる女がまったく理解できない。
仁木は密かに隙を見て縄梯子を作っていた。
ある日、女に焼酎を飲ませ、寝入った頃を見計らって忍者よろしく縄を上の滑車の土台めがけて投げる。
何回かで縄の先端の突起が何かに掛かり、やっと地表に出ると辺りは暗くなりつつあった。
仁木は走ったが、どこをどう走ったものやら、どういうわけか、真っ直ぐ走っている筈が方角が違う。
そして、気付いた時、おぞましい落とし穴にはまっている自分に気付いた。
の男たちがやって来て仁木を穴から救い出し、仁木は再び女の小屋へ逆戻りとなった。
縄梯子が残されていて、このまま逃げようと思えば逃げられるが、仁木は再び穴に戻った・・・。
寸評
砂の壁が崩れていく、砂の中を小さな虫が這う、男と女の肌に砂粒がベタリと粘着する。
砂のイメージが画面を通じて迫ってきて、紛れもなくこの映画の主人公は「砂」そのものである。
しかもその砂は心地よいものではなく、むしろ嫌な思いのするものだ。
海辺の砂浜をサンダルで歩いた時に、濡れた足とサンダルの間に入り込んだ砂のうっとしい感覚が湧いてくる。
僕は若い頃に砂丘近くの松林で野営したことがあるが、暗闇の中、風が極小の砂粒を運んできて鉄板の野菜炒めの中に入り込み、見た目には分からず口に入れたとたん、ジャリッと音がして食べられたものではない。
あの不愉快な感覚が鳥肌を伴って蘇ってきた。
それほどにこの映画における、じわじわとこちらににじり寄ってくるかのような砂の映像は特筆ものである。
女は蟻地獄のような場所に住んでいて、引っ越せばよいではないかと思うが女にその気はない。
岸田今日子の大きな目と口という特徴ある顔立ちはこの映画にピッタリであり、女は砂の精なのかもしれないと思わせるような所もある。
砂の女を非常にエロティックな目線で撮っているのも雰囲気を出している。
男に対し罪悪感を感じつつも、どうしてもそばにいて欲しいと願う寂しい砂の女を岸田今日子は見事に演じている。
男は昆虫採集にこの土地を訪れたのだが、自分が蟻地獄に捕らえられてしまったようで抜け出せない。
何とか抜け出そうともがく姿に引き込まれていく。
現実にはこんな場所はないだろうし、こんな目にあう人もいないだろうが、それが空想の世界を飛び越えて現実の世界の物語と迫ってくる説得力のようなものをこの映画の映像は有している。
身体にまとわりつく砂粒の不快感の中で、水がなくなってゆくというあせりで追い詰められていく男の心と身体の凄まじい渇きが見事に映し出されていく。
男はやっとの思いでここから逃げ出すが、再び戻ってきてしまう。
住めば都なのか、一度馴染んでしまった地域共同体の世界から出ていくことの難しさなのかもしれない。
地域には地域独特の風習や決まりが存在し、見知らぬ土地に同化することの大変さは想像の範囲内だ。
僕もこの土地にきて50年以上になるが、それでも”入り人”としての違和感と線引きを感じることがある。
家の成り立ち、人の生い立ちを熟知している土着の人たちと、途中からやってきた自分とのわずかな溝を何かにつけて感じるのだ。
男は毛細管現象を利用した水の入手を考案する。
水道が当たり前の人には分かってもらえないが、この土地の人ならこの装置の素晴らしさに興味を示してくれるはずだとの理由で男はこの場所に居つくのだが、男はこの場所で自分が存在する価値を見出したのだろう。
自分がこの土地に同化できる手立てを発見した喜びがあったのかもしれない。
皮肉なことに女はこの場所を外部要因によって出ていくことになる。
この対比も何か思わせぶりだ。
何かよく分からない話だが、何かあると感じさせる映画で、モノトーンの映像が効果を最大限に生かしている。
タイトルバックのハンコによるスタッフ・キャストの表現はユニークだった。
「砂の女」 1964年 日本

監督 勅使河原宏
出演 岡田英次 岸田今日子
三井弘次 伊藤弘子 矢野宣
関口銀三 市原清彦
ストーリー
遥か彼方まで延々と連なる砂丘。
一人の中学校教師、仁木順平は3日間の休暇を利用して、昆虫の採集と生態観察をしにやって来た。
日が暮れかかり、休んでいるところへの男が通りかかった。
この近くで泊まるとこの世話ぐらいしてあげられると、仁木がの男たちに案内されたところは砂丘を掘った中に建てられた一軒の小屋で、その家に住む女が家の中へ招き入れた。
主人に死なれ一人で住んでいるのだという。
女が砂をかき、モッコに載せた砂を上の男たちが滑車で引き上げる。
引き上げた砂はどこかへ捨てるのであろうか、そんな作業は朝まで続くのだった。
翌日、仁木は身支度をし、外へ出てみると自分が降りた筈の梯子がない。
砂をよじ登るが、砂はまったく手ごたえがなく、足元から崩れるばかりだ。
夜、仁木は砂かきを手伝うが、仁木にはこんな生活に明け暮れる女がまったく理解できない。
仁木は密かに隙を見て縄梯子を作っていた。
ある日、女に焼酎を飲ませ、寝入った頃を見計らって忍者よろしく縄を上の滑車の土台めがけて投げる。
何回かで縄の先端の突起が何かに掛かり、やっと地表に出ると辺りは暗くなりつつあった。
仁木は走ったが、どこをどう走ったものやら、どういうわけか、真っ直ぐ走っている筈が方角が違う。
そして、気付いた時、おぞましい落とし穴にはまっている自分に気付いた。
の男たちがやって来て仁木を穴から救い出し、仁木は再び女の小屋へ逆戻りとなった。
縄梯子が残されていて、このまま逃げようと思えば逃げられるが、仁木は再び穴に戻った・・・。
寸評
砂の壁が崩れていく、砂の中を小さな虫が這う、男と女の肌に砂粒がベタリと粘着する。
砂のイメージが画面を通じて迫ってきて、紛れもなくこの映画の主人公は「砂」そのものである。
しかもその砂は心地よいものではなく、むしろ嫌な思いのするものだ。
海辺の砂浜をサンダルで歩いた時に、濡れた足とサンダルの間に入り込んだ砂のうっとしい感覚が湧いてくる。
僕は若い頃に砂丘近くの松林で野営したことがあるが、暗闇の中、風が極小の砂粒を運んできて鉄板の野菜炒めの中に入り込み、見た目には分からず口に入れたとたん、ジャリッと音がして食べられたものではない。
あの不愉快な感覚が鳥肌を伴って蘇ってきた。
それほどにこの映画における、じわじわとこちらににじり寄ってくるかのような砂の映像は特筆ものである。
女は蟻地獄のような場所に住んでいて、引っ越せばよいではないかと思うが女にその気はない。
岸田今日子の大きな目と口という特徴ある顔立ちはこの映画にピッタリであり、女は砂の精なのかもしれないと思わせるような所もある。
砂の女を非常にエロティックな目線で撮っているのも雰囲気を出している。
男に対し罪悪感を感じつつも、どうしてもそばにいて欲しいと願う寂しい砂の女を岸田今日子は見事に演じている。
男は昆虫採集にこの土地を訪れたのだが、自分が蟻地獄に捕らえられてしまったようで抜け出せない。
何とか抜け出そうともがく姿に引き込まれていく。
現実にはこんな場所はないだろうし、こんな目にあう人もいないだろうが、それが空想の世界を飛び越えて現実の世界の物語と迫ってくる説得力のようなものをこの映画の映像は有している。
身体にまとわりつく砂粒の不快感の中で、水がなくなってゆくというあせりで追い詰められていく男の心と身体の凄まじい渇きが見事に映し出されていく。
男はやっとの思いでここから逃げ出すが、再び戻ってきてしまう。
住めば都なのか、一度馴染んでしまった地域共同体の世界から出ていくことの難しさなのかもしれない。
地域には地域独特の風習や決まりが存在し、見知らぬ土地に同化することの大変さは想像の範囲内だ。
僕もこの土地にきて50年以上になるが、それでも”入り人”としての違和感と線引きを感じることがある。
家の成り立ち、人の生い立ちを熟知している土着の人たちと、途中からやってきた自分とのわずかな溝を何かにつけて感じるのだ。
男は毛細管現象を利用した水の入手を考案する。
水道が当たり前の人には分かってもらえないが、この土地の人ならこの装置の素晴らしさに興味を示してくれるはずだとの理由で男はこの場所に居つくのだが、男はこの場所で自分が存在する価値を見出したのだろう。
自分がこの土地に同化できる手立てを発見した喜びがあったのかもしれない。
皮肉なことに女はこの場所を外部要因によって出ていくことになる。
この対比も何か思わせぶりだ。
何かよく分からない話だが、何かあると感じさせる映画で、モノトーンの映像が効果を最大限に生かしている。
タイトルバックのハンコによるスタッフ・キャストの表現はユニークだった。