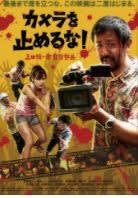「きみの鳥はうたえる」 2018年 日本

監督 三宅唱
出演 柄本佑 石橋静河 染谷将太 足立智充
山本亜依 柴田貴哉 渡辺真起子 萩原聖人
ストーリー
“僕”(柄本佑)は函館郊外の書店で働きながら、小さなアパートで失業中の静雄(染谷将太)と共同生活を送っている。
“僕”は他人から「誠実でない」といわれるようにいい加減で、暴力性も持ち合わせた人間だ。
一方、静雄は優しくておとなしい青年。
まったく性格の違う2人だが、なぜか気があってお互いを尊重している。
ある日、僕はふとしたきっかけで同じ書店で働く佐知子(石橋静河)と関係を持つが、彼女は店長の島田(萩原聖人)とも抜き差しならない関係にあるようだった。
しかし佐知子は毎晩のようにアパートを訪れ、“僕”、佐知子、静雄の3人は夏の間、毎晩のように酒を飲み、クラブへ出かけ、ビリヤードをして遊ぶようになる。
“僕”は佐知子と恋人同士のように振る舞いながら、お互いを束縛せず、静雄とふたりで出掛けることを勧める。
静雄も“僕”に気を使い、“僕”が佐知子と2人きりの時には、できるだけ家にいないようにしたりする。
夏の終わり、静雄はみんなでキャンプに行こうと提案するが、“僕”はその誘いを断る。
ふたりでキャンプに行くことになった静雄と佐知子は次第に気持ちが近づいていく。
“僕”は函館でじっと暑さに耐えていた。
3人の幸福な日々も終わりの気配を見せ始める。
“僕”も静雄も佐知子も、このままの暮らしがずっと続くなどとは思っていない。
楽しい夏が過ぎ去り、いつかこの関係性に終わりがもたらされ、やがて青春の日々が終焉を迎えることを予感しているようだ。
寸評
佐藤泰志作品を映画化したものとして、熊切和嘉の「海炭市叙景」(2010年)、呉美保の「そこのみにて光輝く」(2014年)、山下敦弘の「オーバー・フェンス」(2016年)と見てきたが、2018年は三宅唱監督による「きみの鳥はうたえる」である。
この映画では、ひと夏という季節を背景に、徹夜で遊び呆ける三人の気ままな日常が描かれているだけで、これといって大きな出来事は起きない。
そんなに夜遊びをして疲れないのかと思うが、僕も彼等の年頃の時はそうだったのかもしれない。
ひと夏と言う短期間の無為な日々が、生き生きと、魅力的に、みずみずしく描かれている。
監督がそれぞれ違うのに、佐藤泰志作品を映画化したものはみな秀作ばかりだ。
映画の中では何も起こらないが、それでも三人の間には様々な感情が渦巻く。
セリフに頼りすぎず、しぐさや微妙な表情の変化で心の揺れ動きを繊細に描いているのがいい。
3人の若者たちの日常からは、青春のきらめきが見える。
今どきの若者ではあるが、青春は多かれ少なかれこのようなものだろう。
無意味なもの、無価値なものに埋没するのは僕も経験したことだ。
“僕”はかなりいい加減な男で暴力性を秘めている。
勤務先である書店を無断欠勤するし、風采だけを見れば普通のサラリーマンと比較するとはみ出し者だ。
それでも同じ若者の気安さか、佐知子はそれとなく誘いをかける。
“僕”はそれを感じ取ってその場所で待ち続ける。
やってきた佐知子は「心が通じたね」と言い、夜の10時に店で落ち合うことを約束し別れるが、“僕”は眠りこけてしまい約束の場所に現れない。
一悶着起きそうなシチュエーションだが、何事もなかったかのように二人は付き合うようになる。
そんなやりとりが、実にリアリティを感じさせるものとなっている。
静雄は“僕”に比べれば真面目そうだが、生真面目すぎるとまでは言えない、あくまでも“僕”との対比上で真面目な部類に属しているだけである。
二人は気が合って同居しているが、なぜそうなのかを語る静雄の言葉はリアリティに飛んでいる。
セリフが飛び交う作品ではないが、弁当屋で女二人が語り合うシーンにおける会話などが極めてリアルだ。
三人の若者を演じた柄本佑、石橋静河、染谷将太の演技はなかなかのものだったが、特筆されるのは複雑な感情を垣間見せる石橋静河だ。
この映画は石橋静河によって支えられているといっても過言でない。
特にラストの表情は何とも言えない。
この表情の解釈は観客に委ねられているが、僕は「今更何でそんな煩わしいことを言ってくるのよ」と言っているように見えた。
アップの多い映画だが、それぞれのシーンでの三人の表情は作品を引き締めていた。
若者の生態を描いたような作品で、青みがかった映像が彼等に対する冷ややかな目線を感じさせる。
青春賛歌映画ではないが、三人の関係のゆるやかな変化を繊細に描いていて、僕は久々に青春映画を見た気分になった。

監督 三宅唱
出演 柄本佑 石橋静河 染谷将太 足立智充
山本亜依 柴田貴哉 渡辺真起子 萩原聖人
ストーリー
“僕”(柄本佑)は函館郊外の書店で働きながら、小さなアパートで失業中の静雄(染谷将太)と共同生活を送っている。
“僕”は他人から「誠実でない」といわれるようにいい加減で、暴力性も持ち合わせた人間だ。
一方、静雄は優しくておとなしい青年。
まったく性格の違う2人だが、なぜか気があってお互いを尊重している。
ある日、僕はふとしたきっかけで同じ書店で働く佐知子(石橋静河)と関係を持つが、彼女は店長の島田(萩原聖人)とも抜き差しならない関係にあるようだった。
しかし佐知子は毎晩のようにアパートを訪れ、“僕”、佐知子、静雄の3人は夏の間、毎晩のように酒を飲み、クラブへ出かけ、ビリヤードをして遊ぶようになる。
“僕”は佐知子と恋人同士のように振る舞いながら、お互いを束縛せず、静雄とふたりで出掛けることを勧める。
静雄も“僕”に気を使い、“僕”が佐知子と2人きりの時には、できるだけ家にいないようにしたりする。
夏の終わり、静雄はみんなでキャンプに行こうと提案するが、“僕”はその誘いを断る。
ふたりでキャンプに行くことになった静雄と佐知子は次第に気持ちが近づいていく。
“僕”は函館でじっと暑さに耐えていた。
3人の幸福な日々も終わりの気配を見せ始める。
“僕”も静雄も佐知子も、このままの暮らしがずっと続くなどとは思っていない。
楽しい夏が過ぎ去り、いつかこの関係性に終わりがもたらされ、やがて青春の日々が終焉を迎えることを予感しているようだ。
寸評
佐藤泰志作品を映画化したものとして、熊切和嘉の「海炭市叙景」(2010年)、呉美保の「そこのみにて光輝く」(2014年)、山下敦弘の「オーバー・フェンス」(2016年)と見てきたが、2018年は三宅唱監督による「きみの鳥はうたえる」である。
この映画では、ひと夏という季節を背景に、徹夜で遊び呆ける三人の気ままな日常が描かれているだけで、これといって大きな出来事は起きない。
そんなに夜遊びをして疲れないのかと思うが、僕も彼等の年頃の時はそうだったのかもしれない。
ひと夏と言う短期間の無為な日々が、生き生きと、魅力的に、みずみずしく描かれている。
監督がそれぞれ違うのに、佐藤泰志作品を映画化したものはみな秀作ばかりだ。
映画の中では何も起こらないが、それでも三人の間には様々な感情が渦巻く。
セリフに頼りすぎず、しぐさや微妙な表情の変化で心の揺れ動きを繊細に描いているのがいい。
3人の若者たちの日常からは、青春のきらめきが見える。
今どきの若者ではあるが、青春は多かれ少なかれこのようなものだろう。
無意味なもの、無価値なものに埋没するのは僕も経験したことだ。
“僕”はかなりいい加減な男で暴力性を秘めている。
勤務先である書店を無断欠勤するし、風采だけを見れば普通のサラリーマンと比較するとはみ出し者だ。
それでも同じ若者の気安さか、佐知子はそれとなく誘いをかける。
“僕”はそれを感じ取ってその場所で待ち続ける。
やってきた佐知子は「心が通じたね」と言い、夜の10時に店で落ち合うことを約束し別れるが、“僕”は眠りこけてしまい約束の場所に現れない。
一悶着起きそうなシチュエーションだが、何事もなかったかのように二人は付き合うようになる。
そんなやりとりが、実にリアリティを感じさせるものとなっている。
静雄は“僕”に比べれば真面目そうだが、生真面目すぎるとまでは言えない、あくまでも“僕”との対比上で真面目な部類に属しているだけである。
二人は気が合って同居しているが、なぜそうなのかを語る静雄の言葉はリアリティに飛んでいる。
セリフが飛び交う作品ではないが、弁当屋で女二人が語り合うシーンにおける会話などが極めてリアルだ。
三人の若者を演じた柄本佑、石橋静河、染谷将太の演技はなかなかのものだったが、特筆されるのは複雑な感情を垣間見せる石橋静河だ。
この映画は石橋静河によって支えられているといっても過言でない。
特にラストの表情は何とも言えない。
この表情の解釈は観客に委ねられているが、僕は「今更何でそんな煩わしいことを言ってくるのよ」と言っているように見えた。
アップの多い映画だが、それぞれのシーンでの三人の表情は作品を引き締めていた。
若者の生態を描いたような作品で、青みがかった映像が彼等に対する冷ややかな目線を感じさせる。
青春賛歌映画ではないが、三人の関係のゆるやかな変化を繊細に描いていて、僕は久々に青春映画を見た気分になった。