「終身犯」 1961年 アメリカ

監督 ジョン・フランケンハイマー
出演 バート・ランカスター カール・マルデン
セルマ・リッター ベティ・フィールド
ネヴィル・ブランド エドモンド・オブライエン
ヒュー・マーロウ テリー・サヴァラス
ストーリー
1909年、ロバート・ストラウドは恋人に乱暴した男を殺し12年の刑で連邦刑務所に入れられ、ここでも母のことを罵った同房の囚人を傷害、レヴンワース刑務所へ移された。
看守長はシューメイカーという男で、彼にはラムソンとクレイマーという2人の手荒な看守がついていた。
ストラウドの母エリザベスが3千キロを汽車にゆられ息子に会いに来た。
クレイマーは面会日でないからと追い返したことに逆上したストラウドはクレイマーの心臓を一突きで刺す。
正当防衛を主張するが絞首刑の宣告。
しかしエリザベスのウィルスン大統領夫人への嘆願が功を奏し終身刑に減刑させる。
ストラウドの独房生活が始まった。
ある日、彼は中庭に嵐に打たれズブ濡れになった雀を見つけ、独房に持ち込み育てた。
色々な芸当を教え込んだ。
シューメイカーは転任、後任の看守長コムストックは独房中でカナリヤを飼う許可を与えてくれた。
熱心に小鳥を観察、鳥に関する本を読むストラウド。
やがて彼は鳥類学の権威となり、独房内で鳥小屋と研究室の許可をもらい、さらにカナリヤの命取りともなる熱病の治療法を発見して、その論文を雑誌に発表した。
ある日、ステラ・ジョンスンという愛鳥家の未亡人が彼を訪ねてきた。
例の論文を読んで会いたくてきたというのだ。
2人は意気投合、ステラは彼に援助を申し込んだ。
シューメイカーの差金で刑務所の管理方針が変わり、小鳥の飼育が禁止されそうになった。
ステラはストラウドと獄中結婚、話題を巻起こして世論を喚起、刑務所側と対抗した。
結局ストラウドは孤島のアルカトラス刑務所へ移されて対立はケリがついた。
ここの所長はシューメイカー。
小鳥の飼育は勿論禁止、ストラウドは法律を勉強、こんどは刑務所改善の論文を書いたが没収された。
そこへ待遇の悪さに怒った囚人4人の囚人が首謀者になっての暴動が起こった。
騒ぎは間もなくおさまるが、この間、終始冷静にことをおさめるのに尽力したストラウドの態度は高く評価され、ミズリー州の連邦囚人病院で小鳥の研究を続けることを許された。
彼はもう孤独ではない、終身犯の身でありながら安らぎと幸福がそこにはあった。
寸評
僕はこの映画を劇場で見ていない。
半世紀以上も前にテレビ放映されたものを見たはずだ。
しかも民放の番組だったと思う。
2時間半に及ぶ作品なので、もしかするとカットされたシーンがあったのかもしれないが、それでも民放がこの内容の作品を放送する余裕と体力があったのだと思う。
再見していないのでほとんどのシーンは記憶にない。
ストラウドが入っている留置場が鳥かごで一杯に埋まっていくシーンは何故か記憶にある。
これが実話だということで、アメリカって随分と開けた国なのだなあと当時は感心したと思う。
看守からイジワルされたり、獄中結婚したリ、大統領の指示があったりと一応のドラマはある。
前半のどうしようもない男が、「君は感謝する気持ちがない」と言われて目覚め、後半に変身した姿が描かれていく。
監獄物と違ってストラウドは全く脱獄する意思を持っていない。
囚人仲間がメスの為に鳴かない小鳥をストラウドに返すが、メスなので卵を産むことが分かると再び譲り受けるというおかしなシーンもあったと思う。
僕はこの映画を見てからも長い間、バートラン・カスターだと思っていた。
バート・ランカスターだと知ったのは随分後の事だった。
こういう良心的な作品はまた見てみたい。










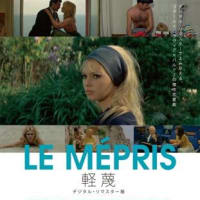
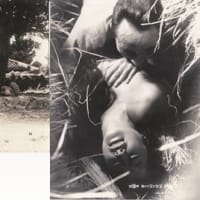

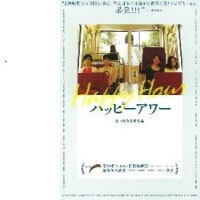
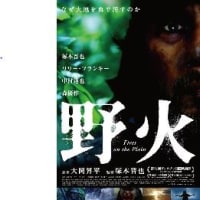
このバート・ランカスターの主人公は、若い頃、殺人犯として入獄するが、ちょっとした気に入らないことでカッとなり、獄中で看守を殺して終身刑になる。
この二度の殺人に、この男が全く罪の意識を示さないことが、まず第一にアメリカ映画的。
彼はただ、この事態を個人の正当な復讐に、国家権力が更に報復をして返しているくらいにしか考えていないように見える。
日本映画で刑務所ものと言えば、そんな経過で囚人になった者が、いかにして自分の罪を自覚するに至るか、というところに狙いが合わされることになるものだが、この主人公は、あくまでも、国家に対立する者としての自分という感じ方を捨てようとはしない。
彼は独房に迷い込んだ小鳥を慰めに育てたのをきっかけに、小鳥の飼育と研究に夢中になる。
そして、小鳥の病気を研究して、全くの独学で鳥の病理学の権威になる。
しかし、囚人が自分の生き方、自分の生き甲斐を独力で探求していくことを、刑務所当局は喜ばない。
規則通りの刑務所生活を彼に強制する。
すると、彼はこれまた、独学の法律知識によって当局をへこまし、マスコミを動員して当局に対抗する。
メイフラワー号以来、あるいは西部開拓時代以来の、"絶対自由人"、"絶対独立人"の伝説がこんなところに生きているような気がする。
だからといって、彼は終始ひねくれ者だったわけではなく、二つの重要な事件を契機にして、彼は人間的にも成長していくことになる。
一つは、いつも彼の方から横柄に呼びつけていた看守に、なぜおまえは人間同士の謙虚な呼びかけの言葉を使わないのかと説教されたことであり、もう一つは自分を溺愛していた母親のエゴイズムを知った時。
アメリカ精神のバック・ボーンである"絶対自由人の伝統"を尊重しながら、しかも、それをどうしたら今日の組織化された社会に適応させていけるのかという、今日のアメリカ精神の基本的な問題点の一つが、ここにくっきりと浮き彫りにされていると思う。
そういう意味では、もう一歩のところで、"高度な思想劇"にもなり得るほどの秀作だと思う。