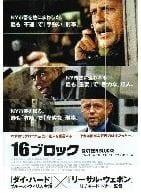「RRR」 2022年 インド
監督 S・S・ラージャマウリ
出演 N・T・ラーマ・ラオ・Jr ラーム・チャラン
アジャイ・デーヴガン アーリヤー・バット
レイ・スティーヴンソン アリソン・ドゥーディ
ストーリー
1920年、英国統治時代の暴君スコット・バクストンと妻キャサリンは、ゴンド族の少女マッリの歌の才能に惚れて彼女を強引に誘拐してしまったので、この行為に激怒した住民たちは暴動を起こした。
大使館を守っていた警察官のラーマが暴徒たちを鎮圧しようと奮闘する。
村の守護者ビームは、巨大な虎をも倒す屈強な男だった。
マッリを助けるために乗り込んでいったビームは、そこで列車事故に遭遇し偶然ラーマと合流した。
そこで共に力を合わせ事故に巻き込まれた子供を助け出すことに成功した。
この事がきっかけでラーマとビームは仲良くなった。
二人が友情を育んでいる間にも、ビームはマッリを誘拐したスコットの屋敷に侵入する方法を探していたが、厳重な警備のためその方法を見つけることが出来なかった。
ある日、スコットの姪であるジェシーにビームが一目惚れしたことをきっかけに、ラーマがビームとジェシーを近づける作戦を決行し、近づくことの機会を得たビームはジェシーからパーティに誘われることになった。
ラーマとのダンス対決を制したビームは、改めてジェシーからスコットの屋敷に招待されることとなり、お茶をすることになった。
そこで監禁されているマッリを発見したビームは、柵の向こうで泣きながら助けを乞うマリをなだめ、必ず彼女を助け出すことを誓って去った。
その頃、ラーマはビームの叔父を捕まえ、拷問をしてビームの正体と目的を知ることとなった。
戸惑いながらもラーマはビームを追った。
スコットの屋敷でパーティが行われていた時、一台のトラックで屋敷に突っ込み混乱を起こしてマッリを助けようとしたビームの前に、軍服をまとったラーマが現れた。
うろたえるビームにラーマは容赦なく手錠をかけようとし、激しい肉弾戦となった。
寸評
単純に面白い!
インド映画ここにありと言った感じで、3時間に及ぶ上映時間がまったく気にならない。
歌と踊りが必ずあるというのがインド映画だが、本作でも十分すぎるくらいそのシーンが用意されている。
重力無視の大アクションが見どころとなっているが、ストーリーに盛り込まれたテーマがしっかりしていることが本作にたぐいまれなエンタメ性を生み出している。
一つはラーマとビームの隠れた友情物語である。
今一つはイギリスの植民地であったインドの独立運動を描いている点である。
インドの独立にはガンジーによる無抵抗主義が有名だが、実際にはこの様な抵抗もあったのではないかと思う。
ラーマとビームの出会いは、列車事故によって川で孤立し生命の危険にさらされている子供を協力して助け出すことによって成し遂げられる。
宗教や地域を超えて子供を救出する姿は人類愛そのもので、ここで生まれた友情はインド人として共通の精神を有していることの証明でもある。
見終ってみると、そのことはテーマと物語の終結への大きな伏線となっていたのだと悟ることが出来る。
冒頭でインド総督スコット・バクストンの一行がゴンド族の村を訪れ、そこで歌の才能を持つ少女マッリに出会い、マッリの才能を気に入ったキャサリン総督夫人は強引に彼女を総督府のあるデリーに連れ去ってしまう。
投げつけたコインは歌への褒美ではなく、マッリを買い取る金だったのだ。
キャサリン総督夫人はひどい女性だが、彼女の冷酷さは最後に究極的に示されることになる。
ニザーム藩王国の特使アヴァダニがマッリの返還交渉に望み、「マッリを引き渡さなければ、彼らの守護者がイギリス人に災いをもたらす」と忠告する。
それはこれから起きる事の予言でもあるのだが、ビームが守護神の化身であることを暗示している。
僕はインドの伝説に詳しくはないが、おそらくインドの人たちは守護神の化身は誰なのかをもっと明確に予想できたのではないかと思う。
ゴンド族のビームが話す言葉とジェニーが話す英語がかみ合わない小ネタには笑ってしまう。
デリー近郊の警察署では、逮捕した独立運動家の釈放を求めるデモ隊が押しかけていて、そこでラーマは警官であることがわかるが、デモ隊鎮圧に功績のあったラーマをイギリス人署長は功績を認めず昇進させない。
ラーマが悔しがることで、イギリス人のインド人への差別が手短に語られている。
後半では物語が終局に向かって一気に走り出す。
マッリの救出にビームが動き出し、ラーマの目的も明らかになってくる。
何でもありの大アクションが繰り広げられるが、そのアイデアは満載であっけにとられながらも堪能できる。
そしてついにラーマとビームはイギリス軍に立ち向かっていく。
武器は銃でもナイフでもなく肩車と言うのも奇想天外だが、ラーマのライフル扱いはジョン・ウェインも真っ青だ。
ラーマ―は武器を手に入れ故郷に帰りシータと再会する。
ラーマ王子とシータ姫の話はインドにあるようで、それもインドの人たちは承知のことだったのだろう。
まったくの架空物語ではなく、伝説や歴史が組み込まれているようで、やはり文化や歴史は他国の人にはまだまだ理解が及ばないことが多いのだと思う。
でも誰が見ても楽しくなってしまうのがインド映画の素晴らしいところだ。