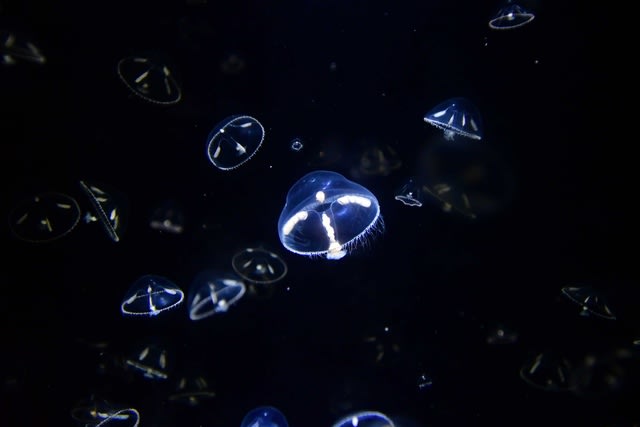オオセッカ 7月12日仏沼
7月12日仏沼〜岩手/宮城:(続き)ソングフライトを繰り返すオオセッカですが、草原バックの方が多少とも色は綺麗だなと飛び出しや着地を狙うのですが、難しいです。

背中側からが模様が見えていいです。

鳴きながら‥‥


高度を下げて‥‥

降りて草原バックになるところが、やっと撮れました。

ソングポストに着陸寸前です。

狙っていたのが撮れたので、少し三角池辺りを散策しました。コジュリンの♀です。

コジュリン♂が近くに何気なくいました。



シシウドの近くでの囀りです。

トリミングするとシシウドが入りません。

ここにはホオアカもいます。花は少ないので花との絡みは難しいです。

唯一コヨシキリがシシウドと絡んでくれました。



コジュリンは結構いました。

以上で今回の東北遠征での鳥見は終了しました。青森/岩手/宮城県と南下しながら少し観光地に立ち寄ってみました。青森県を抜けて最初に岩手県の久慈市に立ち寄り琥珀博物館を訪ねてみました。虫の入った琥珀を眺めながら中生代に思いを馳せるのも楽しいもので、始祖鳥の血を吸った蚊がいたらなあ〜などと。つい虫の入った琥珀で手に入る値段のものがあったので買ってしまいました。さらに南下して岩手県の遠野市に立ち寄りました。遠野ふるさとの村の南部曲がり屋です。立派な造りに感心しました。

泊まりは花巻市、翌朝、宮沢賢治に多少は触れようと雨ニモ負ケズの詩碑が立つ羅須地人協会跡地から「下の畑」を眺めてみました。

途中の道のメトロノームのモニュメント。雰囲気あります。

更に南下して仙台に住む友人を誘って、初めて平泉中尊寺の金色堂を訪ねてみました。金色の輝きの見事な造形に圧倒されました。

更に南下し松島を遊覧。有名な仁王岩を眺めながら‥‥

ついついウミネコにカメラをむけてしまいます。やっぱり性でしょうか。

以上で東北遠征は終了です。長々とご覧いただき有り難う御座います。
次回は岡山に移住後の写真ですが、遠征には行けず、実家の前で撮ったコシアカツバメとツバメの飛翔写真をアップする予定です。