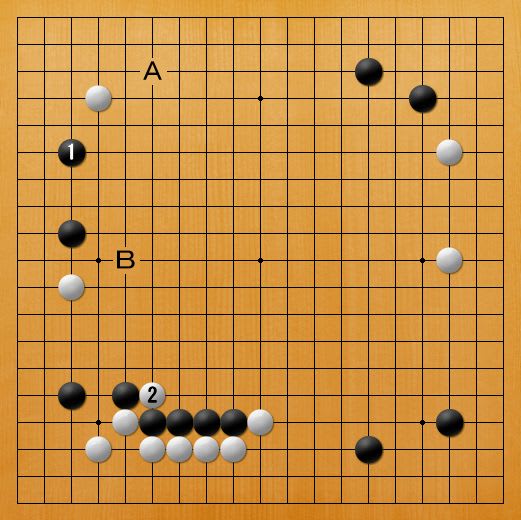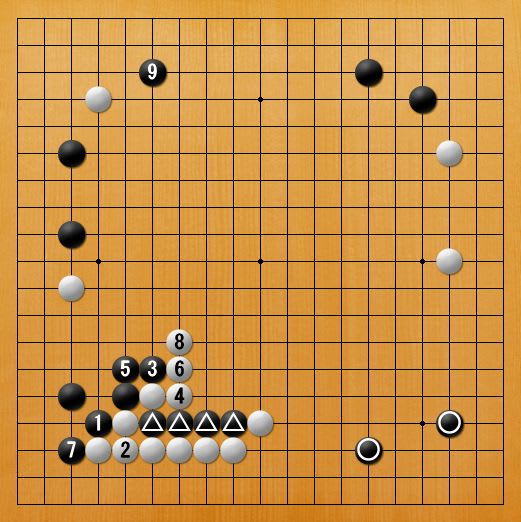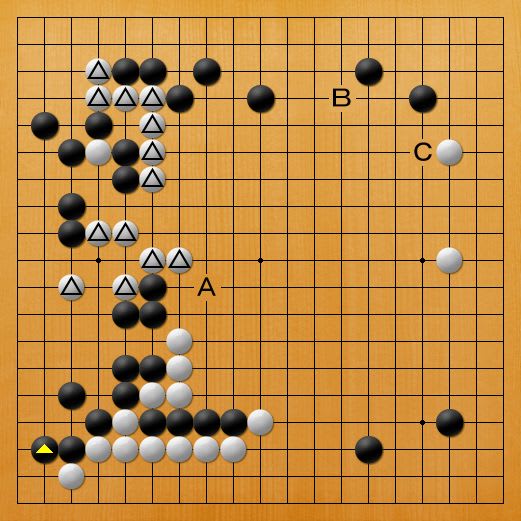皆様こんばんは。
本日は有楽町囲碁センターで指導碁を行いました。
お越し頂いた方々、ありがとうございました。
賀歳杯決勝は、中国の柯潔九段の優勝となりました。
井山裕太九段にとっては大きなチャンスでしたが、残念でした。
それでは振り返っていきましょう。
なお、この対局は幽玄の間にて、一力遼七段の解説付きで中継されました。
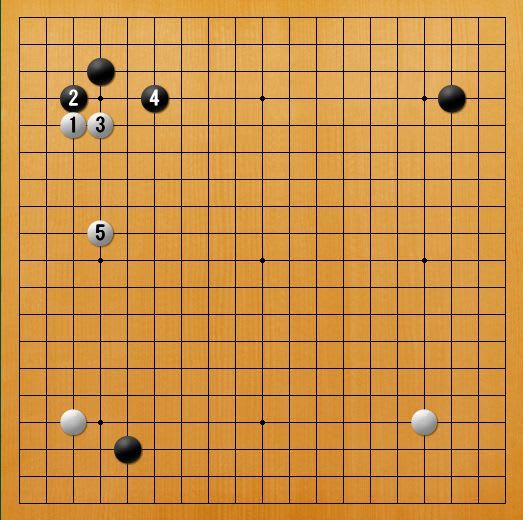
1図(実戦白6~白10)
井山九段の黒番です。
白1のカカリに対して、いきなり黒2のコスミツケとは意欲的です。
白1、3、5の形は所謂二立三析と呼ばれる好形で、黒が良くないとされています。
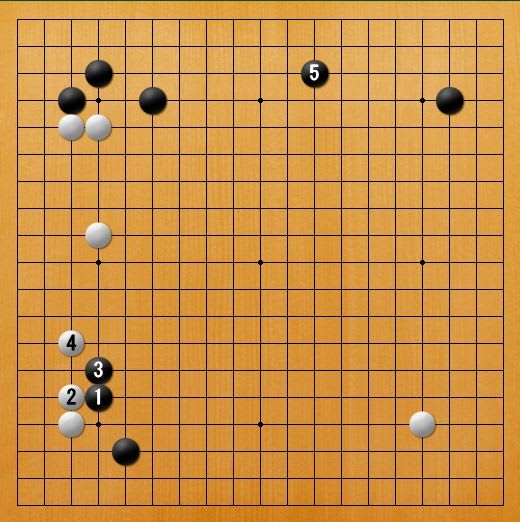
2図(実戦黒11~黒15)
しかし、直後の黒1のカケが予定の行動です。
白の形は良くても、左辺に石が偏り過ぎではないかと言っているのですね。
ちなみに前図黒1のコスミツケは、Masterも43局目で採用しています。
発想としては突飛なものではなく、過去に試みた人もいるでしょう。
しかし実際に見た事は殆ど無かったのですが、Masterや井山九段が打った事で、今後流行るかもしれませんね。
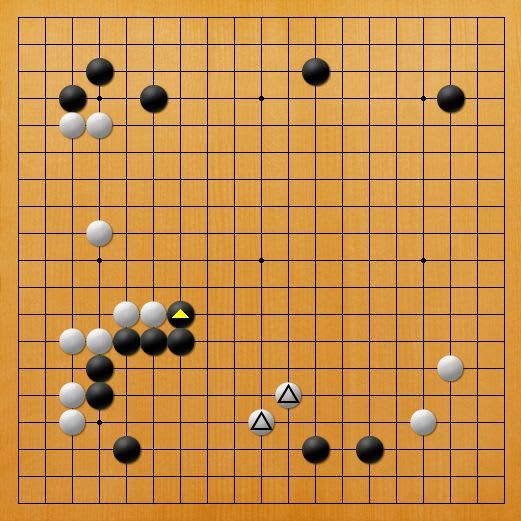
3図(実戦黒27)
その後黒△と曲げ、白△に狙いを付けた場面です。
白としては、右下への連絡を目指すような打ち方をするかと思っていましたが・・・。
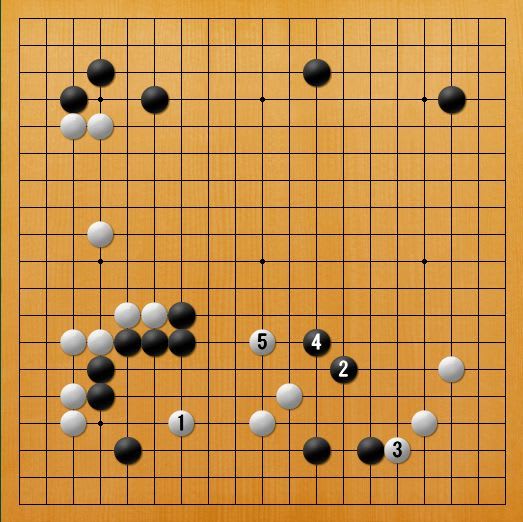
4図(実戦白28~白32)
実戦は白1と、左下の黒に迫って行きました。
さらに、黒2に対しては構わず白3!
黒4と打たれて苦しそうに見えるのですが、あえて攻めさせて打つ作戦でしょう。
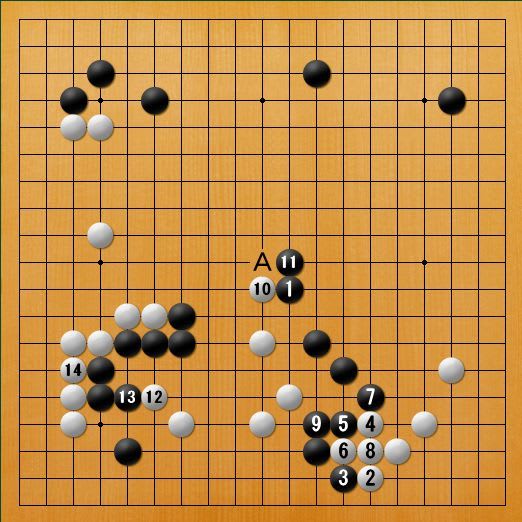
5図(実戦黒33~白46)
黒1と勢い良く攻めますが、白2から右下を頑張り、さらに白12、14で左下も頑張りました。
黒としてはAから、下辺の白を閉じ込めてしまいたい所ですが・・・・。
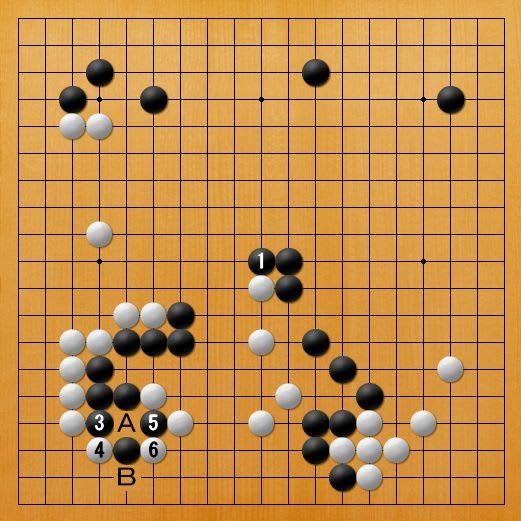
6図(変化図)
黒1には白2(Aの所)、4の手筋を用意しています。
白6の後、黒Aなら白Bで渡ってしまいますし、黒Bなら白Aと抜いてコウです。
どちらも黒がいけません。
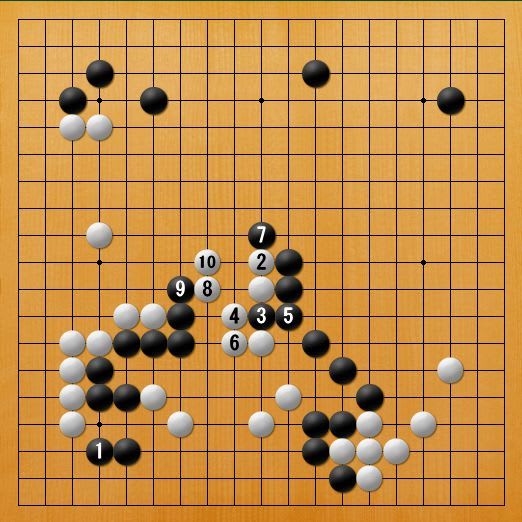
7図(実戦黒47~白56)
という訳で、黒1は仕方無かったのでしょうが、ここに守らされるようでは黒がつらかった気がします。
白10と頭を出されて、手に負えない感じです。
この後は難解な戦いに発展しましたが、黒が上手く行きませんでした。
井山九段の悪手が判然としませんが、いつの間にか柯潔九段のペースに嵌ってしまったようです。
第1戦で出鼻を挫かれながらも、態勢を立て直して2連勝とは、柯潔九段流石でしたね。
優勝できなかったのは残念でしたが、井山九段の強さは示せたのではないでしょうか。
ワールド碁チャンピオンシップや農心杯など、井山九段の活躍の場は他にも用意されています。
井山九段なら、必ず結果を出せると信じています。
本日は有楽町囲碁センターで指導碁を行いました。
お越し頂いた方々、ありがとうございました。
賀歳杯決勝は、中国の柯潔九段の優勝となりました。
井山裕太九段にとっては大きなチャンスでしたが、残念でした。
それでは振り返っていきましょう。
なお、この対局は幽玄の間にて、一力遼七段の解説付きで中継されました。
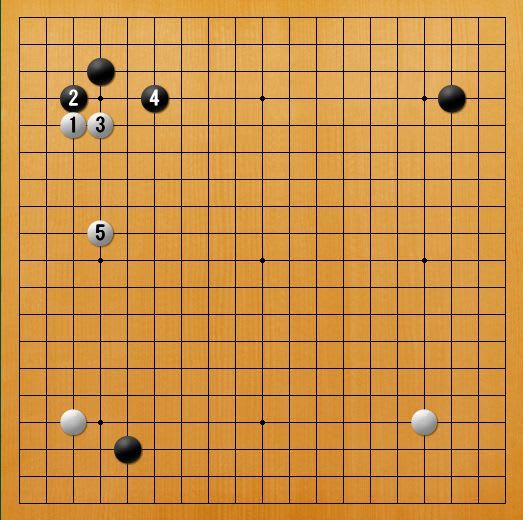
1図(実戦白6~白10)
井山九段の黒番です。
白1のカカリに対して、いきなり黒2のコスミツケとは意欲的です。
白1、3、5の形は所謂二立三析と呼ばれる好形で、黒が良くないとされています。
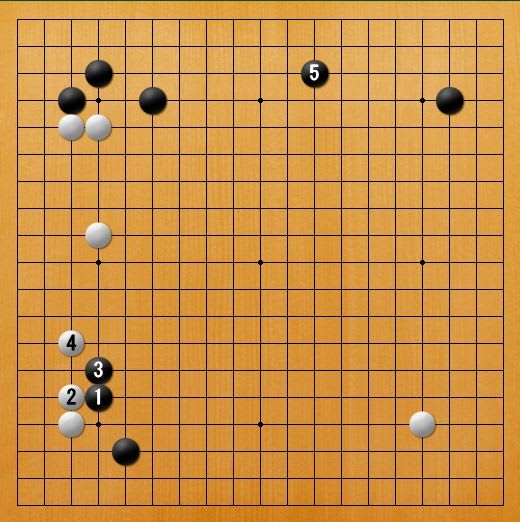
2図(実戦黒11~黒15)
しかし、直後の黒1のカケが予定の行動です。
白の形は良くても、左辺に石が偏り過ぎではないかと言っているのですね。
ちなみに前図黒1のコスミツケは、Masterも43局目で採用しています。
発想としては突飛なものではなく、過去に試みた人もいるでしょう。
しかし実際に見た事は殆ど無かったのですが、Masterや井山九段が打った事で、今後流行るかもしれませんね。
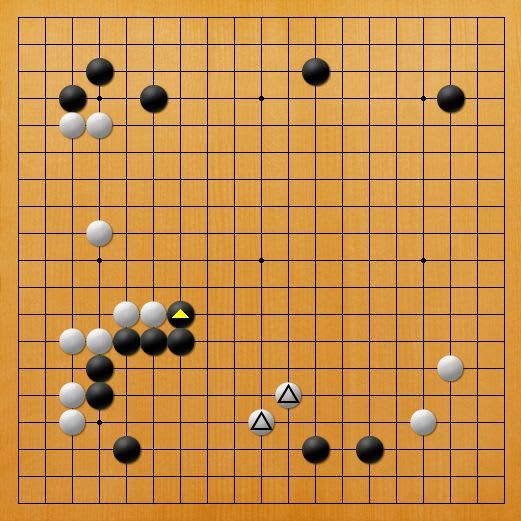
3図(実戦黒27)
その後黒△と曲げ、白△に狙いを付けた場面です。
白としては、右下への連絡を目指すような打ち方をするかと思っていましたが・・・。
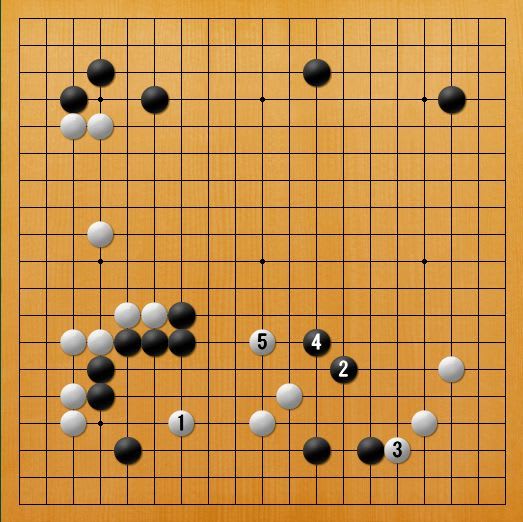
4図(実戦白28~白32)
実戦は白1と、左下の黒に迫って行きました。
さらに、黒2に対しては構わず白3!
黒4と打たれて苦しそうに見えるのですが、あえて攻めさせて打つ作戦でしょう。
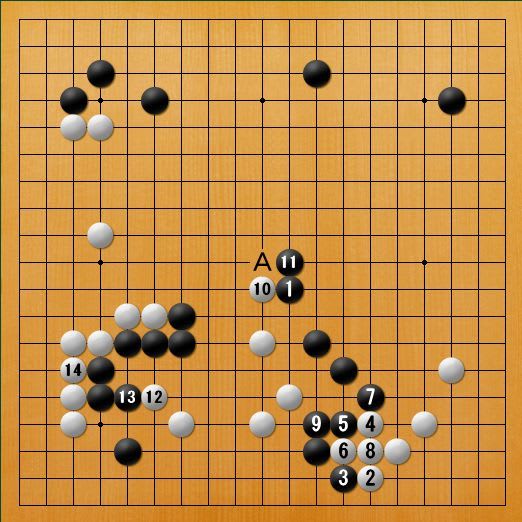
5図(実戦黒33~白46)
黒1と勢い良く攻めますが、白2から右下を頑張り、さらに白12、14で左下も頑張りました。
黒としてはAから、下辺の白を閉じ込めてしまいたい所ですが・・・・。
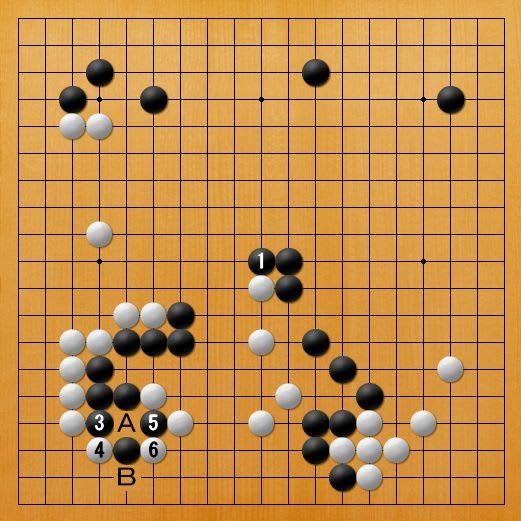
6図(変化図)
黒1には白2(Aの所)、4の手筋を用意しています。
白6の後、黒Aなら白Bで渡ってしまいますし、黒Bなら白Aと抜いてコウです。
どちらも黒がいけません。
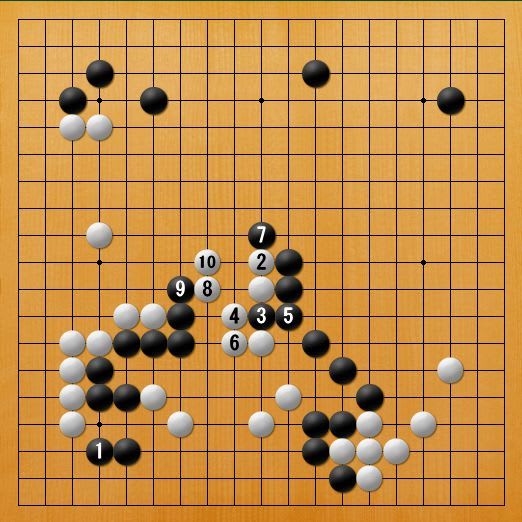
7図(実戦黒47~白56)
という訳で、黒1は仕方無かったのでしょうが、ここに守らされるようでは黒がつらかった気がします。
白10と頭を出されて、手に負えない感じです。
この後は難解な戦いに発展しましたが、黒が上手く行きませんでした。
井山九段の悪手が判然としませんが、いつの間にか柯潔九段のペースに嵌ってしまったようです。
第1戦で出鼻を挫かれながらも、態勢を立て直して2連勝とは、柯潔九段流石でしたね。
優勝できなかったのは残念でしたが、井山九段の強さは示せたのではないでしょうか。
ワールド碁チャンピオンシップや農心杯など、井山九段の活躍の場は他にも用意されています。
井山九段なら、必ず結果を出せると信じています。