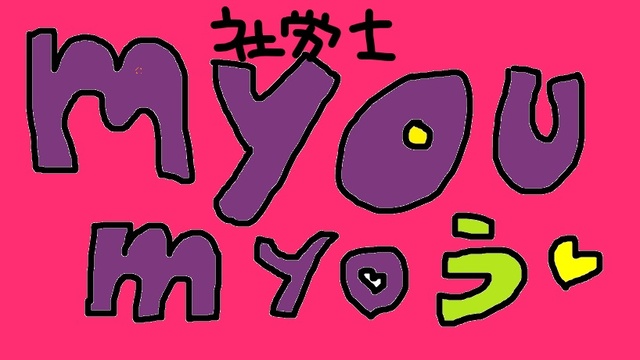月刊社労士には童門冬二の、歴史から学ぶビジネスのあり方的な連載がある。
説教くさいし、孫氏や孔子など偉人をたとえに出す話は好きではないし、日本の武将や商人の話はなおのこと、好きではない。なので読み飛ばしていた。
しかし、1月号の連載のタイトルは「落ちた鐘にも意思がある」ではないか。
人の心は不得意であるが、私は物は好きである。
とはいえ、人相手の仕事をしている社労士向けだ、たいして面白くもないだろうと期待もせずに読み始めた。
江戸時代、河村瑞賢という大工が増上寺の落ちた釣鐘を直す仕事をバカ安で落札したのである。
瑞賢は信心深い性格であり、それが万物に及んでいる。
万物にも生命があり、意思がある、と思っている。
だから、落ちた鐘にも落ちようという意思があった、ととらえる。
自力では戻れないので人の力を頼らざるを得ない。工事が必要となる。
しかし、鐘はその工事中、極力痛い思いをしたくない、と希う。
いろいろぶつけられ、鐘の身になればあざだらけだ、と瑞賢は思う。
となると、鐘はどう考えるだろう?
モノは言えないが痛くないように扱ってほしいはずだ。
吊るしたのでは鐘の不安は消えない。鐘を安心させるためには置いてやらないといけない。
こう考えて、米俵を順々に置いていく。時間をかけるのである。
なぜか?
寺の僧にこの問題に対する意識を改めてもらうためである。
瑞賢はこう思ったのである。
朝夕鐘をつく低位の僧にはある時期から鐘の落ちるのを予知したに違いない。
上位の僧に告げても、まだ大丈夫だと取り合ってもらえない。
鐘の身になってくださいと言ったところでバカにされるだけである。
鐘だけは低位の僧の気持ちがわかる。
そして、とうとうある日、鐘は耐久力の限界に達し、踏ん張るのをやめて落下する。
瑞賢はこんなことを考える人間であるから、建築現場でも心が痛む。
石や材木も生きている。土や樹木と同じだ。いのちあるものと思えば、工事現場の空気ももっとお互いにうやさしくなれる。
このように思うのである。
童門冬二はなぜ、このような「モノ」の話を、人事労務を専門とする社労士に聞かせているのだろう?
つづきが待ち遠しい。
説教くさいし、孫氏や孔子など偉人をたとえに出す話は好きではないし、日本の武将や商人の話はなおのこと、好きではない。なので読み飛ばしていた。
しかし、1月号の連載のタイトルは「落ちた鐘にも意思がある」ではないか。
人の心は不得意であるが、私は物は好きである。
とはいえ、人相手の仕事をしている社労士向けだ、たいして面白くもないだろうと期待もせずに読み始めた。
江戸時代、河村瑞賢という大工が増上寺の落ちた釣鐘を直す仕事をバカ安で落札したのである。
瑞賢は信心深い性格であり、それが万物に及んでいる。
万物にも生命があり、意思がある、と思っている。
だから、落ちた鐘にも落ちようという意思があった、ととらえる。
自力では戻れないので人の力を頼らざるを得ない。工事が必要となる。
しかし、鐘はその工事中、極力痛い思いをしたくない、と希う。
いろいろぶつけられ、鐘の身になればあざだらけだ、と瑞賢は思う。
となると、鐘はどう考えるだろう?
モノは言えないが痛くないように扱ってほしいはずだ。
吊るしたのでは鐘の不安は消えない。鐘を安心させるためには置いてやらないといけない。
こう考えて、米俵を順々に置いていく。時間をかけるのである。
なぜか?
寺の僧にこの問題に対する意識を改めてもらうためである。
瑞賢はこう思ったのである。
朝夕鐘をつく低位の僧にはある時期から鐘の落ちるのを予知したに違いない。
上位の僧に告げても、まだ大丈夫だと取り合ってもらえない。
鐘の身になってくださいと言ったところでバカにされるだけである。
鐘だけは低位の僧の気持ちがわかる。
そして、とうとうある日、鐘は耐久力の限界に達し、踏ん張るのをやめて落下する。
瑞賢はこんなことを考える人間であるから、建築現場でも心が痛む。
石や材木も生きている。土や樹木と同じだ。いのちあるものと思えば、工事現場の空気ももっとお互いにうやさしくなれる。
このように思うのである。
童門冬二はなぜ、このような「モノ」の話を、人事労務を専門とする社労士に聞かせているのだろう?
つづきが待ち遠しい。