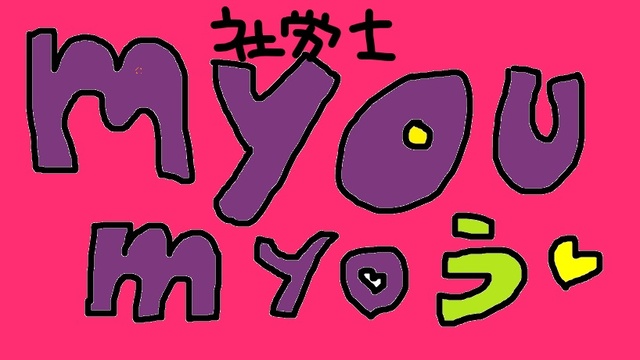長いあいだ専業主婦だった40~50代の女性が、仕事に就くのは至難の業らしい。ただ単に40~50代ってだけで難しいかんじがするが…なにも正規雇用のはなしをしてるんじゃないですよ。パートやアルバイトでもですよ!
『主婦が、仕事を、探すということ。~高学歴40代妻たち、涙と笑いの再就職戦線~』
著者:ウイメンズ望月恭子と就活中の主婦たち
を、真面目な気持ちで真摯な態度で読もうと思ったのに、できなかったです!
桃子さんとりんこさんという2人の50代の女性の就活奮闘記なのですが、読んでいてそのあまりのノー天気ぶりに悶絶しました。2人とも就職したのはバブル全盛期、完全腰掛け気分でOLをやり(OLって今じゃ死語ですが)そこそこの男をゲットし結婚。出産・育児を専門としていたが、子供の教育費の高騰にだんなの給料が追いつかず、「働いてくれ」と懇願され、いざパート探しへ、となるのですが…
事務経験あり得意です、と言いながらワープロしか使ったことがない、「タッチパネル」のコピー機が使えない…
接客なら自信あります、といいつつ販売は立ちっぱなしだからといって嫌がる…
コピー・お茶くみ(これ差別用語になったんでしたっけ?)の派遣で時給1800円という経験があるので、時給700~800円の仕事の存在をスムーズに理解できない…
こどもの影響なのか、言葉遣いが異常にキタナイ…
社会常識の欠如が著しい…
おばさんには、介護・サービスの仕事しかないとひがむ。今は若い子にもそんな仕事しかないの!!
と悪いところを並べ立てたが、いいところだってある。
信じられないくらい強気。今日明日食べるものに困ってるわけじゃないので、当然かもしれないが
若い人はそうじゃない。その仕事じゃなくたって、生きる死ぬに関係ないはずなのに、就活で失敗したからって死んでみたり、オバハンには理解不能な心理・行動だ。
彼女たちはバブルで甘やかされた人たちかもしれないが、だんなの月給が100万じゃないから自分が働きにでなきゃいけないといいつつ、自分が100万男に釣り合う女ではないことをわかっている。
物心ついたときから不況で、そこそこなんでも揃っていてぬるい幸せに浸かっている今の若い人たちとの違いは、ガッツかもしれない…
書類選考で落ちまくり、やっと面接までこぎつけても、和やかに談笑したはずなのに、やはり落ちまくる。
2年ほど就活した後、ようやく自分が好きな縫い物の仕事である「縫製業」をみつける。きちんと習ったことはないが、趣味でミシンを使い続けていて得意だったそうだ。あっさり決まったのは最低賃金のため、他に応募者がいなかったかららしい。そうだろうと思う。彼女が就職した会社も、当然ながら中国人研修生がほとんどであった。研修生といったって、元々中国でミシンを使っていたプロである。最賃法も適用にならないほどの恐ろしく低い賃金で働く中国人「研修生」の腕前は相当なものである。もうひとり日本人が採用されたが、その人は素人だった。なぜって、最低賃金しか払う気がないのでプロだと困るからだ。会社は「経験者はかえってやりにくい。変なプライドがあってこっちの言うことをきかない」という理由をあげていたが、そういいつつ、うまくできないのでイラつき、「休憩時間も練習しない」からという理由でその人は退職に追い込まれた。
いまどきミシンがうまく使えるからって、それが何?縫製業なんて斜陽産業じゃないの。時代のニーズに合わない技術なんてなんの価値もないじゃない。そう思う人は多いだろうね。
私はそう思わないけど。本当に必要がないなら、なんで中国人にやらせるわけ?高い技術を利用しといて、その仕事が最低賃金やそれ以下なら、それは搾取・泥棒でしょ。価格は需要と供給で決まるだの、不要なものは市場で淘汰されるだの、経済の教科書に書かれているのか、インチキコンサルタントが吹聴しているのか知らないけど、それで自分が買いたたかれたり、淘汰されたりしてもそれは「仕方がない」ということなんでしょうか?経営者の方はよく権利ばかり主張する云々と言われますが、権利ばかり主張する労働者に振り回されている一方で、何も主張しない労働者に、自分たちの無能から発生した損失まで押し付けているように見えます。雇用されている人は、自分がそれほど価値がないのか、経営者が言うほど能力に欠ける人間なのか、その経営者(や上司)の価値をみながら、冷静に考えてみるべきだと思います。
ノー天気な、バブルの負の遺産のような50代女性の就活奮闘記でしたが、それゆえに日本の仕事の裏事情がはっきりと映し出されていて面白かったです。こんな彼女たちは、人を完全に「モノ・コスト」としか扱わないファーストフード業界には見向きもしません。