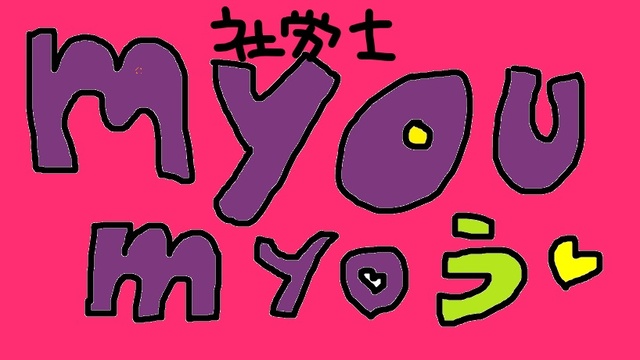新聞でかっこいい社労士さんをみつけた。
行政書士試験に落ちて凹んでいたところ、社労士・行政書士のダブルライセンスを生かして仕事をしている社労士さんの記事を読んだ。
行政書士で食えるか?という問いは古典的で、それに対してはいろんな人がいろんなことを言っている。
例えば、宅建の先生をしている人は、行政書士資格があることで、不動産の仕事が格段に信頼されるようになったとか。
使い方、活かし方の問題であって、その資格で食えるか食えないかという問いは無意味だ、職種じゃないんだからとのこと。
私が行政書士試験を受けようと思ったのは、そもそも(そんな長い話聞きたくないわ!!そんなとこから語られても困るわ!と言う方は飛ばしてください!!)社労士の研修会に講師としてくる弁護士の先生の話がどうにもこうにもさっぱりわからず、???のオンパレードで、泣く泣く法学部の通信教育を始めた。その後、法学部を卒業した人も、弁護士の話はさっぱり分かっていないことが判明。日本の大学とはそういうもの。そんな大学でも、もたもた5~6年かかって、ようやく卒業できそうな気配。法学を学んだからには学びの集大成として行政書士試験を受よう!と決心したからです。法学部に入っているし、受かるやろ~と一昨年受けてみたら眠くなるくらいわからなくてもちろん落ちた。今年、気持ちを入れ替えてがんばったが、がんばり及ばず…来年こそは!
で、ダブルライセンスの社労士さんですが、元は自動車整備士として勤務し、営業部長などを経て、50代半ばにさしかかったころ、好きであり、得であり、社会のためになる仕事として社労士を志したということです。
そのまま定年退職まで勤め上げるという選択肢もあったが、早期退職して背水の陣を敷いていどみ合格。57歳で開業し、その後大学の法学部通信教育を卒業し、行政書士資格も取得。
助成金の申請のときに、締め切り間近のタイミングで、事前確認という作業には行政書士の資格が生かされたとのこと。
人それぞれ、資格の活かし方もそれぞれ。
小山さんの光る頭がまぶしいです。
小山さんは実は大学の法学部通信教育は途中で挫折していました。
そのことがずっと気がかりだったようです。
最初の入学から実に37年。今年3月に晴れて卒業されたそうです。
おめでとうございます。
私も同じ大学の同じ法学部で学んでいます。
来年度こそ卒業できそうです!
先輩のがんばりは励みになります!
行政書士試験に落ちて凹んでいたところ、社労士・行政書士のダブルライセンスを生かして仕事をしている社労士さんの記事を読んだ。
行政書士で食えるか?という問いは古典的で、それに対してはいろんな人がいろんなことを言っている。
例えば、宅建の先生をしている人は、行政書士資格があることで、不動産の仕事が格段に信頼されるようになったとか。
使い方、活かし方の問題であって、その資格で食えるか食えないかという問いは無意味だ、職種じゃないんだからとのこと。
私が行政書士試験を受けようと思ったのは、そもそも(そんな長い話聞きたくないわ!!そんなとこから語られても困るわ!と言う方は飛ばしてください!!)社労士の研修会に講師としてくる弁護士の先生の話がどうにもこうにもさっぱりわからず、???のオンパレードで、泣く泣く法学部の通信教育を始めた。その後、法学部を卒業した人も、弁護士の話はさっぱり分かっていないことが判明。日本の大学とはそういうもの。そんな大学でも、もたもた5~6年かかって、ようやく卒業できそうな気配。法学を学んだからには学びの集大成として行政書士試験を受よう!と決心したからです。法学部に入っているし、受かるやろ~と一昨年受けてみたら眠くなるくらいわからなくてもちろん落ちた。今年、気持ちを入れ替えてがんばったが、がんばり及ばず…来年こそは!
で、ダブルライセンスの社労士さんですが、元は自動車整備士として勤務し、営業部長などを経て、50代半ばにさしかかったころ、好きであり、得であり、社会のためになる仕事として社労士を志したということです。
そのまま定年退職まで勤め上げるという選択肢もあったが、早期退職して背水の陣を敷いていどみ合格。57歳で開業し、その後大学の法学部通信教育を卒業し、行政書士資格も取得。
助成金の申請のときに、締め切り間近のタイミングで、事前確認という作業には行政書士の資格が生かされたとのこと。
人それぞれ、資格の活かし方もそれぞれ。
小山さんの光る頭がまぶしいです。
小山さんは実は大学の法学部通信教育は途中で挫折していました。
そのことがずっと気がかりだったようです。
最初の入学から実に37年。今年3月に晴れて卒業されたそうです。
おめでとうございます。
私も同じ大学の同じ法学部で学んでいます。
来年度こそ卒業できそうです!
先輩のがんばりは励みになります!