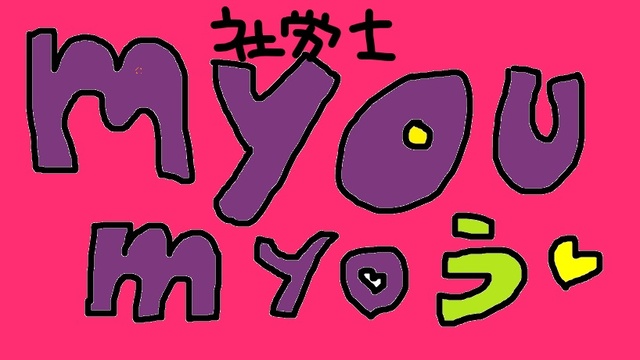お正月は特に予定もないので買うものも少ない。込み合った食料品店に長居することもなく並んでいる客を尻目に空いたレジで早々と会計を済ませて帰ってきた。年末、特に大晦日は込み合うものだが、一夜明けた元旦はどこも店が閉まっており、街は閑散として買い物にも一苦労…というのはいったいいつ頃のことだっただろうか。
近所にスーパーセンターができたのは今から20年ほど前である。小売店の元旦営業が始まった頃である。その店も元旦営業をしていた。たしか年中無休だった。私は中に入っているマクドナルドでアルバイトをしていたのだが、元旦はシフトが入っておらず2日からの仕事であった。シフトインした途端、元旦がどれほど忙しかったか、どれだけ人が押し寄せてきたかを他のクルーから興奮気味に聞かされた。社員が「元旦からハンバーガー食うかよ!!」と嘆いていたほどだ。なんか牧歌的なかんじさえしないだろうか。
図書館や郵便局、病院、低料金で過ごせる町の入浴施設など必要なところは28日あたりから早々と店じまいしているのとは対照的に、商業施設は今や年末年始の営業どころかほとんど年中無休である。
何年か前の新聞の切り抜きに(たぶん日経流通新聞)元旦営業の是非について書かれているものがあった。駅前に位置するイトーヨーカドーが元旦賑わうのは、初詣帰りの影響があるのでわかるが、車立地のイオンモールがここまで賑わっているのは、今後の元旦営業を考えるうえで看過できない。隅々まで客であふれ、前進できないほどであった。前身の商業施設の頃から来ているが、これまでに見たことがないほどの客数だった、と驚きを隠しきれない様子なのは、日本ホームセンター研究所所長である。(こんなんあるんや…)
「元旦に買わなければならないものがあるのか?」だけを議論していたホームセンター業界の人にとっては衝撃だったようだ。
自宅にいてもつまらない→大型店がやっているなら行ってみよう→特売もしてるなら買っておこう、という意識と行動だったのではないかと所長は推測している。
また、「多くの消費者にとって自宅がそれほどくつろげる場所ではないこと」「正月は低俗で魅力を欠くテレビ番組が目立つこと」も背景として影響しているのではと分析している。
時間を消費する場所として大型商業施設が機能している姿である。
業界の生き残りをかけているだけになかなか鋭い分析である。
元旦に限らず、大型商業施設の客を見て思うのは、彼らにとって、そこは時間を消費する場所であるということだ。元ジャスコやサティだったところは別だが、イオンモールとして新しくできたところは、効率よく買い物を済ませたい客にとっては避けたい場所だ。時間を費やしたい人間にとってはありがたい場所だが、そうではない人間にとっては魔の場所である。
巨大なフードコーナーは居場所を提供してはいるが、決してくつろげる場所ではない。にもかかわらず多くの人で賑わっている。年末年始、家族連れで賑わうフードコーナーで一人で食事をとっている人はなんとなくきまりが悪そうに見えるが、家族で廉価な(とはいえ、家族で食べれば数千円の出費である)うどんやラーメンをすすっている光景も他人事ながら物寂しいというか物哀しいというか…
マイホームという名の箱に居場所のない人に居場所を提供する大型商業施設は、社会学者・古市憲寿のいう日本的福祉なのだろうか?
ちなみに大型SCで1円もお金を使わずに水や電気、場所を消費している我が家にとってはありがたい存在です。