
大正時代から大阪は、日本のマンチェスター、リヴァプールだとか、世界一の煙都等と言われた。
昭和のはじめには、労働争議に絡んで、煙突の上に長い間居座った「煙突男」もいた。この形態は川崎で始まったという。また千住には「お化け煙突」なるものも話題となった。見る方角によって本数が変わるというあたり前の話である。後年この煙突の撤去の際も、それに反対する煙突男が表れている。そして赤瀬川原平の「超芸術トマソン」には飯村昭彦の、よく見ると血の気が引くような煙突の写真(昭和58年)が載っている。これは孤立し取り残された煙突であって、今は姿を消し、辺りは[モダン」な六本木の賑わいと化している。
街中の煙突は住民の「公害」非難を恐れて昼間はひっそりとし、夜中に濃厚な煙を上げるようなこともあった。今や焼き場の煙突も、小津安二郎の映画のようには煙をあげないだろう。煙の世界一は中国に譲り影は薄くなった。
そこでまだ煙突が元気な頃の話しである。私の脳裏に残る光景がある。汚れた町の夜更け、太った親父が家をそっと抜け出す。町を密やかに歩き、太い煙突にとりつき上ってゆく。煙突の上部に達するや身を反らす。脱皮だ。見ると町にあるいくつのもの煙突のそれぞれに、親父が一人ずつとりつき脱皮している。念じて這い出したか、あやつられて現れたのか、何に羽化するのか。空には月が傾いていたもしれない。
工場の煙突としもた屋が混在していた50年ほど前、漫画サンデーの4コマ漫画であっただろうか。作者が草原タカオであったことは確かである。その貴重な切り抜きも今はない。これは京浜工業地帯のイメージに違いないと思った。今ネットで調べると、草原タカオはやはり、ある時期、川崎で勤めていた。
豈54号より(一部加筆)
昭和のはじめには、労働争議に絡んで、煙突の上に長い間居座った「煙突男」もいた。この形態は川崎で始まったという。また千住には「お化け煙突」なるものも話題となった。見る方角によって本数が変わるというあたり前の話である。後年この煙突の撤去の際も、それに反対する煙突男が表れている。そして赤瀬川原平の「超芸術トマソン」には飯村昭彦の、よく見ると血の気が引くような煙突の写真(昭和58年)が載っている。これは孤立し取り残された煙突であって、今は姿を消し、辺りは[モダン」な六本木の賑わいと化している。
街中の煙突は住民の「公害」非難を恐れて昼間はひっそりとし、夜中に濃厚な煙を上げるようなこともあった。今や焼き場の煙突も、小津安二郎の映画のようには煙をあげないだろう。煙の世界一は中国に譲り影は薄くなった。
そこでまだ煙突が元気な頃の話しである。私の脳裏に残る光景がある。汚れた町の夜更け、太った親父が家をそっと抜け出す。町を密やかに歩き、太い煙突にとりつき上ってゆく。煙突の上部に達するや身を反らす。脱皮だ。見ると町にあるいくつのもの煙突のそれぞれに、親父が一人ずつとりつき脱皮している。念じて這い出したか、あやつられて現れたのか、何に羽化するのか。空には月が傾いていたもしれない。
工場の煙突としもた屋が混在していた50年ほど前、漫画サンデーの4コマ漫画であっただろうか。作者が草原タカオであったことは確かである。その貴重な切り抜きも今はない。これは京浜工業地帯のイメージに違いないと思った。今ネットで調べると、草原タカオはやはり、ある時期、川崎で勤めていた。
豈54号より(一部加筆)














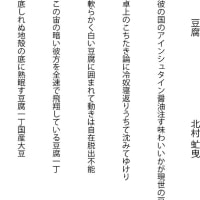
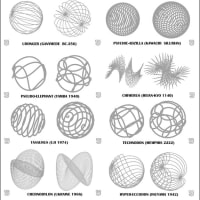












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます