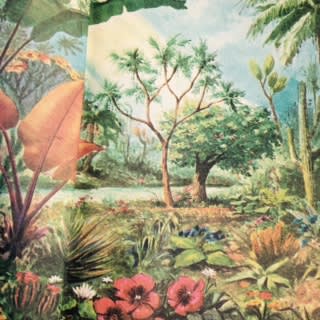
旧約聖書の人間観(その2)
神は土のちりで人を造りと記されているが、ヘブライ語では、土はadamaであり、人間はadamである。この二つの語は、非常によく似ている。〔土のちり〕という表現に、人間のはかなさがよく表されている。
そして、命の息を、その鼻に吹き入れられると、人は生きた者となった。そのことは、肉体というものが、土のちりから出来ていて、そして霊が吹き込まれると人間ができるということである。
そのことから、人間は霊と肉から成り立っていると考えて、霊肉二元説として理解されがちであるが、その霊肉二元説を、関根正雄は〔関根正雄著作集 第13巻〕の中で、はっきりと否定して、〔生きた者となったと訳した所は、生きたネフエシュとなったと書いてある。
ネフエシュという言葉は、ヘブライ語特有の意味を持っているわけで、決して肉体から離れない、具体的な人間を全体として言っている。ここに旧約の人間観の根本がある。霊は必ず肉と一緒になって、生きた人間として、全体として理解される〕と述べている。
アダムは、園を耕す仕事や家畜を世話したりする労働には耐えることができたが、精神的孤独には耐えられなかった。それで、神が〔彼のためにふさわしい助け手〕(〔創世記〕2章18節)を与えることが必要になった。その助け手は、動物の中には見出されなかった。〔それで人は、すべての家畜と、空の鳥と、野のすべての獣とに名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見つからなかった〕(〔創世記〕2章20節)
動物に名を与えたということは、人間が動物を支配することを意味している。したがって、支配と被支配の関係では、対等のパートナーは持てない。そこで、神はアダムを深く眠らせ、その脇腹からあばら骨を一つとり、そして、それを女に組み立てた。アダムが最初に女を見た時、〔これこそ、わたしの骨の骨、肉の肉〕(創世記2章23節)と言って喜んだ。
神は土のちりで人を造りと記されているが、ヘブライ語では、土はadamaであり、人間はadamである。この二つの語は、非常によく似ている。〔土のちり〕という表現に、人間のはかなさがよく表されている。
そして、命の息を、その鼻に吹き入れられると、人は生きた者となった。そのことは、肉体というものが、土のちりから出来ていて、そして霊が吹き込まれると人間ができるということである。
そのことから、人間は霊と肉から成り立っていると考えて、霊肉二元説として理解されがちであるが、その霊肉二元説を、関根正雄は〔関根正雄著作集 第13巻〕の中で、はっきりと否定して、〔生きた者となったと訳した所は、生きたネフエシュとなったと書いてある。
ネフエシュという言葉は、ヘブライ語特有の意味を持っているわけで、決して肉体から離れない、具体的な人間を全体として言っている。ここに旧約の人間観の根本がある。霊は必ず肉と一緒になって、生きた人間として、全体として理解される〕と述べている。
アダムは、園を耕す仕事や家畜を世話したりする労働には耐えることができたが、精神的孤独には耐えられなかった。それで、神が〔彼のためにふさわしい助け手〕(〔創世記〕2章18節)を与えることが必要になった。その助け手は、動物の中には見出されなかった。〔それで人は、すべての家畜と、空の鳥と、野のすべての獣とに名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見つからなかった〕(〔創世記〕2章20節)
動物に名を与えたということは、人間が動物を支配することを意味している。したがって、支配と被支配の関係では、対等のパートナーは持てない。そこで、神はアダムを深く眠らせ、その脇腹からあばら骨を一つとり、そして、それを女に組み立てた。アダムが最初に女を見た時、〔これこそ、わたしの骨の骨、肉の肉〕(創世記2章23節)と言って喜んだ。














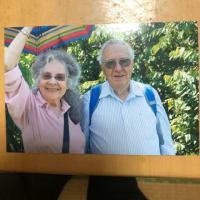





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます