
旧約聖書における人間観
旧約聖書には、次の3つの資料が編集に際して使用されている。ただし、その資料も一人の
作ではなく、それまでにあった詩、物語、伝説、律法などを、かなり長くかかって集め、更に書き加えられたものである。誰が書いたかは、まだわかっていない。
①ヤアウエ資料(J)
神を呼ぶのにヤアウエという語を用いるので、この名がある。その表現は素朴で神を人間のように語り動作する者として書いている。文体が文学的で生き生きとした描写に特徴がある。BC850頃のものとされている。
②エロヒーム資料(E)
神をエロヒームという語で表されるところからくる。BC750頃書かれていて、ヤアウエ資料よりもやや素朴さが失われ、神の擬人化も少なくなって、神の人間への語りかけは、夢、幻や天使を通して行われる。
③祭司資料(P)
成立はBC450頃と推定されているが、イスラエル民族捕囚の地バビロンで祭司グループによって書かれたものである。神の呼び名は、エロヒーム資料と同じだが、文体と内容は全く違っており、よく整っているが機械的形式的である。
神の権威と支配を強調し、年代、系図、年令、数字などを重んじるが、文学的潤いに乏しい。また、それまでの文書資料を整理、編集して、創世記の原典を成立させたのは、この祭司グループである。
創世記の1章、2章に、二つの創造物語がある。第1の物語は、祭司資料に属するもので、1章1節から2章4節の前半まで、第2の物語は、ヤアウエ資料に属するもので、2章4節の後半から2章24節までである。3章4章の全体も、ヤアウエ資料である。
二つの創造物語は、時代も作者も異なっているため、表現や文体が違っている。例えば祭司資料〔神は自分のかたちに人を創造された。すなわち、神のかたちに創造し、男と女とに創造された。〕(〔創世記1章27節〕)は、表現的には、形式的、抽象的で、そっけない感じがする。
一方、ヤアウエ資料〔主なる神は土のちりで人を造り、命の息をその鼻に吹き入れられた。そこで人は生きた者となった〕(〔創世記2章7節〕は、具体的でユーモアがある。
しかし、人間とは何であり、人間とはいかに生きるべきかということのついての根本的な考え方は共通している。
そこで述べられている〔神のかたち〕(ラテン語でImago Dei)について、原栄作氏は〔聖書と人間〕の中で(英訳聖書では、この“かたち”をimageと訳しているが、それは、人間を見れば神を思わずにいられないような、神との深い“関係”に人間が創造されていることを示している。
人間は、神のかたりかけをきき、それに“応答するもの”“responsibility”として”責任ある主体“として創造されていることを示している。このことが“人格”ということである。
さらに、人間は、“神のかたち”として“男と女とに創造されているので、人間同士も互いに”応答し合うもの“として人格的交わりが命じられている。と述べている。
また、神は人に対して言った。〔生めよ、ふえよ、地に満ちよ、地を従わせよ、また海の魚と、空の鳥と、地に満ちよ、地を従わせよ。また海の魚と、空の鳥と、地に動くすべての生き物とを治めよ〕(〔創世記〕1章28節)
すなわち、人間は、地上に存在しているあらゆる自然物や動物を支配する権利を神から与えられている。
旧約聖書には、次の3つの資料が編集に際して使用されている。ただし、その資料も一人の
作ではなく、それまでにあった詩、物語、伝説、律法などを、かなり長くかかって集め、更に書き加えられたものである。誰が書いたかは、まだわかっていない。
①ヤアウエ資料(J)
神を呼ぶのにヤアウエという語を用いるので、この名がある。その表現は素朴で神を人間のように語り動作する者として書いている。文体が文学的で生き生きとした描写に特徴がある。BC850頃のものとされている。
②エロヒーム資料(E)
神をエロヒームという語で表されるところからくる。BC750頃書かれていて、ヤアウエ資料よりもやや素朴さが失われ、神の擬人化も少なくなって、神の人間への語りかけは、夢、幻や天使を通して行われる。
③祭司資料(P)
成立はBC450頃と推定されているが、イスラエル民族捕囚の地バビロンで祭司グループによって書かれたものである。神の呼び名は、エロヒーム資料と同じだが、文体と内容は全く違っており、よく整っているが機械的形式的である。
神の権威と支配を強調し、年代、系図、年令、数字などを重んじるが、文学的潤いに乏しい。また、それまでの文書資料を整理、編集して、創世記の原典を成立させたのは、この祭司グループである。
創世記の1章、2章に、二つの創造物語がある。第1の物語は、祭司資料に属するもので、1章1節から2章4節の前半まで、第2の物語は、ヤアウエ資料に属するもので、2章4節の後半から2章24節までである。3章4章の全体も、ヤアウエ資料である。
二つの創造物語は、時代も作者も異なっているため、表現や文体が違っている。例えば祭司資料〔神は自分のかたちに人を創造された。すなわち、神のかたちに創造し、男と女とに創造された。〕(〔創世記1章27節〕)は、表現的には、形式的、抽象的で、そっけない感じがする。
一方、ヤアウエ資料〔主なる神は土のちりで人を造り、命の息をその鼻に吹き入れられた。そこで人は生きた者となった〕(〔創世記2章7節〕は、具体的でユーモアがある。
しかし、人間とは何であり、人間とはいかに生きるべきかということのついての根本的な考え方は共通している。
そこで述べられている〔神のかたち〕(ラテン語でImago Dei)について、原栄作氏は〔聖書と人間〕の中で(英訳聖書では、この“かたち”をimageと訳しているが、それは、人間を見れば神を思わずにいられないような、神との深い“関係”に人間が創造されていることを示している。
人間は、神のかたりかけをきき、それに“応答するもの”“responsibility”として”責任ある主体“として創造されていることを示している。このことが“人格”ということである。
さらに、人間は、“神のかたち”として“男と女とに創造されているので、人間同士も互いに”応答し合うもの“として人格的交わりが命じられている。と述べている。
また、神は人に対して言った。〔生めよ、ふえよ、地に満ちよ、地を従わせよ、また海の魚と、空の鳥と、地に満ちよ、地を従わせよ。また海の魚と、空の鳥と、地に動くすべての生き物とを治めよ〕(〔創世記〕1章28節)
すなわち、人間は、地上に存在しているあらゆる自然物や動物を支配する権利を神から与えられている。














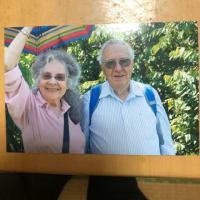





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます