五色の九谷
2012-08-22 | 本

史実や伝承をもとに九谷焼誕生までを描いた子供向けの本です。
九谷という場所は大聖寺川上流にあり、いまでこそ車で走れば舗装した道を30分ほどでたどり着きます。
しかしこの本によれば流刑人が金鉱探しをやっていたところだそうで、橋を掛けることが禁じられるなど、川原の中や崖を上がったり下りたり、とにかく道なき道を歩き1日or2日がかりの地だったようです。
九谷では、白釉をかけて本焼きするところまでで、出来た素地を大聖寺藩邸に運び、そこで絵付けを施して錦窯で仕上げたとしています。
ところで、九谷焼は有田産であるとする定説の証拠として、九谷の窯跡から色絵の着いた陶辺が出ていないというのがあるそうです。
しかし、絵を描くというのは繊細で集中力と根気と発想力が必要なわけですが、そう思うと流刑地である九谷で描かせられるわけもなく、素地を里に運んで、そこで描かせたということの方が真っ当で、九谷から陶辺が出ていないとしても、何ら問題にはならないと思います。
まぁ、九谷焼というブランドを興したことに価値があるので、どこで造ろうがかまわないのかもしれませんが・・・。




















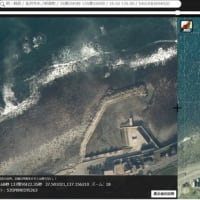






記憶が確かなら、絵付けは大聖寺でしたということを
聞きました。
流人の地九谷は、私の父の里です。
ということは、先祖はなにかやらかしたのかしらん。
九谷には、もともと村もあったそうなんで、必ずしも流人ばかりだったとは限らないと思います。
それにしても、謎が多いというのは、いろいろ想像をかきたてられて面白いものですね。