誰がグローバル・テロリストか?
ノーム・チョムスキー(翻訳:寺島隆吉)
2001年9月11日の惨劇のあと、「犠牲者」は、「テロリズムに対する戦争」を宣言し、実行犯と疑われる人々だけでなく、彼らがいるとされた国も、テロリストだとされた世界中の他の人々をも、標的としている。ブッシュ米大統領は、1985年に「テロリズムの邪悪なる鞭」を弾劾したロナルド・レーガンの口まねをしながら、「悪の実行者たちを世界から除去」し、「邪悪を温存しない」ことを誓約した。
レーガン政権は発足時にテロリズム、特に国家によって支えられた国際テロリズムに対する戦いを米国外交政策の核に据えると宣言していたのである[1]。レーガンによる第一次対テロ戦争の焦点となった地域は、中東と中米であった。後者において、米国は、ホンジュラスを主要な作戦基地とした。
ブッシュが再宣言した戦争の軍事部門を率いるのは、レーガン政権時代、中東特使だったドナルド・ラムズフェルドであり、国連における外交担当は、レーガン時代のホンジュラス大使、ジョン・ネグロポンテである。政策立案は、概ね、レーガン=ブッシュ一世時代の主要人物の手に握られている。
テロリズムを非難するのは健全なことであるが、ここには答えられていない疑問がいくつかある。まず、「テロリズム」という言葉で何を意味するのか。第二に、犯罪に対する適切な対応は何か。どのような答えも、少なくとも、道徳的に当たり前の基準を満たさなくてはならない。
すなわち、対立する相手に何かの原理を提案するならば、その同じ原理が自分たちにも適用されることに同意し、その原理をたゆまず主張しなくてはならないという点である。この最低限の誠意を守れない人々が、正義と不正、善と悪を語っても、真面目に受け取るわけにはいかない。
定義の問題は煩わしく複雑なものと考えられている。けれども、単純な定義を提案したものもある。例えば、米軍のマニュアルは、テロリズムを、「脅迫・強制・恐怖を植え付けることにより政治的・宗教的あるいはイデオロギー的目的を達成するため、意図的に暴力あるいは暴力による威嚇を用いること」と定義している[2]。
この定義はレーガン政権が対テロ戦争を強化していたときに提案されたものだけに時宜を得たものであり一層の権威を備えている。世界は当時からほとんど変わっていないので、レーガン時代の前例は有益であるに違いない。対テロ戦争を再宣言した現在の政府首脳陣が、第一次対テロ戦争を宣言したレーガン政権当時の延長である点は別としても。
第一次対テロ戦争は大きな支持を得た。レーガンがテロリズムを弾劾してから二ヶ月後、国連総会は国際テロリズムを非難し、さらに1987年には、その非難の口調は更に激しさと明確さを増した[3]。けれども、これらの決議は満場一致ではなかった。1987年の決議は賛成153、反対2で採択された。ホンジュラスは棄権した。
反対の2票は米国とイスラエルによるものであり、反対票を投じた理由として、決議には次のような致命的欠陥がある文言が含まれていると述べた。すなわち、「本決議のいかなる部分もいかなるかたちでも、国連憲章で保障された自決の権利、自由の権利、独立の権利を強制的に剥奪された人々、特に植民地体制下および人種主義体制下、そして外国による占領下の人々がこれら権利を備えていることに偏見を与えるものではない」という文言である。
この文言は、南アフリカのアパルトヘイト政権に対するアフリカ民族会議(ANC)の闘争、及び20年にわたって続いてきたイスラエルによるパレスチナ軍事占領に適用されるものと理解されていた。米国政府はアパルトヘイト政権を支持する一方、ANCを公式に「テロリスト組織」としていたし、パレスチナ占領についても、国際的に孤立しながらも事実上、米国一国による軍事的・外交的支援によって維持されていた。結局このテロリズムに反対する国連決議は米国の反対のため却下され無視されたのである[4]。
1985年にテロリズムを非難したとき、レーガンは特に中東のテロリズムに焦点をあてていた。この問題は、1985年のAP通信社のトップ記事に選ばれたものである。けれども、レーガン政権の「穏健派」、ジョージ・シュルツ国務長官にとっては、「国家の支持によるテロリズム」の最も「警戒すべき」兆候は、中米であり、恐ろしいことに米国の近くまで来ていたのだった。
彼によれば、この現代に「野蛮へと後戻りする」「文明そのものに敵対する」邪悪な者によって、疫病がまき散らされており、したがって彼は議会に対し、「国境なき革命」により西半球を支配しようと目論む「癌が、まさにここ我々の大地に」存在すると報告したのだった。例によって、お似合いの身震いとともに繰り返され、すぐにボロの出る、興味深い創作物語である。[5]。
中米のいわゆる「脅威」は非常に深刻であったため、1985年の「法の日」(5月1日)、レーガン大統領は、「ニカラグア政府の中米における侵略的行為により作り出された非常事態への対応」として経済封鎖を発表した。さらにレーガンは、国家非常事態を宣言し、これを毎年更新した。それというのも、「ニカラグア政府の政策と行為は、米国の国家安全保障と外交政策に対し途方もない脅威となっている」からである。
ジョージ・シュルツの警告によれば「テロリストたちは、そしてテロリストたちを支援し扇動する国家は、“民主主義は脆弱なものであり警戒を怠らずに防衛しなくてはならない”ことを厳しく思い起こさせる。」それゆえ、我々は、寛大な方法によってではなく強権的力によってニカラグアの癌を「切除」しなくてはならないのである。
シュルツは「交渉のテーブルに強制の力の影がさしているのでなければ、交渉は降伏の婉曲話法に過ぎない」と宣言した。そして国連や世界法廷といった外部の仲介による「ユートピア的・法的」事態解決を提唱して「方程式における力の項」を無視する人々を、彼は厳しく批判したのであった。
米国はこのとき、ネグロポンテの支持・監督のもとで、ホンジュラスを基地とした傭兵部隊を使い、「方程式の力の項」を実行した。そして世界法廷およびラテン・アメリカのコンタドラ諸国により追求された、「ユートピア的・法的手段」を妨害することに成功した。こうして、ワシントンが仕掛けたテロリスト戦争は、彼らが勝利するまで続けられたのである[6]。
レーガンが「邪悪なる鞭」に対する非難を発表したのはイスラエル首相シモン・ペレスと会談した時だった。ペレスはこのとき悪を根絶するための呼びかけに参加するためワシントンに来たのだったが、イスラエルを発つ直前にチュニスを爆撃機で攻撃し、残虐の限りを尽くしたばかりだった。その残虐行為の一つに、イスラエルの著名なジャーナリスト、アムノン・カペリュクが現場で目撃した、75人をスマート爆弾でバラバラにして殺害した事件がある。
米国政府は、チュニジアが同盟国であるにもかかわらず、爆撃機が向かっていると言わないことにより、このイスラエルによる虐殺に協力した。そしてジョージ・シュルツは、イスラエル外相イツハク・シャミールに、米国政府は「イスラエルの行為に大きな共感を抱いている」と述べた。しかし、国連安保理が、満場一致でこの爆撃を「武装攻撃行為」と非難したことにたじろいだ。その結果、米国は国連安保理では反対ではなく棄権することになった[7]。
中東におけるテロリズムがピークに達した1985年における、最も過激な国際テロリズムの資格を競う第二候補は、3月8日、ベイルートにおける自動車爆弾である。この爆弾では、80名が殺され、256名が怪我をした。この爆弾はモスクの外に置かれ、礼拝をした人々が出てくる時間にちょうど爆発するように仕掛けられていた。
「長い黒のチャドルを身にまとった250人もの少女と女性が、“導師リダ・モスク”での金曜礼拝からどっと出てきたところを爆発に見舞われた」とノラ・ブースタニーは報告している。この爆弾により、「ベッドの赤ん坊が焼かれ」、モスクから家に帰る途中の子供たちが殺され、西ベイルート一角の「人口の集中した表通りが破壊された」。
このテロの標的は、テロリズムの共謀者として告発されていたシーア派の指導者だったが、彼は逃げ延びた。この犯罪は、CIAと従属国サウジが、英国諜報部の助けを借りて仕組んだものだった[8]。
中東における最も過激な国際テロリズムの栄冠をこれら二つのテロ行為と競うことができるものと言えば、他に、ペレスが3月にレバノン占領地で指揮した「鉄拳」作戦くらいであろう。この地域に詳しい、ある西洋外交官は、「鉄拳」作戦を、「計算された残虐行為と恣意的な殺害」が新たな規模に達したものと述べた。
このとき、イスラエル軍(IDF)は村々を砲撃し、男子を強制連行したうえに、多くの村人を殺害した。こうしてイスラエル軍の準軍事組織に虐殺された多数の人々の上に、さらに数十人の村人の犠牲者を付け加えたのである。さらにまた、病院を砲撃し、患者を連れ去り「尋問」した。他にも沢山の残虐行為が行われた[9]。
イスラエル軍上級司令官は、標的は「村人のなかのテロリストだ」と述べた。エルサレム・ポスト紙の軍事特派員(ヒルシュ・グッドマン)は、さらに、「住民に犠牲が出よう」とも、イスラエル軍はレバノン占領地の「秩序と治安を維持する」ため、村人たちに対する作戦を続けるべきだと述べた。
レバノンにおけるこれらの行為は、それより3年前の、1万8千人もの死者を出したイスラエルによるレバノン侵略と同様、自衛のためにではなく、イスラエルではすぐに認識されているように、政治的目的だった。それ以降、1996年のペレスによる残虐な侵略に至るまで、同様の様々な残虐行為が行なわれた。しかし、これらすべての残虐行為は米国の軍事・外交支援に決定的に支えられていた。それゆえ、これらもまた、国際テロリズムの年鑑には記録されなかったのである。
要するに、中東における国際テロの主導的共謀者たる米国の主張には、何ら奇妙な点はないのである。だからこそ、「野蛮へと後戻りする」残虐行為がなされていた絶頂期に、その主張が何らのコメントも引き起こさずに受け入れられたのである。
1985年における「テロ」のチャンピオンとして広く記憶されているのは、クルーズ船アキレ・ラウロ号の乗っ取りと、乗客の一人レオン・クリングホッファー殺害であろう。確かにこれは卑劣なテロ行為であり、正当化されるものではない。たとえそれが、それよりはるかに惨いチュニスでの残虐行為に対する復讐としても、また、そうした行為を阻止するための先制手段としても。
道徳的原理に従えば、報復や先制としてなされる我々アメリカの行為も同様に正当化されない。だとすれば、公式の情報源に記されている「テロリズム」の定義に修正を加えなくてはならないのは明らかである。なぜなら公式の定義では、「テロリズム」という用語を、我々に対するテロリズムにのみ適用し、彼らに対してなされたテロリズムに適用していないからである。
これは、ナチスのような最悪の大量虐殺者によってさえ、いつも行われてきたことである。ナチスは、外国からの指令を受けたパルチザンのテロリストたちから住民を防衛していたのだし、日本は、満州の平和的な人々と合法的な満州政府を「中国人の追い剥ぎたち」によるテロから守るために、私心を捨てて努力していたというわけだ。この例外を見つけるのは容易ではなかろう。
同じ事が、ニカラグアの癌を絶滅するための戦争についても言える。1984年の「法の日」に、レーガン米大統領は、法がなければ、存在するのは「カオスと無秩序」だけだと述べた。ところが、その前日、国際司法裁判所が、レーガン政権にニカラグアに対する「不法な武力行使」を非難し、米国が行っていた国際テロ犯罪をやめ、ニカラグアに相当の賠償金を支払うよう命じていたにもかかわらず、レーガンは、米国は国際司法裁判所の裁定を無視すると宣言していたのである(1986年11月)。
レーガン政権は、この国際司法裁判所裁定を、軽蔑をもって拒絶しただけでなく、「すべての国家は国際法を遵守すべし」とする国連安保理決議と同じ内容の国連総会決議も、繰り返し拒絶したのである。(前者に関しては米国が拒否権を発動し、後者に関しては米国とイスラエルが反対し、エルサルバドルも一度だけ反対票を投じたことがあった。)それどころか、国際司法裁判所の判決が出されたときに、米国議会は、逆に「不法な武力行使」に従事していた傭兵部隊に対する資金提供を大きく増加させたのだった。
それから少しして、米国司令部は、傭兵部隊に対して、ニカラグア軍との戦闘を避け、かわりに、「ソフト・ターゲット」すなわち自衛手段をもたない一般市民を標的とするよう命令を出した。米国が制空権を握り、テロリスト部隊に先端通信機器が米国から与えられたため、傭兵部隊はこの命令を容易に実行することができた。
著名な評論家たちは、「費用」対「便益」の分析テスト、すなわち「流される血・悲惨の量」対「民主主義が出現する可能性」の比較分析テストを満足する限り、この戦略を妥当なものと考えた。ここでいう「民主主義」とは、西洋のエリートたちが理解し解釈するものであり、その実情は中米地域に生々しく示されている[10]。
国務省法律顧問アブラハム・ソファイアは、米国が国際司法裁判所の管轄権を拒絶する資格を持っている理由を次のように説明している。すなわち、国連が発足したばかりの頃は、国連の加盟国のほとんどは「米国の側に立ち、世界秩序に対する米国の見解を共有していた」。けれども、非植民地化が進んで以来、「重要な国際問題を巡って多数の国がしばしば米国に反対する」ようになった。したがって、我々米国は、我々がどのような行動をとるか、そしてどの問題が本質的に「米国の国内司法管轄下」に属するかを「決定する権限を自ら保持して」おかなくてはならないというのである。
ニカラグアに関して言えば、それは、国際司法裁判所と安保理が非難した、アメリカによるニカラグアへのテロリスト的行為をさしている。だからこそ米国は自分たちの行動は自分たちで決める権利を保持するとして拒否権を発動したのである。同様の理由で、1960年代以降、国連安保理決議に対する拒否権発動回数では米国が断然トップであり、英国が第二位、フランスがはるかに遅れて第三位となっている[11]。
米国政府は、前例のない規模の国際テロ・ネットワークを創生し、世界中でそれを活用することにより「テロリズムに対する戦争」を遂行した。これは、長期にわたり致命的な結果を生み出すこととなった。中米では、米国が指導し支援した国家テロは極度の状態に達した。それらの国々では、国家の治安部隊が直接の国際テロ・エージェントでもあったからである。
その結果については、エルサルバドルのイエズス会聖職者たちが開催した1994年の会議で詳しく報告されている。彼らの経験は特に身の毛もよだつようなものであった[12]。この会議の報告は、「権力者たちとは異なる代替策を期待する大多数の人々」を「飼い慣らす」際に、民衆の心に残留する「テロ文化」の効果に、特に注目している。これは、国家テロの効力に関する重要な観察であり、広く一般化できるものである。
ラテン・アメリカでは、2001年9月11日の残虐行為は強く非難されたが、同時に、それは何ら新しいものではないという見解が添えられていた。マナグアのイエズス会大学が出版する学術雑誌は、9月11日の残虐行為を「ハルマゲドン」と呼ぶことができるかも知れないとしながら、同時に、ニカラグアは、米国による攻撃のもとで、「耐え難いほど緩慢な速度で自らのハルマゲドンを生き続け」「現在はその荒涼たる余波の中に沈められている」と述べている。
しかも、1960年代以来、中南米を席巻した国家テロの巨大な悪疫のもとで、ニカラグアよりもはるかに悪い状況に置かれている国もある。しかし、これらの国家テロの多くは、元を辿れば、結局はワシントンに行き着くのである[13]。 だから、ワシントンが、2001年9月11日の攻撃に対する復讐を呼びかけたとき、ラテン・アメリカでは、これに対する共鳴がほとんどなかったことは全く驚きに値しない。
国際ギャラップ世論調査によると、ビンラディンの身柄引き渡しではなく、アメリカの軍事行動を支持する意見は、2%(メキシコ)から11%(ベネスエラとコロンビア)にすぎなかった。9月11日のテロに対する批判は、通常、ラテン・アメリカ諸国自身の苦痛に対する回想を伴っていた。たとえば、1989年12月、パナマのチョリーヨ街をジョージ・ブッシュI世が爆撃し、おそらくは何千人にも上る貧しい人々を殺害した事件である(これは西側による犯罪だったため調査も検討もされていない)。
この「正義」作戦では、命令に従わない悪漢ノリエガを誘拐した。ノリエガはフロリダで終身刑の判決を受けたが、その罪状のほとんどは、ノリエガがCIAに雇われていたときの犯罪であった[14]。
現在に至るまで、こうした状況は、口実と戦略の変更以外、本質的に変化なく、続いている。米国製武器の提供を最も多く受けている国々のリストは、その大きな証拠である。国際的な人権状況の報告を知る人にはお馴染みであろう。
それゆえ、ブッシュ米大統領が、アフガンに対して、(証拠要求と暫定的な交渉提案を拒絶し)米国がテロリズム容疑者とみなす人々を引き渡さない限り爆撃を続けると述べたことは、驚きに値しない。
3週間にわたる爆撃の後に、新たな戦争目的が付け加えられ、英国防衛幕僚長・海軍大将ミカエル・ボイス卿が、アフガンに対し、「指導者が替わるまでは爆撃が継続することをアフガニスタンの人々自身が認識するまで」米英の攻撃は続くと警告したことについても同様である[15]
すなわち、米国と英国は、「本質的に…政治目的を達成するために、計算して暴力を用いる」と主張し続けているのである。これは、専門的な意味では明らかに国際テロであるが、定評のある慣例に従い、彼らの規範からは除外されている。
ここでの理屈は、基本的に、米国とイスラエルによるレバノンでの国際テロ行為に使われた理屈と同じである。ボイス海軍大将は、レーガンが対テロ戦争なるものを初めて宣言したときに、著名なイスラエル人政治家アッバ・エバンが述べた言葉を、ほとんど繰り返しているに過ぎない。
レバノンでの残虐行為に関するメナハム・ベギン首相の説明に関連して、エバンは、次のように、例の定評ある正当化論を展開した。
「攻撃の被害を受けた人々が敵対行為を止めるよう自分たちの指導者に圧力を行使するという、理にかなった見通しがあり、それは結局実現された。」[16]
しかも、エバンは、このイスラエル労働党政権下で遂行された残虐行為が、「ベギン氏も私もあえて名前を述べようとは思わない政権」のやり方で行われたことを暗に認めているのである。
こうした考え方も、また妥当と思われるときにテロリズムに訴えることも、常套的なものである。それどころか、そのような成功は公然と祝福される。
米国のテロ作戦によるニカラグアの破壊は、極めて遠慮なく話題とされ、メディアはその成功を、アメリカ人は「喜びで一丸となった」と報道したのである。
1965年にインドネシアで起きた、土地無し農民を中心とした何十万人もの人々に対する虐殺も、メディアには大きな幸福感をもって歓迎されただけでなく、米国が果した決定的役割をワシントンが隠しおおせたことに対しても賞賛が送られた[New York Times]。
かつて「目もくらむような大虐殺」により社会を浄化した「インドネシアの穏健派たち」すら、この大虐殺には困惑したであろう。CIAは彼らの大虐殺を、スターリンやヒトラー、毛沢東の犯罪にも比するものとしていたのだが[17]。
他にも同じような多くの例がある。このように見てくると、オサマ・ビン・ラディンが9月11日の残虐行為を祝福したことがなぜ怒りと驚きを引き起こしたか不思議に思うかも知れない。
けれども、それは誤りである。なぜなら、そうした疑問は、邪悪な彼らのテロと崇高な我々のテロとの区別をきちんとできていないことによるものだからである。これが、アメリカの歴史において常に実践されてきた原理なのである。
テロリズムが弱者の武器だという公式の定義は重大な誤解である。ほとんどの武器と同じように、テロも強者が行使してはるかに大きな効果を手にしているのである。
ただ、強者のテロは、テロではなく、「対テロ」とか「低強度戦争」とか「自衛」とか言われるだけなのだ。そしてそれが成功すると、「道理にかなった」「現実的な」ものと賞賛され、「喜びで一丸となる」機会というわけである。
ここで、上記のような世界を支配している道徳原理を念頭に置きつつ、犯罪に対する適切な対応を巡る問題を考えよう。
仮にボイス海軍大将の言明が道理にかなったものであるならば、西洋国家によるテロの犠牲者たちも、逆に同じ原理に従って行動する資格を持つことになる。
しかし、このような結論は、当然にも、許し難いものと見なされる。このような原則が公然と敵に対して適用されるならば、それは許し難いものである。そうした行動が膨大な数の人々を危険にさらすと見られるときはなおさらである。
専門機関は、国連による「750万人のアフガン人に冬を越すための食料が必要である。9月11日時点より250万人の増加である。」との見積もりを妥当視している[18]。爆撃の威嚇と、それに次ぐ実行により、50パーセントも難民が増えたのである。
ただし、これまでの歴史が教えるところに依れば、一体何人の人々が犠牲になったのか、その正確な調査がなされることは多分、決してないだろう。
別の提案が色々なところから出されている。その一つはバチカンによるもので、軍事史家のマイケル・ハワードは、それを次のように述べている。
「国連の主導のもとで犯罪的陰謀に対する警察活動を行い…そのメンバーを捕らえて国際法廷に送り、そこで公正な裁判を行って、有罪とされるならば、それに応じた刑を受けさせる。」[19]
全く検討されなかったが、この提案は妥当なものに思える。そうだとするならば、これを西側の国家テロに適用することも妥当であろう。これもまた、全く検討されてこなかった可能性である。理由は反対であるが。
アフガニスタンに対する戦争は広く「正義の戦争」と言われてきた。確かに見かけはそのように見える。
また、この判断を支持するような「正義の戦争」という概念を作ろうという試みも見られた。
それゆえ、こうした提案を一貫した道徳的公理に従って評価すると、どうなるかを考えてもよかろう。私には、すぐさま崩壊するような議論しか、見あたらないのだが。
なぜなら、彼らには、その提案を西側の国家テロにも適用しようというのは、考えも及ばないことなのである。それどころか、そんなことを考えること自身が見下げ果てた行為ということになるかもしれない。
たとえば、最高の権威をもつ国際機関(国際司法裁判所)の判断に照らして論争の余地のない事件、すなわち、米国政府によるニカラグアに対する戦争に、この考えを適用するとどうなるか考えてみることができよう。むろん、「論争の余地がない」というのは、国際法と条約義務をそれなりに遵守するものたちにとってのことであるが。
これは試してみる価値のある、教訓的な思考実験である。
テロリズムに対する戦争の他の諸側面に対しても、同様の疑問が湧いてくる。米英のアフガニスタンに対する戦争が、曖昧な安保理決議により認められたかどうかを巡る論争があった。けれども、これが問題の本質なのではない。
なぜなら、その気があれば、米国は安保理からのはっきりした曖昧でない権限を確実に得ることができたであろう。しかし、その理由は、米国にとってあまり魅力的なものではない。(それは、なぜロシアと中国が、熱心に米国の側に立とうとしたか考えてみれば、それは全く明白である)
けれども、この選択肢は投げ捨てられた。恐らくそれは、安保理からの権限委譲を受けるということは、米国が従わなくてはならない、より高位の権威があることを示唆してしまうからである。これは、圧倒的な力を手にしている米国にとって受け入れがたい条件であろう。
外交と国際関係の文献には、このような立場に対して名前がつけられてすらいる。「威信」の確立というものである。暴力を行使する際に標準的公式的に使われる正当化手段であり、最近の例では、セルビア爆撃にもこの理屈が使われた。タリバン政府が交渉による容疑者ビンラディンの引き渡しの検討を要求したにもかかわらず、米国がそれを拒絶したのも、恐らく同じ理由による。
道徳的真理は、容疑者引き渡しといった問題にも妥当する。米国は、有罪性がはっきり確立しているときでも、テロリスト引き渡しを拒否する。最近の例として、1990年代初頭、ハイチで、軍事臨時政府のもと、何千人もの人々を残虐に殺した責任者である準軍組織の指導者、エマニュエル・コンスタンを挙げることができる。
米国は、公式にはこの軍事政府に反対していたが、米州機構(OAS)の経済封鎖をあからさまに軽視し、秘密裡に石油輸出を認めるなどして、暗黙にこの軍事政府を支持していた。軍事政府が倒れたあと、ハイチ法廷は、コンスタンを不在裁判で有罪とし、選挙で選ばれたハイチ政府は、何度も、米国にコンスタンの引き渡しを求めてきた。
米国がタリバン政権がビンラディンの交渉による引き渡し提案を侮蔑的に拒絶していた、2001年9月30日にも、ハイチ政府は米国に身柄引き渡しを要求しているが、これも再度、無視されている。恐らく、コンスタンが、テロ時代における米国との関係を暴くことを憂慮してのことであろう。
だとすると、ワシントンがアフガニスタンで行っているモデルに倣って、ハイチもコンスタンの身柄引き渡しを実現するために、武力に訴える権利がある、と我々は結論して良いのだろうか。こう考えること自体、米国にとっては許し難いことであろうが、米国のそのような態度は道徳的公理への明らかな侵犯である。
同様な他の例を挙げることは、極めて容易である[20]。1959年以来、恐らく国際テロリズムの主標的となってきたキューバを考えよう。その規模と性質は驚くべきもので、1990年代後半まで続いた。ケネディのマングース作戦に関する文書が機密解除されたために、その実態の一部が暴露されている。
例によって、使える間は冷戦という口実が利用されてきたが、調べてみると、そのような話は政府内部では当たり前のことだったのだ。アーサー・シュレジンジャーは、JFKのラテン・アメリカ・ミッションに関する結論を着任予定の大統領に報告した中で、これを秘密裡に詳説している。
すなわち、キューバの脅威は、「米国からの自立を図るというカストロの考えが広まる」ことにあった。それが、「今やまともに暮らす機会を求めている」他の国々の「貧民や貧困層」を刺激するかも知れないということであり、米国上層部では、「ウィルス」とか「腐ったリンゴ」と言われていたのである。
冷戦との関係でいうと、「ソ連はあたりを飛び回り、大規模な開発資金を途上国に提供し、自ら、一世代で近代化を実現したモデルとして範を示している」という点にあった。それが米国にとっては脅威だったというわけである[21]。
これら国際テロの「偉業」は、かなり深刻なものであるにもかかわらず、実際は、公の場では、標準的慣習により、議論の対象から除外されている。
それはともかく「正義の戦争」の公式的定義に従うことにしよう。その理論とそれに従った適切な対応ということになれば、キューバは米国にどのような反撃をする権利を持っていたのだろうか?
国際テロリズムを「文明そのものに対する邪悪な敵対者」が広める災いとして弾劾するのは全く正当なことである。
また「悪を世界から駆逐する」ための献身は、なおさら真面目にとることができよう。ただし例の道徳的公理を満たすならば、である。
これは決して不条理な考えではないと私には思われるのだが、どうであろうか。













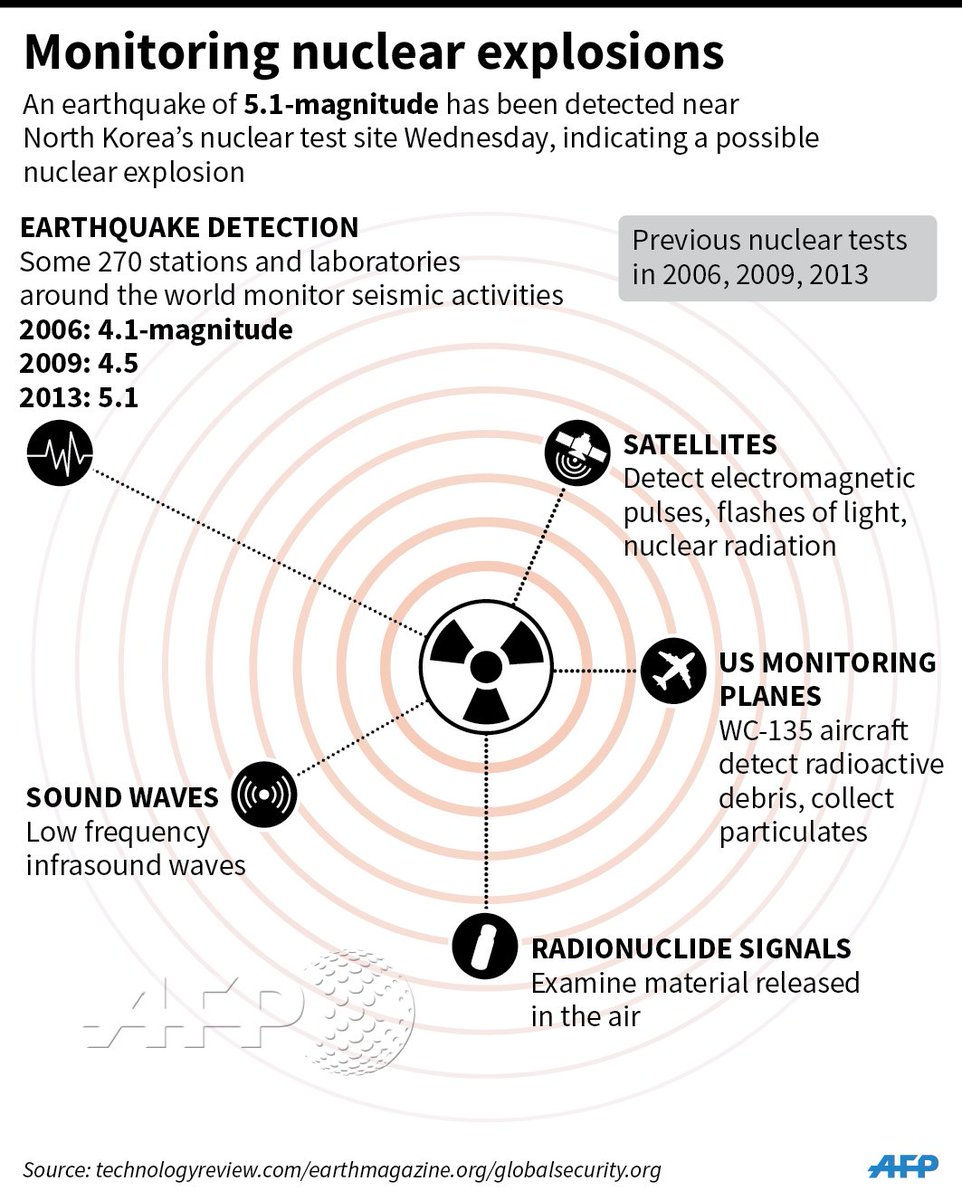









コメント:このニュースは良い前兆はありません。しかし、次のことを考慮すると、無大きな驚きとして来るべきではありません:
関連記事