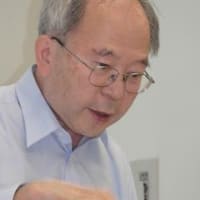須藤監督を知るために
須藤久著
「破邪顕正の浪曼」1974年第一版 三一書房より
『理念の逆転』と『感性の逆転』
またしても、一人の若者が病院の前に捨てられた。約2年前の海老原君は中核派の手によって捨てられ、今度の川口君は革マル派の手によって捨てられた。二年前、革マル派は大量のアンケートを主として知識人達に配って間接的に中核派の非難をもくろんだ。
が、今度は自らがその立場に立った。目には目、歯には歯と彼等は言っているが、物はいいようである。今度のは、この言葉に値しない。こんなのは目くそ鼻くそを笑うという。
赤軍派の隣地殺人事件の時に反スターリン主義を掲げる両派は、それぞれ大衆的、組織的な革命ビジョンを持ち得ない者の末裔と評した。
当然のことながら問題はそんなところにあるのではない。問題は、『人殺しが平気で行える感覚を持てなければ革命家とはいえない』などという『感性の逆転』にこそあるのだ。
「14名もの大切な仲間を私は殺してしまった。『なぜ殺してしまったのか』『私はこんなために闘おうとしたんじゃない』と解決の付かない疑問にどうして良いのか解らなくなります。しかし、私がここで錯乱してはいけない。私がなぜ殺したのかここで必死に考えることを止めたら、14名の死者、そして今殺人犯として捕らわれている仲間の犠牲があまりにも無意味になる。これだけ大きな誤りを犯してしまった今は、すべての重みを心に受け止めるようにしたい。
私はこれおから明らかにする事実は、徹底して冷酷であり、人間性のひとかけらもないものです。この事実を私はいまでは、認めます。しかし、3月の中旬ごろまでは、これほど冷酷であり、絶対許されるものではないとは思わず、私は革命戦争を闘おうとしたんだ。温かい人間になろうとしたんだと叫びたかったのです。いまはこの(人間性のひとかけらもない)事実の重みを芯に受け止めようとし、そのうえで、私は叫びたいのです。
この事実が精神異常者性格異常者によるものとして片付けられようとしている危険をいまはっきり私は感じます。このように片付けてはいけないのです。普通の青年男女が、こんなに残虐なことをしたところに歴史的教訓があると思います。この教訓を無視して、事実を精神的異常者の犯行として片付けてしまったら、14名の死はまったく無駄になり、現在殺人犯で問われている私たちの痛苦がなんだか判らなくなります。」(47年4月18日『朝日新聞』永田洋子自己批判書より下線筆者)
このような痛ましい『感性の逆転』が何故起こってしまったのか、永田洋子の自己批判書にもある通り、本人達にも判らないのである。私たちは彼女たちと一緒にこのことをあくまで考え抜かなければならない。
獄中にいる当事者の永田洋子ら自身が、ふつうの青年男女が何故このような残酷な事をしたのかと血を吐く思いで自らを問いつめているのに、獄外で原稿料を稼いでいる自称赤軍派評論家どもは気楽である。なかでも平岡正明と言う男はまことに威勢が良い。もっとやれ、どんどんやれと彼の原稿の売れ行きはなかなかである。しかし、彼の駄法螺を革命への勇気と取り違えて感心している知的特権階級養成所のガキ共ばかりが革命を考えているのではない。私はあくまで故高橋和巳の遺志を受け継ぎ、私は私なりの方法で、この問題をあくまで問いつめてゆく。
ここで書いたいま、テレビニュースによれば早稲田の一般学生による、川口君虐殺糾弾集会が18時間も続き、糾弾される側の革マル派の肉体的衰弱が心配との理由で大学側が機動隊を入れ、機動隊は一般学生を打ちのめしながら革マル派学生を救出したと言う。
あぁ、平岡正明よ、この機動隊によって救い出された、殺人の平気な革マル派も革命的であるのか?
ところでこの『感性の逆転』ということばは、吉本隆明氏の『理念の逆転』という言葉に対応して使ったものである。ここで読者の手元に本誌10月号があるならば、お手数だがもう一度私が引用した吉本氏の文章を読んでいただきたい。
吉本氏は、なんでもかんでも最下層民衆や後進地域を持ち出せば、そこには、そのまま正義倫理が完成してあるなどと楽なことを思うなと言っている。そこになんらかの『腹わたをつかみ出す』ような知的覚醒の努力を持たぬ限り、最下層民衆は常に理念が逆転して在るのだということを説いている。
私はこれをちょうど裏側から見たことになると思う。なんでもかんでも知的覚醒に基づく『正当なる理念』を持てば、それがそのままですなわち正義=倫理の完成であるなどと<B>楽に</B>思いよがられては困るのだ。そこになんらかの最下層民衆の共同体感性との間に血のつながりを持たぬ限り、知的覚醒は常に感性が逆転してあるのだということをいいたいのである。
おそらく吉本隆明氏も私も負っているものは一つのものであろうと予感するのだが、その立脚点は正反対のように思われる。吉本氏は『共同体の幻想』なるものを、そのまま、まるごとでなければダメだということを言っているのである。この『理念の逆転』と『感性の逆転』の対応関係は今後相当に辛い血みどろの格闘を自分に強いるものと覚悟している。
近代主義はまず人間の共同体構成と共同体感性を否定するところから出発している。親・子・兄・弟・姉・妹さらに夫と妻でさえ、これを『理性』によってすべて『他人』という『個』にバラし、そしてこれを『階級』という『利害』を共通の分母とする2つの階級社会によって再構成する。そして、この階級構成と階級理念以外は一切認めない。この一方が近代マルクス主義というわけである。
すなわち、人間と人間の実在関係の根本を『族』として『類』としての共同体感性によるものとせず、人間関係の原動力を『利害』という政治的人工的エサに定めて、理性的分配理念に求めようとした。
したがってそこでは人と人の結びつき、すなわち『団結』は人工的に構成された『敵』階級を殺すためのものであって、もっとも団結することは殺すためであり、もっとも殺すことは最も団結するためなのであるという『感性の逆転』が現実のものとなっていったのである。
近代のいう『統一と団結』はあくまで『利害』や『分配』を目前にした同一ブロック内だけのものであり、万一、何かの間違いでブロックを超えて団結しようものなら、たちまち裏切り者として殺されてしまうと言うわけである。始め、この『統一と団結』の提唱者はこんなはずではなかった。敵対する階級は2つだけであり、しかも片方はホンの一握りで、もう一方は残りの圧倒的多数全部だということであった。いつの世にもホンの僅かな悪逆非道な奴はいるものだ。だから2つの階級といっても、実際はひとつの階級みたいなものよとたかをくくっていた。したがって、この論理では、人類の『統一と団結』と我等が『階級の統一』は上手く重なって、問題ないはずであった。ところがどっこい現実はそうはいかなかった。利害の分配論理というものはタッタひとつであり得るわけがないから、圧倒的多数を自称するブロックが雨後の竹の子のように発生し、それぞれが『圧倒的多数』の利益を主張し、互いが相手を『圧倒的多数』の敵と規定し(反革命ともいう)、互いのブロック内だけにしか適用しない、『統一と団結』を叫んでちょっとでもブロックを超えようとすると、すぐさま病院の前に捨てられたり、裸にして埋められたりと言うことになった。こうなると、我が階級の『統一と団結』と、人類の『統一と団結』は重ならなくなる。近代のブロックはすべて統一理念を分母とした集団である以上、理念の種類が存在する数だけ集団の数もあることになり、理念は人の頭数だけ異なっておかしくないのだから、近代はもう自分以外はすべて『敵』として認識する他はない。そこでの『団結』はなんのことはない『自己愛』の役割しか果たさない。
人間関係の分母に論理や理性的認識を置くという近代主義はかくて、他者との結びつきに関して絶望的である。他者が<B>すべて敵</B>ならば、そこに『正当なる感性』があり得よう筈がない。
ここで『昭和残侠伝・死んで貰います』マキノ雅弘監督作品の一節を転載する。全東映任侠映画の中でその『正当なる感性』を証す代表的シーンであえる。
金もなく、メシも喰えず、おまけのチンピラたちに寄ってたかってなぐられ血だらけになった秀次郎(高倉健)はやっとのことである大きな銀杏の木にたどり着き坐る。そこへ15才の幾江(藤純子)が通りかかる。幾江「お兄ちゃん、ケンカしたの」
といい乍ら近寄る。
秀次郎 「(思わず)よるなよ」
幾江 「(その声に驚くが)だって血が出ているよ」
秀次郎 「血が付くよ」
幾江 「大丈夫(徳利を差し出し)これで洗ってあげる。直ぐなおるんですって」と近づき、カサを置いて、かいがいしく徳利から酒を手拭いにしませて、 傷の手当てをし始める。
秀次郎の目にうつる----あかぎれた手寒そうにほっぺたの赤い顔。
しゃべっている幾江の眼はおどおどしている。秀次郎 「すまねえな・・・・ひでえあかぎれだな、痛えだろう」
幾江 「ううん、修行ですもの」
秀次郎 「修行」
幾江 「あたし、ネ、芸者さんの卵なの。12の時に、可愛らしいなア、いい娘になるっていわれて買われたの、
お父っあん、たくさんお金貰ったヮ・・・・」(中略)
幾江 「兄ちゃん、お金持ってる」秀次郎、寂しそうに首を振る。
幾江 「今晩どこで寝るの」
秀次郎 「うん、どこって・・・・・俺ア寝なくたっていいんだ、それよりその酒どうするの」
と傷のところをおさえる。
幾江 「いいの、いいわ・・・・もう慣れてる・・・・ねえ、おかみさんにね、キセルでゴツーンと一つ、いや二つかな、たたかれたらいいの・・・・そう、そうだあたい、おかみさんに頼んでみる・・・今夜だけうちにとまりなさい・・・」秀次郎 「とんでもねえ、そんな事したら、10も15もキセルで」
幾江 「あたい、おかみさんに、たのんでみる。兄ちゃんここで待っててね」
秀次郎 「いいよ、オイ」幾江はそんな秀次郎の心配も聞かず、おかみに一生懸命頼む。がやはり、前借で半期奉公しているくせにと取り合ってもらえない。そのやりとりを表で立ち聞いた秀次郎はソッと去る。しかし、幾江はなおも粘り抜き、やっと物置ならよいという許しをもらって、飛び立つように表に出る。
走って出る幾江、見回すが秀次郎はいない---。
あっちへ行ったり、こっちへ行ったり・・・・・。
幾江 「お兄ちゃあん!お兄ちゃあん・・・
(と名前を知らないので困って・・・・しまって両手を口に当て)ヤクザの・・・ヤクザのお兄ちゃあーん」
と大声で叫ぶ・・・
置き捨てられたカサに霧が尚も続いている・・・・。(F・O)
何という『正当なる感性』であることか。これは正に名作「難破船」に匹敵する名場面である。この少女の、この感性の美しさは一体どこから来るのであろうか。
ヒューマニズムや人民解放という近代思想が叫ばれ始めて、もう100年はゆっくり経った。にもかかわらず黒人問題、ユダヤ人問題、国内では被差別問題、在日朝鮮人問題等々と人間を差別してはならぬという実に簡単なことさえ、まだほとんど解決していない。政治的処置の問題ではなく、人間の心の問題として、近代人はまだほとんど「差別」一つ、なんとも解決していない。この100年の間に「差別」に関して幾百万の論文が書かれ、幾千万の書物が出版されたことだろう。差別を解消するための幾百の論理が立てられ、幾千の法律が立てられただろう。
「天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らず」と或るエライ人がいったそうである。そしてそのためには「学問のすすめ」をおこなわなければならぬといったそうである。だがしかし、学問や知識を充分に積んだと自称する者がどうであるかは今具体的に例をあげた通りである。それに引きかえ、この15才にして芸者に売られた、「汚れなき天使」は一個の文字も一片の理論も持っていないにもかかわらず、人間のまさに人間としての『正当なる感性』を、そのアカ切れた手の中で知っているのである。孤独で淋しい15才の「売られた少女」は住所不定のルンプロに対して、なんらかの不信感、差別感も持たず、その姿が見えなくなると「ヤクザのお兄ちゃーん!」と涙声になって叫ぶのである。この少女の、この叫び声は、あらゆる文字や革命戦略をはるかに超えている。この少女の声が世界をおおいさえすれば、あらゆる差別はなくなる。あらゆる人間の悪を超えることができる。なぜか、なぜなのか。『正当なる感性』はなぜ、この少女の世界にしかないのであろうか。
近代理性は人間の感性をそのままでは「毒」になるものとして見てきた。しかし、人間の感性は、そのままでは共同体感性として現れる。人間が自然界の一部をなす動物という存在である限り、人間は性的な存在である。「男」か「女」かという存在であり、この両者の統合によってのみ人間は存在を続けているのであるから、それは否応なく、親子兄弟姉妹等の血縁共同体の世界である。従って、人間の最も自然な感性は共同体的感性であるわけである。
ところが、近代理性はこの共同体感性を蛇のように忌み嫌い、あらゆる血縁的存在を嫌悪し、「兄弟は他人の始まり」という後天的人工的因子で「階級」というような政治的なものにムリヤリ再構成しようとした。とくに近代マルクス主義は、この人間の協同的構成や感性こそが天皇制(領主制)の素因だとして、なお一層これを嫌悪し、一切の共同体理念を圧殺する挙に出た。これでは正当なる左翼理念(左翼理念を正当なものとして仮定して)が常に感性の逆転を伴うはずである。いかに天皇制(政治体制)が否定すべきものであっても、男と女が愛し合って、両親の下に子供が生まれる限り、工場から生産される自動車やロボットのように「個」という立場はあり得ない。人間であると言うことは、すなわち、男か、女か、親か、子か、兄か、妹かということである。人間が性的存在である限り、それは「血」の世界であり、近代のいう「個の主体性」なんてものは正確にはあり得ない。あるのは、共同体感性があるだけである。人間が共同体的存在であると言うことは、何といっても動かすことの出来ない事実である。このことと、どうにでも動かすことの出来る政治体制(天皇制)が良いか悪いかということは全く別の問題である。何よりも重要なのは、人間のまさに人間的実在であって政治ではない。もし政治が人間をおびやかすならば、政治をこそ粉砕すべきである。「良き政治」「良き革命」のために、人間の実存のほうが破壊されてたまるかということと全く同じ事である。
近代主義の理性や知識が、にもかかわらずあくまで「政治」や「生産」に奉仕し、共同体感性に敵対するものである以上、近代の「理念の正当」は常に「感性の逆転」を必然とせざるを得ない。
これを全く逆に考えれば、政治や生産に奉仕すべき何物をも持たない「売られた少女」がまさにその感性を毒されずに居ることは納得できるではないか。
東宝任侠映画。「任侠」とは近代権力に反逆する白刃の世界である。「任侠」が共同体感性の組織者であることは疑う余地のないものであるが、もう一つ、「任侠」はまた被差別絶対少数者のものであることから、これもまた、「政治」や「生産」に奉仕せねばならぬものと全く無縁である。だからこそ、東映任侠映画が、このような「汚れなき天使」の世界を創出し得たのである。否、東映任侠映画でなければ、このような「売られた少女」の立場にはとうてい立ち得ず、したがって、『正当なる感性』は手にすることが出来なかった筈である。
「ヤクザのお兄ちゃーん!」
これおほど『正当なる感性』に支えられた『正当なる理念』の世界が他にあろうか。