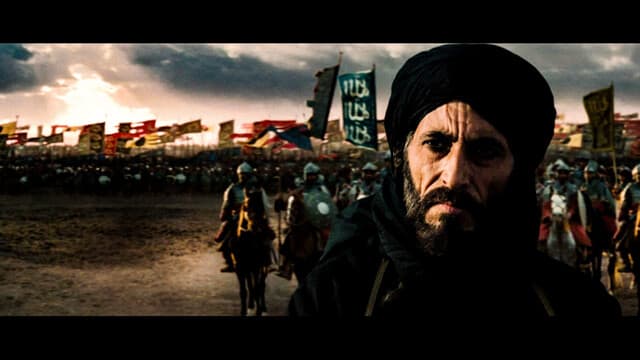
『中世ヨーロッパ 世界の歴史5』社会思想社、1974年
6 十字軍
2 イスラムの反撃
イスラム側の反撃は、イラク北部に王朝を興したザンギーと、その子ヌール・エッディンによって開始された。
ザンギーは、ティグリス川上流のモスールからアレッポにいたる地域に勢力をひろげ、一一四四年にはエデッサを占領し、エデッサ他領を解体させた。
ザンキーの死後、一時、エデッサは、旧エデッサ伯にとりかえされたが、ヌール・エッディンは、再度、これを奪取し、アレッポに都して、ダマスクス方面にまでその勢力をのばし、フランク人たちをうしろから圧迫する態勢をとった。
ここに起こされたのが、聖ベルナールのすすめによって、ドイツ王コンラート三世とフランス王ルイ七世を頭にいただいた第二回十字軍である。
シトー教団の事実上の建設者ベルナールのイスラム観は、たいそう偏狭で戦闘的なものであった。
その点で、彼は同世代のクリュニー修道院長の尊者ピエールと対照的であった。
尊者ピエールはキリストの愛によるイスラム教徒との和合を説いた、当時数少ないヒューマニストのひとりだった。
その聖ベルナールのゆがんだイスラム観をそのままに反映して、十字軍士の心理構造は、第一回十字軍のときのそれと、ぜんぜんかわらなかった。
こんどは東ローマ帝国も迷惑した。当時、東ローマは、小アジア半島のイコニウムを中心に勢力をひろげていたスルタン、マスードと和したばかりであったから、イスラム教徒とことをかまえたくなかったのである。
シリア、パレスティナの「フランク人」たちにとっても、彼らは、ある意味ではありがた迷惑な客であった。
当時のアンティオキア候レーモン・ド・ポワチエは、ヌール・エッディンの本拠アレッポを取ろうと画策していた。
そこヘフランス王ルイの一隊がきたので、レーモンは、当然、その協力を期待した。
だが、ルイは、海路を直行したドイツ王コンラートの待つ聖都イェルサレムへと、ひたすらいそぎ、レーモンの賢明な策を無視したのであった。
イェルサレムについたコンラート、ルイ両王は、イェルサレム国エボードワンその他の現地側の首脳と作戦会議を開き、ダマスクス攻撃の方針を決定した。
これは、それまでイェルサレム王国に対し友好的であったダマスクスのスルタン政権を敵側にまわす結果になる愚かな決定であった。
ダマスクスは、それまで敵対関係にあったヌール・エッディンと提携する動きをみせた。
一一四八年夏、新来の十字軍と現地の諸侯軍の連合軍はダマスクスを攻囲した。
だが、すぐに作戦の失敗をさとった現地側の諸侯は、おそらくダマスクスのスルタンとのあいだにひそかな交渉がもたれたのであろう、突然、十字軍士に対し徹退を提案した。
現地軍の協力が得られなくなった以上、作戦は失敗である。
攻撃陣はわずか五日でとかれ、十字軍は、事実上、解散した。
シリア、パレスティナに住みついたフランク人は、あるていど、イスラム世界に同化する方向に向かっていたし、かなり現実的に情勢を判断することのできる心理状況にあった。
いわば狂信の十字軍熱から、すでに醒めていたのである。
そのような彼らにしてみれば、新手(あらて)の熱心党の到来は、これはいささか迷惑なことであっただろう。
さて、当時、エジプトのファーティマ朝のカリフ政権は、衰退はなはだしかった。
ヌール・エッディンは、信頼する一部将シール・クーフを派遣してファーティマ朝の政権統制にあたらせた。
一一六九年、彼は同朝の宰相の地位についたが、まもなく病没し、その甥がそのあとを襲った。
この人物こそ、イスラムの支えとなったサラー・アッディン(サラディン)である。
一一七一年、ファーティマ朝最後のカリフが没すると、サラディンは衆望をになってスルタンの地位につき、バクダードのカリフに忠誠を晢った。
その二年後、ヌール・エッディンが没すると、彼は、ダナスクス、シリア方面に対する行動を宣言し、翌年ダマスクスを占領した。
だいたい一一八五年ごろまでに、サラディンに、ユーフラテス川からナイル川におよぶシリア、エジプト全体の統一君主になった。
これまでイスラム側の内紛に助けられるかたちであったシリア、パレスティナ沿海地域のフランク人諸国家は、いまや重大な危機にさらされるにいたった。
サラディンの版図(領土)
それでもなおしばらくは友好関係がつづいたが、メッカの隊商を掠奪するというフランク側の軽挙妄動(けいきょもうどう)があって、両者間の関係は急速に冷却した。
一一八七年夏、イェルサレム王国軍は、総力をあげて、ガリラヤ地方の制圧におもむいたが、ガリラヤ湖西岸のハッティン峠でサラディンの軍に包囲され、炎天下に水を絶たれ、おまけに火攻めにあって、あえなく降伏し、イェルサレム国王以下、全員捕虜になってしまった。
このハッティンの戦いののち、サラディンは、アッコン、ヤッファ、ベイルートをつぎつぎに攻略し、十月はじめにはイェルサレムの城門の前に立てた。
イェルサレムは戦わずして降伏した。八十八年前、七万余のイスラム教徒を虐殺した第一回十字軍の場合とは、まったく対照的であった。
このたびは、殺戮も掠奪も破壊もなかった。
キリスト教徒は、男が金貨十枚、女が五枚、子供が一枚の身代金で助命され、立ち退きを許された。
身代金の払えぬ貧乏人、戦死者の寡婦や孤児には、サラディン自身が私財を投じて身代金を払ってやった。
みにくい振舞をみせたのは、イェルサレム総大主教をはじめキリスト教会の高位聖職者たちであった。
彼らは、自分の身代金だけを払うと、金銀財宝を荷車に山と槓んで、さっさと立ち退いてしまったのである。
「岩の大聖堂」の上に建てられてあった黄金の大十字架は撤去された。
城壁には、サラディンの旗がひるがえった。
聖都イェルサレムは、イスラム教徒の手に回復ざれた。
フランク人は、いまや、ティルス、トリポリを領するにすぎなかった。
現地フランク人の緊急援助の要請にこたえて、史上有名な第三回十字軍がおこされた。
神聖ローマ帝国皇帝フリードリヒ一世「赤ひげ(バルバロッサ)」王、フランス王フィリップ二世「尊厳(オーギュスト)」王、イギリス王リチャード一世「獅子心(ライオンハーティド)」王のひきいる十字軍である。
南シリア
だが、この十字軍も、喧伝されているほどにははなばなしいものではなかった。
「赤ひげ」王が、まず一一八九年、先行したのだが、翌年、小アジア半島のセレウキア付近の川で溺死するという失態を演じてしまった。
将士の多くは帰国したが、一部のものは、そのまま聖地へむかった。
「尊厳」王と「獅子心」王は、一一九〇年の冬を、ともにシチリア島ですごし、翌年春、あい前後して、海路パレスティナに向かった。
すでに一一八九年八月以降、現地フランク軍は、サラディンが守備隊をおいていたアッコンの町を奪いかえそうと、港の反対側にあたるツーロンの丘を基地として、攻囲陣を張っていた。
やがて「赤ひげ」王の残党も、これに加わった。
一方、サラディンは、東と南から、この攻囲陣を逆に包囲していた。長い攻囲にフランク勢はようやく疲れ、援軍の到着を待ちのぞんでいた。
そこへ「尊厳」王と「獅子心」王が到着した。役石機や鉤梯子など、新鋭の攻城機も加わった。
フランス、イギリスの艦隊は制海権をにぎり、海上から市内への補給路を断った。
攻囲陣突破をはかったサラディンの努力もむなしく、守備隊はついに降伏した。七月五日のことだった。かくてアッコンは、ふたたびフランク人のものとなった。
「尊厳」王フィリップはただちに帰国し、残った「獅子心」王リチャードは、サラディンとの協定を無視して、アッコン守備隊の捕虜二千七百人を処刑したのち、一路、イェルサレムへの道をいそいだ。
あいも変わらぬ十字軍士の残虐に、サうディンは怒った。
以後、一一九二年九月に停戦協定がむすばれるまでのあいだ、サラディンは、リチャードと各所に戦い、リチャード軍の重装騎兵隊と弓手隊の協働作戦に悩まされながらも、よくリチャードの動きを封じ、ついにイェルサレムの城壁には近づかせなかった。
サラディンは、ヤッファからティルスにかけてのパレスティナ沿海地域の支配と、聖都イェルサレムへの巡礼通行権とを、三年間にかぎり、フランク人にみとめた。
翌年サラディンは、ダマスクスで世を去り、「新」イェルサレム王国は、なお一世紀ほどのあいだ存続することになった。
だが、シリア、パレスティナにおける「フランク人」、西方キリスト教徒の脅威は、事実上、ここに消滅したのである。

6 十字軍
2 イスラムの反撃
イスラム側の反撃は、イラク北部に王朝を興したザンギーと、その子ヌール・エッディンによって開始された。
ザンギーは、ティグリス川上流のモスールからアレッポにいたる地域に勢力をひろげ、一一四四年にはエデッサを占領し、エデッサ他領を解体させた。
ザンキーの死後、一時、エデッサは、旧エデッサ伯にとりかえされたが、ヌール・エッディンは、再度、これを奪取し、アレッポに都して、ダマスクス方面にまでその勢力をのばし、フランク人たちをうしろから圧迫する態勢をとった。
ここに起こされたのが、聖ベルナールのすすめによって、ドイツ王コンラート三世とフランス王ルイ七世を頭にいただいた第二回十字軍である。
シトー教団の事実上の建設者ベルナールのイスラム観は、たいそう偏狭で戦闘的なものであった。
その点で、彼は同世代のクリュニー修道院長の尊者ピエールと対照的であった。
尊者ピエールはキリストの愛によるイスラム教徒との和合を説いた、当時数少ないヒューマニストのひとりだった。
その聖ベルナールのゆがんだイスラム観をそのままに反映して、十字軍士の心理構造は、第一回十字軍のときのそれと、ぜんぜんかわらなかった。
こんどは東ローマ帝国も迷惑した。当時、東ローマは、小アジア半島のイコニウムを中心に勢力をひろげていたスルタン、マスードと和したばかりであったから、イスラム教徒とことをかまえたくなかったのである。
シリア、パレスティナの「フランク人」たちにとっても、彼らは、ある意味ではありがた迷惑な客であった。
当時のアンティオキア候レーモン・ド・ポワチエは、ヌール・エッディンの本拠アレッポを取ろうと画策していた。
そこヘフランス王ルイの一隊がきたので、レーモンは、当然、その協力を期待した。
だが、ルイは、海路を直行したドイツ王コンラートの待つ聖都イェルサレムへと、ひたすらいそぎ、レーモンの賢明な策を無視したのであった。
イェルサレムについたコンラート、ルイ両王は、イェルサレム国エボードワンその他の現地側の首脳と作戦会議を開き、ダマスクス攻撃の方針を決定した。
これは、それまでイェルサレム王国に対し友好的であったダマスクスのスルタン政権を敵側にまわす結果になる愚かな決定であった。
ダマスクスは、それまで敵対関係にあったヌール・エッディンと提携する動きをみせた。
一一四八年夏、新来の十字軍と現地の諸侯軍の連合軍はダマスクスを攻囲した。
だが、すぐに作戦の失敗をさとった現地側の諸侯は、おそらくダマスクスのスルタンとのあいだにひそかな交渉がもたれたのであろう、突然、十字軍士に対し徹退を提案した。
現地軍の協力が得られなくなった以上、作戦は失敗である。
攻撃陣はわずか五日でとかれ、十字軍は、事実上、解散した。
シリア、パレスティナに住みついたフランク人は、あるていど、イスラム世界に同化する方向に向かっていたし、かなり現実的に情勢を判断することのできる心理状況にあった。
いわば狂信の十字軍熱から、すでに醒めていたのである。
そのような彼らにしてみれば、新手(あらて)の熱心党の到来は、これはいささか迷惑なことであっただろう。
さて、当時、エジプトのファーティマ朝のカリフ政権は、衰退はなはだしかった。
ヌール・エッディンは、信頼する一部将シール・クーフを派遣してファーティマ朝の政権統制にあたらせた。
一一六九年、彼は同朝の宰相の地位についたが、まもなく病没し、その甥がそのあとを襲った。
この人物こそ、イスラムの支えとなったサラー・アッディン(サラディン)である。
一一七一年、ファーティマ朝最後のカリフが没すると、サラディンは衆望をになってスルタンの地位につき、バクダードのカリフに忠誠を晢った。
その二年後、ヌール・エッディンが没すると、彼は、ダナスクス、シリア方面に対する行動を宣言し、翌年ダマスクスを占領した。
だいたい一一八五年ごろまでに、サラディンに、ユーフラテス川からナイル川におよぶシリア、エジプト全体の統一君主になった。
これまでイスラム側の内紛に助けられるかたちであったシリア、パレスティナ沿海地域のフランク人諸国家は、いまや重大な危機にさらされるにいたった。
サラディンの版図(領土)
それでもなおしばらくは友好関係がつづいたが、メッカの隊商を掠奪するというフランク側の軽挙妄動(けいきょもうどう)があって、両者間の関係は急速に冷却した。
一一八七年夏、イェルサレム王国軍は、総力をあげて、ガリラヤ地方の制圧におもむいたが、ガリラヤ湖西岸のハッティン峠でサラディンの軍に包囲され、炎天下に水を絶たれ、おまけに火攻めにあって、あえなく降伏し、イェルサレム国王以下、全員捕虜になってしまった。
このハッティンの戦いののち、サラディンは、アッコン、ヤッファ、ベイルートをつぎつぎに攻略し、十月はじめにはイェルサレムの城門の前に立てた。
イェルサレムは戦わずして降伏した。八十八年前、七万余のイスラム教徒を虐殺した第一回十字軍の場合とは、まったく対照的であった。
このたびは、殺戮も掠奪も破壊もなかった。
キリスト教徒は、男が金貨十枚、女が五枚、子供が一枚の身代金で助命され、立ち退きを許された。
身代金の払えぬ貧乏人、戦死者の寡婦や孤児には、サラディン自身が私財を投じて身代金を払ってやった。
みにくい振舞をみせたのは、イェルサレム総大主教をはじめキリスト教会の高位聖職者たちであった。
彼らは、自分の身代金だけを払うと、金銀財宝を荷車に山と槓んで、さっさと立ち退いてしまったのである。
「岩の大聖堂」の上に建てられてあった黄金の大十字架は撤去された。
城壁には、サラディンの旗がひるがえった。
聖都イェルサレムは、イスラム教徒の手に回復ざれた。
フランク人は、いまや、ティルス、トリポリを領するにすぎなかった。
現地フランク人の緊急援助の要請にこたえて、史上有名な第三回十字軍がおこされた。
神聖ローマ帝国皇帝フリードリヒ一世「赤ひげ(バルバロッサ)」王、フランス王フィリップ二世「尊厳(オーギュスト)」王、イギリス王リチャード一世「獅子心(ライオンハーティド)」王のひきいる十字軍である。
南シリア
だが、この十字軍も、喧伝されているほどにははなばなしいものではなかった。
「赤ひげ」王が、まず一一八九年、先行したのだが、翌年、小アジア半島のセレウキア付近の川で溺死するという失態を演じてしまった。
将士の多くは帰国したが、一部のものは、そのまま聖地へむかった。
「尊厳」王と「獅子心」王は、一一九〇年の冬を、ともにシチリア島ですごし、翌年春、あい前後して、海路パレスティナに向かった。
すでに一一八九年八月以降、現地フランク軍は、サラディンが守備隊をおいていたアッコンの町を奪いかえそうと、港の反対側にあたるツーロンの丘を基地として、攻囲陣を張っていた。
やがて「赤ひげ」王の残党も、これに加わった。
一方、サラディンは、東と南から、この攻囲陣を逆に包囲していた。長い攻囲にフランク勢はようやく疲れ、援軍の到着を待ちのぞんでいた。
そこへ「尊厳」王と「獅子心」王が到着した。役石機や鉤梯子など、新鋭の攻城機も加わった。
フランス、イギリスの艦隊は制海権をにぎり、海上から市内への補給路を断った。
攻囲陣突破をはかったサラディンの努力もむなしく、守備隊はついに降伏した。七月五日のことだった。かくてアッコンは、ふたたびフランク人のものとなった。
「尊厳」王フィリップはただちに帰国し、残った「獅子心」王リチャードは、サラディンとの協定を無視して、アッコン守備隊の捕虜二千七百人を処刑したのち、一路、イェルサレムへの道をいそいだ。
あいも変わらぬ十字軍士の残虐に、サうディンは怒った。
以後、一一九二年九月に停戦協定がむすばれるまでのあいだ、サラディンは、リチャードと各所に戦い、リチャード軍の重装騎兵隊と弓手隊の協働作戦に悩まされながらも、よくリチャードの動きを封じ、ついにイェルサレムの城壁には近づかせなかった。
サラディンは、ヤッファからティルスにかけてのパレスティナ沿海地域の支配と、聖都イェルサレムへの巡礼通行権とを、三年間にかぎり、フランク人にみとめた。
翌年サラディンは、ダマスクスで世を去り、「新」イェルサレム王国は、なお一世紀ほどのあいだ存続することになった。
だが、シリア、パレスティナにおける「フランク人」、西方キリスト教徒の脅威は、事実上、ここに消滅したのである。




















