別冊宝島、2014年発行。
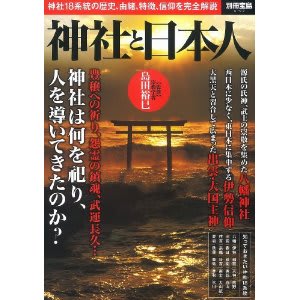
宗教学者の島田裕巳氏監修。
私にとってある意味「目から鱗が落ちる」内容で、想定外の収穫のあった本です。
神社には祀られている神様達がいます。
その神様達に、以前から私はある疑問を持ってきました。
「なぜ、『古事記』や『日本書紀』に出てくる神様ばかりなんだろう?」
もともと、神社はその土地の守り神である「産土神」を祀る場所であったはず。
田舎の小さな神社に「天照大神」とか「大国主命」などの天皇家の祖先神が祀られている違和感。
なので、私が好きな神社は、仏教や『古事記』『日本書紀』の影響を受けない産土神を祀る場所です。
滅多にお目にかかれませんが・・・。
島田氏がその理由を教えてくれました。
神様達は、皆明治時代に再編されたとのこと。
「明治になると神話を歴史的な事実としてとらえて、神話に登場する神様も重要なものと考えるようになるから、それまで各地域で祀られていた神様を、記紀に因んだ祭神置き換えていく作業が行われた。」
疑問が氷解するとともに、がっかりしました。
市町村統廃合による地名の喪失よりひどい。
明治時代に南方熊楠が「神社合祀反対運動」を繰り広げましたが、それ以前に神様のすり替えが行われていたとは・・・呆然。
<メモ>
自分自身のための備忘録。
■ 「磐座」(いわくら)
神道の一番古い信仰の形は、岩に神様が降りてくるというもの。そしてその岩そのものが、現在でも信仰の対象となっている。これを「磐座」と呼ぶ。
■ 神道の柔軟性
Q. 海外の場合、原始信仰の上にキリスト教が乗ったことで、実体が見えなくなった。しかし日本において、仏教と混ざりながらも原始信仰が現在まで残ってきたのはなぜか?
A. 神道には、開祖も教義も「ない宗教」であるがゆえに、仏教という「ある宗教」と衝突することがなかった。時代に応じて、状況に応じて融通無碍にその姿を変えていけるという、神道の性質そのものが存続した理由である。
■ 神社と記紀神話の神様
神社にとって、記紀神話の神様は、それほど重要なものではなかった。日本で一番数の多い八幡神社を見ても、八幡神は記紀神話とまったく関係ない。稲荷、天神も関係ない。
例えば、「祇園さん」で有名な京都の八坂神社の祭神は素戔嗚(すさのお)ということになっているが、もともとは牛頭天皇(ごずてんのう)という正体不明の神様を祀っていた。長野の諏訪大社ももともとはミシャグチ神という正体不明の神がいたのに、後に記紀の国譲り神話に因む建御名方(たけみなかた)という神が祀られたということになっている。
つまり、日本人は記紀神話に記載された神を祀ってきていなかったということになる。結局、記紀で体系化されている今の神社の世界を一度忘れないと、昔の姿はわからない。
明治時代になると神話を歴史的な事実としてとらえて、神話に登場する神様も重要なものと考えるようになるから、それまで各地域で祀られていた神様を、記紀にちなんだ祭神に置き換えていく作業が行われた。すでに置き換えから百数十年経っているので、みんな自分たちの神社の神様は昔からのものだと思っているけど、実際にはそんなに古いものではない。根本的に日本の宗教世界というものは、近世から近代にかけて偽造あるいは変容させられたのである。
その目的は、近代の日本国家において、国民全てが共通の「神話」をもった一つの民族であるというふうに統合するため。それ以前の日本は藩のゆるやかな集合体であり、それぞれの地域の神様を拝んでいた。そういう意味では、今、我々が知っている神社神道は、近代が生んだ「新宗教」である。
■ 日本の神社システムはコンピュータのクラウドに似ている
家の神棚にお札を祀れば、本来の神様と家の神棚はつながったということになる。
これは現代でいうと、コンピュータの「クラウド」の構造に近い。だからインターネットの論理で考えた方が、神道の論理はわかりやすい。
神を降ろすのはダウンロード、お札の更新はソフトのバージョンアップ、穢れや災難はウイルスだと考えればしっくりくる。
■ 神籬(ひもろぎ)と 磐境(いわさか)
神道の起源は縄文時代にまで遡るといわれる。
初期の神道では、自然の中でも異彩を放っている巨木や巨石を神の降りる「依代」として崇拝するようになったと考えられる。
このとき、巨木の代わりに榊などの樹木に神を降ろしたものを神籬、神を祀るための岩でできた祭場を磐境という。現在でも家やビルなどを建築する前には結界としてその中に簡単な祭壇を作り、地鎮祭を行うが、この祭壇が神籬である。
ちなみに磐境に似た言葉で「磐座」(いわくら)というものがある。厳密にいうと、神が直接降りる石を磐座といい、その磐座を中心とした祭祀場磐境と呼ぶようだ。
良くも悪くも神道には「実体」がない。さまざまなことを受け入れ、いかようにも姿を変えていく。それでいて、本質はまるで変えられることもない。
■ 稲と神道と天皇
日本は「豊葦原の瑞穂の国」だと『古事記』には書いてある。瑞穂は稲だから、日本は稲の国であり、国の繁栄が永遠に続くように神に祈り続ける役割を担った祭祀王、それが天皇ということになる。
神道では神への供物として食料が捧げられる。これを「神饌(しんせん)」というが、一般的には以下のようなものが品目として定められている。
「にきしめ(白米)・あらしめ(玄米)・酒・餅・海魚・川魚・野鳥・水鳥・海菜・野菜・果物・塩・水」
筆頭は米であり、いかに稲が重視されていたかがわかる。
現在でこそ日本は米余りだ。しかし、稲穂あふれる国はずっと日本人にとっての理想郷であり、夢の国だった。白い米を誰もが好きなだけ口にできるようになったのは比較的最近(せいぜい第二次世界大戦後)であり、日本の歴史全体から見ればわずかな期間でしかない。逆に言えば、神道が理想とする稲穂の国は、最近になってようやく実現したと云えるのかもしれない。
■ 神社の社はいつできたのか。
神籬(ひもろぎ)や磐座(いわくら)をルーツとするが、初期の神社は祭祀のたびに設けられるものであり、常設されるものではなかった。
宗像神社の沖津宮が置かれた沖の島(福岡県宗像市)の古代祭祀場跡が参考になる。祭祀は4世紀後半にはじまり、以後600年にもわたり神への祈りが捧げられてきたことが調査で判明しており、この遺跡をみれば4~10世紀の日本人の信仰形態が窺い知れる。
沖の島では島内で祭祀が行われた場所が時代と共に変化している。もともと神への祈り、祭祀は神が降りる巨大な岩(磐座)の上で行われていたのだが、時代と共に磐座の陰になり、ついには磐座から離れた露天で行われるようになる。その結果、最終的に神の降りる磐座と祭祀場は分離され、祈りのための社ー神社が人里に近い山の麓などに造られるようになったのではないか、と想像される。
一つの説として、神社の社は寺院建築の影響を受けて造られるようになったのではないか、というものがある。もしそうなら、神社の出現は仏教伝来(6世紀中頃)よりも確実に後ということになる。
仮に神社建築が仏教建築の影響を受けて始まったものだとしても、その後の発展過程では、意図的に神社側が仏教建築の特徴を排除しようとしたらしい。
■ 呪術としての神道
魏志倭人伝(魏の史書『魏志』の「倭人の条」)での記載。
倭国では、人が死ぬと喪に服して泣き、他の者は歌い踊って飲酒していた。その後、遺体は棺に納められ、土に埋められて塚が作られた。そして葬儀が終わると、人々は水に入って体を清めた。
これを読むと、基本的には後の土葬による葬儀の風景とあまり差はない。また、水に入って体を浄めるというのはいわゆる神道の禊ぎであり、今日の神道儀式につながる思想が既にあったことがうかがわれる。
呪術的な面では、倭の船が海を渡るときに「持衰」(じさい)という航海の無事を神に祈る生け贄を置いた記述もある。食事も肉は決して口にせず、ひたすら船の帰りを待つ。そして無事に船が帰ってくれば褒美が与えられ、不幸にも災難があれば殺されてしまう。
同書には卑弥呼が行った「鬼道」という言葉も出てくる。卑弥呼は生涯独身で、弟が彼女を助けていたとされ、女王になってからは彼女の姿を見た者はほとんどなく、一人の男子だけが給仕で出入りしていたと伝えられている。この形態から推測されるのは、卑弥呼が神に仕える巫女で、神の言葉を取り次ぐ役割を担っていた可能性がある。
神道には「亀卜(きぼく)」という占いが残されている。九州・対馬の雷(いかづち)神社では、現在でも亀の甲羅に焼けた棒を指し、一年の吉凶が占われている。これは中国の「令亀(れいき)の法」という、亀の甲を焼き、熱によってできる裂け目を見ることで吉凶を占う方法に由来する。
また、『古事記』には雄鹿の肩の骨(肩甲骨)を使った占いの記述も見られる。こちらは雄鹿の肩の骨を抜き、そこに波波迦(ははか)(朱桜)の枝を突き刺して占うもので、天皇家の伝統的な占いとされた。この方法は東アジア全般に広く見ることができる。
古代の日本には亀卜と鹿卜の二つの占い法が存在していたが、律令時代になってからは朝廷の役所である神祇官ではもっぱら亀卜のみが行われるようになった(『令義解(りょうのぎげ)』・・・『養老令』(757年)の注釈書)。そして驚いたことにこの亀卜は、現在でも天皇の即位式である大嘗祭において悠紀(ゆき)・主基(すき)の斎場を卜定する宮中祭祀の秘儀とされている。朝廷での亀卜は応仁の乱以降に急激に衰退し、本格的に復活したのは大正天皇の即位大典のときだったといわれている。
かつて、朝廷内に占いを専門とする役所「卜部(うらべ)」が置かれていた。もともとは諸国の神社に属していたが、なかには神祇官に所属する者もいた。その一部は役職を世襲するようになり、ついには「卜部氏」と称するようになっていく(例:吉田兼好の本名は卜部兼好)。興味深いのは、朝廷内に卜部氏が存在していたにもかかわらず、国家に関わる大きな占いでは、地方の神社からも人が集められていたことだ。『延喜式』には辺境であるはずの壱岐と対馬から3/4が集まられているところを見ると、いかに壱岐と対馬地方の卜部の力が優れていたかがわかる。
■ 分霊・勧請
神社は、もともとその土地の神様を祀る信仰から始まった。一般にいう「氏神」「鎮守の森」「産土神」と呼ばれる神々がそれで、神社は全てローカルな存在であった。
そのローカルな神々が全国展開するシステムが分霊(あるいは勧請)である。勧請とは神仏の来臨を請うことを意味し、神道・仏教のどちらでも用いられる。全国展開する契機はさまざまだ;
【八幡神】
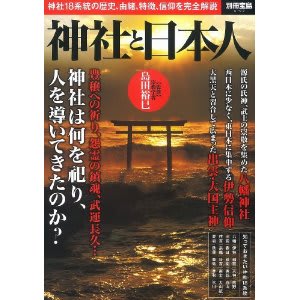
宗教学者の島田裕巳氏監修。
私にとってある意味「目から鱗が落ちる」内容で、想定外の収穫のあった本です。
神社には祀られている神様達がいます。
その神様達に、以前から私はある疑問を持ってきました。
「なぜ、『古事記』や『日本書紀』に出てくる神様ばかりなんだろう?」
もともと、神社はその土地の守り神である「産土神」を祀る場所であったはず。
田舎の小さな神社に「天照大神」とか「大国主命」などの天皇家の祖先神が祀られている違和感。
なので、私が好きな神社は、仏教や『古事記』『日本書紀』の影響を受けない産土神を祀る場所です。
滅多にお目にかかれませんが・・・。
島田氏がその理由を教えてくれました。
神様達は、皆明治時代に再編されたとのこと。
「明治になると神話を歴史的な事実としてとらえて、神話に登場する神様も重要なものと考えるようになるから、それまで各地域で祀られていた神様を、記紀に因んだ祭神置き換えていく作業が行われた。」
疑問が氷解するとともに、がっかりしました。
市町村統廃合による地名の喪失よりひどい。
明治時代に南方熊楠が「神社合祀反対運動」を繰り広げましたが、それ以前に神様のすり替えが行われていたとは・・・呆然。
<メモ>
自分自身のための備忘録。
■ 「磐座」(いわくら)
神道の一番古い信仰の形は、岩に神様が降りてくるというもの。そしてその岩そのものが、現在でも信仰の対象となっている。これを「磐座」と呼ぶ。
■ 神道の柔軟性
Q. 海外の場合、原始信仰の上にキリスト教が乗ったことで、実体が見えなくなった。しかし日本において、仏教と混ざりながらも原始信仰が現在まで残ってきたのはなぜか?
A. 神道には、開祖も教義も「ない宗教」であるがゆえに、仏教という「ある宗教」と衝突することがなかった。時代に応じて、状況に応じて融通無碍にその姿を変えていけるという、神道の性質そのものが存続した理由である。
■ 神社と記紀神話の神様
神社にとって、記紀神話の神様は、それほど重要なものではなかった。日本で一番数の多い八幡神社を見ても、八幡神は記紀神話とまったく関係ない。稲荷、天神も関係ない。
例えば、「祇園さん」で有名な京都の八坂神社の祭神は素戔嗚(すさのお)ということになっているが、もともとは牛頭天皇(ごずてんのう)という正体不明の神様を祀っていた。長野の諏訪大社ももともとはミシャグチ神という正体不明の神がいたのに、後に記紀の国譲り神話に因む建御名方(たけみなかた)という神が祀られたということになっている。
つまり、日本人は記紀神話に記載された神を祀ってきていなかったということになる。結局、記紀で体系化されている今の神社の世界を一度忘れないと、昔の姿はわからない。
明治時代になると神話を歴史的な事実としてとらえて、神話に登場する神様も重要なものと考えるようになるから、それまで各地域で祀られていた神様を、記紀にちなんだ祭神に置き換えていく作業が行われた。すでに置き換えから百数十年経っているので、みんな自分たちの神社の神様は昔からのものだと思っているけど、実際にはそんなに古いものではない。根本的に日本の宗教世界というものは、近世から近代にかけて偽造あるいは変容させられたのである。
その目的は、近代の日本国家において、国民全てが共通の「神話」をもった一つの民族であるというふうに統合するため。それ以前の日本は藩のゆるやかな集合体であり、それぞれの地域の神様を拝んでいた。そういう意味では、今、我々が知っている神社神道は、近代が生んだ「新宗教」である。
■ 日本の神社システムはコンピュータのクラウドに似ている
家の神棚にお札を祀れば、本来の神様と家の神棚はつながったということになる。
これは現代でいうと、コンピュータの「クラウド」の構造に近い。だからインターネットの論理で考えた方が、神道の論理はわかりやすい。
神を降ろすのはダウンロード、お札の更新はソフトのバージョンアップ、穢れや災難はウイルスだと考えればしっくりくる。
■ 神籬(ひもろぎ)と 磐境(いわさか)
神道の起源は縄文時代にまで遡るといわれる。
初期の神道では、自然の中でも異彩を放っている巨木や巨石を神の降りる「依代」として崇拝するようになったと考えられる。
このとき、巨木の代わりに榊などの樹木に神を降ろしたものを神籬、神を祀るための岩でできた祭場を磐境という。現在でも家やビルなどを建築する前には結界としてその中に簡単な祭壇を作り、地鎮祭を行うが、この祭壇が神籬である。
ちなみに磐境に似た言葉で「磐座」(いわくら)というものがある。厳密にいうと、神が直接降りる石を磐座といい、その磐座を中心とした祭祀場磐境と呼ぶようだ。
良くも悪くも神道には「実体」がない。さまざまなことを受け入れ、いかようにも姿を変えていく。それでいて、本質はまるで変えられることもない。
■ 稲と神道と天皇
日本は「豊葦原の瑞穂の国」だと『古事記』には書いてある。瑞穂は稲だから、日本は稲の国であり、国の繁栄が永遠に続くように神に祈り続ける役割を担った祭祀王、それが天皇ということになる。
神道では神への供物として食料が捧げられる。これを「神饌(しんせん)」というが、一般的には以下のようなものが品目として定められている。
「にきしめ(白米)・あらしめ(玄米)・酒・餅・海魚・川魚・野鳥・水鳥・海菜・野菜・果物・塩・水」
筆頭は米であり、いかに稲が重視されていたかがわかる。
現在でこそ日本は米余りだ。しかし、稲穂あふれる国はずっと日本人にとっての理想郷であり、夢の国だった。白い米を誰もが好きなだけ口にできるようになったのは比較的最近(せいぜい第二次世界大戦後)であり、日本の歴史全体から見ればわずかな期間でしかない。逆に言えば、神道が理想とする稲穂の国は、最近になってようやく実現したと云えるのかもしれない。
■ 神社の社はいつできたのか。
神籬(ひもろぎ)や磐座(いわくら)をルーツとするが、初期の神社は祭祀のたびに設けられるものであり、常設されるものではなかった。
宗像神社の沖津宮が置かれた沖の島(福岡県宗像市)の古代祭祀場跡が参考になる。祭祀は4世紀後半にはじまり、以後600年にもわたり神への祈りが捧げられてきたことが調査で判明しており、この遺跡をみれば4~10世紀の日本人の信仰形態が窺い知れる。
沖の島では島内で祭祀が行われた場所が時代と共に変化している。もともと神への祈り、祭祀は神が降りる巨大な岩(磐座)の上で行われていたのだが、時代と共に磐座の陰になり、ついには磐座から離れた露天で行われるようになる。その結果、最終的に神の降りる磐座と祭祀場は分離され、祈りのための社ー神社が人里に近い山の麓などに造られるようになったのではないか、と想像される。
一つの説として、神社の社は寺院建築の影響を受けて造られるようになったのではないか、というものがある。もしそうなら、神社の出現は仏教伝来(6世紀中頃)よりも確実に後ということになる。
仮に神社建築が仏教建築の影響を受けて始まったものだとしても、その後の発展過程では、意図的に神社側が仏教建築の特徴を排除しようとしたらしい。
■ 呪術としての神道
魏志倭人伝(魏の史書『魏志』の「倭人の条」)での記載。
倭国では、人が死ぬと喪に服して泣き、他の者は歌い踊って飲酒していた。その後、遺体は棺に納められ、土に埋められて塚が作られた。そして葬儀が終わると、人々は水に入って体を清めた。
これを読むと、基本的には後の土葬による葬儀の風景とあまり差はない。また、水に入って体を浄めるというのはいわゆる神道の禊ぎであり、今日の神道儀式につながる思想が既にあったことがうかがわれる。
呪術的な面では、倭の船が海を渡るときに「持衰」(じさい)という航海の無事を神に祈る生け贄を置いた記述もある。食事も肉は決して口にせず、ひたすら船の帰りを待つ。そして無事に船が帰ってくれば褒美が与えられ、不幸にも災難があれば殺されてしまう。
同書には卑弥呼が行った「鬼道」という言葉も出てくる。卑弥呼は生涯独身で、弟が彼女を助けていたとされ、女王になってからは彼女の姿を見た者はほとんどなく、一人の男子だけが給仕で出入りしていたと伝えられている。この形態から推測されるのは、卑弥呼が神に仕える巫女で、神の言葉を取り次ぐ役割を担っていた可能性がある。
神道には「亀卜(きぼく)」という占いが残されている。九州・対馬の雷(いかづち)神社では、現在でも亀の甲羅に焼けた棒を指し、一年の吉凶が占われている。これは中国の「令亀(れいき)の法」という、亀の甲を焼き、熱によってできる裂け目を見ることで吉凶を占う方法に由来する。
また、『古事記』には雄鹿の肩の骨(肩甲骨)を使った占いの記述も見られる。こちらは雄鹿の肩の骨を抜き、そこに波波迦(ははか)(朱桜)の枝を突き刺して占うもので、天皇家の伝統的な占いとされた。この方法は東アジア全般に広く見ることができる。
古代の日本には亀卜と鹿卜の二つの占い法が存在していたが、律令時代になってからは朝廷の役所である神祇官ではもっぱら亀卜のみが行われるようになった(『令義解(りょうのぎげ)』・・・『養老令』(757年)の注釈書)。そして驚いたことにこの亀卜は、現在でも天皇の即位式である大嘗祭において悠紀(ゆき)・主基(すき)の斎場を卜定する宮中祭祀の秘儀とされている。朝廷での亀卜は応仁の乱以降に急激に衰退し、本格的に復活したのは大正天皇の即位大典のときだったといわれている。
かつて、朝廷内に占いを専門とする役所「卜部(うらべ)」が置かれていた。もともとは諸国の神社に属していたが、なかには神祇官に所属する者もいた。その一部は役職を世襲するようになり、ついには「卜部氏」と称するようになっていく(例:吉田兼好の本名は卜部兼好)。興味深いのは、朝廷内に卜部氏が存在していたにもかかわらず、国家に関わる大きな占いでは、地方の神社からも人が集められていたことだ。『延喜式』には辺境であるはずの壱岐と対馬から3/4が集まられているところを見ると、いかに壱岐と対馬地方の卜部の力が優れていたかがわかる。
■ 分霊・勧請
神社は、もともとその土地の神様を祀る信仰から始まった。一般にいう「氏神」「鎮守の森」「産土神」と呼ばれる神々がそれで、神社は全てローカルな存在であった。
そのローカルな神々が全国展開するシステムが分霊(あるいは勧請)である。勧請とは神仏の来臨を請うことを意味し、神道・仏教のどちらでも用いられる。全国展開する契機はさまざまだ;
【八幡神】
















