-----参考文献-------------
1) ウィリアム・パウンドストーン;松浦俊輔(訳)『パラドックス大全-世にも不思議な逆説パズル-』青土社(2004/9/30) ISBN-10 479176143X
2) 富永裕久『図解雑学パラドクス(図解雑学シリーズ)』ナツメ社(2004/02) ISBN-10 4816336915
3) 戸田山和久 『科学哲学の冒険―サイエンスの目的と方法をさぐる(NHKブックス)』日本放送出版協会(2005/01) ISBN-10 4140910224
4) 英語版ウィキペディア、"Grue_and_bleen"、"Nelson_Goodman"
----------------------
前回の続きです。
ref-2ではグルーの定義は「それがグリーンであり人の目に触れているもの、あるいは、ブルーであり人の目に触れていないもの」です。この想定だと私は自然にパラドックスとして受け入れることができました。なぜかと考えてみると、3000年1月1日とか恣意的に選べるようなある時点で一斉にものごとが変化するのは不自然と感じても、人の目に触れたものが触れたことが原因で何らかの変化をするのは不自然ではないと感じたからだと思います。何しろ観測が対象を変化させてしまうことは、量子力学ではなくてもよくあることですから。ref-3では「グルーは途中でその言葉が当てはまるものが変わってしまう」という批判に対して「『子ども』という言葉もそうだ」との反論を挙げています。しかし、子供が大人になるのは一人一人の子供が誕生から一定期間経過した時にそれぞれに固有の時刻に変化するのであり(*1)、世界の全てが一斉に変化するのではありません。そして、それぞれの子供が大人になることには「誕生から一定期間経過した」というそれぞれに固有の【原因】が想定できるし、エメラルドが人の目に触れることで色が変化することにも「人の目に触れた」という固有の【原因】が想定できます。しかし3000年1月1日に世界の全てが一斉に変化することには特定の【原因】が想定できません。なぜ3000年1月3日ではなく3000年1月1日なのかという【理由】も想定できません。
しかしref-1の逆理とは異なる構造に見えるref-2の形の逆理も、ref-1に沿って展開したのと同じ構造として述べることができます。以下、表現は私流に変えています。
想定 グルーとは「それがグリーンであり人の目に触れているもの、およびブルーであり人の目に触れていないもの」である。ブリーンとは「それがブルーであり人の目に触れているもの、およびグリーンであり人の目に触れていないもの」である。
こう書くとグルーとブリーンがカテゴリーに分けるやり方の一つであり、ブルーとグリーンというカテゴリーに分けるやり方とは別のやり方であることがわかりやすいのではないでしょうか。そしてグルーブリーン語人の世界では全く対称的な想定がなされます。
想定 グリーンとは「それがグルーであり人の目に触れているもの、およびブリーンであり人の目に触れていないもの」である。ブルーとは「それがブリーンであり人の目に触れているもの、およびグルーであり人の目に触れていないもの」である。
以下、
1a) 今までに観察したエメラルドは全てグリーンだった。ゆえに、この箱の中のまだ人の目に触れていないエメラルドもグリーンに違いない。
1b) 今までに観察したエメラルドは全てグルーだった。ゆえに、この箱の中のまだ人の目に触れていないエメラルドもグルーに違いない。
2a) たいていの物質は人の目に触れようが触れまいが同じ色であり、エメラルドはそんな「たいていの物質」なのだから、まだ人の目に触れていないエメラルドもグリーンと推定するのが妥当だ。
2b) たいていの物質は人の目に触れようが触れまいが同じ色であり、エメラルドはそんな「たいていの物質」なのだから、まだ人の目に触れていないエメラルドもグルーと推定するのが妥当だ。
3a) まだ人の目に触れていないエメラルドの色に関するグルーブリーン語人の推定は我々の推定とは食い違う。彼らの言葉はおかしい。
3b) まだ人の目に触れていないエメラルドの色に関するグリーンブルー語人の推定は我々の推定とは食い違う。彼らの言葉はおかしい。
さて「まだ人の目に触れていないものの色」が食い違うことは英語人もグルーブリーン語人も永遠に確かめることはできません。人の目に触れたとたんに両者の見解は一致するのですから。この点で「3000年1月1日を境に変化する」という想定とは大きな違いが出てきます。後者の想定では3000年1月1日になった時に英語人かグルーブリーン語人かのどちらか、もしくは両者ともが何らかの矛盾に直面しますが、「まだ人の目に触れていないものの色」に関する想定では両者とも永遠に矛盾に直面することはありません。つまり永遠にパラドックスは生じません。
もちろん人の目に触れていないものの色を知る何らかの手段があれば別ですが、そんな手段はないというのがこの想定の本質のはずです。
ref-2では「ゆでた後でしか観測できないロブスター」を例示して、「人の目に触れているものが全て赤だったから触れていない時も赤だ、とは断定できない」と述べています。しかしそういう想定であれば、「それがグリーンであり人の目に触れているもの、あるいは、ブルーであり人の目に触れていないもの」であるグルーの他に「それがグリーンであり人の目に触れているもの、あるいは、グリーンであり人の目に触れていないもの」に該当する言葉も必要です。そもそも「ゆでたロブスター」は人の目に触れていなくても赤いし、「ゆでる前のロブスター」は人の目に触れていなくても赤くない、というのが正常な判断というものです。
とまあ、目に触れないバージョンでは逆説構成に適切じゃないね、みたいなことを書きましたが、実は03/21の記事に挙げたRef1の定義(日本語訳)では曖昧なのですが、英語版ウィキペディアなどの記載を見ると、グッドマンの本来の趣旨では観測されているかいないかが重要なのだとわかります。
「"X is grue" if X is green and was examined before time 't', or blue and was not examined before 't'.」
"and" ではなくて "or" なのです。時刻t以降に初めて観測された時にブルーのものがグルーなのです。時刻t以前に観測されたものは、既にグリーンかつグルーであり、時刻t以降もグリーンかつグルーのままであっても良いのです。03/21の記事では「【初めて観察された】という条件が重要かも知れない」と書きましたが、極めて重要でした。英語版ウィキペディアでは "and" バージョンとの違いの明確な説明がありますが、 "and" バージョンでは同一物体の観察結果が時刻tを境に変化してしまうのです。こうなるとref-1,ref-3の表現はグッドマン本来の趣旨とは異なると言わざるをえません。
10/05/29の記事へ続く
-----------
*1) 人間では子供と大人の境界時点は明確ではありませんが、例えば「日本の法律上の成人」とすれば境界時点は明確です。昔なら「元服した時点」でも良いし、ヒトではなく昆虫なら「さなぎになった時点」とか「羽化した時点」を考えれば良いのです。
1) ウィリアム・パウンドストーン;松浦俊輔(訳)『パラドックス大全-世にも不思議な逆説パズル-』青土社(2004/9/30) ISBN-10 479176143X
2) 富永裕久『図解雑学パラドクス(図解雑学シリーズ)』ナツメ社(2004/02) ISBN-10 4816336915
3) 戸田山和久 『科学哲学の冒険―サイエンスの目的と方法をさぐる(NHKブックス)』日本放送出版協会(2005/01) ISBN-10 4140910224
4) 英語版ウィキペディア、"Grue_and_bleen"、"Nelson_Goodman"
----------------------
前回の続きです。
ref-2ではグルーの定義は「それがグリーンであり人の目に触れているもの、あるいは、ブルーであり人の目に触れていないもの」です。この想定だと私は自然にパラドックスとして受け入れることができました。なぜかと考えてみると、3000年1月1日とか恣意的に選べるようなある時点で一斉にものごとが変化するのは不自然と感じても、人の目に触れたものが触れたことが原因で何らかの変化をするのは不自然ではないと感じたからだと思います。何しろ観測が対象を変化させてしまうことは、量子力学ではなくてもよくあることですから。ref-3では「グルーは途中でその言葉が当てはまるものが変わってしまう」という批判に対して「『子ども』という言葉もそうだ」との反論を挙げています。しかし、子供が大人になるのは一人一人の子供が誕生から一定期間経過した時にそれぞれに固有の時刻に変化するのであり(*1)、世界の全てが一斉に変化するのではありません。そして、それぞれの子供が大人になることには「誕生から一定期間経過した」というそれぞれに固有の【原因】が想定できるし、エメラルドが人の目に触れることで色が変化することにも「人の目に触れた」という固有の【原因】が想定できます。しかし3000年1月1日に世界の全てが一斉に変化することには特定の【原因】が想定できません。なぜ3000年1月3日ではなく3000年1月1日なのかという【理由】も想定できません。
しかしref-1の逆理とは異なる構造に見えるref-2の形の逆理も、ref-1に沿って展開したのと同じ構造として述べることができます。以下、表現は私流に変えています。
想定 グルーとは「それがグリーンであり人の目に触れているもの、およびブルーであり人の目に触れていないもの」である。ブリーンとは「それがブルーであり人の目に触れているもの、およびグリーンであり人の目に触れていないもの」である。
こう書くとグルーとブリーンがカテゴリーに分けるやり方の一つであり、ブルーとグリーンというカテゴリーに分けるやり方とは別のやり方であることがわかりやすいのではないでしょうか。そしてグルーブリーン語人の世界では全く対称的な想定がなされます。
想定 グリーンとは「それがグルーであり人の目に触れているもの、およびブリーンであり人の目に触れていないもの」である。ブルーとは「それがブリーンであり人の目に触れているもの、およびグルーであり人の目に触れていないもの」である。
以下、
1a) 今までに観察したエメラルドは全てグリーンだった。ゆえに、この箱の中のまだ人の目に触れていないエメラルドもグリーンに違いない。
1b) 今までに観察したエメラルドは全てグルーだった。ゆえに、この箱の中のまだ人の目に触れていないエメラルドもグルーに違いない。
2a) たいていの物質は人の目に触れようが触れまいが同じ色であり、エメラルドはそんな「たいていの物質」なのだから、まだ人の目に触れていないエメラルドもグリーンと推定するのが妥当だ。
2b) たいていの物質は人の目に触れようが触れまいが同じ色であり、エメラルドはそんな「たいていの物質」なのだから、まだ人の目に触れていないエメラルドもグルーと推定するのが妥当だ。
3a) まだ人の目に触れていないエメラルドの色に関するグルーブリーン語人の推定は我々の推定とは食い違う。彼らの言葉はおかしい。
3b) まだ人の目に触れていないエメラルドの色に関するグリーンブルー語人の推定は我々の推定とは食い違う。彼らの言葉はおかしい。
さて「まだ人の目に触れていないものの色」が食い違うことは英語人もグルーブリーン語人も永遠に確かめることはできません。人の目に触れたとたんに両者の見解は一致するのですから。この点で「3000年1月1日を境に変化する」という想定とは大きな違いが出てきます。後者の想定では3000年1月1日になった時に英語人かグルーブリーン語人かのどちらか、もしくは両者ともが何らかの矛盾に直面しますが、「まだ人の目に触れていないものの色」に関する想定では両者とも永遠に矛盾に直面することはありません。つまり永遠にパラドックスは生じません。
もちろん人の目に触れていないものの色を知る何らかの手段があれば別ですが、そんな手段はないというのがこの想定の本質のはずです。
ref-2では「ゆでた後でしか観測できないロブスター」を例示して、「人の目に触れているものが全て赤だったから触れていない時も赤だ、とは断定できない」と述べています。しかしそういう想定であれば、「それがグリーンであり人の目に触れているもの、あるいは、ブルーであり人の目に触れていないもの」であるグルーの他に「それがグリーンであり人の目に触れているもの、あるいは、グリーンであり人の目に触れていないもの」に該当する言葉も必要です。そもそも「ゆでたロブスター」は人の目に触れていなくても赤いし、「ゆでる前のロブスター」は人の目に触れていなくても赤くない、というのが正常な判断というものです。
とまあ、目に触れないバージョンでは逆説構成に適切じゃないね、みたいなことを書きましたが、実は03/21の記事に挙げたRef1の定義(日本語訳)では曖昧なのですが、英語版ウィキペディアなどの記載を見ると、グッドマンの本来の趣旨では観測されているかいないかが重要なのだとわかります。
「"X is grue" if X is green and was examined before time 't', or blue and was not examined before 't'.」
"and" ではなくて "or" なのです。時刻t以降に初めて観測された時にブルーのものがグルーなのです。時刻t以前に観測されたものは、既にグリーンかつグルーであり、時刻t以降もグリーンかつグルーのままであっても良いのです。03/21の記事では「【初めて観察された】という条件が重要かも知れない」と書きましたが、極めて重要でした。英語版ウィキペディアでは "and" バージョンとの違いの明確な説明がありますが、 "and" バージョンでは同一物体の観察結果が時刻tを境に変化してしまうのです。こうなるとref-1,ref-3の表現はグッドマン本来の趣旨とは異なると言わざるをえません。
10/05/29の記事へ続く
-----------
*1) 人間では子供と大人の境界時点は明確ではありませんが、例えば「日本の法律上の成人」とすれば境界時点は明確です。昔なら「元服した時点」でも良いし、ヒトではなく昆虫なら「さなぎになった時点」とか「羽化した時点」を考えれば良いのです。










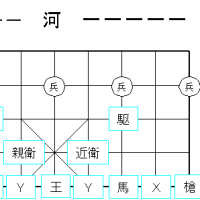
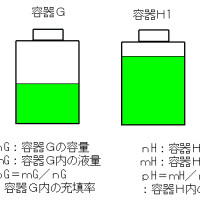
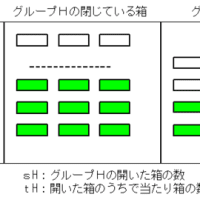
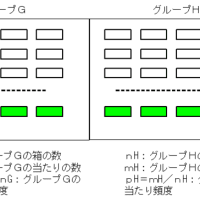
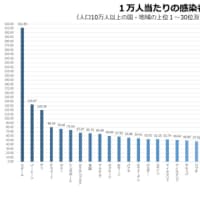
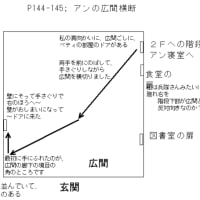
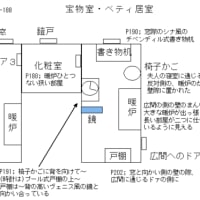
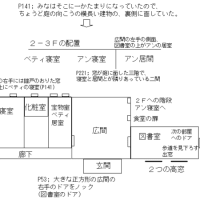
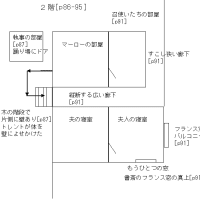
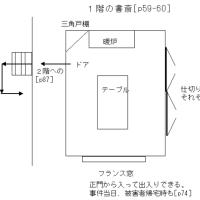






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます