![]() 本作品、~青春うたものがたりシリーズ~「生きる力」は、私の妻が38歳という若さで癌(乳がん)にかかり、その癌というとてつもない巨悪な病魔と戦う現実の姿を、ほとんど実話に近い形で書いているものです。それだけに、本作品が本当に人の生きることや命の大切さの意味を訴えているのを、よくみなさんにご理解していただいているのか、本作品が、小説や音楽、ドラマetcのジャンルを越えて、今凄い多くのみなさんに読まれていることが分かりました。本作品、~青春うたものがたりシリーズ~「生きる力」が、何故?そんなに人の心を魅了し感動を与えるのか!ぜひあなた自身もその目とその心で直接確かめてみてください。
本作品、~青春うたものがたりシリーズ~「生きる力」は、私の妻が38歳という若さで癌(乳がん)にかかり、その癌というとてつもない巨悪な病魔と戦う現実の姿を、ほとんど実話に近い形で書いているものです。それだけに、本作品が本当に人の生きることや命の大切さの意味を訴えているのを、よくみなさんにご理解していただいているのか、本作品が、小説や音楽、ドラマetcのジャンルを越えて、今凄い多くのみなさんに読まれていることが分かりました。本作品、~青春うたものがたりシリーズ~「生きる力」が、何故?そんなに人の心を魅了し感動を与えるのか!ぜひあなた自身もその目とその心で直接確かめてみてください。
「家族ってなんだろう?」 そんな疑問に悩み苦しんで
いつも孤独と不安におののきながら 死ぬことさえも考えた僕だった
だけど、そんな孤独と不安の中で もがき苦しむ僕に優しく手をさしのべて
愛ある温もりと生きる勇気を与えてくれて 僕を救ってくれたのは家族だった
だからもう過去を振り返って 人生の道に立ち止まりメソメソ泣くのはやめよう
だからもう心に鍵を掛けて 今の生活(くらし)から逃げ出すのはやめよう
僕にはこの世で一番 僕を愛してくれる 家族がいるから・・・・・
(14)
いくら、“マザー・テレサ”との本の出会いで生きる光明を得たと言っても、いちど狂ってしまった人間の人生の運命が、そう簡単に修正できるはずがなかった。
そして、月日が経つのは早いもので、もうかれこれ家族と離散して暮らすようになってから、三年近くが経っていた。
ただ、家族に見放されて独りぼっちになり、生きることを含めて人生の何もかにも嫌になって、自分が生活していくための仕事でさえ探そうとはせずに、一日中外出することすらも億劫に感じて家の中でゴロゴロしながら、事あるごとに生きることより死ぬことばかりを考えて毎日を送っていたときとは違い、少しずつではあるがすべての物事をポジティブに考えられるようになっていた。
そして、これまでに比べるとかなり規模的に小さい会社で安い給料だったが、つい最近まで親兄弟に迷惑を掛けて、すべての生活の面倒を見てもらっていたものを、きちんとした職が見つかって働けるようになるまでに立ち直れたことで、なんとか一人立して自活できるようにまでにはなっていた。
だが、まだ正直に言って、家族みんなを呼び戻して生活できるような収入を得る身分までには、復帰できていなかった。
そんな中、いくら病気〔乳がん〕とはいえ、自分を見捨てて実家に子供をつれて帰ってしまった、妻の愛美から一通の手紙が届いた。
愛美に対しては、心のどこかに“自分が見捨てられた・・・”という憎しみが、まだ何だかんだとすべてを吹っ切ることが出来ずに残っていたが、でもいざ子供のことになると話は別問題だった。
愛美から来た手紙は、次のような内容のものだった。
大沢拓也様
前略
もう早いもので、家族がばらばらになってくらすようになってから、三年の月日が経ちました。今さら、こういうことを言っても信じてもらえないかもしれませんが、私も、あなたを一人取り残して実家に帰るときには、正直にいうとかなり悩みました。しかし、父(新三郎)に“病気に一番良くないのは、病気以外の生活面や仕事面のことなどで、必要以外の精神的に圧迫を受けることだ・・・”だと強引に説得されたことと、いつ命を奪われるかもしれない癌という病気への恐怖心から、父の意見に従って実家に帰り、宮崎の大学病院で治療を受けることを決意しました。
ただしかし、私の病気もだいぶ良くなりましたので、今はまた一日でも早く家族みんなが、同じ屋根の下で暮らせるようになるのを願っているのも事実です。その話とは別になりますが、今回突然手紙を書かせてもらったのは、だんだんと健太が年齢と共に、自分自身で物事の判断をするようになった機に、父に反抗的な態度を取るようになったからです。それは、健太に対して “お父さんのように家族も守れないような男になりたくなかったら、地元の中学を出たら、少年自衛隊に入隊して給料を貰いながら、高校に通うのが一番安定している道だから・・・」と言って、自分が自衛隊員だったこともあり、何か事あるごとに強引に説得するようになった父も悪いのですが・・・。そのせいで、今では毎日のように家族中での喧嘩が絶えなくなるし、健太と父の二人の憎しみ合いの間で板ばさみになって、もう私の手ではどうしようもなくなっています。そして、このまま二人の問題を放っておいたら、将来的には健太が父に反抗して、何か悪い道にでも入ってしまうのではないかと思い、心配でたまりません。つきましては、この問題を解決するためには、健太が希望しているように彼をあなたに引き取ってもらって、東京の中学校に通わせる以外に方法がないと思っています。何卒、本件につきましてご理解いただき、健太の将来のためにも、彼の希望を叶えてあげていただきますよう、どうぞよろしくお願いします。
草々
平成14年10月25日
大沢愛里
ただ、いずれにしても現在の拓也一人の手ではどうすることも出来ないのは分っていたために、次女で外資系の一流金融会社で働いているで、次女の寿代に相談するしかなかった。(父の歳三が亡くなったときの葬儀を取り仕切りや、ちょうどそのとき失業中の長女郁恵一家の東京から種子島までの交通費や宿泊費を全額負担し、歳三の葬儀に呼んであげたのもそうだが、今回の愛美たちが彼を見捨てて家を出て行った後の、すべての物事に対してネガティブな考え方しか持つことが出来ずに、精神安定剤(躁鬱)の薬だけに頼って悩み苦しんで、日ごとすさんだ生活を送り続けている彼を、常に励ましてすべての面度を見てくれて、彼が立ち直るきっかけを作ってくれたのも彼女だった。おそらく、そう考えると、もし寿代という姉の存在がなかったら、もう拓也自身がこの世でこうして存在していることがなかったことだけは確かだろう。)
寿代との相談の結果、彼女がこれまで住んでいた1LKのマンションを引き払い、拓也たち家族が住んでいたマンションに移り住み、これまで二家族分支払っていた家賃を切り詰めて、息子の健太を東京の中学校に通わせることが決まった。
そして、寿代が自分の住んでいるマンションを引き払って、拓也たち家族が住んでいるマンションに移り住むことを決意したのには、それ他にはもうひとつの理由があった。
それは、健太が以前のように東京に移り住んで、こっちの中学校に通うことになると、いずれは長女の舞も東京に帰ってくることが予想されたからである。
そうなった場合は、いくら寿代が外資系の一流金融会社で働いていて、それなりの給料を貰っているとはいえ、いずれは拓也がもっと今より大きな会社に就職して高い給料をもらえるようにならない限り、現在の寿代の生活に支障が出て来ることが分かっていたからである。
そうこうしているうち、月日の経つのは早いもので息子の健太が冬休みを利用して、中学受験のための塾に通うために上京することになった。
そのときのことを思いのままに、日記代わりの大学ノートに書いたのが、下記の作品である。
「息子」
ピンポーン。
「あっ!けん坊だ。」
けん坊が帰ってきた。
最初に顔を合わせた瞬間には、どんな顔をして、どんな言葉を掛けてやろうか。
頭の中では、色んな想像を思い巡らし、けん坊を迎える準備をしていたつもりだった。
それがいざ現実になると、つい慌てしまってそう上手くいかないものである。
それもそうかもしれない。
それは、三年ぶりの再開だからだった。
僕が突然リストラされて職を失い、家族が一緒に暮らせなくなってから、もうはや三年の歳月が経っていた。
その間色々なことがあった。
父が死んだ。
妻が病気(乳がん)になった。
家族が家族でなくなった。
僕は僕の非力さを恨んだ。
学歴なさを恨んだ。
社会を恨んだ。
それでも恨みたりずに、四十歳が近い年齢だというのに馬鹿げたことだが、貧しい家に生まれたことまで恨んだ。
僕は泣いた。
暗闇の中で泣いた。
独りぼっちで泣いた。
それは、僕の周囲から昨日まであった、家族の温もりがすべて消えたからである。
―ガチャ・・・―
ドアを開けると、けん坊が立っていた。
十二歳になったけん坊が立っていた。
三年前に分かれたときには、百二十センチそこそこだったけん坊が、百五十センチ超える大男になって立っていた。
親子なのに、年月と時間の空白が、やはりお互いの心のどこかに壁を作るのだろうか?
最初は、三十センチもない距離の間にいるのに、二人とも声を掛けられずに、ただ黙って見つめ合っていた。
一分。二分。三分・・・
「ただいま」けん坊が、笑顔で言ったそのひと言が、これまでの年月と時間を飛び越えて、僕をかつてと同じように父親に戻してくれた。
僕は泣いた。
自分と同じくらいの背丈になった、けん坊を強く抱きしめて泣いた。
ふと顔を見たら、けん坊の目にも涙が光っていた。
―カキーン―
「かんぱ~い」
けん坊が笑ってる。
僕が笑ってる。
冷凍物の寿司と飲み物(ビールとジュース)で祝う、二千円足らずの歓迎会だった。
だけど、今の未だに仕事が決まっていない僕にとっては、これが精一杯のけん坊にしてやれる、ご馳走であり歓迎会だった。
「ごめんね・・・」と、心の中で詫びる。
それでも、けん坊が喜んでくれている。
それでも、けん坊が僕を訪ねて来てくれた。
久しぶりに、僕に家族の温もりを届けてくれた、けん坊に感謝。
パパから”お父さん”と呼ぶようになり、一回り大きくなったけん坊に感激・・・
久しぶりにけん坊と弾む会話の最中に、「ここに、お母さんとお姉ちゃんがいたら、もっとよかったね・・・」という、けん坊の口から何気なく出た言葉が、僕に父親としての責任を、いや人間としての責任を再認識させた。
その瞬間、この“家族”という温もりを手に入れられるのなら、もう過去のプライドなんてどうでもいいと思った。
けん坊が帰る。
まだ薄暗い、人気がない裏道を帰る。
リュックを背負って、一人で帰る。
母と姉が待つ、家族のもとへ帰る。
父が欠けた、家族のもとへ帰る。
僕は黙って、その後姿を見てる。
声も掛けずに、ただ黙って見てる。
あっ、けん坊が振り向いた。
笑った。
手を振った。
僕も思わず、けん坊の釣られるように笑った。
手を振った。
そして、手を振りながら、ふとこの子たちと本当の家族に戻れるのは、いつの日だろうと心に思った・・・・・











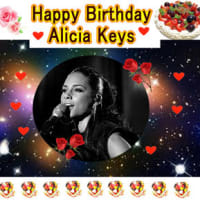


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます