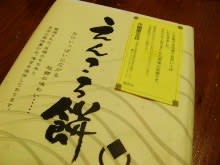震災時の暮らしが落ち着きはじめ、あちこちの様子を確認して歩いて、ようやく宮城の最南端である山元町へ行くことができたのは、震災から8ヶ月ほど過ぎた頃だった。
2011年11月、海側の道は片づけで通れそうにない。
陸前浜街道(国道6号線)から様子を見た。
道路はうねっていたが、津波の被害はこの道から東側で止まっている。
海沿いに連なっていた緑が、すっかり欠けてしまって海が見える。
1階が空洞になるほど壊れている民家が、所々に残っていた。
そうした家々の人々が、「どうか無事でありますように」と祈りながら眺める。
被災地を巡る時は、いつもそうだ。心の中で語る。
失った人々に、どうか苦しかった時に縛られず、楽しかった時を思い出して安らぐように。
生き残った人々に、どうかよりよき再出発ができるように。
ただし、暗い顔ばかりせず、笑顔も見せながら通る。
和楽を忘れないことが、今を生き、明日を生きる力だから。
そんな思いを、汲み取るかのような人々がいる。
山元町役場に寄ると、そこには、いち早く地元に情報を届けようと出来た、仮設のラジオ局があった。
「りんごラジオ」だ。
必要な情報はもちろん、人々が生きることに明るさを見出せるようにという願いを、日々、町の人々へ届けている。
外から手を振った。
向こうも、笑顔で返してくれた。
役場の敷地内には、もうひとつ、写真を拾い集めて修復保存する場も設けられていた。
情報の発信と、市民のこれからを支える場所として、役場が使われていた。
町の人々が、少し落ち着きを取り戻した様子で通り過ぎる。
震災の春から、日々は過ぎ、季節は冬に近づいていた頃。
坂元小学校では子ども達の笑い声も聞こえ、今を明日を、大切にしている輝きを見た。
掲載写真:2011年11月8日撮影