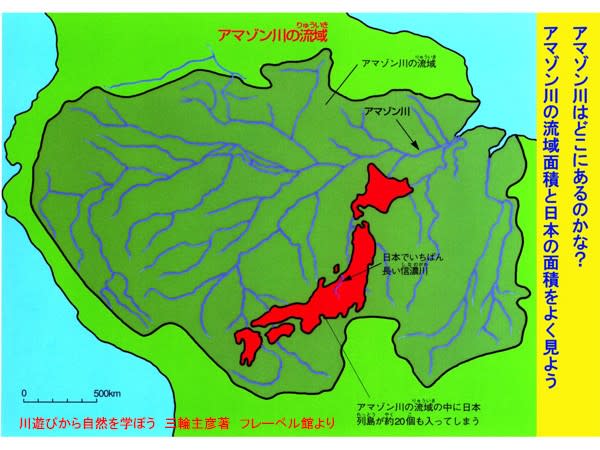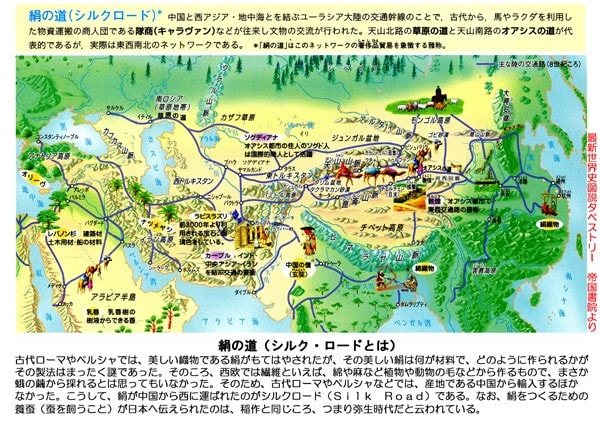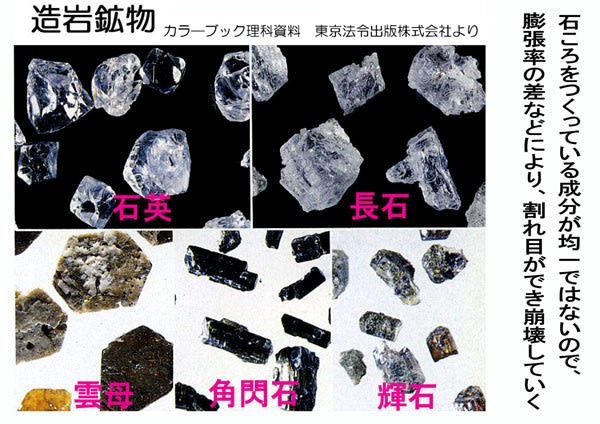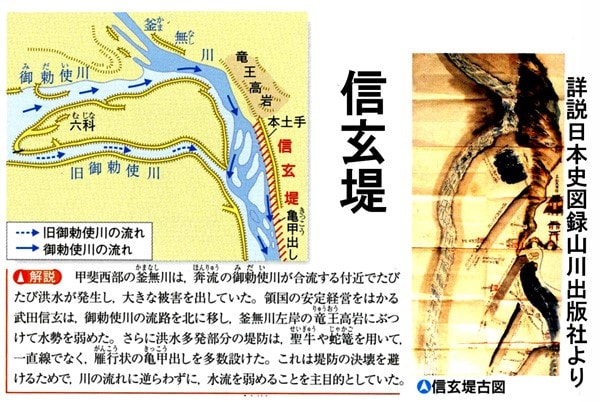「『学体力』指導が成立しない環境」を憂える①
今週の写真は今年の赤目渓流教室のスナップです。
ファーブル先生の学体力
「学体力」とは、もう十五年以上前に作った「造語」です。
塾を開設し子どもたちの『学力』にふれ、指導経験を積みながら学習指導法を考えはじめて、学力や学習指導以前に考えなければいけない材料・条件がたくさんあることがわかりました。そして、それらが等閑視されたままでは、いつまでたっても肝心の学力問題が解決するはずがないこともわかってきたのです。
なかでも、「学力」とはまったく別に考えるべき、「学力」を論じるうえでもっともたいせつといってもよい「学体力」の重要性です。「学習することを自らの人生や生活に欠かせないものとして認識し、積極的に学習に向かう力」、「学習過程の困難を乗り越える(られる)力」です。
以前ファーブルの弟への手紙を引用したとき、ファーブルが弟を鼓舞していた一節は、いわば「学習する際の学体力の必要性」です。自ら教員生活をしながら自学した経験をもとに、同じ境遇に悩む弟にアドバイスを贈っています。引用が長文になりますが、「学体力」の展開と、そのしくみのより深い理解に供するため、ご寛容に願います。
はたして彼はどんな方法で代数や化学を修得したのだろうか。その秘訣は?
ファーブルはのちに、そのことを弟にわかりやすく報告している。当時、弟は兄の後から同じ道をたどり、教職についていた。(ファーブルの生涯 C・V・ルグロ著 平野威馬雄訳 ちくま文庫 p41)
「なにかこまることがあっても、けっして他人の力を借りてはいけない。はたのものから助力を受けたのでは、けっして難問は解けないばかりではなく、困難はまた、ちがったかたちでおまえを苦しめるだけだ。大切なことはじっと耐えしのぶこと。そして自分で考えること。さらに、みずからすすんで学びとろうとすること・・・・・・。これほど役に立つことはない。これが理解への遠くて近い道なのだ」(同書 p42 下線は南淵)
「・・・私はこれだけは忠告しておく。それは特に科学に関しては観察が第一、絶対にほかのものにたよってはならないことだ。一冊の科学書は、これから解かねばならない“なぞ”なのだ。その解明のキーを他人にもらったら、たちまちに解けるだろうが、なんのプラスにもならない。もしも第二のなぞが出てきたらどうする? いぜんとして最初のなぞにぶつかったときと同様、手も足も出ないだろう。それは第一のなぞが、他人の助言でかんたんに解けてしまったからだ。自分の力で解こうとしなかったから進歩がないのだ」(同書p42~43)

自力で問題解決を図ることの利点と有効性、つまり定義する「学体力」の必要性です。赤貧の彼が苦学して教員資格を取り、子どもたちを教える道に邁進すべく努力を積み重ねていたとき。未熟な自らの「学体力」を、まず鼓舞していました。
師範学校を卒業したとき、私の数学の知識などじつに貧弱なものであった。せいぜいのところ、平方根を引き出したり、球の面積(原文まま)を証明しながら計算したりすることが、私にとって、この学科の絶頂点であった。偶然、対数表を開いたとき、あの、数字を積み上げたおそろしい表は私にめまいをおこさせた。尊敬まじりの恐怖から、わたしはこの「計算」の前で立ちすくんだ。(同書 p40)

経済的事情で満足に教育を受けられなかったファーブルは、必要とする勉強をほとんどすべて、『学体力』を駆使して自ら克服していきます。ちなみに、これらの学体力はファーブルの場合は教員としての学習でしたが、どんな職業であろうと、真摯に仕事に対して向かう姿勢については大差ないと思います。「学体力」とは、社会で生きる以上、万人に必要とされる力です。
どんな状況から、彼は学習を始めたのか。次です。
代数についていうと、なんの知識ももっていなかった。ただ、『代数』という名称だけは聞き知っていた。だが、その話を聞いただけで、頭の中はモヤモヤしてきて、やたらにむずかしいことだという恐怖がわいてくる・・・・・。そして、とても近づきがたいもののような気がするのだ。そんなむずかしいものにはいっさい手をふれるのもいやだった。(同書p41)

この一節を読む人はすべて、自らの学習経験を顧みれば、同感の記憶があるだろうし、世の中のあらゆる落ちこぼれ君が、おそらく大同小異の状況であろうということが、はっきり想像できるだろうと思います。つまり、こうした状況から脱出できるか否かが、学体力やモチベーションの存在によって決定される、ということなのです。学力が身につくかどうか、基本の力です。「学力!」と単純にひとくくりにはできません。
「学習困難児」や「勉強に身を入れないという学習問題」の原因解明と解決が、こうした視点をとれば、いかに(社会にとって)おおきな意味をもっているか、理解できるのではないでしょうか。見方によれば、それらの方法の現実化で、ファーブルのような偉人が何人も生まれるかもしれません。ぼくたちが相手をしているのは、教員免許をもつようになった大人ではなく、可能性あふれる子どもなのですから。
受験塾や予備校の、中身のあまりない宣伝文句に目くらましされ、自らの子どもたちの現状や問題点を正視せず、解明できない状況が相変わらず続いているのではないでしょうか。それでは、ファーブルの場合は、この「危機!」をどう乗り越えられたのか。続きです。

それは食わず嫌いのようなもの、いや食べたこともないのに、栄養満点だとほめあげる不消化な食べ物のようだった。だが、とにかく、私は泣いても笑ってもあとには引けない。代数という学科の担任教師にさせられてしまったのだから。(同書p41)
この一節を読むと、ファーブルは代数の教師にさせられたので仕方なく勉強を始めなければならなかった(!)と誤解を生むかもしれません。しかし、彼の『学体力』の支えは、そんな下世話で打算的なものではありません。学体力を支えるものは生徒たちへの愛そのものだったのです。

わたしの生徒の多くは、いずれもいなかからやってきている。彼らは早晩、いなかへ帰っていくのだ。そして、大地をたがやし、耕作に没頭するのだ。だから、自分の土地がなんでできているのか、そして植物はなんで栄養をとっているかを教えてやらなければならない。
また、ほかの生徒たちは工業方面の仕事につくだろう。また、なめし革の職人になったり、鋳金の仕事につく者もいるだろう。さらには、アルコールの蒸留工や、石鹸やイワシの樽漬けをあきなう者もいるだろう。そんな連中には、樽漬けの魚粕(魚肥)や石鹸や蒸留道具やタンニンや金属類についてひととおりのことを教えてやろう。(同書p40)

ファーブルのこれらの一節を前後させ、こう読みとったとき、彼がどういう思いをもって学体力を鼓舞したのか、よくわかります。自らの『学力不足』を、「教える生徒に対する『愛』」で補っていたのです。愛が彼の教員時代の学体力に大きなエネルギーをもたらしていました。子どもたちの指導にたいせつなことは、何よりも「子どもたちの将来を見つめる目」と「愛」だと改めて自戒しました。
ファーブルの時代と現代を同一視することはできませんが、小学校の一部科目に専門指導の先生が動員されているようです。よかれと、あるいは必要性や要請があった結果でしょうが、そうして単純に分化・専任することが、果たして子どもたちの『学体力』を養成するための良い方向かどうか、ぼくは疑問視しています。
さらに、ファーブルはひとりで学び、引用のようなさまざまな学科や子どもたちへの職業指導に従事できたことを思うとき、はたして現代の方向性はどうなのか? 一部でも専任に任せてしまうことは、当然のことながら、自らの指導力不足を招いてしまう可能性があります。立体授業の指導スライドやテキストを作成しながら、そうした方向性は逆方向ではないのか。分断によって、指導者自らが環境をとらえる目が『曇らないのか?』 そう危惧します。
可能性にあふれた小学生の学体力の発現・環覚の養成を目指すとすれば、ファインマンのお父さんやエジソンのお母さんの指導例を見ても、環境を総合的にとらえる視点が、より子どもたちがおもしろく興味を広げる、理にかなっている方向ではないのか。
ファーブルのように、専門知識とはいわないまでも、バランスの良い「環(!)性」をもっている先生(指導者)が必要なのではないか。そう思えてなりません。

そういえば、以前紹介した灘中の橋本先生の「銀の匙」指導も、腱鞘炎を発症するまで、そうした総合的な方向性を狙い、子どもたちに受け入れられ、成長してからも教え子たちに高い能力と強烈な印象を残していました。参考の余地ありだと考えます。
さて、ファーブルの学体力を顧みて思うのは、かつて「寺子屋」で学んだ子どもたちの学体力です。彼らの存在はファーブルの時代の子どもたちを彷彿させます。
意識の高さ
学ぶことに対する「意識の高さ」とは? これは「向上する心」、「向上したい心」といってよいと思います。
江戸時代に「寺小屋」があれほど広まった理由は、商業経済の浸透による「読み・書き・そろばん」の必要性が実感されたからではないのか? 「字も読めない、計算もできない、字も書けない」では、商業化する社会に適応できません。生活(自立)・生きていくことに対する自他共の「意識の高さ」が必要です。子どもたちがあれほど集まったのは、「学習の必要性」からです。
この必要性は、「学ぶこと」が生活や将来に直接かかわるもの(と感じられるもの)だったからでしょう。現代の「よい学校に入りたい」という目的とは、大きく異なります。「もっと生活と切り離せない切実感」があったはずです。
「読み、書き、計算」ができるというようなことは、(厳しくレベルを問わなければ)誰でもでき、当たり前すぎて、現代では仕事に即適応できる、というような条件ではありません。また、よい学校に入ったからと云って、それが生活を保証してくれる絶対条件ではありません。
江戸時代の「読み書きそろばん」に匹敵する職業上の必要性は、現代ではもっと高度な専門知識や技術の習得がそれらにあたるでしょう。しかし、職業の雑多な混在や拡散が目標や目的を見えにくくし、その高度性がさらにそれらに対する学習の必要性を感じなく(!)させているわけです。そこが問題です。
職業(生きていく手段)に関係なく学習しなければならないとすれば、それに代わる必要性がなければなりません。つまり、子どもたちが「学習したくなる」条件が「別に」必要になります。それがないと、「あえて」勉強する必要は見つかりません。現在のように、学校はたくさんあっても、寺子屋に子どもたちがたくさん集ったようにはいかないでしょう。必要がなければ、「元来怠け者の人間」は勉強しません。
学ぶ必要性が見つからなければ、それに代わるモチベーションがなければ、学体力は身につかず機能しません。受験はどう考えても一過性で、一生の学体力の必要性の補完はできません。
そこで、頼りになる、学体力定着へのもう一つの、というより最大のモチベーションは「学ぶおもしろさの獲得」です。即ち「学ぶことがおもしろい」という状況をいかにつくりあげるか。その時、その大きなきっかけになってくれるのが「環覚」だと、ぼくは思います。
日々生活している「生活空間」のなかで、学習対象や学習内容、つまり自らの生活空間を「学習内容的側面」から見直す、そのなりたちとしくみを究めていく、という行動や姿勢が「学ぶおもしろさ」を大きく引き寄せてくれると思います。
学習(「した」あるいは「する」)内容が生活や生きていく上で、実は身近なこと・欠かせないものだとわかったとき、学習は『異次元』の存在ではなくなります。ファインマンが幼い頃、お父さんに周囲の事象についてさまざまなレクチュアを受け、世界を探求するおもしろさに目覚めたように。逆に、受験に出てくるもの・試験のためのものという意識から抜けられなければ、永遠に学習は人生のパートナーにならないでしょう。
ファインマンの場合は、日常生活や生活環境がミラクル・ワールドに変わったのです。それを知りたいから調べる・学ぶ・考えるという経過をたどりました。そこには当然それらにかかわる学習内容や学習事項の習得も伴ったはずです。ファインマンら科学者に限らず、心の底から知りたいことが現れれば、そういう経緯をたどります。そして、科学者になったファインマンは、こんな感じでした。
「ブラックホール」という名高い用語の発案者でもあり、学生時代のファインマンの指導に当たったジョン・ホイーラーは、「大学に学生がいるから先生連中が学生に教えられるってことはあるもんだが、中でもファインマンは最高の学生のひとりだったね。ひょんな巡り合わせで、わたしが彼の指導を任されることになった。単に数学の経験を積んだだけの多くの人には欠けているものを彼は持っていたんだ。世界を物理的に見るという直観だ」("No Ordinary Genius" Christopher Sykes / W・W・NORTON p44・拙訳)
超天才ファインマンの誕生です。
生活をする上での必要性や学ぶおもしろさの追求も結局、日々に流されない「意識の高さである」ということもできます。裏にあるものは生命や寿命の一回性の確認です。
日常性だからといって、すべて単なる物知りで終わるわけではありません。何気ないものに目を留めてこそ、そこから科学の大発見も生まれます。ガリレイ・ニュートン・アインシュタインなど、すべてその結果です。
興味の対象・学習経験が増えていくにつれ、相互の関連により、さらなる高みや深みに足を踏み入れることができ、おもしろさが増してゆく。その過程では、もはや煩わしい計算や予備知識の習得が苦にならない、当然のことと考えるようになる、という姿が学体力の定着だと考えています。