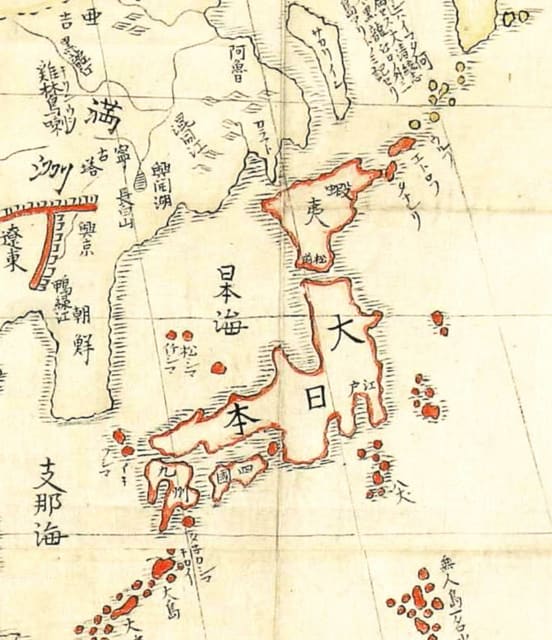〇東京都大田区 厳定院(ごんじょういん)
〒146-0082 東京都大田区池上2-10-12
[縁起]
正応2年(1289)本門寺2世日朗聖人の直弟子、厳定院日尊聖人が開創。天文5年(1536)西谷の西之院のとなりにあった成就坊と合併、現在地に堂宇を構えたと伝えられる。成就坊の境内にあった弁財天を池上七福神として石造りの弁天宮にお祀りしている。大正9年(1920)厳定院40世 山田潮栄上人が「子育て鬼子母神」を勧請し、昭和6年(1931)本門寺総門前に別院として鬼子母神堂が建立された。
[住職からのメッセージ]
境内に弁天さまを御祀りしています。どうぞご自由に御参拝下さい。おひとりでも多くの方との御縁を結ぶ事ができます様、お待ちしています。
正応2年(1289)本門寺2世日朗聖人の直弟子、厳定院日尊聖人が開創。天文5年(1536)西谷の西之院のとなりにあった成就坊と合併、現在地に堂宇を構えたと伝えられる。成就坊の境内にあった弁財天を池上七福神として石造りの弁天宮にお祀りしている。大正9年(1920)厳定院40世 山田潮栄上人が「子育て鬼子母神」を勧請し、昭和6年(1931)本門寺総門前に別院として鬼子母神堂が建立された。
[住職からのメッセージ]
境内に弁天さまを御祀りしています。どうぞご自由に御参拝下さい。おひとりでも多くの方との御縁を結ぶ事ができます様、お待ちしています。
〇嚴定院の歴史
大正十二年九月、関東大震災により本堂、庫裡が崩壊し、過去帳を除いて古文書、諸記録の一切を消散してしまいましたが、昭和六十二年、東京都指定文化財である本門寺多宝塔の調査に関連して、その裏山が発掘調査され、そこから発掘された題目板碑により、当山の寺歴が明らかになりました。
板碑には成就院日尊上人の名と宝徳三壬申年(1451年)の年号が刻まれており、この頃(室町時代初期)の古図に「厳成院」として記されていることから、当山の開創がその頃にさかのぼることは確かで、あわせて過去帳をたどると初祖日尊上人以来、中興二十一世禅定院日逞(享保八年)、さらに近来の中興ト仰がれる四十世久成院日芳上人(大正五年)を経て現在まで、連綿として法灯が継承されてきたことがわかります。
板碑には成就院日尊上人の名と宝徳三壬申年(1451年)の年号が刻まれており、この頃(室町時代初期)の古図に「厳成院」として記されていることから、当山の開創がその頃にさかのぼることは確かで、あわせて過去帳をたどると初祖日尊上人以来、中興二十一世禅定院日逞(享保八年)、さらに近来の中興ト仰がれる四十世久成院日芳上人(大正五年)を経て現在まで、連綿として法灯が継承されてきたことがわかります。
なお、この板碑は縁泥片岩製で高さ46cm、幅16cm 、 厚さ2cm 、 造立当時は題目と両尊の名に金箔がほどこされたことがうかがえ、しかもその形をほぼ完全にとどめており、文化財としての価値も大きいところから、現在本門寺の霊宝殿に格護されています。
〇池上七福神、慧光弁財天
かって当山には蓮華ヶ池があり、季節には見事な蓮が咲き誇り参詣の人々の目を楽しませましたが、周辺の住宅事情から次第に水が枯れはじめ、昭和三十六年無水状態となり、現在は境内にある祠に慧光弁財天が安置されています。
〇しだれ梅

〇池上七福神の弁才天を祀っています。しだれ梅が見頃を迎えていました。
https://www.ensenji.or.jp/blog/13761/
https://www.ensenji.or.jp/blog/13761/



今は二十四節気の雨水、桜、池上本門寺総門、Risoni
https://blog.goo.ne.jp/globalstandard_ieee/e/108fb9e2833e5e1b06e69afe179d6482
https://blog.goo.ne.jp/globalstandard_ieee/e/108fb9e2833e5e1b06e69afe179d6482
今は二十四節気の雨水、桜、池上本門寺の石段、池上本門寺総門、こんなところにCafe、養源寺柔心地蔵尊、六地蔵尊巡り
https://blog.goo.ne.jp/globalstandard_ieee/e/be630e6219b9b8c2c94108d39e38c65e