生産能力10倍 「石油」つくる藻類、日本で有望株発見
藻類に「石油」を作らせる研究で、筑波大のチームが従来より
10倍以上も油の生産能力が高いタイプを沖縄の海で発見した。
チームは工業利用に向けて特許を申請している。
将来は燃料油としての利用が期待され、資源小国の日本に
とって朗報となりそうだ。
茨城県で開かれた国際会議で14日に発表した。
筑波大の渡邉信教授、彼谷邦光特任教授らの研究チーム。
海水や泥の中などにすむ「オーランチオキトリウム」という
単細胞の藻類に注目し、東京湾やベトナムの海などで計150株
を採った。これらの性質を調べたところ、沖縄の海で採れた株が
極めて高い油の生産能力を持つことが分かった。
球形で直径は5~15マイクロメートル
(マイクロは100万分の1)。水中の有機物をもとに、
化石燃料の重油に相当する炭化水素を作り、細胞内にため込む
性質がある。同じ温度条件で培養すると、これまで有望だと
されていた藻類のボトリオコッカスに比べて、10~12倍
の量の炭化水素を作ることが分かった。
研究チームの試算では、深さ1メートルのプールで培養
すれば面積1ヘクタールあたり年間約1万トン作り出せる。
「国内の耕作放棄地などを利用して生産施設を約2万ヘクタール
にすれば、日本の石油輸入量に匹敵する生産量になる」としている。
炭化水素をつくる藻類は複数の種類が知られているが生産効率
の低さが課題だった。
渡邉教授は「大規模なプラントで大量培養すれば、自動車の
燃料用に1リットル50円以下で供給できるようになるだろう」
と話している。
また、この藻類は水中の有機物を吸収して増殖するため、
生活排水などを浄化しながら油を生産するプラントをつくる
一石二鳥の構想もある。
(15日朝日新聞より引用させていただきました)
>>これは…実用化できれば、日本にとっては、正に“悲願”が
叶う快挙。
(まだまだ、工業化プラント等の技術的なハードルがあるので
しょうが、それも予算次第かと。)
『石油の一滴は血の一滴』(第一次大戦時の仏・クレマンソー首相
が米国へ石油供給を要請する電報の言葉)
そして、日本でも…主に石油資源の供給を止められたため、
あの戦争に走りざるを得ませんでした。
現在、石油から原子力ほかへのエネルギーの転換を図っているとは
いえ、まだまだ石油資源依存しなければならないのが現実。
この100年、戦争を含めて、散々苦労してきた“石油”問題が
解決できるということは、日本にとって、本当の未来、21世紀
が到来することを意味します。
日本が本当に豊かになれるのか?
それは、この技術を徹底的に守り、育てていけるか?にかかって
いるのかもしれません。
『友愛』などという、世界から見れば、只の『お人よしの馬鹿』
で、この技術を外国に【只同然】で供与などということが
無い様に、しっかり見守っていかなければいけません。
(特に現政権が“中国”や“韓国”に譲り渡すようなことが
無いように…)
レキのニュース・スクラップ
▼ 関連ブログ(ランキング)を表示します。クリックお願いします!



藻類に「石油」を作らせる研究で、筑波大のチームが従来より
10倍以上も油の生産能力が高いタイプを沖縄の海で発見した。
チームは工業利用に向けて特許を申請している。
将来は燃料油としての利用が期待され、資源小国の日本に
とって朗報となりそうだ。
茨城県で開かれた国際会議で14日に発表した。
筑波大の渡邉信教授、彼谷邦光特任教授らの研究チーム。
海水や泥の中などにすむ「オーランチオキトリウム」という
単細胞の藻類に注目し、東京湾やベトナムの海などで計150株
を採った。これらの性質を調べたところ、沖縄の海で採れた株が
極めて高い油の生産能力を持つことが分かった。
球形で直径は5~15マイクロメートル
(マイクロは100万分の1)。水中の有機物をもとに、
化石燃料の重油に相当する炭化水素を作り、細胞内にため込む
性質がある。同じ温度条件で培養すると、これまで有望だと
されていた藻類のボトリオコッカスに比べて、10~12倍
の量の炭化水素を作ることが分かった。
研究チームの試算では、深さ1メートルのプールで培養
すれば面積1ヘクタールあたり年間約1万トン作り出せる。
「国内の耕作放棄地などを利用して生産施設を約2万ヘクタール
にすれば、日本の石油輸入量に匹敵する生産量になる」としている。
炭化水素をつくる藻類は複数の種類が知られているが生産効率
の低さが課題だった。
渡邉教授は「大規模なプラントで大量培養すれば、自動車の
燃料用に1リットル50円以下で供給できるようになるだろう」
と話している。
また、この藻類は水中の有機物を吸収して増殖するため、
生活排水などを浄化しながら油を生産するプラントをつくる
一石二鳥の構想もある。
(15日朝日新聞より引用させていただきました)
>>これは…実用化できれば、日本にとっては、正に“悲願”が
叶う快挙。
(まだまだ、工業化プラント等の技術的なハードルがあるので
しょうが、それも予算次第かと。)
『石油の一滴は血の一滴』(第一次大戦時の仏・クレマンソー首相
が米国へ石油供給を要請する電報の言葉)
そして、日本でも…主に石油資源の供給を止められたため、
あの戦争に走りざるを得ませんでした。
現在、石油から原子力ほかへのエネルギーの転換を図っているとは
いえ、まだまだ石油資源依存しなければならないのが現実。
この100年、戦争を含めて、散々苦労してきた“石油”問題が
解決できるということは、日本にとって、本当の未来、21世紀
が到来することを意味します。
日本が本当に豊かになれるのか?
それは、この技術を徹底的に守り、育てていけるか?にかかって
いるのかもしれません。
『友愛』などという、世界から見れば、只の『お人よしの馬鹿』
で、この技術を外国に【只同然】で供与などということが
無い様に、しっかり見守っていかなければいけません。
(特に現政権が“中国”や“韓国”に譲り渡すようなことが
無いように…)
レキのニュース・スクラップ
▼ 関連ブログ(ランキング)を表示します。クリックお願いします!











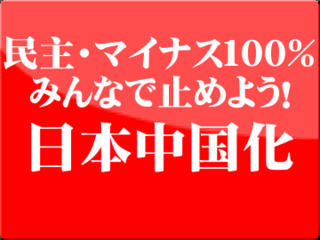
 ea
ea