
今回は、JR七尾線金丸駅すぐに鎮座する鎌宮諏訪神社の紹介です。
この神社の特徴は、いわゆる拝殿や本殿が無く玉垣に囲まれた神域に生える二本のタブノキが御神体の原始信仰が残る神社です。
また、毎年8月27日 執り行われる特殊神事“鎌打ち神事”は、長野県諏訪地方で執り行われる“薙鎌打ち神事”と同様に興味深い共通項があります。
(以下は、Microsoft Copilotで生成したAIに加筆)

ここは、社殿や本殿が存在しません。境内には玉垣で囲まれたご神域があります。その中に御神体として「タブの木」が祀られています。

境内の一画の覆屋に申し訳程度に拝所が設けられていました。

御神木のタブノキ 手前の切株はかつてのご神木と思われますが新芽が出ていました。
祭祀:建御名方命
由緒:
由緒案内(写真クリックで拡大)
祭神 建御名方命は、大己貴命(大国主命 の別名)のみ子神で、大己貴命、少彦名命 の二神と力をあわせ、邑知潟に住む毒蛇 化鳥を退治、能登の国平定の神功をたてられた。
おすわまつりと呼ぶ祭典が、毎年七月 二十七日(今は八月)に行われ、日足鎌とも左鎌とも呼ぶ二丁の鎌に、稲穂と白木綿 をつけ、古来、鎌宮洲端名神風祭と呼びき たった風祭を行い祭典後その鎌を神木に 打ちつける。
この鎌は諏訪の薙鎌ともいって、外に刃が向っており、暴風よけ雷よけ辰巻よけとして神木の高所に打ちつける。なお金丸鎌祭は中昔まで参指人は遠近より鎌を持って群集し「鎌の舞」を演じたという。
「俗に「二十七日お諏訪の祭、雨が降らねば 風が吹く」と伝えられている。
鹿西町教育委員会 鹿西町文化敗審議会
(案内板より書き起こし)

ここでは、特殊神事として毎年8月27日に“鎌打ち神事”と言う神事が執り行われています。

「日足鎌(左鎌)」とも呼ばれる2丁の鎌を御神木のタブの木に打ち込む神事です。この神事は神代の頃、大名持命(おおなもちのみこと)と少名彦命が能登を平定した折、諏訪神社の祭神である建御名方命が鎌で草木を払って先導し、害虫や害鳥(毒蛇や化鳥と言う記述もあり)を退治した故事にちなみます。

真新しい鎌

打ち込んだ鎌は木の成長とともに埋まってしまい、こぶになっています。
興味深いのは、同様の神事が長野県の諏訪地方に伝わっています。
薙鎌打ち神事:諏訪大社の御柱祭の前年にあたる丑年に、信越国境にある「中股小倉明神」と「戸土境の宮」のご神木に交互に打ち込む神事です。

薙鎌(なぎかま)鶏のトサカのような形をした諏訪明神の神器のひとつです。

御神木に打ち込まれた薙鎌(再現)
(写真:神長官守屋資料館で撮影)
WEB上でこの神事の紹介記事には、諏訪神の信州開拓の象徴、また「なぎ」が「凪ぐ」に通じることから風雨鎮護、諸難薙ぎ祓うの意味との記述が多いのですが、興味深い内容の記事がありましたので、関連リンクより一部引用します。
御柱の見立ては2回あります。御柱祭の 2 年前に仮見立て、前年に本見立て。本見立 てが最終決定に当たる神事で、選んだ8本の木に宮司さんが薙鎌を打ち込みます。 薙鎌を打つことによって山の木が神の木になるんだと言う人もいますね。神の木として山 を降らせるにあたり、山の木を鎮めて、災いがないようにということで薙鎌を打つと私たち は聞いています。 以前は打ち込んだ薙鎌は伐採の時まで木にそのままにしてあったそうですが、現在は本見 立てが終わるといったん外して持ち帰るようになっています。
☞関連リンク:
鎌宮諏訪神社で執り行われているこの神事は諏訪信仰の特色を伝えるものとして、昭和35年に町の文化財に、平成4年に石川県の無形民俗文化財に指定されています。
どのような経緯で、諏訪の神事がここに伝わってきたのか興味のあるところです。文献調査などを続けてまた何か分かりましたら、ご報告したいと思います。
【マップ】





















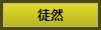



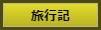
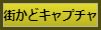

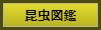


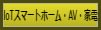

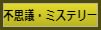
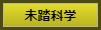
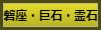


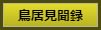
次回も楽しみにしてます。
おっしゃるとおり全く同じ神事が、どのような経緯でここ石川県で伝えられたのか?興味があるところです。
考えたら、先にこちらで行われたいたものが、諏訪へ伝わったのかも知れませんね。
また何か分かりましたらご報告させて頂きますね。