
伊香保から峠を越えて、漫画「イニシャルD」の 聖地(秋名 下りのスタート地点)を過ぎた県道33号(メロディーライン)を榛名富士~榛名湖へ向かう途中、左手に異様な岩山が見えて来ます。
そこが今回の目的地「スルス岩」です。

ここだけの岩塊が遠くからでも目立ちます。

駐車場に車を置き沼ノ原の木道(ゆうすげの道)散策路を歩いて行きます。

榛名富士(1,391m)

相馬山(1,411m)

右手にスルス岩が見えて来ました。先着数名現在登山中のようです。

スルス岩は、磨墨岩と書きます。もちろん(磨墨=するすみ)からの当て字ですが“スルス”とは地元の言葉で粉を挽く石臼の事だそうです。形が似ているところからついたそうですが…。

案内はありますが途中相馬山への分岐があったり少々分かりくいので注意が必要です。

眼の前に見えて参りました。

いきなりの鉄梯子です。昇りは余裕ですが下りは眼下に断崖絶壁の箇所があるので、結構スリル感があります。なるべく下を見ないようにして降りましょう。

岩の上に到着です。周囲は絶景ですが…。ビビりのため景色の写真を撮り忘れていました。(^^;

頂上には、烏天狗の彫像が祀られていました。
榛名山とは、カルデラ湖の榛名湖を中心とした外輪山“榛名富士、相馬山、烏帽子岳、二ツ岳、三ツ峰山、蛇ヶ岳、水沢山、天目山”の総称で山自体が御神体の山岳信仰の地であり、天狗信仰の山でもあります。
榛名山には、昔から伝わる天狗伝説もあります。
榛名の天狗が、天界の神さまと競い合い
榛名富士をもっと大きくしようとして、
大地を掘って、山の上にどんどん積んでゆき
これは神様に勝てそうだなぁと、山に腰掛け休んでいたら
夜が明けてしまい、神通力が切れてしまった。
勝負は神さまの勝ち。
あ〜あ、ちぇ!と最後に積んだ山がヒトモッコ山で、
掘り下げた時に出来たのが、後の榛名湖になった
神さまが天狗と競って出来たのが、富士山だと言われている
下山後は、スルス岩の麓にある行人洞へと移動しました。

行人洞 スルス岩の麓にあります。

スルス岩の背面となるでしょうか。

「相馬山百回登山 善光院 豊山行者之霊」と、ありました。

こちらはお不動様でしょうか?

岩屋内には、石像が三体祀られています。

左側に祀られている石像 右手に徳利(酒)と左手に盃を持っています。

中央に祀られている石像 右手に槍(杖?)と左手に巻物?を持っています。

右側に祀られてる石像 左肩に担いでいるのは槍でしょうか?
それぞれ三体の石像が何なのかは知識が無いので分かりませんが見た目からそれ程古いものでは無さそうです。

岩の表面には先刻画も描かれています。「陰陽学士 小野関三太夫清繁」 と、言う人物が彫ったと署名がありました。この人物ちょっと調べてみたらここ榛名村周辺に彼の残した仏画や漢詩?が、数か所点在しているようです。雨乞いに関連しているんだとか。

親分業?下 霊山過去七 佛相俱還白 是人間達彼 岸脱得濁世 七苦難
(読める人 教えて下さい <(_ _)>)

線刻仏画部分のアップ
スルス岩へは、沼ノ原の木道遊歩道より30分ほどで登れますが途中鉄梯子など危険な箇所があります。充分注意して散策ください。
(撮影日:2007-5)
お断り:2007年当時の情報となります。当時とは異なる事が想定されますので訪れる際には、事前に調べて頂き記事は参考程度とお考え下さい。
お断り:2007年当時の情報となります。当時とは異なる事が想定されますので訪れる際には、事前に調べて頂き記事は参考程度とお考え下さい。
【マップ】




















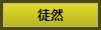



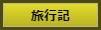
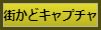

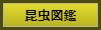


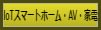

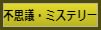
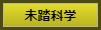
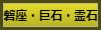


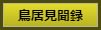
「行人堂」は不動明王もいらっしゃるので修験道の跡でしょうか。金錫を持っている岩屋内の石仏は、役小角でしょうか?
面白そうな岩場です。
金錫と巻物を持っている石造は役行者ですか!
そうなるとやはりここは、修験道で修業に使われていたお堂っていう事ですね。
そういえば、よく覚えていませんが洞内は手彫りっぽい感じでした。
と、言うかもともとあった岩屋を拡張したっていう感じだった記憶が残っています。