
諏訪地方には以前も記事にした「諏訪七石」という巨石に纏わる信仰と「諏訪七木」というやはり巨木に纏わる信仰が存在しています。
いずれも諏訪地方ならではのアミニズム信仰でその起源は、縄文まで遡る事が出来ます。
そんな巨木信仰と深い関わりのあるのが諏訪の古くからの地主神「洩矢神」と深いつながりを持つ「ミシャクジ信仰」です。
諏訪には“社宮司”と名が付く神社が多く存在するのはそんな理由からです。
「ミシャクジ」の祀られている多くの場所には必ず古樹が茂り、その木の根本には祠があって、御神体として石棒や石などが祀られています。
「ミシャクジ」は、湛木(たたえぎ)を伝って降りてきて、御神体である石棒や石に宿ると伝えられ諏訪に七ヵ所ある湛木は、以下の通りです。
(※「湛(え)」とは神使いが村から村を回り、湛の巨木の下で神事を行うこと。)
- 桜湛木(さくらのたたえぎ)(茅野市玉川粟沢天白社境内 )
- 柳湛木(やなぎのたたえぎ)(茅野市本町の石田・竹村両氏の祝神様の近くの田圃)
- 桧湛木(ひのきのたたえぎ)(茅野市玉川神之原七社明神社 境内)
- 橡木湛木(とちのきのたたえぎ)(本稿記事 諏訪郡原村室内 闢盧社 )
- 檀湛木(まゆみたたえのき)(諏訪市湖南真志野)
- 松湛木(まつのたたえぎ)(諏訪市中洲神宮寺宮田渡 )
- 峯湛木(みねのたたえぎ)(茅野市宮川小町屋 )
そんな諏訪の湛木の七木のうちのひとつがここ諏訪郡原村室内に鎮座する「闢盧社(あきほしゃ)」です。

石鳥居
 拝殿 この拝殿は昭和55年に諏訪大社下社の宝殿を移築したものなのだそうです。
拝殿 この拝殿は昭和55年に諏訪大社下社の宝殿を移築したものなのだそうです。 本殿は拝殿からも外からも確認出来ません。諏訪大社上社の御射山祭の際執り行われる神事に垣間見られるだけのようです。
本殿は拝殿からも外からも確認出来ません。諏訪大社上社の御射山祭の際執り行われる神事に垣間見られるだけのようです。祭祀:保食神(うけもちのみこと)

現在の御神木

隣に枯れた古い切株がありましたが、たぶんこれが御狩神事で使われた「橡木湛木」だと思います。傍らに石もありますし。
なんて事は無い狭い境内ではありますが、ここでミシャグチの神降ろし神事が執り行われていた事を創造したら背筋がピンと伸び空気がツーンと張りつめた感じが致しました。
今も、拝殿内には湛木の断片が、大切に保存されていると言った情報もありました。
これを機会にいずれ「諏訪七木」巡りをしてみたいと思った次第です。
☞参考サイト:
【マップ】





















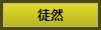



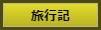
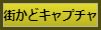

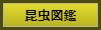


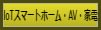

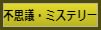
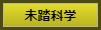
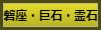


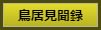
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます