『フィナンシャル・タイムズ』の英語の現状そして未来に関する記事です。記録しておきましょう。
**********
英語とは誰の言葉か 形を変え続けて広まる英語――フィナンシャル・タイムズ(1)(フィナンシャル・タイムズ) - goo ニュース
2007年11月30日(金)23:15
(フィナンシャル・タイムズ 2007年11月8日初出 翻訳gooニュース) マイケル・スカピンカー
テレビニュースの元アンカーマンで韓国大統領候補の鄭東泳(チョン・ドンヨン)氏は支持率で遅れをとっているかもしれないが、選挙公約にはかなり目を引くものがある。大統領に当選した場合、韓国の若者が英語を学ぶためにわざわざ外国に行かなくてもいいように、国内の英語教育を充実させるつもりだというのだ。英字紙「コリア・タイムズ」は、「英語を学ぶために、家族が離れ離れになる問題を解決する」必要があると、鄭氏がコメントしたと伝えている。
中国では、ユー・ミンホン(マイケル・ユー)氏が創設した英語スクール・受験塾、新東方教育科技集団(ニューオリエンタル・エデュケーション・アンド・テクノロジーグループ)が、国内最大手となった。昨年度の学生数は100万人以上。ほとんどが英語を勉強している。南米チリでは、次世代までに全国民が英語とスペイン語のバイリンガルになるよう目指すというのが、政府方針だ。
世界中でいったい何人が英語を学んでいるのか、誰もはっきりとは把握できていない。英国の公的な国際文化交流機関ブリティッシュ・カウンシルは10年前、10億人ぐらいではないかと見ていた。同カウンシルが昨年発表した報告書「English Next(次は英語)」では、今から10~15年後ごろに、英語学習者は20億人でピークに達するのではないかと見ている。
では、現時点ですでに英語を話す人は世界で何人ぐらいいるのだろう? 英語についての世界的な権威で、100冊以上の著作も発表している言語学者デビッド・クリスタル教授によると、世界中で約15億人(地球人口の約4分の1)がまあまあそれなりに英語で意思疎通できるのではないかという。
かつて広大な地域で共通言語として使われていたのは、ラテン語だった。しかしそれは欧州と北アフリカ限定。今の英語のようにこれほど広い地域でひとつの言語が使われたことは、人類史上かつてなかった。何百万もの人が英語を勉強する理由は簡単だ。国際ビジネスの言葉は英語。よって富を得るための手段が英語なのだ。マイクロソフトやグーグルやボーダフォンがビジネスに英語を使っているから、だけではない。中国人がブラジル人と話す時、ドイツ人がインドネシア人と話す時、そういう時に使うのが、英語だからだ。
英語が世界中に広まったこの物語は、北アメリカ、ブリテン諸島、オーストラレシアに住むネイティブ・スピーカーたちの勝利だ——と解釈したくなる気持ちも分かるが、それは間違いだ。「English Next」の筆者デビッド・グラドル氏は、こう指摘する。グローバル英語は最早もっと複雑な段階に入っている。英語は世界中でどんどん変化していて、古くから英語を使っている国々はその変化の仕方をコントロールもできないし、変化の仕方が必ずしも気に入らないかもしれないのだ。
グローバル英語について論じる人たちは主に、3つの論点を挙げる。第一に、いま利用者が急増しつつある北京語やスペイン語、あるいはアラビア語に、英語がとって代わられることはあるだろうか? 第二に、英語が世界各地に広まり、地元の言語の影響を受けるのに伴い、どう変化していくのか? ラテン語がイタリア語とフランス語に変容していったように、枝分かれしてそれ自体は消滅するのか。それともドイツ語がオランダ語とスウェーデン語を生み出したように、それ自体も残りつつ新しい言語を派生させるのか。第三に、もし英語がこのまま「どこでも通じる」という共通性を特徴として残すとして、その「共通する英語」とは、古くから英語を使っている国々の英語になるのか、それともこれまでの英語とは違う新しい英語になるのか?
英語ではない別の言葉が世界言語になる。これは全くありえない話ではないと、グラドル氏。約50年前には、英語を母国語にする人数は、北京語に次いで多かった。しかし今日では、スペイン語を母国語とする人数も、ヒンディー・ウルドゥー語を母国語にする人数も、英語なみの数になっている。21世紀半ばまでに、英語を第一言語とする人数はアラビア語にも抜かれ、第5位に後退しているかもしれないのだ。
中には、英語にはそもそも有利な条件が備わっているから、英語は生き延びるという人もいる。有利な条件とはつまり、覚えやすい、という。三人称単数現在形にやっかいな「s」がつくのを別にすれば(例「She runs」)、誰が主語だろうと動詞は変化しない(I run, You run, They run; We ran, He ran, They ran)。定冠詞・不定冠詞は名詞の性別によって変化しないので(the actor, the actress; a bull, a cow)、ほかのヨーロッパ言語のように「テーブル」は女性名詞なのか男性名詞なのか、覚えておく必要もない。
しかしその一方で、英語にも覚えにくい要素はいくらでもある。よく似た句動詞の細かな違いを説明するのは大変だ。たとえば「I stood up to him」と「I stood him up」の違いとか(訳注・前者は「私は彼に立ち向かった」。後者は「私は彼をすっぽかした」)。
英語は簡単だから世界言語になった——というこの説を、クリスタル氏は一蹴する。昨年発表した論文で同氏は、ラテン語は文法的にきわめて複雑だったけれどもそれでも広く普及したと指摘している。「ある言語が世界共通語になる理由は、その言語そのものの構造とは無関係だ。世界共通語になる理由は、その言葉を使う人たちの強さと関係している」。「太陽の沈むことなき」と言われるまで勢力圏を広げた大英帝国は、その太陽の沈まない国々にあまねく英語を広めた。
そしてその大英帝国が衰退した後も、アメリカが経済や文化に多大な影響力をもったおかげで、英語の圧倒的な地位は守れられてきた。
ということは、中国の台頭によって北京語がいずれは世界共通語になるのだろうか? あり得ることだ。「数千年前にさかのぼってみれば、いったい誰が、ラテン語がこんなに衰退すると予想できただろう?」とクリスタル氏。とはいえ現時点では、中国語が英語にとって代わりそうには見えない。中国の人たちはこぞって英語を勉強しているからだ。
英語が世界共通語でなくなる事態は、自分たちが生きている間にはなさそうだ。グラドル氏もこう同意する。いったん世界共通語が成立してしまうと、次の言葉に交代するまでにはかなりの時間がかかる。ラテン語は確かに消滅しつつあるかもしれないが、それでも何世代にもわたって科学の言語であり続けたし、カトリック教会は20世紀に入ってもラテン語をずっと使い続けた。
英語の枝分かれ現象については、もうすでに起きたことだとグラドル氏は言う。「私たち英語ネイティブには理解できない英語が、もうあちこちで発生している」
香港教育学院のアンディー・カークパトリック教授が最近発表した「World Englishes(世界の色々な英語)」という本には、具体例が並んでいる。たとえばインドのティーンエージャーは日記に(英語で)「ライバル同士のグ ループが遊びに出かけてって、だいたいはダマル(踊りの一種)して時間をつぶすんだけど。何をするかっていうと、大学に入ったばかりのベチャーラバクラ (可哀想なヤギ)をみつけてからかうんだ」と書いている。英語と現地語が境界線なく同じ文章の中に同居しているのだ。あるいはナイジェリアで現地語と英語 が混ざり合った「ピジン英語」を使うと「サルは働き、ヒヒは食べる(monkeys work, baboons eat)」が「Monkey de work, baboon dey chop」という風になる。
しかしこの枝分かれ現象がそのまま世界共通語=英語の消滅につながるとは、考えにくい。英語スピーカーが、TPOに応じて、色々な言葉を使い分けるのはよくあることだ。多くの人は職場、学校、外国人とのコミュニケーションと、状況に応じて最適な言葉を使い分けている。それに現代のコミュニケーションがテレビや映画、インターネットに大きく依存している以上、より大勢が使っていて理解しあえる共通言語=英語の必要性は、なかなかなくならないだろうとクリスタル氏は言う。
とするとテーマは別だ。世界共通語が英語だというのは分かったが、それはいったい誰のバージョンの英語なのか、ということになる。英語を母国語とするネイティブ・スピーカーと、外国語として英語を使う非ネイティブ・スピーカーの比率は今や1対3。ネイティブの3倍もの人が外国語として英語を使っているのだ。これからさらに何百万という人たちが新たに英語を勉強し始めるに連れて、この比率の開きはどんどん大きくなる。
実際に今や、英語を使って交わされる会話の大半は、非ネイティブ・スピーカー同士のものだとグラドル氏は言う。さらに言えば、ビジネス会議を英語で行う場合、英語ネイティブがいない方が、やり取りはスムースに進むようだという。
英語を母国語とするネイティブスピーカーは、国際会議で自分の言うことを理解してもらおうと努力するのが下手だ。外国人相手に音節の多い長い単語は使わない方がいいと、英語ネイティブは思いがちだが、外国人にはむしろ、比喩や口語体を多用した英語のほうが難しいのだ。
ウィーン大学で英語・応用言語学を教えるバルバラ・ザイドルホファー教授は、英語ネイティブが会議にいないのでみんなホッとするという場面はよくあると話す。
「ビジネス関係者などに外国人とのコミュニケーションについて尋ねると、多くの人がこのことを挙げてくる。システマティックな調査をしたわけではないので、これはまだたとえ話レベルのことだが、多くの人が同じことを感じているらしい」
たとえばあるオーストリア人銀行家は教授に対して、「(英語を使って)ギリシャやロシアやデンマークの仕事相手と話をする方が簡単だ。けれどもアイルランド人が電話してくると、意思疎通はとてもややこしくて、くたびれる」と話したという。
またオランダ・アムステルダムで国際学生会議が開かれた時、共通語として英語を使って学生たちが話し合っていたのだが、英国代表の学生に対してほかの参加者から、何を言っているか理解できるよう「イギリスっぽさを抑えて」欲しいと注文されたのだそうだ。
ザイドルホファー教授はウィーン・オックスフォード国際英語団体(VOICE)の創立責任者でもある。VOICEでは、世界中で英語を使っている人たちの実際の会話を録音し書き起こして記録として残す活動を続けている。調査する内に、非ネイティブスピーカーたちは英文法をいくつかの形で修正させていることが明らかになってきたという。英語をかなり流暢に使える人でも、三人称単数現在形の語尾の「s」を落とすことがあるし、関係代名詞「who」と「which」の使い方もネイティブとは違っていることが多いという。ネイティブはやらないが、非ネイティブはよく、人間を示す関係代名詞に「which」を使い、人間以外を示すのに「who」を使うのだそうだ(「things who」「people which」という風に)。
そのほかにもザイドルホファー教授によると、非ネイティブスピーカーは本来なら必要な場所の定冠詞・不定冠詞を落とし、本来ならいらない場所に定冠詞・不定冠詞を使いがちだという。たとえば、次のような具合にだ。
・「they have a respect for all(彼らは全てを尊敬している)」(訳注・スタンダードな英文法では、「respect」は抽象名詞なので冠詞は不要)
・「he is very good person」(訳注・スタンダードな英文法では「person」には「a」が必要なので、「he is a very good person」となる)
またネイティブならば複数形にしない名詞を、非ネイティブは複数形にしがちだという。たとえば「information」を非ネイティブは「informations」としたりする。「knowledges」「advices」などの複数形も非ネイティブスピーカーが使いがちだ。
ほかにも、ネイティブはそういう言い方はしないが非ネイティブはよくやるという英語のバリエーションとして、「make a discussion(話し合う)」「discuss about something(何それを話し合う)」「phone to somebody(誰それに電話する)」などがある(訳注・ネイティブ的用法では順番に「have a discussion」「discuss something」「phone somebody」という形になる)。
英語が母国語のネイティブなら往々にして、これまで挙げてきた例はどれも「バリエーション」ではなくて「間違い」だと言うだろう。「knowledges」も「phone to somebody」も、紛れもなく間違いだと。世界各地で英語を教えている非ネイティブの英語教師たちも、そう言うだろう。しかし言葉とは変化するもの。文法的に何が正しいか正しくないかも、時代によって変化するものなのだ。クリスタル氏によると、「informations」などの複数形はかつて文法的に正しいとされていた。「英語辞書」の編纂で名高い18世紀の英文学者サミュエル・ジョンソンも「informations」と使っていたのだそうだ。
正統的な「正しい」英文法にこだわる人たちは、強い立場にいる。たとえば科学者や研究者が世界的な学術誌に論文を発表したいと思ったら、英語が母国語のエリートたちが定める文法に従って論文を書かなくてはならない。
しかし、会話に使う英語は別だ。ネイティブが「正しい」とするものに、どうして非ネイティブがこだわる必要がある? 非ネイティブが英語を使う目的はとどのつまり、お互いが何を言っているか理解しあうため。そしてグラドル氏が言うように、そこにネイティブスピーカーはいないことの方が多いのだ。
ザイドルホファー教授は、非ネイティブスピーカーが使う英語のことを「自発的な自然な言語」と呼ぶ。「自然な言語を『規則』で縛り付けるのは難しい」とも教授は言う。
「浮上しつつあるのは、新しい英語の国際スタンダードというよりは、英語に対する新しい国際的な『態度』だと思う」とザイドルホファー教授。「国際的な文脈においては、何も別にネイティブスピーカーのように話す必要はないのだ、という認識のことだ。ネイティブと自分を比べて、どうしたってネイティブに比べれば下手だと卑下する必要はないという、そういう自信あふれる態度とも言える」
ネイティブスピーカーが国際機関で働くと、自分自身の英語の使い方・話し方が変化するという報告もある。クリスタル氏はこう書いている。「英語を第一言語とする政治家や外交官、公務員からたびたび聞かされた話だ。ブリュッセルの国際機関で働く彼らは、自分自身の英語が、周りの外国人の英語に引っ張られるのを実感するという。彼らは別に、同僚たちのレベルに自分を『落として』いるわけでも、同僚たちの英語を真似ているわけでもない。彼らの周りにいる外国人は多くの場合、ネイティブ並みに英語が堪能だからだ。そうではなくてむしろ、日常的に接している言葉を受け入れることからくる自然な変化で、そこから新しい英語のスタンダードが生まれてくる過程なのだ」
会話英語のこうした変化と同様に、文章英語もいずれはこうして変化を受け入れていくのかもしれない。今の世界では、ハーバード・ビジネス・レビューやブリティッシュ・メディカル・ジャーナルに論文が掲載されることは、中国のビジネス研究者やタイの医療研究者にとって相当に大きな功績だ。しかしゆくゆくは、アジア発の学術誌に論文が載ることが同じように、あるいはそれ以上に高く評価される、大事な功績とみなされるようになるかもしれない。
そのときはアジア発の専門誌の編集者たちが、世界中の研究者に、自分たちの「世界語」の文法に合わせるよう要求するのだろう。そうなったら、もし論文に「the patient feels」と書いてあったら、編集者は「the patient feel」と文章を校正するに違いない。三人称単数現在形の語尾の「s」を落として。
ネイティブスピーカーは、顔をしかめるかもしれない。けれども私たちは日に日に少なくなりつつあるマイノリティーなのだ。
**********
英語教師として複雑な心境になる記事です。アメリカ人・イギリス人が使う英語を規範として教えていたものがいまや通用しなくなる可能性をあることになると、何を基準に教えたらよいのか分からなくなります。日本における英語教育に混乱が起きることは容易に想像できます。
とはいえ、ひとつのコミュニケーション・ツールとしての英語が身近になっているのは事実。グローバリズムの波に本家のアメリカ・イギリスが翻弄されているという皮肉はありますが。
**********
英語とは誰の言葉か 形を変え続けて広まる英語――フィナンシャル・タイムズ(1)(フィナンシャル・タイムズ) - goo ニュース
2007年11月30日(金)23:15
(フィナンシャル・タイムズ 2007年11月8日初出 翻訳gooニュース) マイケル・スカピンカー
テレビニュースの元アンカーマンで韓国大統領候補の鄭東泳(チョン・ドンヨン)氏は支持率で遅れをとっているかもしれないが、選挙公約にはかなり目を引くものがある。大統領に当選した場合、韓国の若者が英語を学ぶためにわざわざ外国に行かなくてもいいように、国内の英語教育を充実させるつもりだというのだ。英字紙「コリア・タイムズ」は、「英語を学ぶために、家族が離れ離れになる問題を解決する」必要があると、鄭氏がコメントしたと伝えている。
中国では、ユー・ミンホン(マイケル・ユー)氏が創設した英語スクール・受験塾、新東方教育科技集団(ニューオリエンタル・エデュケーション・アンド・テクノロジーグループ)が、国内最大手となった。昨年度の学生数は100万人以上。ほとんどが英語を勉強している。南米チリでは、次世代までに全国民が英語とスペイン語のバイリンガルになるよう目指すというのが、政府方針だ。
世界中でいったい何人が英語を学んでいるのか、誰もはっきりとは把握できていない。英国の公的な国際文化交流機関ブリティッシュ・カウンシルは10年前、10億人ぐらいではないかと見ていた。同カウンシルが昨年発表した報告書「English Next(次は英語)」では、今から10~15年後ごろに、英語学習者は20億人でピークに達するのではないかと見ている。
では、現時点ですでに英語を話す人は世界で何人ぐらいいるのだろう? 英語についての世界的な権威で、100冊以上の著作も発表している言語学者デビッド・クリスタル教授によると、世界中で約15億人(地球人口の約4分の1)がまあまあそれなりに英語で意思疎通できるのではないかという。
かつて広大な地域で共通言語として使われていたのは、ラテン語だった。しかしそれは欧州と北アフリカ限定。今の英語のようにこれほど広い地域でひとつの言語が使われたことは、人類史上かつてなかった。何百万もの人が英語を勉強する理由は簡単だ。国際ビジネスの言葉は英語。よって富を得るための手段が英語なのだ。マイクロソフトやグーグルやボーダフォンがビジネスに英語を使っているから、だけではない。中国人がブラジル人と話す時、ドイツ人がインドネシア人と話す時、そういう時に使うのが、英語だからだ。
英語が世界中に広まったこの物語は、北アメリカ、ブリテン諸島、オーストラレシアに住むネイティブ・スピーカーたちの勝利だ——と解釈したくなる気持ちも分かるが、それは間違いだ。「English Next」の筆者デビッド・グラドル氏は、こう指摘する。グローバル英語は最早もっと複雑な段階に入っている。英語は世界中でどんどん変化していて、古くから英語を使っている国々はその変化の仕方をコントロールもできないし、変化の仕方が必ずしも気に入らないかもしれないのだ。
グローバル英語について論じる人たちは主に、3つの論点を挙げる。第一に、いま利用者が急増しつつある北京語やスペイン語、あるいはアラビア語に、英語がとって代わられることはあるだろうか? 第二に、英語が世界各地に広まり、地元の言語の影響を受けるのに伴い、どう変化していくのか? ラテン語がイタリア語とフランス語に変容していったように、枝分かれしてそれ自体は消滅するのか。それともドイツ語がオランダ語とスウェーデン語を生み出したように、それ自体も残りつつ新しい言語を派生させるのか。第三に、もし英語がこのまま「どこでも通じる」という共通性を特徴として残すとして、その「共通する英語」とは、古くから英語を使っている国々の英語になるのか、それともこれまでの英語とは違う新しい英語になるのか?
英語ではない別の言葉が世界言語になる。これは全くありえない話ではないと、グラドル氏。約50年前には、英語を母国語にする人数は、北京語に次いで多かった。しかし今日では、スペイン語を母国語とする人数も、ヒンディー・ウルドゥー語を母国語にする人数も、英語なみの数になっている。21世紀半ばまでに、英語を第一言語とする人数はアラビア語にも抜かれ、第5位に後退しているかもしれないのだ。
中には、英語にはそもそも有利な条件が備わっているから、英語は生き延びるという人もいる。有利な条件とはつまり、覚えやすい、という。三人称単数現在形にやっかいな「s」がつくのを別にすれば(例「She runs」)、誰が主語だろうと動詞は変化しない(I run, You run, They run; We ran, He ran, They ran)。定冠詞・不定冠詞は名詞の性別によって変化しないので(the actor, the actress; a bull, a cow)、ほかのヨーロッパ言語のように「テーブル」は女性名詞なのか男性名詞なのか、覚えておく必要もない。
しかしその一方で、英語にも覚えにくい要素はいくらでもある。よく似た句動詞の細かな違いを説明するのは大変だ。たとえば「I stood up to him」と「I stood him up」の違いとか(訳注・前者は「私は彼に立ち向かった」。後者は「私は彼をすっぽかした」)。
英語は簡単だから世界言語になった——というこの説を、クリスタル氏は一蹴する。昨年発表した論文で同氏は、ラテン語は文法的にきわめて複雑だったけれどもそれでも広く普及したと指摘している。「ある言語が世界共通語になる理由は、その言語そのものの構造とは無関係だ。世界共通語になる理由は、その言葉を使う人たちの強さと関係している」。「太陽の沈むことなき」と言われるまで勢力圏を広げた大英帝国は、その太陽の沈まない国々にあまねく英語を広めた。
そしてその大英帝国が衰退した後も、アメリカが経済や文化に多大な影響力をもったおかげで、英語の圧倒的な地位は守れられてきた。
ということは、中国の台頭によって北京語がいずれは世界共通語になるのだろうか? あり得ることだ。「数千年前にさかのぼってみれば、いったい誰が、ラテン語がこんなに衰退すると予想できただろう?」とクリスタル氏。とはいえ現時点では、中国語が英語にとって代わりそうには見えない。中国の人たちはこぞって英語を勉強しているからだ。
英語が世界共通語でなくなる事態は、自分たちが生きている間にはなさそうだ。グラドル氏もこう同意する。いったん世界共通語が成立してしまうと、次の言葉に交代するまでにはかなりの時間がかかる。ラテン語は確かに消滅しつつあるかもしれないが、それでも何世代にもわたって科学の言語であり続けたし、カトリック教会は20世紀に入ってもラテン語をずっと使い続けた。
英語の枝分かれ現象については、もうすでに起きたことだとグラドル氏は言う。「私たち英語ネイティブには理解できない英語が、もうあちこちで発生している」
香港教育学院のアンディー・カークパトリック教授が最近発表した「World Englishes(世界の色々な英語)」という本には、具体例が並んでいる。たとえばインドのティーンエージャーは日記に(英語で)「ライバル同士のグ ループが遊びに出かけてって、だいたいはダマル(踊りの一種)して時間をつぶすんだけど。何をするかっていうと、大学に入ったばかりのベチャーラバクラ (可哀想なヤギ)をみつけてからかうんだ」と書いている。英語と現地語が境界線なく同じ文章の中に同居しているのだ。あるいはナイジェリアで現地語と英語 が混ざり合った「ピジン英語」を使うと「サルは働き、ヒヒは食べる(monkeys work, baboons eat)」が「Monkey de work, baboon dey chop」という風になる。
しかしこの枝分かれ現象がそのまま世界共通語=英語の消滅につながるとは、考えにくい。英語スピーカーが、TPOに応じて、色々な言葉を使い分けるのはよくあることだ。多くの人は職場、学校、外国人とのコミュニケーションと、状況に応じて最適な言葉を使い分けている。それに現代のコミュニケーションがテレビや映画、インターネットに大きく依存している以上、より大勢が使っていて理解しあえる共通言語=英語の必要性は、なかなかなくならないだろうとクリスタル氏は言う。
とするとテーマは別だ。世界共通語が英語だというのは分かったが、それはいったい誰のバージョンの英語なのか、ということになる。英語を母国語とするネイティブ・スピーカーと、外国語として英語を使う非ネイティブ・スピーカーの比率は今や1対3。ネイティブの3倍もの人が外国語として英語を使っているのだ。これからさらに何百万という人たちが新たに英語を勉強し始めるに連れて、この比率の開きはどんどん大きくなる。
実際に今や、英語を使って交わされる会話の大半は、非ネイティブ・スピーカー同士のものだとグラドル氏は言う。さらに言えば、ビジネス会議を英語で行う場合、英語ネイティブがいない方が、やり取りはスムースに進むようだという。
英語を母国語とするネイティブスピーカーは、国際会議で自分の言うことを理解してもらおうと努力するのが下手だ。外国人相手に音節の多い長い単語は使わない方がいいと、英語ネイティブは思いがちだが、外国人にはむしろ、比喩や口語体を多用した英語のほうが難しいのだ。
ウィーン大学で英語・応用言語学を教えるバルバラ・ザイドルホファー教授は、英語ネイティブが会議にいないのでみんなホッとするという場面はよくあると話す。
「ビジネス関係者などに外国人とのコミュニケーションについて尋ねると、多くの人がこのことを挙げてくる。システマティックな調査をしたわけではないので、これはまだたとえ話レベルのことだが、多くの人が同じことを感じているらしい」
たとえばあるオーストリア人銀行家は教授に対して、「(英語を使って)ギリシャやロシアやデンマークの仕事相手と話をする方が簡単だ。けれどもアイルランド人が電話してくると、意思疎通はとてもややこしくて、くたびれる」と話したという。
またオランダ・アムステルダムで国際学生会議が開かれた時、共通語として英語を使って学生たちが話し合っていたのだが、英国代表の学生に対してほかの参加者から、何を言っているか理解できるよう「イギリスっぽさを抑えて」欲しいと注文されたのだそうだ。
ザイドルホファー教授はウィーン・オックスフォード国際英語団体(VOICE)の創立責任者でもある。VOICEでは、世界中で英語を使っている人たちの実際の会話を録音し書き起こして記録として残す活動を続けている。調査する内に、非ネイティブスピーカーたちは英文法をいくつかの形で修正させていることが明らかになってきたという。英語をかなり流暢に使える人でも、三人称単数現在形の語尾の「s」を落とすことがあるし、関係代名詞「who」と「which」の使い方もネイティブとは違っていることが多いという。ネイティブはやらないが、非ネイティブはよく、人間を示す関係代名詞に「which」を使い、人間以外を示すのに「who」を使うのだそうだ(「things who」「people which」という風に)。
そのほかにもザイドルホファー教授によると、非ネイティブスピーカーは本来なら必要な場所の定冠詞・不定冠詞を落とし、本来ならいらない場所に定冠詞・不定冠詞を使いがちだという。たとえば、次のような具合にだ。
・「they have a respect for all(彼らは全てを尊敬している)」(訳注・スタンダードな英文法では、「respect」は抽象名詞なので冠詞は不要)
・「he is very good person」(訳注・スタンダードな英文法では「person」には「a」が必要なので、「he is a very good person」となる)
またネイティブならば複数形にしない名詞を、非ネイティブは複数形にしがちだという。たとえば「information」を非ネイティブは「informations」としたりする。「knowledges」「advices」などの複数形も非ネイティブスピーカーが使いがちだ。
ほかにも、ネイティブはそういう言い方はしないが非ネイティブはよくやるという英語のバリエーションとして、「make a discussion(話し合う)」「discuss about something(何それを話し合う)」「phone to somebody(誰それに電話する)」などがある(訳注・ネイティブ的用法では順番に「have a discussion」「discuss something」「phone somebody」という形になる)。
英語が母国語のネイティブなら往々にして、これまで挙げてきた例はどれも「バリエーション」ではなくて「間違い」だと言うだろう。「knowledges」も「phone to somebody」も、紛れもなく間違いだと。世界各地で英語を教えている非ネイティブの英語教師たちも、そう言うだろう。しかし言葉とは変化するもの。文法的に何が正しいか正しくないかも、時代によって変化するものなのだ。クリスタル氏によると、「informations」などの複数形はかつて文法的に正しいとされていた。「英語辞書」の編纂で名高い18世紀の英文学者サミュエル・ジョンソンも「informations」と使っていたのだそうだ。
正統的な「正しい」英文法にこだわる人たちは、強い立場にいる。たとえば科学者や研究者が世界的な学術誌に論文を発表したいと思ったら、英語が母国語のエリートたちが定める文法に従って論文を書かなくてはならない。
しかし、会話に使う英語は別だ。ネイティブが「正しい」とするものに、どうして非ネイティブがこだわる必要がある? 非ネイティブが英語を使う目的はとどのつまり、お互いが何を言っているか理解しあうため。そしてグラドル氏が言うように、そこにネイティブスピーカーはいないことの方が多いのだ。
ザイドルホファー教授は、非ネイティブスピーカーが使う英語のことを「自発的な自然な言語」と呼ぶ。「自然な言語を『規則』で縛り付けるのは難しい」とも教授は言う。
「浮上しつつあるのは、新しい英語の国際スタンダードというよりは、英語に対する新しい国際的な『態度』だと思う」とザイドルホファー教授。「国際的な文脈においては、何も別にネイティブスピーカーのように話す必要はないのだ、という認識のことだ。ネイティブと自分を比べて、どうしたってネイティブに比べれば下手だと卑下する必要はないという、そういう自信あふれる態度とも言える」
ネイティブスピーカーが国際機関で働くと、自分自身の英語の使い方・話し方が変化するという報告もある。クリスタル氏はこう書いている。「英語を第一言語とする政治家や外交官、公務員からたびたび聞かされた話だ。ブリュッセルの国際機関で働く彼らは、自分自身の英語が、周りの外国人の英語に引っ張られるのを実感するという。彼らは別に、同僚たちのレベルに自分を『落として』いるわけでも、同僚たちの英語を真似ているわけでもない。彼らの周りにいる外国人は多くの場合、ネイティブ並みに英語が堪能だからだ。そうではなくてむしろ、日常的に接している言葉を受け入れることからくる自然な変化で、そこから新しい英語のスタンダードが生まれてくる過程なのだ」
会話英語のこうした変化と同様に、文章英語もいずれはこうして変化を受け入れていくのかもしれない。今の世界では、ハーバード・ビジネス・レビューやブリティッシュ・メディカル・ジャーナルに論文が掲載されることは、中国のビジネス研究者やタイの医療研究者にとって相当に大きな功績だ。しかしゆくゆくは、アジア発の学術誌に論文が載ることが同じように、あるいはそれ以上に高く評価される、大事な功績とみなされるようになるかもしれない。
そのときはアジア発の専門誌の編集者たちが、世界中の研究者に、自分たちの「世界語」の文法に合わせるよう要求するのだろう。そうなったら、もし論文に「the patient feels」と書いてあったら、編集者は「the patient feel」と文章を校正するに違いない。三人称単数現在形の語尾の「s」を落として。
ネイティブスピーカーは、顔をしかめるかもしれない。けれども私たちは日に日に少なくなりつつあるマイノリティーなのだ。
**********
英語教師として複雑な心境になる記事です。アメリカ人・イギリス人が使う英語を規範として教えていたものがいまや通用しなくなる可能性をあることになると、何を基準に教えたらよいのか分からなくなります。日本における英語教育に混乱が起きることは容易に想像できます。
とはいえ、ひとつのコミュニケーション・ツールとしての英語が身近になっているのは事実。グローバリズムの波に本家のアメリカ・イギリスが翻弄されているという皮肉はありますが。













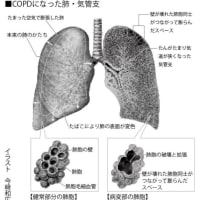
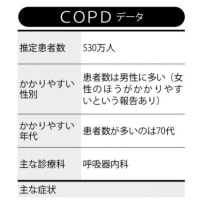




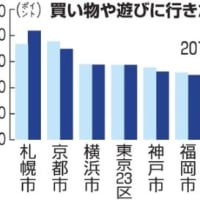





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます