ラウラは毎日のペースを崩さない
起きたら、暖房つけろ
お腹が空いたからご飯くれ

起きたからおやつくれ
アタシは寝る

そんな毎日
でも、お前の顔を見ていると「なんて幸せなんだ!!」と思う
それにしても「デブ顔」だなぁ
ほっぺたがこぼれているぞ

ラウラは毎日のペースを崩さない
起きたら、暖房つけろ
お腹が空いたからご飯くれ

起きたからおやつくれ
アタシは寝る

そんな毎日
でも、お前の顔を見ていると「なんて幸せなんだ!!」と思う
それにしても「デブ顔」だなぁ
ほっぺたがこぼれているぞ

夕食を食べている脇で、安心しきって寝ているラウラ
昼間、お母さんがいなかったので、落ち着かなかったようだ
仕事をしている源太郎の様子を覗いては寝ていたようだが
何をしても起きない状態で寝ているラウラ
よく見ると「結構ブサイクだ」
化粧をとった〇〇とは言わないが、安心しているラウラを見ると笑いが溢れる
さぁ、オリンピックの閉会式が始まる

先ずは、昔Prahaの教会で撮影したステンドグラスで心を落ち着かせる

忙しいと、つい「カリカリ」してしまう性格
人間ができていないのだろう
もう他界した両親は大正生まれ、祖父や祖母は明治生まれだった
そしていつも言われた言葉があった
「あと一間向こうまで」、「後は皆お客」
聞いたことのある人は、きっと親がこの世代だろう
庭先を掃除していると、
「自分の家の敷地だけではなく、隣の敷地の一間(六尺)先まで掃除しなさい」
そうすれば、掃除の境はできない
「学校の廊下の拭き掃除も隣の教室の一間先まで拭け」
そうすれば、拭き残しの境はなくなるとよく言われた
そして、
「物や事柄を頼むときは、相手がお客様だと思って言え」
今で言うと「あと工程はお客様」と言うことだ
人にお願いするとき、相手の都合や、相手の気持ちを感じて
やりやすいように配慮しなさいと言う戒めの言葉だった
それが近頃、働き改革を率先しなければならないのに、あえて言えば石器時代の感覚を持った人たち(決して父母の世代ではない、そして源太郎よりも若い世代)の言動に「カリッ」とくる旧人類の源太郎
金曜日の、しかも夕方にたった一通のメールで、一ヶ月前のレポートの修正を月曜日にお願いしますときたもんだ
こちとらも人の子、ならば「日曜日に詳細な事柄を教えてくれ」と返信、すると応答なし
確かに、依頼する人だから、そして要求は許される
ところが、請け側が早めに対応しておいた事柄は、ずっとほっといて、締め切りが近づきお尻に火がつくと
こんな慌てた行動に出る
「おもてなし」の日本と言われるが、これじゃ、「甲乙主義」に逆戻りだ
そして、源太郎の一言「じゃ、自分でしなさいよ、こちら一ヶ月前に提出しているのだから」
と・・・・
いかんいかん、これでは両親の教えを守っていない
この言葉を思い出しながら、働き改革とはなんだろうと思う次第
今日も、一日、気持ちを抑えて頑張っていこう
「お父しゃん、どこに行っていたの?」
「おぉ、久しぶりだなラウラ」
「今日は暖かいのよ」
「そっか!! じゃこれからお昼寝か」
「お父しゃんもお昼寝したら」
「いいゃ、お仕事だよ」
久しぶりの自宅、のんびりしたいが、この時期は無理
さて、もう一踏ん張りしましょう

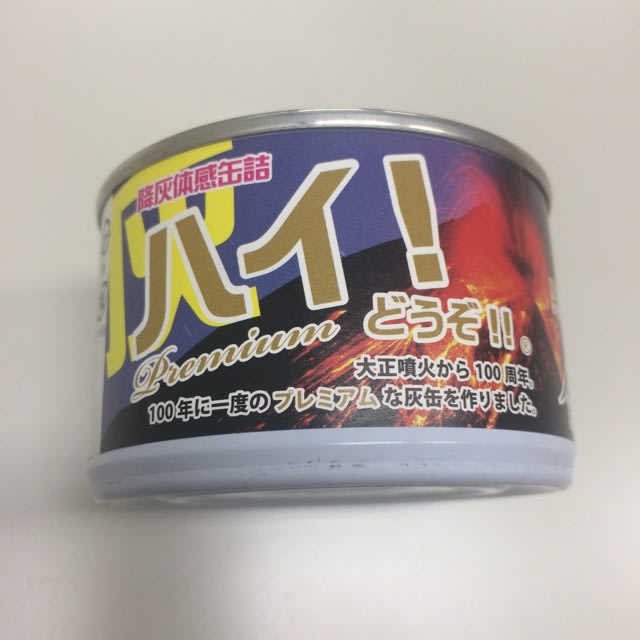

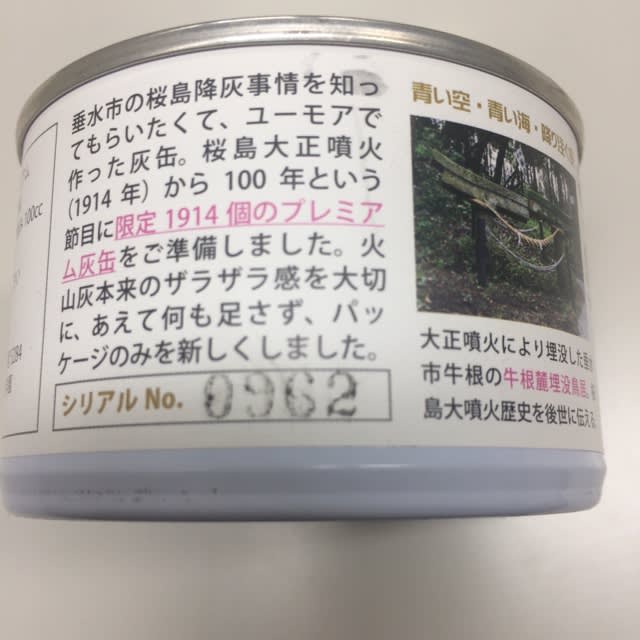
今朝は風はなく
夜明け前に、北の空に大きな流れ星が落ちた
ほんの一瞬だったので「願い事」なんて唱えられなかった
その前に「何を願うか」考える時間が足らなかった

そして、富士山は夜が明けた

太平洋側は乾燥し、ただ寒い
それにしても、今年の雪は凄い
よく、38豪雪、56豪雪はすごかったと言ったが、
平地でも現代の除雪機械の能力を持っても対抗できない
まして、屋根の雪下ろしは結局人力に頼らなければならないし
敷地内の通路確保も人力
なんとか、この雪対策に国を挙げて取り組むことを考えねば
昔、白馬でお世話になった民宿の女将さんから
「ほら、早く起きて若者が雪かきしないと朝飯なしだからね」と
泊まっていた常連の我々を起こし、総出で雪かきをした
「ご苦労様、今晩はご馳走するから」と女将さん
結局、若者の力が必要だったことは今も昔も変わらない
これだけ雪が降ると、雪を捨てる場所もなくなり
用水路も雪に隠れてしまい
誤まって転落してしまうことも・・・
とにかく、早く雪が降り止んでくれることを祈る
富士山は夜が明ける前、凍ってカチカチの雪面がよくわかる

雪は少ないが、これだけ東斜面で残っているのは久しぶり
誰が「地球温暖化」と言ったのだろう
人間が気象観測初めて数百年、そんなデータで50億年近い地球を予測するなんて
誤差だらけの議論だろ、と源太郎は思う次第
「ラウラ、寝ている場合じゃないぞ。若者はお手伝いするんだ」
「冗談じゃないわ、そんな冷たい手で触らないでよ」
と、この後指を噛んで抵抗(甘噛みだけど)
「いいから、起きろよ」
「ヤァーなこった」

昔よく出かけた山形の肘折温泉
お蕎麦が美味しくて、早朝の温泉場を散策して朝市を楽しんだこともある
その肘折で、今年全国一番の積雪深さになったというニュースが流れていた
2013年に積雪深が414cmに達したが、それにあと10cmに迫ったというのだ
新庄でも170cmを超えたという
富士山の雪が少ない年は、日本海側の雪は多い

西風が強い、西高東低の気圧配置
明日もまた、降雪の予報だ
もう、十分だ
これ以上の雪害がないことを祈る
ガンバレ雪国!!
Laura、お前は1日まったりしていたが、明日はグッと冷え込むだろう
また1日寝ているのか!!

風の音で目が覚めた
西風が強く吹いている
富士山の方向を見ても雲が流れて、姿が見えない
なので、昨日の夕暮れの富士山を記録として残しておこう

寒いので、例に漏れずLauraは、おかぁしゃんのベッドから起きてこない
仕方ないので、昨夜のLaura
男子5000mのスピードスケートを見ながら

昼前、強い風が雲を取り去り、真っ白な富士山
このブログを書きながら「男子スロープスタイルの決勝」を見ていた
新鋭17歳が優勝、空中で4回転半・・・

昨日Mihoちゃんが「見つけたよ。これでしょ」と「木軸の綿棒」を買ってきてくれた。
もう、残り少なっていた綿棒に気づいてくれた。
今の綿棒は、まず紙かプラスチックで、木軸の綿棒はなかなか見つからない。
この綿棒使い道は、化粧用ではなく、オープンテープデッキのヘッドを清掃するために欠くことができない道具なのだ。この綿棒に、ヘッドクリーニングリキッドをつけて、丁寧にヘッド表面についた磁気粉や汚れを取り除く。そのためにある程度力が入らなくてはならないが、紙やプラスチックの軸では湾曲して使い物にならないのだ。
綿棒を確保できて在庫を心配なくていいので、今朝はその綿棒を贅沢に使い、RT-1050のテープデッキのヘッドをクリーニングして、録音してあったFiorella Mannoiaの「Caruso」を深みのある音で楽しんでいる。「いゃー、実にいい音だ。音楽はアナログに限る」
「オープンテープデッキ」と言っても、今の若い人にその良さはわからないだろう。何回かこのブログでもその一端を書いたが、真面目に書いてはいなかった。ブロ友の「どろ亀」さんも大切に今でもオープンテープデッキを使われていて、まだまだ愛好者はいることに感激している。
今はカセットテープが復権・復活し、LPレコードもまた活気を得てきている。ところが、このオープンテープの製造は国内ではされていなく、唯一民生用(輸入品)で手に入るのは「RMG STUDIO MASTER 911」に限定される。だから古いテープであっても大事に使わなくては、再生や録音の機会はなくなってしまう。我が家でも「限界集落の音楽機械」という状態だ。
いくら素晴らしいデジタル録音技術が発達しても、やっぱりアナログ録音機械には足元に及ばない。この前ある番組で、作曲家の小林亜星さんがコレクションの蓄音機を持参してこんな話をしてくれた。「CDは音がいいというが、人間の耳に聞こえる音域にコントロールされている。レコードは、その領域を超えて録音されている。音は耳だけで聴くものではない、いろいろな部位で聞いている」ということを述べられていた。源太郎の歳ではもう高音域は聞こえない、誰もが歳をとればそうなる。でも、何かアナログの音は安心して柔らかい。そう思って、今でも大事に使う気持ちは揺るがない。
このRT-1050本体は、重さ22.5kg、幅が46cm、高さは45.3cm、奥行きは24.4cm。
かよわい女性なら移動は困難な躯体だし、持ち歩きは困難だが、上部には持ち手があり、録音に出かけられるようにしっかりとしたフロントカバーがある。
そして消費電力は115Wだから、省エネを提唱する諸氏からは避難を浴びそうだ。
モーター3個、リール用の2個のモーターは6極インナーローターインダクション型、そして肝心なキャプスタン用は、4極-8極ヒステリシスシンクロナス型、周波数特性は38cm/sで30~22,000Hz、これだけ重装備だが、10号リールのスタンダートテープで30分の録音しかできない。700mほどあるテープが、左から右に高速に送られる。しかも2トラだから一方向にしか使えない。我が家のRT-1050の二号機は、4トラのヘッドに変えてあるので往復できるがそれでも1時間の再生時間だ。きっと「じゃ使いモンにならないじゃ」と言われそうだが、当時はこれで十分だった
ところで源太郎が、録音されたテープを聴くためにどのような方法でやっているか紹介する。勿論、我流ですが。(今朝撮った写真で説明)

はじめに(写真上段左)、キャリング用フロントカバーの止め金具四つを外す。
綿棒で軽くヘッドを清掃し、そして、左端のPowerスイッチを押して電源を入れる。すると、レベルメーターが一度振り切れ戻る。(車のメーターみたいに)
そのあとにアンプの電源を入れる。ここが肝心。電源を入れるときは外周から、そして最後に中央のアンプだ。今の機械なら保護回路がいっぱいあって、電圧や電流も少ないから気にはしないが、何せ40年以上前の機械、サージが入ったり、過電流が流れないように、そこはセオリーに沿って。
そして、リール台に空のリールを左側にセットする。
「なぜ左側」かというと、この機械が2トラック2チャンネルということと、源太郎は聴き終わったテープが綺麗に巻かれて仕舞えることが、保存には一番と思っているからだ。だから、右側にテープリールをセットして、一旦、空リールに巻き戻し、そしてガイドローラーと巻き取り側のテンションアームをセットして、ようやく再生することになる。反対に再生すると「曲が逆に演奏される」、これはこれで結構笑える。
そして聴き終わったら、あの綿棒で磁気粉などを綺麗に清掃して終わる。
こんな、めんどくさい機械は復活することはないなぁ。でも、アナログ録再機械復活してほしい。
昨夜は、天気予報通り「雨」
でも南風だったので、今朝は「暖かいね」と感じる
冬季オリンピックが始まった
そこで「白い恋人たち」の映画から一節
「Je sais bien ce que tu ressens : 僕は君が何を感じているかをよく知っている」
続くフレーズは「あの勝利の感情も・・・」
選手たちは素晴らしく頑張っている
ただ、「解説者のコメントがショータイムのようで落ち着かない」
音声を止めて、映像だけを見る

富士山の姿も「一瞬の時」
だから、解説はいらない
ただ、「今日はカラー撮影は無理、色彩がないのでセピア撮影」
頂上付近は少し化粧直ししたようだ
いつも撮影している固定焦点のレンズでは、富士山周辺の雲の流れがこれほどダイナミックになると、カバーしきれない。17mm-40mmの広角レンズでやっととらえられる
ほんの数時間で周辺の雲の様子が変わった
富士山の笠雲も成長している

昔、雪解けが始まり、里に下山して
冬に届いていた手紙の束を職員から渡された
大正生まれで多くの大災害をなんども経験してきた母からの手紙は
相変わらず、旧仮名遣いの文体で、「冬は辛からふ、混凝土も凍るのか・・・」
と、読みにくかった。ただ和紙に縦書きの筆使いは綺麗だったことを覚えている
今、大正時代の文章を旧漢字に戸惑うが読んで理解できるのは母のお陰だと思う
昨晩、大正10年の縦書きの論説を読んでいて、こんなことをふと思った
「本篇は私が極乏しい参考書のあちこちから抜粋して綴り合はしたものであるが、いくらか根本に觸れて居ると思ふ・・・」と書き出される
「佛國政府、獨逸國、澤山、・・・・おひゞ研究せられて来るであらう」
面白い、そして母からの手紙を読んでいるようだ
昔、葉山嘉樹さんだったか、「セメント樽の中の手紙」という非常に短い小説を読んだことを思い出した(源太郎はプロレタリア文学は好きではないが)
その文章の中で、恵那山という言葉が出てきていて、大正終わりぐらい発表の小説だから、舞台はあの福澤桃介が木曽川を堰き止めた大井ダムだろうと想像した
でも、読んだそれは現代仮名遣いだったように記憶しているが、それでも「十才」が吐き出されるというくだりは読んだ人のどれほどが理解できただろう
「才」という計量(容積)を表す単位は、もう忘れられたのだろう。源太郎が若い頃は、この単位は当たり前のように使われていたのだが・・・・

今朝のLauraはご機嫌だ
少し暖かいし、草津温泉に友人たちと出かける息子が早起きして、朝「おやつ」をもらったようだ
今は、暖かいカーペットの上で寝てしまっているが・・・
昨日からの富士山の姿を見ていただきたい
午後から雨という予報だが、小さな笠雲が今朝夜明け前に見え、それが消えて巨大な釣鐘雲が少し離れたところにできている

そして今朝

夜が明けた

そして、大きな雲が留まっている
