1位との差が段々開いていく・・・・
どうしましょう?
連休最終日の今日もお天気に恵まれました。
寒いですけどね。これがこの時期の平均的気温だそうですから
今までが暖かすぎた、ということでしょう。
昨日は 洋服の上に着物お羽織を着ている方をお二人見かけて
(元町で、と地元のスーパーで)流行ってるんですか?
さて 昨日書きかけていた 経糸と緯糸のお話です。
これ(新田間道)と
これ。
全く違う着物のように見えますが実は経糸は同じ、というお話をしました。

経糸部分を並べると 確かに同じ色が同じ順番で並んでいます。
そこに 水色の緯糸を織り込んだものが上。 薄紫の緯糸なら下になります。
布というのは 経糸と緯糸が交互に重なり合って織り上がります。
その時に 経糸の色と緯糸の色が干渉しあって織り上がりの色となります。
糸を染める時にある程度の量を染めた方が効率が良いですし 染やすいです。
そこで 数反分の経糸を一度に染めて 緯糸で織り上がりに変化を付けることで
コストを下げることもできます。
じざいやがオリジナルの反ものを依頼する時によくやる方法です。
この時に経糸と緯糸の色の相性を考えないと
想定外の織り上がりいなったりします。
もちろん、織る人の経験値で この経糸の色にこの緯糸を入れると
どんな織り上がりになるか・・・は予測できるのです。
それが 「織り色」と呼ばれるもので
時には 玉虫色に輝く布を織り上げることもできます。
かつては皇族のみに許されていた「菊塵」という色は
紫根と刈安を使った織り色で
光線の種類や角度によって色が変化して見える微妙で美しい色です。
古代の人々には不思議で高貴な色とされていました。
山下さんの黄八丈などでもその 色の組合せの妙を見ることができます。
色だけでなく 経糸と緯糸の太さで織物の特徴を捉えることもできます。
普通の紬は
経糸が細く、緯糸を太くすることで 織り進みやすくしています。
真綿の紬でも 経糸を生糸にすることで滑りが良く、織やすくなります。
経も緯糸も真綿の諸紬と呼ばれるものや
本場結城紬、広瀬さんの手おりの中の手織り、は経ても緯も真綿なので
糸同士がくっ付きやすく経糸の開口に力が必要なのと
緯糸を織り込む時に引っかかりやすく、細心の注意が必要となります。
また、芝崎さんの座繰り糸の紬は経て糸と緯糸が同じ太さです。
同じ力で組み合わさり、織りの密度が高くなっています。
経糸と緯糸の色の組合せが「織り色」ですが
どんな色の経糸を使っても緯糸しか見えないのが綴れ織です。
経糸を緯糸が包み込むように織り、柄も緯糸のみで表現されます。
横方向に畝が生まれます。
綴れ織の実演はこちら
博多については勉強不足なので ちょっと勉強中。
そのうち改めてご紹介しますね
https://www.instagram.com/sakurako_jizaiya/
フォローよろしくお願いいたします
目指せ!フォロワー1000人!!
最後までお読み頂きありがとうございます。
下の「着物・和装・業者」というバナーか、「にほんブログ村」という文字をクリックして下さい。ブログ村ランキングページへ飛びますので、そうしたら1ポイント入ります。(inポイント)次にブログ村の「きものがたり」じざいやブログのところをクリックしてこのページに戻りますと、outポイントが付きます。











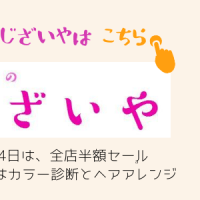











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます