信長の「天下布武」には「日本全土を統一する」という意味が込められている。と書けば、天下とは畿内だとか、武は七徳の武だとかいう「言葉遊び」がはじまります。
しかし実際の「行動」を見ずに「天下布武の解釈」だけしていても「なんの意味も」ありません。
七徳の武とは、
1.暴を禁じる 2.戦をやめる 3.大を保つ 4.功を定める 5.民を安んじる 6.衆を和す 7.財を豊かにする
であり、天下布武とは織田信長による「天下に七徳の武を布く」という思い、天下泰平の世界を築くという強い意志の表れだ、、、そうです。
また「布武」には「武を布く」なんて意味はなく、「歩く」「行動する」ぐらいの意味だという方もいます。天下布武とは天道に従って行動するという意味だということです。
じゃあ実際はどうだったのかという話です。
天下布武の印章を使い始めたのが、永禄10年の末です。そして足利義昭を奉じての上洛。
それから信長は畿内の勢力とずっと抗争を続けます。和をもって懐柔しようとした勢力もいます。浅井や松永。しかし浅井とはすぐに対立し、結局は、朝倉、浅井、延暦寺、伊勢、本願寺を敵に回して、ずっと戦い続けます。松永だって最後は敵に回ります。「どこが七徳の武なんだ」というが実際の行動です。「一時朝廷や義昭に仲介させて和を求める」ことはあっても、戦略であり、すぐに戦闘状態にもどります。
特に和を求めた大勢力は武田と上杉ですが、それも「今は敵にできないから」という戦略上の方便です。
やがて信玄が死ぬと、信長は義昭を追放し、元号を天正と改めさせます。
天正に入ると、死ぬまでの10年間、畿内だけでなく武田、上杉、毛利、長宗我部も敵に回し、戦い続けます。これを秀吉の行動と比べてみれば「和をもって」などという思考が信長になかったことは歴然としています。
アメリカは戦争ばかりしていますが、戦争が好きだと言ったことは一度もありません。あくまで「平和のために戦争をしている」のです。タテマエとしてはそうなります。「天下布武」には「平和への願いが込められている」のかも知れません。しかし信長も「平和のために戦争ばかりしている」のです。
「天下布武」の解釈を中国の古文書まで遡って、いくらいじくりまわしても、それは単なる「言葉遊び」に過ぎないでしょう。
すべての戦国武将のうち、日本全土の大名を敵に回して戦おうとした勢力はほかに一つもありません。謙信には上洛する気なぞさらさらありませんし、毛利もそうです。かろうじて信玄がいますが、すでに病に侵されており、どこまでやる気だったかには疑問が残ります。
この「信長の行動の特異性」は「歴然」としているのに、「新しいことを言うために」、天下布武の意味とかをこまごまと解釈しても意味はない。実際の行動をみて考えるべきです。
しかし実際の「行動」を見ずに「天下布武の解釈」だけしていても「なんの意味も」ありません。
七徳の武とは、
1.暴を禁じる 2.戦をやめる 3.大を保つ 4.功を定める 5.民を安んじる 6.衆を和す 7.財を豊かにする
であり、天下布武とは織田信長による「天下に七徳の武を布く」という思い、天下泰平の世界を築くという強い意志の表れだ、、、そうです。
また「布武」には「武を布く」なんて意味はなく、「歩く」「行動する」ぐらいの意味だという方もいます。天下布武とは天道に従って行動するという意味だということです。
じゃあ実際はどうだったのかという話です。
天下布武の印章を使い始めたのが、永禄10年の末です。そして足利義昭を奉じての上洛。
それから信長は畿内の勢力とずっと抗争を続けます。和をもって懐柔しようとした勢力もいます。浅井や松永。しかし浅井とはすぐに対立し、結局は、朝倉、浅井、延暦寺、伊勢、本願寺を敵に回して、ずっと戦い続けます。松永だって最後は敵に回ります。「どこが七徳の武なんだ」というが実際の行動です。「一時朝廷や義昭に仲介させて和を求める」ことはあっても、戦略であり、すぐに戦闘状態にもどります。
特に和を求めた大勢力は武田と上杉ですが、それも「今は敵にできないから」という戦略上の方便です。
やがて信玄が死ぬと、信長は義昭を追放し、元号を天正と改めさせます。
天正に入ると、死ぬまでの10年間、畿内だけでなく武田、上杉、毛利、長宗我部も敵に回し、戦い続けます。これを秀吉の行動と比べてみれば「和をもって」などという思考が信長になかったことは歴然としています。
アメリカは戦争ばかりしていますが、戦争が好きだと言ったことは一度もありません。あくまで「平和のために戦争をしている」のです。タテマエとしてはそうなります。「天下布武」には「平和への願いが込められている」のかも知れません。しかし信長も「平和のために戦争ばかりしている」のです。
「天下布武」の解釈を中国の古文書まで遡って、いくらいじくりまわしても、それは単なる「言葉遊び」に過ぎないでしょう。
すべての戦国武将のうち、日本全土の大名を敵に回して戦おうとした勢力はほかに一つもありません。謙信には上洛する気なぞさらさらありませんし、毛利もそうです。かろうじて信玄がいますが、すでに病に侵されており、どこまでやる気だったかには疑問が残ります。
この「信長の行動の特異性」は「歴然」としているのに、「新しいことを言うために」、天下布武の意味とかをこまごまと解釈しても意味はない。実際の行動をみて考えるべきです。











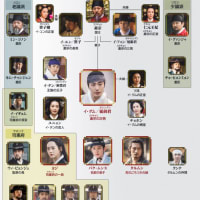




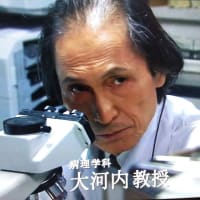



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます