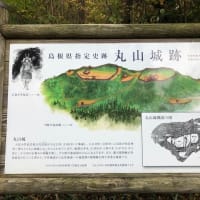47.耳たぶ伝説
江津市桜江町坂本に「耳タブ伝説」というものがあった。
「あった」というのは、現在では、地元でもほとんど知られていないし、また当該地は国道設置(国道261号線、昭和50年(1975年)に開通)により、すっかり変貌しており、その伝説を思い浮かべることは不可能であるからである。
今はただ、「島根県口碑傳説集」、「邑智郡誌」、「桜江町誌」などの本に載っているだけである。
<タブの木>

この伝説の内容は、
かつて、坂本の渦巻地区に耳タブといって周囲2mもの大樹が、江の川沿いに生えていた。
大樹鬱蒼として茂り、老枝蟠屈して、江の川の対岸渡河原に達し、樹下に江の川の碧流迫り流れて大渦を巻いていたので、この地を渦巻といい、老枝川を渡っていたところから、木の瀬ともいっていた、という。
その枝は、前述したように江の川対岸の渡河原に達していたという。
時代は、不明であるが、この地で戦があった。
その両軍は、江の川を挟んで対陣し、毎日交戦した。
しかし、ついに渡河原に布陣していた軍勢が江の川を渡り、渦巻き側に攻め込んだ。
この戦闘の結果は、悲惨だった。
渦巻き側に布陣していた軍勢が大敗し、死者が千人にも及んだという。
そして、死者千人の耳を切り取り、このタブの木の根本に埋めたという。
以来、このタブの木を「耳タブ」と呼ぶようになった。
そして、戦に勝ったという意味で、この地の畑を「勝畑」と呼ぶようになった。
それが、訛って、時代が下り「八畑」というようになった。
現在、この地はすっかり国道とその堤防などで占められて、その当時の状態を想像することもできない。
また「八畑」という言葉もなくなったようである。
現在の江の川の様相は、当時とはかなり異なっていると思うが、現在の景観は次のとおりである。
(当時は、現在よりも水量も多く川幅も広かったといわれている)



或る妄想
この伝説は、戦がいつ起こったのか、誰と誰が戦ったか、などは何も語っていない。
でも、この伝説が全くの虚構であるとは思えない。
ただし、伝説につきものの、伝わる数が倍、3倍に増えて伝わるということは十分ありえる。
その数が増える法則を一旦置いて推察してみる。
渦巻きの地勢から考えるに、この地に布陣できる人数は2千人以下であろう。
戦において、兵が3割減ると全滅、5割減ると壊滅という。
10割減の場合にどう言うのか分からないが、殲滅あるいは消滅とでも呼ぶのかもしれない。
戦国時代においては、戦での死者数は多くても20%前後で、通常は10%になると降参するか退却するようである。
この伝説でいう死者が千人とすると、この戦で破れた側は壊滅状態だったと思われる。
相手を壊滅状態にするには、少なくとも3倍〜4倍の戦力が必要である。
そうすると、渡河原の勢力は6〜8千人ぐらいだったと思われる。
6〜8千人の兵は大軍である。
このような大軍を率いることができた、武将は誰かということである。
そこで、思い浮かぶのは、文和3年/正平9年(1354年)の5月足利直冬の小笠原征伐である。
この物語の、第42章足利直冬(2)、小笠原征伐の項で次のように述べた。
上洛を目指して、益田を出発した直冬軍本体は、上府村から跡市村、清見村、井澤村を通って市山村にでて渡利村に(江津市川越)に本陣を置いた。
ここで、軍を二分して小笠原一族の諸城の攻撃に向かった。
一軍は、江の川の西側を鹿賀村(江津市桜江町)より因原村(邑智郡川本町)へ入り、川本の温湯城(邑智郡川本町市井原)を攻めた。
ここは小笠原長氏の本城であって、ここには、石見守護の荒川三河三郎兼頼と小笠原長性が立て籠っていた。
後の一軍は江の川を渡り、坂本村より川下村(邑智郡川本町川下)に向かい築紫原城(邑智郡川本町三原)を攻略して、そこより谷戸の飯の山城(別名仙岩寺城)(邑智郡川本町谷戸)を攻めた。
この、江の川を渡った足利直冬の一軍が、この「耳タブ」伝説の勝利した軍であり、敗戦した軍が小笠原軍だったのではないかと思うのである。
その、渡河の状況を以下の様に想像する。
両陣営は江の川を挟んで睨み合っていたが、ある晩足利直冬側が川をこっそり渡ったのである。
浅瀬の下流は急に川が深くなっており、そこは強い渦巻を巻いている。もし足を滑らして流されると生死にもかかわることになる。
そこで、足利直冬方は渦巻側に生えているタブの大木の枝に縄を付け、対岸の河原までその縄を引っ張り、川を渡る時のガイドロープにしたのである。
こうすれば流れに足を取られても流されることはない。
このような縄を夜中に5,6本架けて準備し、明け方に一気に江の川を渡った。
伝説では、タブの木の枝が、対岸まで伸びていたので、これを伝って江の川を渡ったということになっているが、いくらなんでも枝が対岸まで、届くほど伸びるわけがないと思う。
そこで、このタブの枝を利用して渡ったと考えたのである。
そして戦が終わって、何故「耳たぶ」を取ったのか?
これは恐らく、戦の勲功褒賞を殺した人数で行っていたため、「耳たぶ」でその人数を確定していたのではないかと思われる。
片側の「耳たぶ」だけを持ち去り、反対側の「耳たぶ」を埋めて立ち去ったのではないかと思われる。
その後、死体をどうしたのか?恐らく江の川に流したのではないかと思う。
その昔、江の川は各種廃棄物の処理場でもあった。
次に、「島根県口碑傳説集」に掲載されている「耳タブ伝説」を掲げる。
耳タブの傳説
同村(川下村)字渦字八畑に、耳タブさて周園六尺余の大樹がある。
其周圍は畑地になつて居るから、枝は概ね伐取られて、数千年の老幹人間の艱みを、いたましく語つて居るが、古老の言に依ると、此地は古戦場であって、千人の耳を埋めた地であると。
さうして此地は八畑では無くて、 勝畑で戦勝を意味して居るのである。
いつの頃であつたか、こゝにタブの大樹があった。
鬱蒼として茂り、老枝幡屈して江川の對岸、渡利河原に達し、樹下には江川の碧流迫り、流れて大渦を巻いて居たので、此地を渦巻といひ、老枝河を渡つて居る所から木の瀬と云つて居たとか。
何れの時代であつたか、河を挟んで對陣し、毎日交戦して居たが、遂にタブの枝を枝を傅はりて、渡利河原がら攻寄せ、激戦の後一方を慶鏖し大勝利を得たによつて、勝畑と名づけ、戦死者千人の耳朶を切り取って此處へ埋めたと傳えられている。
(川下村小学校報より)
<続く>