【薩長天下が勘違いの始まり=維新という大きな誤解】
小日向白朗学会が預かっている大野芳文庫のなかに、あの東京裁判で弁護士を務めた法学者、瀧川政次郎の「東洋史上より見た日本人の歴史」の一部のコピーがある。その中の第十二章維新時代(下)第三節明治政府の成立の項中に次の一文がある。
≪わが国が国際法上の一独立国として欧米各国と伍してゆくためには、封建の制を廃して強力なる中央集権を行わなければならないという思想は、西洋事情に通じた識者が共通に懐いていた思想であって、小栗上野介(忠順)は、まず長洲を征して毛利侯の封を収め、その他を郡県とする意図を勝麟太郎に漏らしている。木戸孝允は、全国の土地人民を朝廷に帰せしめるにあらざれば、新政府樹立の意義なしとし、慶応四年二月、版籍奉還の議を三条・岩倉に献じ、明治二年正月、大久保利通と謀り、薩長両藩主に説いて版籍を朝廷に奉還せしめた。ここにおいて諸藩主のこれに倣うもの多く、同年六月には、いまだ版籍の奉還を請わざる三十余藩の藩主に命じて版籍を奉還せしめ、旧藩主を任じて中央政府の潘知事とした。このことは、大化の改新の際に国造の地を収公して、国造を新政府の郡司に任じたことと酷似している。≫
こうして廃藩置県へとつないでいき、全国諸藩の連合政権から専制政権へと脱皮、一応のスタートを切ったのが明治政権だ。しかしその実態は、「薩長藩閥政府を作ることによって、慶喜が自ら進んで放棄した権力を、天皇の名にかくれて詐取したに過ぎないのである。彼らの眼中には、天皇もなく、國もなく、人民もなかった。あるものは、ただ自ら天下を取ろうとする陋劣な野心のみであった。」(蜷川新「維新正観・明治維新と称する破壊活動」より)・・・と喝破される。
その通りだと思う。その時に大きな間違いを犯しているのだ。日本船の向かう未来はいったいどんなものなのか。まさかの「植民地」、主権を喪失したパペット国家だとでも‥‥。
明治維新とは実はイギリスとフランスの代理戦争に過ぎない、との識者の声もある。幕府についたフランスはスペイン王位継承問題がこじれてプロイセンの脅威を意識、普仏戦争にのめり込んでいかざるを得ない中で、極東のことはちょいと手薄にならざるを得なかったのだろう。こうしてイギリスの勢いが極東を襲う。英外交官といえばアーネスト・サトウが著名だが、アロー号事件でも明治維新でもハリー・パークスの外交というか諜報というか、彼の活躍振りは特記されるだろう。イギリスはアロー号事件でさらに権益をゲットしたが、ロシア南下を懸念、日本という傭兵部隊を育成しておきたい事情があった。時まさに南アフリカでは金、ダイヤモンドという宝物が発見されて、喉から手が出るほどどうしても手に入れたいという欲望に駆られたという事情もある。薩長をヨイショして手懐けることによって、心おきなくボーアの戦争に突っ込んでいくのである。
こうした経緯を経て、主権国家・日本が新しいスタートを切った。而してその実態は、イギリスというプロデューサーが巧妙に作り上げたパペットなのである。悲しいスタートではないだろうか。家康の国家理念のもとに元禄文化を謳歌したあの頃のほうが良かった、と思うのは私だけだろうか。その証拠に、日清戦争から日英同盟、そして日露戦争へと、鎖国の時代とは異次元の戦争の時代へと引きずりこまれていくのである。イギリス帝国主義のやり方を見せつけられた明治の元勲たちはマネをせざるを得なかったというか、「大陸」という異国を甘い蜜と勘違いし始めるのである。「だって、あの大先進国のイギリスがやっているじゃないか…世界のあちらこちらで」、というわけだ。昭和初頭の満州幻想である。
こうして間違い・勘違い・錯覚は泥沼化し、傷は深く深く浸透し始めていく。考えてみれば当然のことかもしれない。異国も主権を持つ一国家であるという単純なことさえ認識できないまま大国イギリスの見よう見まねで膨張路線を突っ走ろうとしていたのだから、自国の主権の認識までもが疎かになったとしても、言わずもがな、ということだ。
【白朗の主権認識と対立する自民党の売国体質】
1971年、昭和46年7月号の経済誌「富士ジャーナル」に「台湾解決でアメリカに招かれた元馬賊王 講和で売渡した密約で縛られる日本」という記事がある。その中では小日向白朗は「・・・・講和条約を結んだ時に、吉田さんは日本の航空権、国防権、電波権を売り渡し、その自由使用をアメリカに認める特別覚書きを密かに入れているんだ。」と述べている。さらに「・・・・だから、憲法も安保条約も、実は見せかけにすぎないんで、日本をしばっているのは、この密約なんだよ。・・・・」とも言っている。この密約こそが戦後一貫して今もなお、日本から主権を掠め取っている元凶なのである。主権を盗まれている状態とは、すなわち植民地であるということだ。れいわ新選組の山本太郎氏が令和5年3月23日第211回国会参議院予算委員会において岸田総理に対して「総理、日本はアメリカの植民地ですか。」と質問したのは、このことを指しているのである。
参考までに「売国」っていうものの一例を見ておこう。池田知隆氏の著「謀略の影法師」の第十二章国際情勢を見つめての中に「密談の場に乗り込む」というエピソードが紹介されている。有馬温泉の池之坊満月城という旅館での密議の場に白朗と合気道で有名な植芝盛平氏とその嫡男吉祥丸氏が乗り込んだのだ。中では竹島をどう料理しようかと売国犯たちが韓国側要人と密談していたのである。同書では「・・・・岸信介と児玉誉士夫、その両脇に三浦義一と矢次一夫。向かい合って韓国人らしい者が三、四人いた。」 そして白朗曰く「・・・・何の相談か!竹島のことでなにやら企んでいるならば、ここから帰すわけにはいかん。」と大声を出した。岸らはすぐに立ち上がり逃げるように部屋を出ていったということである。そう、売国犯という輩は結構中枢にいるのである。維新の時の野望に満ちた薩長のDNA、天皇も国も人民も全く眼中になく天下への陋劣な野望のみに取り憑かれたDNAを多少とも継承しているのではないだろうか。御用盗事件でさらした西郷のテロ体質こそがまさに売国体質の素のようなものであろう。このことは銘記すべきことである。普通ならば、「お偉いさんの会談ね、私にゃー関係ないや」とスルーするところだろうが、白朗は許すことができなかったということだ。岸、賀屋、佐藤などという自民党主流の台湾ロビーとの対決も辞さず、白朗なりの方法で対処していた、のだと思っている。
私にとって小日向白朗とは一つの方法を示してくれる灯台のようなものである。アジアの平和に敵対する者たちを、あるいは売国の輩がうごめく暗闇をサーチライトのように照らし出してくれるのである。彼らに対してどう対峙したらよいのか、それこそが小日向白朗の遺志であり、小日向白朗学会のテーマであると思っている。そして、今まさに白朗の季節が巡ってきていると感じる。(文責:吉田)












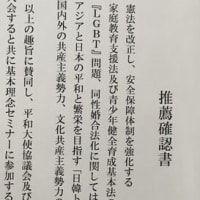
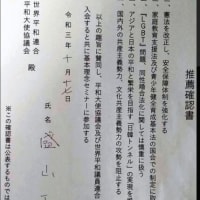














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます