
これまでに読んだ作家さんたちを紹介してみたいと思います。画像は、インターネットからゲットしてきたものです。
 高村光雲(79冊)
高村光雲(79冊)『幕末維新懐古談』という本を読んだだけなんですけど、章(節)ごとに「1冊」という扱いになっているので、79冊ということになってしまいます。まあ、79冊分の価値があるとまでは言わないけど、この本は面白いです。幕末から維新にかけて、仏像屋の丁稚にすぎなかった少年が世界的な彫刻家となっていく過程を、本人からナマの話を聞けるわけですからね。当時の世相とかがヒシヒシと伝わってきます。
 芥川竜之介(24冊)
芥川竜之介(24冊)芥川先生は長編を書かなかった人だけに、短編がいっぱいあります。中にはそれほど面白くない(カエサルの趣味に合わない)のがあったりもするけど、ヒット率は高いですね。文学を研究している人にしかわからないような、難しいのがないのもいいです。安心の竜之介クオリティというところでしょうか。
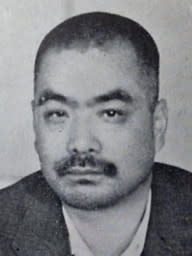 中里介山(22冊)
中里介山(22冊)『大菩薩峠』ですね。全41巻(未完)とのことなので、半分ちょっとを読んだというところです。いろんな登場人物がいて、面白いと言えば面白いと言えなくもありません。でも、何かのお話の途中で別のお話になっちゃったり、全体的な流れというか柱みたいなものがないんですよね。この後もこの調子が続くんでしょうけど、41巻まで読み続けることになると思います。
 三遊亭円朝(21冊)
三遊亭円朝(21冊)円朝さんの噺を口述筆記したものです。これを読んだ二葉亭四迷先生が「言文一致体」を始めたということなので、言ってみれば、日本近代文学の祖ですね。「小話」の中にはかなり面白いものがあるし、「人情話」みたいなのもいいです。でも、長い奴についてはちょっとくどいかなと思えるところがあって、『塩原多助』は読んだものの、怪談ものには手を出していません。
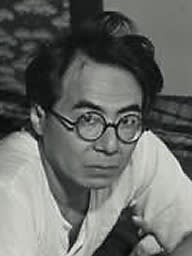 坂口安吾(21冊)
坂口安吾(21冊)安吾先生の作品は、高校生のときにかなり読んでいるんですよ。でも、これは読んでないと思えるようなのがチラチラとあって、そういうのをチョビチョビと読んでいたのだけど、最近は、昔読んだのを読み返したりしています。まあ、読んだと言っても40年近くも前の話ですからね。たいていの作品は新鮮な思いで読むことができます。
 夏目漱石(19冊)
夏目漱石(19冊)漱石先生には、名前は知っているけど読んだことのない作品が少なからずあるので、全部読んでしまおうと思っています。今のところ、少しずつ手を出しているという感じで、長編はあまり読んでいません。短編の他に「雑文」とか「談話」みたいなのがけっこうあって、そういうのに手を出しているうちに19冊まで来ちゃいました。
 豊島与志雄(19冊)
豊島与志雄(19冊)『レ・ミゼラブル』『ジャン・クリストフ』の訳者として知られているが、創作者としては無名・・・とのことで、カエサルも、青空文庫を読み始めるまで、豊島与志雄という名前も知りませんでした。でも、実に多彩な作品を書いていますね。意図的に、さまざまな分野に挑戦していたんじゃないかと思います。けっこう面白いです。
 太宰治(18冊)
太宰治(18冊)太宰先生の作品は、かなりの波がありますね。いかにも、締め切りに追われていい加減に書き殴った・・・みたいなのが少なくありません。でも、いいものはいいですね。そういうアタリ・ハズレが楽しかったりします。
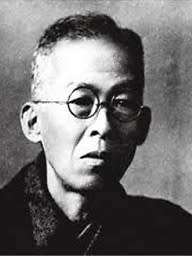 岡本綺堂(17冊)
岡本綺堂(17冊)綺堂先生には「怪談」の面白さを教えてもらったという気がしています。オチがないんですよ。物理的な説明がつかないのは当然として、霊魂の働き(○○の怨みで・・・みたいなの)を考えても説明がつかなかったりします。でも、そういうのが「意味不明」ではなく「不思議」になるんですね。
 中島敦(17冊)
中島敦(17冊)中島先生と言えば『山月記』だし『李陵』だし、漢文調の中国ものなんだけど、現代物なんかも書いています。それよりも、何よりも、南島ものですね。同じ作家が書いたとは思えないくらい、サッパリ、スッキリしています。そういう作品、もっともっと読みたいところなんですけどね。そう遠からず、全作品を読み終えてしまうことになると思います。
楠山正雄(16冊)・・・写真を見つけられませんでした。
楠山先生は、内外の童話や昔話なんかを集めた人ですね。そう言えば「かちかち山」ってどんな話だったんだっけ・・・とか、「鎮西八郎為朝」って名前は知ってるんだけどどんなことをしたのか知らないんだよねぇ・・・などというときは、楠山先生なんですね。なるほどなるほどです。
田中貢太郎(16冊)・・・写真を見つけられませんでした。
田中先生も「怪談」ですね。綺堂先生ほどの洗練された文章ではないんだけど、なかなか楽しめます。そういう言い方は失礼かもしれないけど、いろんな小説を読んでいて、このへんでちょっと口直しをしたいな・・・みたいなときに読ませてもらうのですよ。
 横光利一(15冊)
横光利一(15冊)横光利一という名前は知っていたんだけど、読んだことはありませんでした。タメシに読んでみたのが『日輪』だったのだけど、ヒミコの話で、血なまぐさいバトルなんかもあります。いかめしい、むつかしい話を書く人というイメージがあったんだけど、全然違いましたね。以来、ちょぼちょぼと手を出すようになったんだけど、芸風が広いですね。『春は馬車に乗って』とか、本当に心が洗われます。
 宮沢賢治(14冊)
宮沢賢治(14冊)賢治さんの童話、はっきり言って、わけわかんないです。そういうところを楽しむべきなんだろうけど、カエサルは上手に乗れません。・・・などと言いながら読んでいるわけですけど、軽い気持ちでは読めないんですよ。「さあ、これから、宮沢賢治を読むぞ」みたいな、気合いがいるんですね。
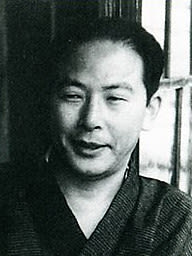 久生十蘭(13冊)
久生十蘭(13冊)たとえば『キャラコさん』とかの、明るく軽いノリ、いいんですよね。でも、マンネリになっちゃうんですよね。
 新美南吉(13冊)
新美南吉(13冊)新美先生の童話はいいですね。新美童話ばかりを続けさまに読もうとは思わないけど、ちょっと一息・・・みたいなときに読みたくなるんですね。そういうのが、短編作品を単独で読むことのできる青空文庫のいいところだと思います。短編集とかだと、そうはいきません。
 森鴎外(12冊)
森鴎外(12冊)鴎外先生はいけません。文語調の作品が多いので、読みにくいです。でも、名前が名前だからついつい読んでしまいます。鴎外先生に限らないけど、この時代の作家さんたちって、いろんな分野の作品を書いているんですよね。文学史には出て来ないような小品に、けっこう面白いのがあったりします。
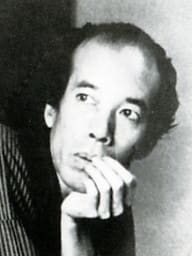 直木三十五(11冊)
直木三十五(11冊)直木先生の『南国太平記』は、さすがだと思います。この時代(昭和6年)のものとしては、ちょっと飛び抜けていると思います。短編についても同じようなことが言えるのかもしれないけど、時代を考えなければ、可もなく不可もないというところでしょうか。
 菊池寛(10冊)
菊池寛(10冊)菊池先生も、可もなく不可もなしという感じがしちゃいますね。代表作についてはあらすじがわかってるし、なんか、感動が薄くなっちゃうんですよね。ただ、いろんな作家の私小説やエッセーなどに登場するので、そのついでという感じで読んじゃったりします。菊池先生、人脈が広いですよね。
 織田作之助(9冊)
織田作之助(9冊)とりあえず『夫婦善哉』を読んでみて、まあ、こんなもんか・・・なんて思ってたんだけど、『猿飛佐助』を読んでビビックリ。芸域が広いですね。
今、一番お気に入りの作家かもしれません。
この他に、5冊以上読んだ作家さんとしては、寺田寅彦、海野十三、小川未明、岡本かの子、小酒井不木、林不忘、正岡子規、夢野久作がいます。
逆に、1冊しか読んでいない作家さんが100人くらいはいます。1冊目の途中で読むのを止めちゃった作家さんもいます。まあ、難しかったり、つまらなかったりするわけですね。文語体であるとか、旧字・旧かなづかいであるとかで読みにくいというのは困りますね。
カエサルは、文学の研究とかをしているわけじゃなくて、趣味として、楽しみとして読んでいるだけなので、難しいのとか、読みづらいのとかはアウトです。
最後になりましたが、青空文庫の創設者であった富田倫生さんのご冥福をお祈りします。富田さん、ありがとうございました。























読書ランキングに入ってくるとは。
恥ずかしながら、小生はゼロです。
読んでみよっかな~。
おお、『桐生通信』というエッセーもありますね。後で読んでみたいと思います。