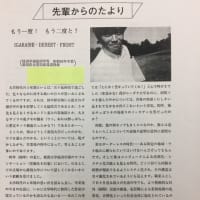●櫛形山脈を日本一の小ささで活性化(その2)
「馬塲 政雄」さんは、櫛形山脈の麓を流る清流「加治川」の名を関した「加治川山の会」の会長さん。
加治川山の会では旧登山道の復活に御苦労されてきており、春の大峰山ハイキングの登山ガイド、新発田市から委託を受け登山道整備、山小屋の維持管理などを行っている。
もともと新発田市に合併する前の旧加治川村の役場の職員であり、当時「日本一小さい山脈」と名付けPRしたその人なのである。国土地理院のデータなどで"裏"を取り「日本一小さい」という最高のキャッチフレーズを見出したその功績は素晴らしいものと思う。
降雪期も親しめる低山として冬場に特に人気がある大峰山頂上付近の「チェリーヒュッテ大峰」(山小屋)の建設にも関わったり、旧加治川村・旧中条町及び新発田市で櫛形山脈のマップをひとつにまとめたものを作成したりと、基盤づくりへの貢献には頭が下がるばかりだ。
「丹後 裕子」さんは胎内市における山を愛する会である「胎内MPC(マウンテンパワークラブ)」の中心人物の一人。
胎内MPCは胎内市への合併以前の町名を冠した「中条山の会」から名称変更したもので、活動は櫛形山脈の縦走登山ガイド及び胎内市内の里山のガイド、山道の草取りや補修等でご苦労されている。登山を楽しむ来訪者にとって陰ながらの大いなる支えだ。
しかし、ご自身が入会した当初よりも人数が減り、年齢層も高くなってきている。また、胎内MPCは女性が多いため、力仕事を要する山道の整備や”やぶ刈り”等に苦労していると言う。
同じ新潟県内でも田上町にある「護摩堂山(ごまどうやま)」は櫛形山脈と同じく城址、石切場があるのだが、登山道には歴史などを紹介する看板が立っていて、アピールが上手だと感じている。ご自身が登山ガイドをしている時も、山の歴史の説明をすると喜んで聞いてもらえるのだが、櫛形山脈も歴史を感じながら登ることができる山なので、来た人に楽しんでもらえるような工夫、アピールが必要だと感じると話す。
「神田 真由美」さんは「板額会」事務局での中心的人物。
「板額会」とは鎌倉時代に実在した弓の名手で”日本三大御前”の一人とされる「板額御前(はんがくごぜん)」を広く知ってもらうために活動している団体で、毎年、秋には板額御前の生涯を演劇で紹介したり、弓矢体験等ができる「板額の宴」を胎内市で開催している。
平成13年(西暦2001年)に「板額御前奮戦800年記念イベント」が開催され、その翌年に「板額会」が設立されたのだが、イベントの手伝いを通して板額御前の存在を知り、魅力を感じたため入会したという。
子ども向けに「板額御前物語」というマンガを作成するなどして、若者に向けてアピールしているため、会には若い人が多いのが特徴。そのためアイデア、機動力はあるが歴史に疎いため、先輩に教わりながらPRをしていきたいと意気込みを語ってくれる。
「土屋 美幸」さんは、「一般社団法人五頭自然学校」のスタッフで、日本山岳ガイド協会認定登山ガイドなのだが、ふるわせ座談会の第8回「五頭連峰を活用した地域活性アイデア」にも参加していただいた。新発田地域振興局管内のもう一つの親しみやすい山並みといえる「五頭連邦」に関わる視点が「櫛形山脈」にも活かせるのではと思い参加をお願いした。
現在の低登山ブームの中で「日本一小さい山脈」はとてもインパクトがあり、うまくPRすれば人はもっと来るのではないか。櫛形山脈は標高は低いが、ブナ林や花木、日本海の眺めなどを一日で楽しむことができる素晴らしい山だと話す。
学生、若者に魅力を感じてもらい、取り込んでいくことが必要であるとの指摘は、元教諭らしい。
「板垣 一寿」さんは「山岳手打ちそば一寿」店主で、蕎麦に打ち込む取組が全国誌のマンガ連載に描かれたり、地域を大事にする生活ぶりも合わせて「人生の楽園」で取り上げられるなど、蕎麦や櫛形山脈に関心を持つ”その道の人達”には超有名人。
大峰山桜公園には100種類以上の桜が植栽されているが、立札に書かれている桜の種類が間違っていることに気付き、5年ほどかけて調べ、正しいものに付け替えたという熱意と行動力が凄い。また、近くの橡平(とちだいら)サクラ樹林は国の天然記念物に指定されているのだか、大峰山の桜は冬に咲くものもあり、毎年10月から6月中旬まで様々な種類の桜が楽しめる場所で、大峰山で発見された「大峰桜」という木もある。今後はそれらをデータに残して、後世に引継いでいくことが必要である。日本人は桜が好きなので、桜はPRに有効だと感じていると雄弁に話してくれる。
櫛形山脈は、「板額御前」や「佐々木三郎盛綱」などなど、歴史ロマンを感じられる場所であり、歴史だけでなく、温泉や全通100年を迎えた羽越本線、何よりも”日本一小さい山脈”というように、魅力的なコンテンツがたくさんある。それらをアクセスポイントとして結びつけたり、櫛形山脈の「縦走証明書」を、例えば桜の木札にして発行するなどし、それも併せてPRすればもっと人気がでてくるなどと止めどなく語ってくれる。
「大矢 大」さんは「胎内市役所商工観光課」からお越しいただいた。櫛形山脈の誘客促進の実効性向上のために役所としても実務的に関わりを深めてもらいたいからだ。
令和6年4月から現職に就いたばかりだが、「日本一小さい山脈」をPRして、今後はソフト面を中心に整備していくことが必要だと感じているという。
胎内市が毎年春に開催している「縦走登山」は、市外からの参加者も多く人気がある。初参加の方も多く、インターネット等を通して知ったようだ。登山以外にも目的ができるよう、食なども結びつけて更にPRしていきたいと意欲を示してくれて嬉しい。
(「新発田地域ふるわせ座談会35「櫛形山脈を日本一の小ささで活性化(その2)」」終わり。「新発田地域ふるわせ座談会36「櫛形山脈を日本一の小ささで活性化(その3)」」に続きます。)
☆ツイッターで平日ほぼ毎日の昼休みにつぶやき続けてます。
https://twitter.com/rinosahibea
https://twitter.com/rinosahibea
☆「活かすぜ羽越本線100年」をスピンオフ(?)で連載始めました。
☆「新発田地域ふるわせ座談会」を日記と別建てで連載してます。
☆新潟久紀ブログ版で連載やってます。
①「へたれ県職員の回顧録」の履歴リストはこちら
②「空き家で地元振興」の初回はこちら
③「ほのぼの日記」の一覧はこちら
➃「つぶやき」のアーカイブスはこちら
☆新潟久紀ブログ版で連載やってます。
①「へたれ県職員の回顧録」の履歴リストはこちら
②「空き家で地元振興」の初回はこちら
③「ほのぼの日記」の一覧はこちら
➃「つぶやき」のアーカイブスはこちら